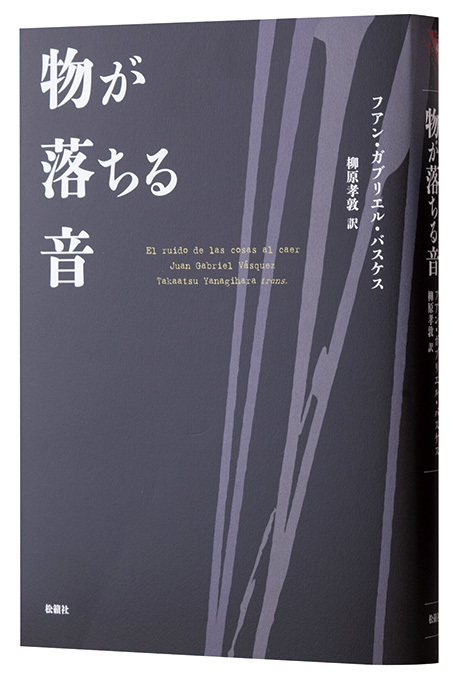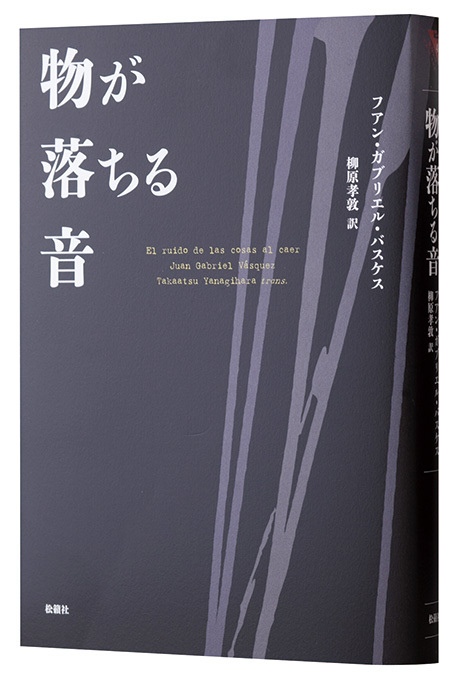「大切なのは、やり直すすべを知ることなんだ」
~ガルシア=マルケス以後の、新世代のラテンアメリカ文学を牽引するフアン・ガブリエル・バスケスの翻訳小説
タイトルに惹かれはしたものの、どうも内容は違うらしい。なんでもアメリカ合衆国とコロンビアとの麻薬取引をめぐる小説であるようだ。何とはなしに暴力やきな臭さが漂っている。黒い下地に灰色の線、白い文字、そして赤い帯に黒い文字。そんな装幀や帯の文句も相俟って、先入観はつくられる。
いや、正しいのだ。間違ってなどいない。そのとおりにちがいない。「しかし」……。 四分の一、三分の一、半分と読み進めながら、勝手にイメージしていたものとの違いにあわあわしてくる。帯にある麻薬をめぐる話なんてなかなかでてこない。むしろ前景化してくるのはもっともっと個人的なこと、すごく狭い、かぎられた人たちが交わしあう愛の物語、愛に不器用な者たちが何とかうまくやろうとしてべつのことをしてしまう物語。
背景には1980年代のコロンビアが、都市ボゴタがある。すこし血なまぐさいところはあっても、大したことはない。むしろあまり関係がないとおもわれていたタイトルが、また、いろいろな音のあらわれが、だんだんとつよまってくるのに気づく。それはしっかり伝わって、瞬間ではなく、ある一定の持続とともに、小説の外にいるわたし、わたしたち、このなかに起こっている出来事の部外者であるはずの心身をも否応なく振動させる。
麻薬マフィアが暗躍しコロンビアはコワいところと言われつづけた1980年代。背景には合衆国があり、ヴェトナム戦争もあった。それでいてボゴタの街にはふつうの人びとが暮していたのだ。そうした時代を子どもとしておくった語り手、語り手たちが、ただ話を聞き、語りなおすだけではなく、その後の時代を抜けても、どこかでその遠いこだまに巻きこまれている。何々なんか知らない、前の世代のことで自分たちには関係がないと言ってるし、おもっているけど、それは、極東の列島でもおなじ、めぐりめぐって波及してくることどもをおもわせずにはいない。
「いいか、ヤンマラ、良く聴け、過ちを犯すことなんかたいしたことじゃない。大切なのは、やり直すすべを知ることなんだ。時間が経ってもいい、何年、何十年でもいい、壊しちまったものをやり直すすべを知ることなんだ。」(p.33)
はじめのほうにでてくるこのことばがどう残響するのか、そしてそのことこそがこの小説において、ある場所に生まれ、住み、ある時間のながれのなかにいて、歴史を引き受ける、引き受けざるをえないことをラヴストーリーのなかで浮かびあがらせる。
チェコスロバキアの人気作家カレル・チャペック
書き上げることのできなかった、最後の作品
ひとりの「作曲家」を語る何人もの人びと。それぞれのことばのあいだから本人は浮かびあがるばかりだ。子ども時代に親しかった友人、十代のガールフレンド、大学時代そばにいた人物、つれあい、オペラ台本をつくるために教えを乞われた人物……。はじめのうちは、もしかすると、とおもっているのだが、そのうちにみえてくるのは「“似非”作曲家」の姿、古の「芸術家」像への渇望、自意識の肥大といったところか。だから、ベダ・フォルティーンなる人物って何だろう、と読み手は自問する。何をしているんだ? 何がしたいんだ? と。
カレル・チャペック(1890-1938)、あらためて紹介するまでもない、チェコの作家でジャーナリスト、劇作もした。『山椒魚戦争』があり、『ロボット(R.U.R.)』があり、マサリクとの対話があり、ヤナーチェク《マクロプロス事件》の台本があり、多くの人たちに愛される「犬のダーシェンカ」や「猫のプドレンカ」の物語がある。本書、表紙には「カレル・チャペック 最後の作品」と小さくあって、原題はŽivot a dílo skladatele Foltýna。直訳だと「作曲家フォルティーンの生涯」か。執筆はナチスの擡頭と重なっているという。
語られる“似非”作曲家・フォルティーンは、勘違いをしているようだ。あるいは時代錯誤。音楽は好きかもしれないが、スキルがない。作曲家や芸術家のイメージに憧れ、またアタマのなかでぐるぐるしている。サエはないわけではないが、ほとんどは既存のものからの借用と盗用。いま読むと、作曲家とか芸術家のある種のイメージが生きていて、それを揶揄するとみえなくもない。というより、さらにいうながら、音楽ソフトで既存の音源を組みあわせ「作曲」と称している21世紀の人たちを一世紀近く前から見通していたようでさえある。
チャペック自身は書きあげることができなかった本作。一応、結末(のようなもの)はチャペックのつれあいが書き足したという。いろんな意味で不安定な「作曲家-像」、読む人の数だけイメージは分散するか否か、かな。