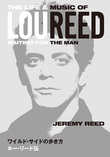伝統的な側面と実験的な発想が一体化した音楽が好きなんだ
――冒頭にも言ったように、今回のレコードはギターの音がとても美しくて、そして曲が長めですね。
「それはポール・エプワースの音録りに負うところが大きい。彼が作るギター・サウンドは素晴らしいよ。そして同じくらい、ランドール・ダンによるミックスの役割も大きい。ランドール・ダンはもっと、ダークなストーナー系、ヘヴィー系のバンドを手掛けている人だ。サンO)))やアース、Boris、アクロン/ファミリーとかね。僕は、高級なポップ・スタジオでやったセッションを、もっとこう……ダークで実験的でヘヴィーな音楽に取り組んでいる人のところへ持って行きたいと思った。なので、テープをワシントン州シアトルへ持参して、ランドールと一緒にアナログのスタジオで作業して、彼にミックスしてもらったんだよ。つまり、ポール・エプワース的美意識と、ランドール・ダンの美意識のあいまったところに、あのギター・サウンドが生まれたわけだ」
――正反対の立場にいる人がアルバムを完成させたわけですね。
「そう。その2つの場所を共存させたかった。僕はその橋渡しをしたにすぎない」
――そういう考え方ができるのがあなたらしいと思います。
「そういえばポールがデビー・グッギにバック・ヴォーカルを入れるように頼んだのは、いい発想だった。録音上で聴いてもよくわからないんだけど、彼女はいろんな曲で歌っているんだよ。彼女の声で甘さを加味するようなことを、あちこちのフレーズでやっている。あれは彼の発想だった。女性の声でフレーズに微妙な感触を加える、というのかな。僕もあれはいいと思った。このレコードの性質からしても相応しい。すごく、こう……女性性を肯定するような」
――先ほどのラディオ・レディオの歌詞のテーマにも通じる話ですね。そういうアルバムに、という発想はどこから得たんですか。
「僕のレコードはどれもそうだったと思うよ。正直、僕の作品に常に一貫している発想だ。性別に関する意見交換、性別に関する均衡、性別に関する尊厳、性別に関するあれこれ……。僕自身、ずっと男女混合グループで活動してきたし。男ばかりのバンドには興味が向かない。男ばかりのバンドでやったこともあるけど、僕には違和感があった(笑)。慣れてないんだよな(笑)」
――女性メンバーを意識して入れるようにしているんですか。
「いや、計算づくではないよ。それはない。ただ、僕にはそれが歴史的事実になっている。そもそもNYに越したのも、NYで聞こえ始めていた新しいヴォイスに惹かれたからだったんだが、それも主には女性だった。パティ・スミスの声、デビー・ハリーの声、あるいはスージー・スーの声、スリッツの声、レインコーツの声……。そしてそういうヴォイスが取り立てて変わっているとか悪目立ちするとかいうのではなく、男性の声と同等の評価を得ていたんだ。ある意味、パンク・ロックやニューウェイヴやノーウェイヴのシーンは性別のバランスがとれていた、ということだね。僕が観に行っていたようなバンド……例えばトーキング・ヘッズにもティナ・ウェイマスがいて当たり前で、あれ以外の姿は想像もできない。ああいうところなんだよな、僕が惹かれたのは。ああいう、音楽における異性間の意見交換みたいなものなんだと思う。僕にとっては、そこからずっと続いている男女のコミュニケーションというのが音楽のあり方なんだろうな」
――確かにソニック・ユースが出てきたときも、女性が男性メンバーと同じように重要な位置を占めているのが、新鮮だったのを思い出します。マッチョな男性中心的なバンドも多かった当時は。
「確かにね。しかし僕らはそれを売りにはしていなかった。僕らにとってはあれが自然だったからね。無理強いされたわけでもないし、意識すらしていなかったのに、周りはそれを話題にした。僕らからすると普通のことに思えたのに」
――そうですね。そして今作『Rock N Roll Consciousness』からは、今のバンドがうまくいっていることがよく伝わってきました。
「実にクールなグループだよ」
――本質的にどんなバンドで、ソニック・ユースとはどう違いますか。
「まず僕らは、必要を感じていない。つまりその……自分たちを売り出す必要がない、ということだ。サーストン・ムーアやスティーヴ・シェリーやデビー・グッギが何者か、世間は既に知っている。だから、他の百万といるバンドと一緒になってこっちから手を振って注目を集めようとは思わないし、その必要もない。それはもう、MBVなりソニック・ユースなりで実現したと感じているからね。僕らの野心はそれではない。僕らの野心は、このグループで興味深い音楽をやっていける状況を大事にすること。僕も人生ここまでくると……たぶんスティーヴもデビーもそうだと思うけど、ありがたいことに既に自己証明は済ませている。今はただ、仕事に純粋に集中して継続していく時だと思うんだ。ジェイムズ・エドワーズがこのグループで一番若くて知名度の低いメンバーなのは確かだが、だからこそある意味、あいつは秘密兵器なんだ(笑)。物凄い、ダイナマイトのような破壊力のあるギター・プレイヤーだから」
――あなたは58才でしたよね。僕も同世代なので、特に去年、プリンスが死んだ時は……。
「あぁ……」
――自分の人生も終わりが近づいているんだな、と思い、残りの人生であと何ができるだろう、なんてつい考えてしまいましたが、あなたにもそういう瞬間はありますか。
「わかるよ。確かに感じるのは……50代も終盤になると、あと20年生きられたら幸運だな、と思うようになるものさ(笑)。人は人生の大半を、ほとんど永遠に生きるつもりで過ごしてくる。寿命なんてものは意識しないし、寿命を意識するようになるのは60の声が聞こえてからだろう。でも……ね、僕はそればかり考えているわけではないし、僕は……何と言っていいのかわからないや(笑)。60歳になるのはきっと心理的に厳しいものがあるだろうな。肉体的にはもちろんだけど。ただ、僕は恐れていない。実際、最高にラディカルな音楽やアートって、60代や70代の人から生まれているじゃないか。ソニック・ユースにも“Radical Adults Lick Godhead Style” って曲があったが、あれはニール・ヤングやヨーコ・オノのような人たちが過激な音楽を作っているのに対して、若いバンド……グリーン・デイあたりは無難なパンク、〈セーフ・パンク〉を作っているという歌だった。
僕は10代の頃にセックス・ピストルズやスロッビング・グリッスル、リチャード・ヘルを過激だと思っていた。その過激なミュージシャンたちが年を取って今、相変わらず過激派なのに対して、その後、長いこと若いミュージシャンたちが無難で商業的なニューウェイヴをやる時代があった。つまりユース・カルチャーが送り出した過激なヴォイスはみんな広大なアンダーグラウンドの世界に存在していたのであって、ここ10年に生まれた優れた音楽というのも同様に、非常にヘヴィーな、地下でやっている実験的なノイズだったりフリー・インプロだったりする前衛的な発想の音楽だということだよ。そして僕も、ここ10年ほどはそういう音楽の探求にかなりの時間を費やしてきた。ポップ・ミュージックに異論があるわけではないが、そこは僕の居場所じゃないし、魅力を感じない」
――しかし、あなたの音楽は実験的でありながらとてもポップに聴こえる瞬間があります。
「うん、確かに。僕は伝統的な側面と実験的な発想が一体化した音楽が好きなんだよ。ソニック・ユースもずっとその世界にいたと思う。いつも聴いていておもしろいと思うのは、超メインストリームな音楽が実はある意味すごく実験的だということ。例えばラナ・デル・レイとか、あとはR&Bには多いね、ソランジュとか、あっち方面の音楽は全体に実験的で過激なものが多い。メディアに取り上げられているような典型的なギター・ロックのバンド以上にね。そっちはずっと伝統的で、(レッド・ホット・)チリ・ペッパーズやパール・ジャムにしても、フー・ファイターズにしても、あるいは……U2にしても、みんな優れたバンドではあるけれども傾向としてけっこう音楽が伝統的だ。ヒップホップやR&Bの方が、メインストリームのレベルで実験的な発想を生むことについて、遥かに成功しているんじゃないかな。
ギター・バンドにおける実験的な音楽は、あってもメインストリームのレーダーに引っかからない低い位置にあるんだろう。末端にいくほど実験性は高まる。そしてR&Bやヒップホップではメインストリームで実験的なものの成功が許されている。それはそれで全然OKだと思うけど、ただ、もっと実験的な音楽を聴けたらいいのに、とは思うよ。メインストリームのロック・シーンでもさ。かつてピンク・フロイドやジミ・ヘンドリックスが存在したように。トーキング・ヘッズの頃もしばらくそれがあったし、ニルヴァーナもある程度そうだったと思うが、どうも今はそういうのが……最大公約数的なところに受け入れられているようには思えないんだよな、他の音楽ジャンルでは受け入れられているらしいのに」
――そんなロックに未来はあると思いますか。あなた自身、ロック・ミュージシャンであることから逃れられない人だと思いますが……。
「いや、僕はロックンロールは決して死なないと思うし、未来を失う理由もないと思う。ただ、この音楽の自制心がかつてなく顕著に働いてしまっている時代のように見えるんだ。EDMやエレクトロニクスのバンドだってロックンロールの要素を孕んではいるし、形は違っても僕はそれを差別化しようとは思わない。DJカルチャーやダンス・ミュージックにしてもそうで、根源にある欲求は同じだ。しかし可能性としては、エレクトリック・ギターにベースとドラムという古い様式への反動がそこにあるのかもしれない。だとしたらその様式を踏まえなければいけないという自制心がロックを縛っているのかもしれないよね。僕は伝統的なロックンロールの設定で音楽をやるのが好きだから、それを踏まえて実験性を追求しているんだけど」