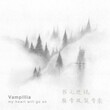湯川潮音が〈sione〉名義で発表した初のアルバム『ode』は、world's end girlfriendがプロデュース/アレンジを担当。音楽表現における〈声〉と〈唄〉の可能性をアップデートするような一枚だ。今回は、Mikikiの連載〈Next For Classic〉を監修している音楽ライターの八木皓平がレビューを執筆。ポスト・クラシカル/インディー・クラシックとの同時代性も垣間見える本作を掘り下げてもらった。 *Mikiki編集部
sioneの初フル作『ode』は彼女の声/唄を中心に制作された作品だが、ここには歌詞が存在しない。言葉によって伝達しうるメッセージや物語はなく、声/唄とworld's end girlfriend(以下、weg)がアレンジ/プロデュースをしたトラックだけがあるのだ。ここで起こっている言葉の剥奪は、ある種の貧しさをもたらすどころか、むしろ言語/唄というものの内奥に迫るような、言葉を超えた芳醇な物語やメッセージをリスナーに運んでくれる。
その剥き出しの声/唄の豊かさは、実は歌詞というものはヴォーカリストにとって、声/唄の表現の可能性を限定する足枷でしかないのではないかという疑念すら沸いてくるような凄みに到達している。そういった意味で、本作は〈声〉の表現領域を拡張し続けている一流のヴォーカリスト、メレディス・モンクの一連の作品や、インディー・クラシックにおけるヴォーカリズムの最高峰、ルームフル・オブ・ザ・ティース『Render』などに比肩しうるものだ。
sioneの声/唄のルーツについて彼女自身が綴った文章がある。これは今回の『ode』に先駆けて2016年に配信リリースされたEP『Golden Age』のときに、彼女が寄せたコメントだ(同作のBandcampページに全文が掲載)。
「私の原点は小学校時代に出会った合唱隊にあります
歌うのは、宗教音楽や現代音楽ばかりで
その意味やことばを深く理解していたわけではなかったかも知れないけれど
複雑に入り組んだ、構築された世界の中で
ただ声を出す歓び
ハーモニーによって表現される
躍動感、喪失感、安堵感
まだ実際に経験したことのない感情までもを
感じとるのが心地よかったのを今でも覚えています」
彼女の原点が宗教音楽や現代音楽にあり、そこで触れた言葉のやりとりのためのツールではない声のあり方、声そのものの響きに対する感動を明確に綴っている。宗教音楽や現代音楽というトピックは、先ほど名前を挙げたメレディス・モンクやルームフル・オブ・ザ・ティースという固有名詞にも共通しているところであり、ポスト・クラシカルやインディー・クラシックが盛り上がりを見せる現在では、タイムリーなものとも言える。本作は、ある意味ではポスト・クラシカルやインディー・クラシックへの日本からの回答ということもできるかもしれない。
また、同コメント内で「私の声から新しい響きを導き出してくれた WEGにとても感謝しています」とあるように、wegのアレンジ/プロデュースは、彼女の唄の可能性を極限まで引き出しているように思える。その堂々たる仕事ぶりは、エレクトロニック・ミュージック以降の感性で〈声〉の在り方を徹底的に突き詰めたメルクマールであるビョーク『Medulla』(2004年)におけるマーク・ベル、『Medulla』の方法論をさらに突き詰めることで最新のヴォーカル・ミュージックを提示してみせたハチスノイト『ILLOGICAL DANCE』(2015年)におけるマトモスにも匹敵するものだ。
sioneのヴォーカリズムについて先ほど、ポスト・クラシカルやインディー・クラシックを引き合いに出したが、それはそのままwegのアレンジ/プロデュースにも当てはまる。流麗なストリングスや細かくエディットされたアコースティック・ギター、電子音が繊細に空間に配置され、その中を自在に飛翔するsioneのハミングが美しい“Wealth of Flowers”を聴けばそのことがよくわかるはずだ。
他にも、鳥の鳴き声を真似るsioneとストリングスのドローンが柔らかに溶け合ってゆく“bird”や、ゆっくりと脈打つビートやヴォイス、電子音のすべてが点描的なサウンドの中で唯一ストリングスが線的な“The Seeker”、アンビエント・テイストのクラウトロックを彷彿とさせるアナログ・シンセが特徴的な“Golden Age”をはじめ、様々な楽曲でクラシック~現代音楽的なストリングス・アレンジが施されている。このあたりは、「空気人形」や「星空」といった映画の劇伴を手掛けてきたwegならではのアレンジメントだ。
ポスト・クラシカル~インディー・クラシックとも連続性があることだが、〈北欧〉というキーワードに絡めた聴き方もできそうだ。先ほど挙げた“Wealth of Flowers”や、エレクトリック・ギターが音響において中心的な役割を果たす“Plein Soleil”などでの点描的な電子音/グリッチ・ノイズとストリングスの絡みからはムームを連想させられるし、聖性を宿したsioneの声/唄と、wegが持つクラシック~現代音楽のヴォキャブラリーが溶け合う本作のサウンド・デザインは、シガー・ロスのフロントマンであるヨンシーのソロ作『Go』(2010年)と多くの部分で共通性があると思う。
ここ数年、先進的な音楽家たちにとっての大きな課題の一つに、人間の〈声〉をどのようにして音楽の中に組み込むかがある。その課題に対する音楽家たちの答えは本稿にもいくつか挙げたが、他にもボン・イヴェールやフランシス&ザ・ライツのようにプリスマイザーを用いたり、ジャイアント・クロウやホリー・ハーンドンのように〈声〉を徹底的にエディットしたりと、様々な方法論が追求されている。
Sioneの『ode』もそういった潮流への一つの回答と言えるだろう。言葉と出会う一歩手前の、複雑な感情を内包した声/唄を探し求めるようなひたむきな冒険は、テクノロジーを取り入れながらもオーガニックな質感を重視しながら行われ、そのサウンドは上述してきた顔ぶれのどれとも違うものになった。言葉を運ぶツールではない、感情がそのまま空間を振動させるような声/唄がここにはある。