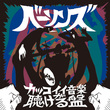“超新星”の背景にあるのはスプリングスティーン
――“超新星”という曲は、僕にはレクイエムのように響いた。鎮魂と、自分たちが新たに続けていく決意みたいなものを感じて……。
「この曲、ネタばれするとブルース・スプリングスティーンなんですよ。俺、全然通ってこなかったんですけど、ある時期からメチャクチャしっくりきて、ハマりだしたんです」
――スプリングスティーン、最高だよ。
「それまでは何となく『Born In The U.S.A.』(84年)のイメージがあって。なんかヤだったんですよ、ヒロイズムみたいなところが。だけど『明日なき暴走(Born To Run)』(75年)の“Thunder Road”とか、あの辺りのレコードをかけて、歌詞を読みながら聴いたときに、もっと早く聴いておけば良かったと思ったし、なんていうか、スプリングスティーンみたいなロックを鳴らしたいなと思った。今、全然流行ってないのは知っているんですけど。それをどうしてもね、40歳近い男たちがステージに並んで、オールドスタイルなものを汗かきかきやりたいなって思っちゃったんですよね。それと、たまたま友達が12月に死んで……という時期が一緒だったんですね……。とにかく、自分たちにデッドエンドなんてないんだ!って言いたかったんです」
――なんて言うか……わかる、としか言えない。
「俺、このレコードを作っているときに、スプリングスティーンはないぜって思いましたもん。もっとやらなきゃいけないこと、鳴るべき音っていうのは、この2017年にたくさんあるし、いろんなムーヴメントもたくさん出てきている……。ただ、俺たちに必要だったのが今はこれだったっていうのが、バンドをやってる人間ならではの良さだし、頭の足りなさでもある。それもフルテンでやるっていう」
――でも、映画「ハイ・フィデリティ」の原作者、ニック・ホーンビィが書いた、これまで生きてきたなかで好きになった31曲の歌にまつわる「ソングブック」というエッセイ集にも、それに近いことが書いてあったな。その本は曽我部(恵一)くんが薦めてくれてね。とにかくニックの人生で一番好きな曲は“Thunder Road”なの。
「おお~」
――で、やっぱりニックも書いてるよ。この感じがいま全然アウトなのはよくわかってるって。スプリングスティーン自体、揶揄されている存在というか、ステレオタイプなイメージがあるじゃない?
「同じ、同じ」
――プリファブ・スプラウトのパディ・マクアルーンが、“Cars And Girls”というシングル盤のジャケットからしてスプリングスティーンのパロディになっている曲を書いていて、〈人生は車と女の子だけじゃないよ〉って、88年の時点で言ってる。それはスプリングスティーンがまとっている曲のイメージについての批評なんだけど、やっぱり『Born In The U.S.A.』効果というものが大きすぎて、その所為でスプリングスティーンのイメージそのものが変わっちゃったところがある。でも、僕は未だにどこかスプリングスティーンのことが好きだし、曽我部くんもそうなんだって。だから曽我部くんとは気が合うんだ。スプリングスティーンはアリだよね、というのがお互いの共通項にあるから(笑)。
「あれはアリ。埼玉で育った男も“Thunder Road”を聴くと、あれ? 嗅いだことある匂いがするなあ、みたいな感じがして。それは英語や日本語とか関係なくて。すごいですよね」
――この町にいる限り行き止まりの人生だから、俺は必ずここを出ていく、っていう決意表明と存在表明の歌。だけど、お前(恋人)と一緒に出ていくというラヴソングでもある。
「最高だもんなあ。10代、20代前半では、まったく聴いてこなかったから」
――再発見というか初の発見なんだ。いまさら聴こうというきっかけはなんだったの?
「きっかけは、それこそ曽我部さんが“満員電車は走る”をソカバンで出して。こういう曲のあり方っていいな、みたいな話をしてたんですよ。要するに主人公が変わっていったり……あれ満員電車の風景じゃないですか。いいメロディーかどうか、なんていうことでもなく、トーキング・ブルースというか、この感じカッコイイすねえって言ってたら、曽我部さんが〈スプリングスティーンじゃーん〉みたいなことを言ったんですよね。そこで、そういえば俺、スプリングスティーンまるっきり知らないから聴いてみようと思って。しかも、安かったんですよ。帯も歌詞もついていて、400円くらいで売ってた。家で聴いたら震えましたよね。これは俺の歌だって」
――なるほどね。日本人だからワンクッションあるけど、スプリングスティーンの歌――あの歌詞とあの音が合体して、ダイレクトに英語がわかる人の耳に飛び込んでくるのは、僕らにとってのブルーハーツ状態だったと思うよ。
「絶対そうだと思うな。スプリングスティーンを家のステレオで聴いて、めっちゃいい~!ってなった、その温度で自分たちの音楽も作りたかったっていうのはありますね。特に“超新星”はそうですね」」
――その温度はメチャクチャ伝わってくる。すごくシンプルなロックだけど、やっぱりグッとくるんだよね。
「ほんとは、この曲じゃなかったんですよ。別の曲を作ろうと言って、スタジオに集まって、そしたらこの曲が出来た。で、そのまま録音」

――この曲の後半のギター・ソロがかなりグッとくる。
「中澤(寛規)さんすね」
――いいギター弾くなあ。ギター・ソロは、音だけで物語を語って説得力がないと意味がないけど、そういう説得力がものすごくある。
「今、流行ってる音楽って、みんなきちっと編集されてて、音がシャキッとしてるじゃないですか」
――そうだね。
「今の音楽のなかに入れてこの曲を聴くと、俺たち、異物感がハンパねえなって思います。みんなカチっとしてるんですよね。俺らは(編集で)直してないから」
――でも、だからこそ生々しさがある。今回のシングルには、ポジティヴな想いだけじゃないものが入っている気がする。“よそもの”の断ち切られるような終わり方には、むしろ不穏なものが感じられるし。
「でも、その憧れはありますね。そのまま断ち切ってもいいんじゃん?みたいな美学というか」
――日常が突然反転するということは、悪い方へ転がることもある。それも含めての人生。いろんな別れも経験している人たちが発する音だし、歌だなと。
「そうですか。負けの美学、ルーザーの美学というよりも、その人がそれでいいと思ったら口出さないでよっていう気持ちはいつも持っていたし、生き方やモラルは常識とかでは計りきれないところじゃないですか。それを最高じゃんと言っていいのは、やっぱり音楽だし映画だし、カルチャーなんです」
――ラモーンズのドキュメンタリー「END OF THE CENTURY」(2003年)とか観ると泣くもんね。
「泣きますね。結構いろんな音楽を聴くし、この時代にどんな音楽がスタイリッシュなのかも考えるけど、結局ロック・バンドだから、そこでドーピングせずにどこまで違う景色を観られるのかというのが、今の俺らのモチヴェーション。それをやってからじゃないと、自分のなかでは薄っぺらいものになっちゃう。俺はドーピングするぐらいならバンドをやらなくていい」
インスタに載せるための場所でないところで起こる、音楽の魔法
――バンドってことはつまり、そのメンバーで作るという一種の制約がどうしてもあって。
「そうすね」
――でも、そのメンバーだからこそ生まれる魔法というものもある。
「そうすね」
――それがバンドだから。このシングルはそれを持ったまま進もうっていうひとつの決意表明。
「もう最初の車種がどんな車なのかわかんなくなっちゃっているみたいなのが、一番いいなと思う。直しすぎて、いじりすぎて、最初はなんだったっけ、でもエンジンとタイヤさえあれば走るっしょ、みたいな。そういう存在でありたい」
――「the band 記録と記憶」でも、解散ギリギリまで行ったと明かされているでしょう? それでも続けたいと主張したのがベースの石原(聡)さんだったというのも、ドラマチックだなと。
「あいつは、ほんっとにポンコツなんですよ。マジで音楽的センスもないし、ただ、同じ町の近所だったというだけ。あいつがベースを弾かないほうがどれだけ曲がグル―ヴィーになるかもわかってるんです。だから、石原が〈やっぱバンドまだやりたいっしょ〉みたいに言ったときに、〈ウソだろ?〉と思って」
――(爆笑)。
「(両手を30センチくらいに拡げて)家にこの幅くらいのCDしかない奴がですよ(笑)。でも彼じゃないと意味がないと思っている俺もいるんですよね」
――自分の出自に忠実にやるのは、嘘がないから。それはやっぱり作るものに出るし、そういう説得力はすごくあると思う。僕はカルチャーとはすなわち継承だと思っていて。それは自分が経験してきたことや見た景色、影響を受けた人から教わったことを、それを見ていない人や知らない人に〈これは大事だから伝えたい〉っていう想いを込めて全力で伝えること。受け渡す行為そのものがカルチャーだから、GUGはまさに文化そのものですよ。
「これ、俺にしかわからねえだろうなと思わせる伝わり方。俺は(自分たちの歌を)そういうふうに受け取ってもらえるのが一番嬉しい。それは、なぜなら自分もそうやって受け取っているから。〈このレコードの本当の良さは俺だけにしかわからないだろ〉って。バンドもそういうものでありたいというのはありますね」
――カート・コバーンがマイナーな音楽をいっぱい愛していたじゃない? それらを紹介することで、ヴァセリンズとか全然スポットが当たっていなかったバンドが注目された。そういうのがすごく大事というかね。
「俺もそう思います」
――GUGが自主イヴェント〈全方位全肯定〉でHomecomingsやスカートと対バンしていることも、新たな出会いをもたらしているんじゃないかな。
「ひとつの体験として、〈俺、今日ひとりだったけど、このライヴに行ってよかった〉とか、ロックフェスの現場では味わえないもののほうが、俺のなかでは本当だったりするんです。そういうものを掴みとってほしいな、とは思いますね」
――シャムキャッツの夏目くんとホムカミの2人(畳野彩加、福富優樹)との座談会を読んだけど、ああいう熱いものを後輩たちが受け取ってくれているのは素敵だな、って。
「いや、俺は相当嬉しかったです。自分が好きなバンドで、レコードを買っていたバンドだったから〈マジか!?〉みたいな。その感覚はありましたね。この間、福富からDMがきたんですよ。〈僕、今散歩しながらGUGの『Home』を聴いてたんですけど、これはアナログにすべきです〉って(笑)」
――福富くんは〈バンドマンの中では日本で1、2を争うGUGファンだと思う〉と言っていたもんね。でも、そういう想いが素敵だよね。さっきの話じゃないけど〈これは俺にしかわからない〉というか。
「いつだって、そういう男の子に、そういうふうに聴いてほしいというのはありましたね。クラスで生きてんだか死んでんだかわからない奴に伝わればいいなと思って、やっていたな。体育祭でヘラヘラしている奴は聴かなくていいとさえ思ってましたね(笑)」
――いわゆるジョックスとは縁がなくていいと(笑)。
「そうそう。バンドとして、フェスには出たほうがいいとかそういう話にもなったりするんですけど、今の俺たちなら〈全方位全肯定〉をいっぱいやったほうがいいなと思う。それはやる側もピリッとするし、観る側の〈何を観せてくれんだ〉っていう視線から生まれる緊張感もあるし、そこで〈最高だ、来てよかった〉となればいい。音楽のなにがしかの魔法は、Instagramに載せるためのモノではないところで起こりえることが多いからね」
――カウンターであれ、ってことだよね。それは大事。
「俺は常にカウンターである人が好きです。それは、ブルーハーツもそうだし、甲本ヒロトもそうだし、曽我部恵一もそうですけど。メインストリームになりそうになると、カウンターに回るっていうか」
――そうは言っても、曽我部くんは〈俺、ヒット曲ない〉って本気で嘆いてるんだよね。
「なんか、俺は曽我部さんには長い映画をずっと観ているみたいに接しているんですよね。俺が、曽我部さんのことを日本の音楽家で一番好きな理由は、やっぱりあの人の人生や活動のあり方が人間臭いんですよ。いきなりソカバンになりましたって言って、ファンは〈マジか!〉って一回面食らう。それでバンドをやっていると思ったら、いきなりソロで『超越的漫画』(2013年)を出して、その後に『まぶしい』(2014年)と『My Friend Keiichi』(2014年)を作った。あの3枚は、俺の人生のなかで、ブルーハーツと同じくらいの衝撃でしたね。こんなにクエスチョンマークな作品を出すんだ!って。あのときはビビりました」
――でも、良い曲が入ってるんだよね。
「そう。去年、俺らが『Out Of Blue』というアルバムを作って、俺はちょっと曽我部さんの背中が近くに見えてきたぜと思ったんですよ。でも、サニーデイ・サービスは『DANCE TO YOU』(2016年)を出したじゃないですか。あれで、また遥か彼方に行かれたんですよね(笑)」
――でも、今日話を訊かせてもらった限りでは、GUG自体の調子は良さそうだね。
「いや、良いのか悪いのかもわからないですね。ただ、歌いたいことはあるから、それをやらないと次に行けないんです。本当に厭ですよ(笑)。この感じをずっとやっているなと思って。追いついたと思ったら、また遠ざかって、それを死ぬまでやらなきゃいけないと思ったら、ゲボでそう」
――大変だろうけど、期待しています。
「わかんないなりにやったジャッジこそが、バンドをやっているおもしろさや、本当のプロフェッショナルじゃないロックのおもしろさですしね。音楽って本当にふくよかなものだから、そこは正直にやっていきたいです」
――素生くんは他のメンバーに意見を求めたりもするの?
「ナカザ(中澤)は作家と言うよりもプレイヤーだから、俺が悩んでいても〈一回作ってみりゃあいいんだよ〉と言うけど、俺は〈いや、ここの一行が気に入らなかったら次が出てくるわけないじゃん〉となる。ただ、ナカザといっさん(石原)は俺が本当に閃いたときの顔を知っているし、その匂いを嗅げるということが、いまの3人でやっている理由かもしれないですね。目には見えないし、どんな匂いかも口では表現できないけど、でもある匂いを同じテンションで嗅ぎ取れる。バンドにはそれが大事なんです」
Live Information
『超新星/よそもの』リリース・ワンマン・ツアー 〈SUPERNOVA〉
2017年7月1日(土)名古屋・池下CLUB UPSET
2017年7月2日(日) 大阪・心斎橋JANUS
2017年7月17日(月・祝)東京・新代田FEVER
★詳細はこちら