スマホやSNSが普及したことも手伝い、今やグッと敷居が低くなった海外フェス。やはり〈グラストンベリー〉は死ぬまでに一度は訪れてみたいものだが、〈コーチェラ〉や〈プリマヴェーラ〉らが誇る垂涎もののラインナップも悩ましいし、アイスランドの〈エアウェイヴス〉のようにロケーションありきでフェスを選ぶのも楽しいかもしれない。
そこでぜひ、来年以降の選択肢のひとつに加えてほしいのが、米オースティンで開催されている〈レヴィテーション(LEVITATION)〉だ。今回は、まだ日本では馴染みの薄い同フェスの誕生経緯や知られざる魅力をはじめ、その首謀者としても活躍する不世出のロック・バンド=ブラック・エンジェルズの基本情報をおさらいしつつ、圧倒的ポテンシャルを秘めた彼らの最新アルバム『Death Song』の進化と変化に迫っていきたいと思う。
サイケを軸に、ツウなラインナップを提示し続ける〈レヴィテーション〉の強み
サイケデリック/ガレージの始祖的存在、13thフロア・エレベーターズの名曲から拝借した〈レヴィテーション〉は、もともと〈オースティン・サイケ・フェス〉という名前で2008年に誕生したフェスティヴァル。オースティン・パワーズも顔負けの極彩色と幾何学模様とペイズリー柄が入り乱れるドラッギーな世界観を連想するが、中身は(もちろんサイケを軸としつつも)至極真っ当なオルタナティヴ/ガレージ・ロックの祭典だ。初回は出演者が10組程度のコンパクトなフェスだったものの、2014年以降はフランスのアンジェでスピンオフ・イヴェントを開催、シカゴやヴァンクーヴァーでも〈レヴィテーション〉の出張編を行うなど、年々その規模を拡大し続けている。
驚くべきはミュージシャンも唸る通過ぎるラインナップで、まだ無名だった頃のリンゴ・デススターやウォーペイント、ノー・ジョイのような連中をいち早くフックアップしているほか、ゾンビーズやシルヴァー・アップルズ、そしてテキサスの大御所、ロッキー・エリクソン(2015年には13thフロア・エレベーターズとして48年ぶりのライヴも披露!)などのレジェンドも召喚。傑作ドキュメンタリー「DIG!」(2006年)でクローズアップされた、ブライアン・ジョーンズタウン・マサカーとダンディ・ウォーホルズの2組が顔を揃えた2014年のスロットはガレージ・ファン卒倒ものだったし、Acid Mothers Temple、Bo Ningen、Kikagaku Moyo、ZZZ'sといった日本人バンドが多数出演しているのもポイントだ。
また、2014年に〈レヴィテーション〉と改名して以降は、フレーミング・リップス、プライマル・スクリーム、スピリチュアライズドといった、サイケやスペース・ロックの文脈でも語れるビッグ・アーティストが次々と出演。続く2015年には、同年の〈コーチェラ〉で準トリを務めたテーム・インパラをヘッドライナーに抜擢するなど、チャレンジングかつ同時代性を感じられるブッキング・センスも頼もしい(ポスターのデザインもことごとくお洒落!)。しかし、ブライアン・ウィルソンによる『Pet Sounds』(66年)の再現ライヴも予定されていた2016年は、残念ながら大雨洪水警報により中止に……。その影響から2017年の開催は見送られてしまったが(フランス編は9月に開催予定)、10周年を迎える来年はよりパワーアップしてオースティンに戻ってくるそうだし、これまでの開催時期をふまえると日本のGWと日程が被る確率も高いため、旅行の目玉イヴェントとしても最適。気になった読者は、公式のSNSで随時情報をチェックしてみてはいかがだろうか?

〈レヴィテーション〉首謀者の正体は〈フジロック〉にも登場した現代サイケの旗手!
さて、そんな〈レヴィテーション〉の共同設立者として知られ、第1回から皆勤賞で出演し続けているハウス・バンドがブラック・エンジェルズだ。〈レヴィテーション〉の開催地、オースティンで2004年に結成された彼らは、これまでに5枚のフル・アルバムをリリース。1960年代で時計が止まってしまったかのようなラフで埃っぽいギター・サウンドを特徴とし、テーム・インパラやMGMTが頭角をあらわす以前から〈ネオ・サイケデリア〉の旗手とも称されてきた、ヴェテラン中のヴェテランである。バンド名は平松伸二のヴァイオレンス・アクション漫画が由来……ではなく、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのデビュー・アルバム『The Velvet Underground And Nico』(67年)に収録された楽曲“The Black Angel's Death Song”から採られたそうで、バンド・ロゴにもニコのイラストを刻み込むほどの筋金入りだ。
ブラック・エンジェルズの音楽性は、良い意味で一貫しておりブレがない。よってどの作品からアプローチしても問題ないのだが、しいて言えばオープニングを飾る1曲目がそのアルバムのトーンを決定づけていることが多い。2006年のデビュー作『Passover』の幕開けを告げる“Young Men Dead”ではブルージーでドローン的な重く引きずるギター・リフと、中心人物アレックス・マースによるマントラのごときヴォーカルがリスナーを得も言われぬ恍惚感で包み込んでくれるし、2作目『Directions To See A Ghost』(2008年)のオープナー“You On The Run”は、より重層的に編み込まれたギター・フレーズやノイズがもはや芸術的だ。なお、同曲はジム・ジャームッシュ監督の2009年作「リミッツ・オブ・コントロール」のサントラにも収録された。彼らの音楽を聴くと――そんな経験は無いはずなのに――テキサスの荒野をアメリカン・バイクで駆け抜ける自分の姿を妄想してしまうのは、きっと筆者だけではないだろう。
最初の出会いとしては、ブラック・エンジェルズにしては収録時間36分11秒とコンパクトな3作目『Phosphene Dream』(2010年)がオススメだ。バンド本来の持ち味を損ねることなく、キャッチーなコーラスや先の読めない超展開でフックを散りばめたサイケ・サウンドは、さすがオアシスやインキュバスの諸作で知られる売れっ子プロデューサーのデイヴ・サーディを迎えただけのことはある。
ちなみに、ブラック・エンジェルズは『Phosphene Dream』リリース後の2011年に、〈フジロック〉で初来日公演も実現。最終日のレッドマーキーとクリスタル・パレスで、セットリストを変えながら2ステージを披露していたので、彼らの暗黒酩酊グルーヴに骨抜きにされてしまった……なんて読者もいるのでは? そう、彼らの真骨頂はライヴにあると言っても過言ではないのだ。
歌詞に深みを、サウンドに厚みを増し、圧倒的なポテンシャルを秘めた新作『Death Song』
アートワークに初めてメンバーの顔をあしらい、サウンド的にもより取っ付きやすく間口を広げたものの、〈いくらなんでもコテコテ過ぎるんじゃないの?〉と言わんばかりにピッチフォークで4.9点の辛口評価を下された4作目『Indigo Meadow』(2013年)での迷走(ただし、後にセイント・ヴィンセントやスワンズ仕事で出世するジョン・コングルトンを、このタイミングで起用している点は評価したい)から早4年、6月7日に国内盤でリリースされたばかりの最新作が『Death Song』だ。
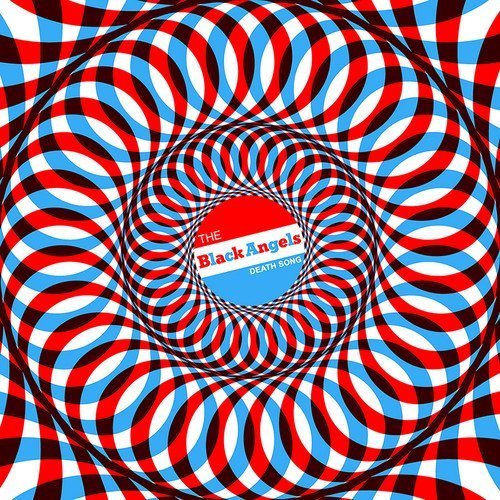
多作な彼らにしては過去最長のスパンだが、新たにシガレッツ・アフター・セックスやジョン・グラントを擁するNY&ロンドンのレーベル〈パルチザン〉とサインを交わし、バンド名の由来でもある〈Death Song〉と銘打っていることからも、その気合と覚悟は充分伝わってくる。〈ひたすら刷りまくれ/きみが使う紙幣を/ひたすら使いまくれ/きみが刷る紙幣を〉と呪文のように繰り返す冒頭の“Currency”は、拝金主義をユーモラスに描いたピンク・フロイドの“Money”を彷彿とさせるし、サビ以上に主張しまくりのアシッドなギター・リフが耳に残る“I'd Kill For Her”における、クライマックスに向けてバーストしていく重厚感たっぷりの演奏も素晴らしい。
今作でプロダクション全般を任されたのは、最新作『Crack-Up』(2017年)を含むフリート・フォクシーズの全作に加えて、シンズやバンド・オブ・ホーセズらUSインディー・シーンを牽引するバンドを数多く手がけてきたフィル・エック。レコーディングはシアトルと地元オースティンで行われたそうだが、最大の変化はズバリ歌詞である。〈どうせ何か唄うなら、意味のある方がいい〉とアレックスが明確に語っているとおり、人間関係、暴力、政治、宗教、戦争といった昨今の世界情勢ともシンクロする言葉の節々には、現代のアメリカを生きる市民としての不安や絶望感が滲み出ているような気がするのだ。楽曲自体はトランプ政権発足前に書かれたそうだが、たとえば、上述の“I'd Kill For Her”では歪んだヴァイオレンスの美学を持つ男のメンタリティーが綴られ、“Half Believing”においては現代社会の無関心やコミットメントがテーマになっている。
そんななか、13thフロア・エレベーターズ直系のリフが鳴り響く“Comanche Moon”では〈Inside out/Upside down/All around/Underground(裏返しに/逆さまに/あらゆる場所で/地下に隠れて)〉とラップを意識したような言葉遊びが飛び出すなど、決して一筋縄ではいかないメロディー・ラインがアルバムに躍動感を与えている。さらに、西部劇を思わせるアコギのカッティング&太鼓のビートに始まり、神聖なオルガンの音色で浄化されていく“Estimate”、クラウトロック的な奇天烈ループが病みつきになる“I Dreamt”、そしてバンド史上もっともスケール感のあるコードがかき鳴らされるロック・ソング“Medicine”まで、長らくアンダーグラウンドに留まってきたはずの彼らが、明らかに〈サイケ・バンド〉というレッテルから脱却しようと試行錯誤している形跡があちこちで垣間見えるのだ。
ブラック・エンジェルズの転機作にして、代表作となるポテンシャルを秘めた『Death Song』であるが、件の〈レヴィテーション〉に参画・出演してきた経験が、バンドを飛躍的に成長させたことは間違いない。アレックスもそれは自認しているらしく、公式インタビューでは次のように述懐している。
「〈レヴィテーション〉はサイケデリックの枠組み以上の人気と注目を得ることができた。このアルバムもフェスと同じことをやってのけてくれると思うよ。時流に合っているし、サイケデリックと言うよりはロックンロールなアルバムだと思うしね」
最近はやや食傷気味となりつつあった、サイケデリック・ミュージックのネクスト・レヴェルを提示し続ける〈レヴィテーション〉とブラック・エンジェルズ。同じくヴェルヴェット・アンダーグラウンドの曲名から採られた〈ATP(オール・トゥモローズ・パーティーズ)〉の名を挙げるまでもなく、音楽フェスとアーティスト/バンドによる共犯関係は、これからも我々リスナーにさまざまなヒントを与えてくれることだろう。
































