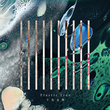清春
かつては黒夢のトリビュート盤『FUCK THE BORDER LINE』(2011年)にPlastic Treeが駆け付けたり、SNS上での有村とのやり取りでも先輩/後輩間の距離の近さが窺えるカリスマは、フロアにヘドバンの大波が巻き起こるプラのライヴの定番曲にして代表曲“メランコリック”に着手。清春作品でお馴染みの三代堅の編曲は、パンキッシュ&ラウドに激走するもともとの方向性に冷ややかなシンセを添えることで、透徹した美しさを加味したもの。そのなかで、主役は聴き間違いようのないあのヴォーカリゼーションで有村節を完全にモノにしている。歌い手としての記名性を改めて確認。

氣志團
木更津での主催フェス〈氣志團万博〉も恒例の5人組。結成10周年企画として開催した対バン形式のGIGシリーズ〈極東ロックンロール・ハイスクール〉にPlastic Treeを指名した過去のある彼らは、当然同郷の千葉代表として参戦。セレクトされたのは本作中で唯一のナカヤマアキラ曲“プラットホーム”だが、選曲の段階で王手をかけているというか、大幅なアレンジを加えることなく自身の持ち味を最大限に活かした印象だ。原曲の持つ性急さ、切なさ、疾走感を守りつつ、バンドのキャリアをもってしても色褪せることのない瑞々しさで駆け抜けている。

PELICAN FANCLUB
それにしてもフレッシュ! 冒頭から新鮮な驚きを与えてくれるのは、Plastic Treeをリスペクトする後輩アクトの1番手としてエントリーした4人組。オリジナル・ニューウェイヴ~ドリーム・ポップなどプラの面々とルーツも重なる彼らは、そもそもからして甘酸っぱいラヴソング“水色ガールフレンド”をよりユースフルに変換。アノラックなギター・ポップと骨太な質感の共存は、やはりテン年代以降の感覚だろう。輪郭を淡く滲ませたミックスもピッタリで、担ったのは昨年の有村のソロ作にも「ミックスもアレンジのうちのひとつ」という意識で招かれた釆原史明。

a crowd of rebellion
Plastic Treeをフェイヴァリットとして挙げる新世代の2組目として登場するのは、女性的なハイトーン/デス・ヴォイスのツイン・ヴォーカルを擁するメタルコア~スクリーモ・バンド。唐突にジャジーな意匠も挿入されるカオティック&ヘヴィーなバンド・サウンド上で、絶叫やグロウルが乱れ飛ぶ……そんな驚愕の“梟”はいかにもacorらしい仕上がりだが、一方で、有村と長谷川の共作によるメロディーの揺るぎない強度も際立ってくる。両者の〈イズム〉がガチンコでぶつかり合いつつもしっかり結び付いたこのカヴァー、その変容ぶりは“エンジェルダスト”にも迫る衝撃度。

GOOD ON THE REEL
Plastic Treeを慕う後人バンドの3組目は、ツイン・ギターを駆使してドラマティックなギター・ロックを鳴らす5人組。デビュー時のメンバーによる最終アルバム『Parade』(2000年)に収録の感傷的なミディアム“空白の日”にチャレンジした彼らは、鍵盤も交えてノスタルジーとスケール感を増強したアンサンブルと、素朴なエモーションを滲ませる千野隆尋のヴォーカリゼーションを通して沁み入るような感動を与えてくれる。シューゲイズなギターを従え、詞に込められた〈思い〉を昇華させるようなエンディングの余韻と言ったら! どこまでも青いリリシズムが眩しい。

R指定
V系シーンからエントリーした後輩世代は、いわゆる中二病的な〈病み〉〈メンヘラ〉感を真逆の躁状態へと転換する5人組。昨年はバンド/曲名が元で使用許可が下りなかった日本武道館をパスして幕張メッセ公演を成功させ、最新シングル“魅惑のサマーキラーズ”ではMCのほうのR-指定にそっくりな別人をMVに招いてバズを起こすなど、ある種のタチの悪さも魅力の彼らだが、今回そうした面は封印。オリジナルへのリスペクトをストレートに寄せた印象だ。楽曲が孕むセンティメンタリズムは損なわないままポップなメタル・マナーを徐々に解禁し、よりカラフルで軽快な足取りの“Sink”に。

THE NOVEMBERS
2012年の〈JAPAN JAM〉で有村、ヤマジカズヒデ(dip)と共演し、Plastic Treeのライヴ開演前の定番SEであるマイブラ“Only Shallow”やプラの“アンドロメタモルフォーゼ”といったシューゲイザー曲をプレイ。以降もフロントマンの小林祐介が有村のソロ作へ参加したりと良好な関係を築いてきた実力派バンドは、上述の思い出の曲に自身の美学を目一杯に投入。グロッケンやストリングス、柿沢健司(NATSUMEN)による生のフルート&トランペットなどが重なるオーケストラルなバンド・サウンドで、厳かな光の射す世界観を創出している。