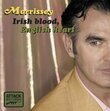耳で聴いたピープル・トゥリー
スミスをめぐる音楽の果実は、ここに一本のトゥリーを生んだ

ノエル・ギャラガーはTV番組「Top Of The Pops」で演奏するスミスに衝撃を受けてギターを始め、彼がマーにデモを渡したことからオアシスはデビューのきっかけを掴んでいる。で、〈楽器くらいは良いものを使えよ!〉と、この初作では自分のギターを貸したマー。以降も2人は共演を重ね、良き師弟関係を築くことに。 *吾郎

プレスリーが放った60sのヒット“(Marie’s The Name) His Latest Flame”と“Are You Lonesome Tonight?”を2曲もカヴァーしているスミス。他人の曲をあまり演奏しない彼らにとってこれは珍しい例だ。まあ、クリアトーンのカッティングとあの声が乗ればバンドのオリジナルにしか聴こえないんだけど。 *吾郎

デビュー前の配信曲でスミスをネタ使いしていた彼は、モリッシーの皮肉っぽい詞世界に憧れていると公言し、本作の影響源としてもバンドの名を挙げています。〈金と女〉をテーマにした“False Alarm”やラナ・デル・レイ客演曲など、歯痒くなるほど愛を信じない様子に触れ、その思いが本物であることを確信。 *山西

シンセ音を嫌っていることや叙情的でウィットに富んだ詞世界を大事にしていることから、〈現代のスミス〉との異名も持つロンドンの新人3人組。ねっとりした歌声と、アルペジオとカッティングを絡めたギター奏法を駆使し、モリッシー&マーの役割をひとりでこなしてしまうフロントマンに大きな可能性を感じる。 *柴田

スミスは60sのポップスに大きな影響を受けているが、こちらのシンガーもそのひとり。引退していた彼女はメンバーの熱心な働きかけで表舞台へ戻り、スミスの“Hand In Glove”を録音した。サンディのヴァージョンは凛として切迫感のあるヴォーカルが胸に突き刺さり、スミス版とはまた違った魅力で溢れている。 *吾郎

D.A.R.K. 『Science Agrees』 Cooking Vinyl/BIG NOTHING(2016)
モリッシーとマーの影に隠れ、イマイチ存在感の薄い残りのメンバー。でも、例えばアンディ・ルークは跳ねたベースを武器に、同郷ピーター・フックが率いるフリーベースへ加入したり、ごく最近もクランベリーズのドロレス嬢らとD.A.R.K.を結成したり。スミスではご法度だったエレポップを伸び伸びと披露している。 *柴田
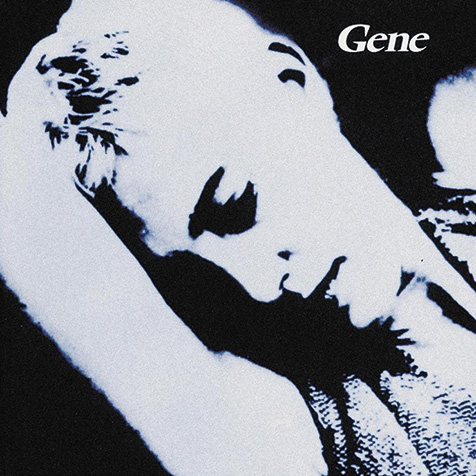
エコーベリーと並び、ブリット・ポップ時代にスミス流儀のギター・ロックを鳴らした4人。感傷的な歌やアートワークの雰囲気など、〈カムデン・スミス〉なる宣伝文句もズバリな正統フォロワーとして名を馳せるも、いつまでもそのイメージがつきまとってしまったことは、彼らにとって大きな不幸だったのかも。 *吾郎

マーク・ボランはマーにとっての英雄だ。初めて買った7インチも、初めてギターでマスターした曲もT・レックスだったとか。だからスミスの“Panic”が本作収録の“Metal Guru”にそっくりで、なおかつ同じコード進行なのはご愛嬌。なお、モリッシーもソロでT・レックス“Cosmic Dancer”をカヴァーしている。 *吾郎

幼い頃からスミスを愛聴していたというロード。夜遊び漬けの少女がたびたび登場するこの2作目でも、巧みな情景描写にバンドの影響が見て取れます。とりわけ、パーティーでの刹那的な昂揚感を交通事故の衝撃に例えたナンバーなどは、86年の“There Is A Light That Never Goes Out”をモロに連想させるもの? *山西

メンバーの音楽趣味を毎回ストレートに表現するPlastic Tree。なかでもスミスにもっとも接近したのが本作収録の“バンビ”で、ここでのリフは誰が聴いてもほぼ“This Charming Man”。翌年のシングル“瞳孔”でもマー譲りのカッティングを採用したり、彼らのスミス愛は尽きることがない。 *柴田

本作からのシングル“Stop Me”はスミスのリメイク。オリジナルはマーがソウル/ファンクを聴きまくっていたという87年の録音で、マーク版にはシュープリームス“You Keep Me Hangin’ On”を合体させて原曲の成分解説までプラス。その親切心が逆に一部のファンから反感を買うも、結果的には全英2位のヒットに! *山西

PANIC! AT THE DISCO 『Death Of A Bachelor』 DCD2/Fueled By Ramen/ワーナー(2016)
スミス“Girlfriend In A Coma”をライヴのレパートリーとし、バンドの名前もかの“Panic”から取ったと言われているP!ATD。そして、それを名付けたブレンドン・ユーリーのワンマン・ユニットとして活動中の現在は、50~60年代のサウンドを自己流に消化。解散後のモリッシーの歩みと重なって仕方ない。 *柴田
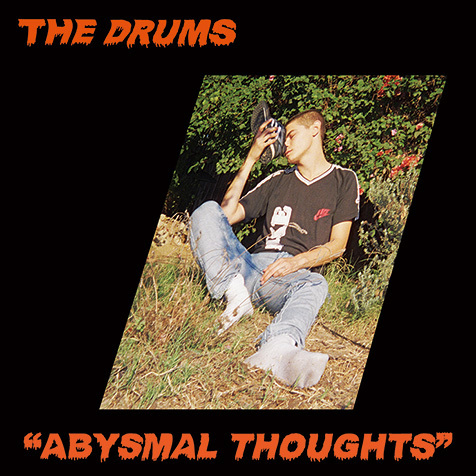
〈USが生んだスミスの最強チルドレン〉なんてキャッチコピーと共にデビューし、サイド・プロジェクトでも“Back To The Old House”をカヴァーするほどの優等生。一時期はシンセを入れて師匠と距離を置いていたが、この最新作ではフロントマンのソロ体制になり、頼もしくルーツ回帰を企てている。 *柴田

若き日のモリッシーが同バンドのファンクラブを作り、会報も発行していた話は有名だろう。楽曲から直接的な影響を読み取るのは難しいが、時を経てもモリッシーのドールズ愛は変わらず、2004年には彼の呼びかけで再結成が実現している。外仕事に消極的なモリッシーも、この時ばかりはライヴ盤をプロデュース。 *吾郎
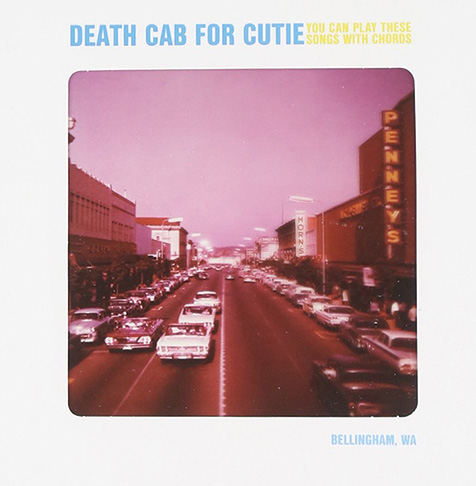
DEATH CAB FOR CUTIE 『You Can Play These Songs With Chords』 Barsuk(2002)
スミス曲のカヴァー例を調べていたら、USは大量にあるのに本国ではあまり見つからず。超名曲を演奏するのは気後れするというか、UKでのスミスはそういう絶対的な存在なのでしょう。で、本作での“This Charming Man”は原曲に忠実なアレンジが施され、大西洋を挿んだからこその無邪気さが微笑ましいです。 *山西