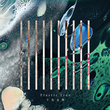昨年の20周年イヤーを通じ、改めて確認した〈自身らしさ〉と〈新たな可能性〉。ドアの向こう側にあるのは、その両方が密に交錯する最新型のバンドの姿で……
〈らしさ〉と〈次なる可能性〉
昨年はメジャ・デビュー20周年〈樹念〉と銘打ってさまざまな企画に取り組んできたPlastic Tree。その前段階のシングル“サイレントノイズ”(2016年)ではゲームソフト〈Collar×Malice〉とのコラボで〈Plastic Treeというバンドから連想される王道〉を提示し、その後はギラギラした毒っ気を孕むロック・バンドとしての在り方、映像喚起力のある淡い音像と、自身の根幹とも言える要素を濃厚に抽出した“念力”“雨中遊泳”という2タイトルを発表。さらには異なるシーンから12組が参加したトリビュート盤『Plastic Tree Tribute ~Transparent Branches~』も制作され、このバンドのベーシックな音楽性と楽曲が持ち得る新たな表情を改めて確認できた一年だった。
「『剥製』(2015年)以降、特に去年は曲作りでもライヴでもいろんな経験ができたなって。バンドの存在意義に向き合うことが多かったので、今回のアルバムにもしテーマがあるとしたら、単純に〈いままでの自分たちに勝てるのか〉っていうことだと思いますね。作曲、作詞、バンドに持ち込みたいアレンジ、プレイヤーとしての資質とか、そういうものを改めて問うというか。〈今のPlastic Tree〉をきちんと提案しようっていう」(有村竜太朗、ヴォーカル)。
そんな意識で完成させたPlastic Treeのニュー・アルバム『doorAdore』は、まさに彼らの〈らしさ〉と〈次なる可能性〉が反映された仕上がりだ。本作は、有村が「冒頭の3曲はアルバム作りの核となった感覚があります。デモの時点から、バンドでやってみたいこと、やりたいことが詰まってるなっていう印象でした」と語る3曲――陰影に富んだ幻想性を立ち上げるメランコリックなミディアム“遠国”、スピーディーにドライヴする“恋は灰色”、アグレッシヴなギター・リフと強力なグルーヴで聴き手を巻き込む“エクジスタンシアリスム”と、Plastic Treeらしさが更新された楽曲群をもって幕を開ける。
「“遠国”みたいな曲は、やっぱりプラにとってバンドの持ち味を伝えやすいのかなあと思って。今のプラに限らず、バンドに欲しい曲だなと思って作りました」(長谷川正、ベース)。
「歌詞は音から浮かんだ画を言葉と声で写実的に描いていった感じというか。恋愛の歌と言えばそうだけど、そこに偏ってるわけでもなく。〈君〉と〈僕〉が男女であることは確かなんですけどね。ただ、〈輪舞曲〉で踊ってるのが〈君〉と〈僕〉と同じ人でもなかったりして……男の人の立場のような、女の人の立場のような、恋愛模様をただ見ている人だけのような……自分のような、そうでないような。もちろん、蓄積された自分の感情も入ってるとは思うんですけど」(有村)。
「“恋は灰色”は、音の面で今のプラの自己紹介みたいな曲になったかなって。ベースだけになったり、ギター・ソロがあったり、キメのある展開で、メロディーも自分なりにフックを持たせることができて。緊張感のある曲ですけど、歌詞はウィットを若干持たせて、人によってはクスッとするような要素を入れました」(長谷川)。
「“エクジスタンシアリスム”はノリで作りました、空想MTRで(笑)。〈こういうイントロ、カッコいいよなあ~〉ってところから始まったんですけど、変わった跳ね方をしてる曲だから、先に進めば進むほど〈これ、イントロと関係あんのかな?〉ってなっていって」(ナカヤマアキラ、ギター)。
「最初聴いたときはロックでカッコイイ曲だなって印象だったんですけど、いつもだったらギターと一緒に弾き倒しちゃったりするところを、今回はファンクとかのグルーヴ――昔のミクスチャー・ロックっぽい感じに神経を使いながら録りました。ゴリゴリじゃなくて、もうちょいしなやかな、お洒落な感じ(笑)?」(長谷川)。
「“遠国”が〈画を描く〉だったら、“エクジスタンシアリスム”の歌詞は〈数式を解く〉みたいな感じ。このオケとメロディーには絶対にこの言葉しかハマらないはずだ、みたいなものを解いていくというか。そういう言葉を集めると、全体で見たときに絶対意味が生まれるんです。テーマとしては、〈バンドとそのバンドを好きで観ている人〉〈僕らと僕らの音楽を聴く人との関係〉ですね」(有村)。
耳新しさの背景
そして、“雨中遊泳”“サイレントノイズ”を挿んで登場するのは、佐藤ケンケン(ドラムス)の作曲による“サーチ アンド デストロイ”。クリーン・トーンの多様なギター・フレーズで緻密に編まれた、ポスト・ロック的なアレンジが新鮮だ。
「曲はまず4人で演奏することを思い浮かべて作るんですけど、ほかの3人はたぶん持ってこないだろうな、っていう曲をあえて持っていくんですよ。だからか、〈これ、どういう曲なの?〉っていつもみんなを困らせてしまうんです(笑)。俺としては〈すごくプラっぽいなあ〉と思う曲を毎回作ってるんですけどね。“サーチ アンド デストロイ”は自分ができる範囲のギターをデモで弾いて、〈あとはお願いします!〉って(笑)」(佐藤)。
「お願いされたらやるしかないです! 言ってしまえばこの20年ずっとそうで、総じて困ったことはないんですけど、この曲の物凄いダビング量は現実的ではないかもしれない(笑)。ポスト・ロックだとそれなりの人数がいてやってますけど、これはダビングに頼ってるんで、音色こそクリーンながら、手法としてはシューゲイザーみたいなものかもしれないですね。僕が5人ぐらいいると楽だなあっていう(笑)。歌詞は、いつもはわけのわからないものを意図して書くこともありますが、これは物語性を持たせたほうがいいなと思って。かつ、読んで意味のわかるもの。まあ、これはタイトル通りに〈サーチ&デストロイ〉ぐらいしかやれなくなった人の話です。その程度しか残されていない人の話」(ナカヤマ)。
続く“残映”もケンケンの作曲で、作詞も当人が担当。「いつもはリズムから曲を作るんですけど、これはコードと歌から作っていて。今回のチャレンジのうちのひとつでした」というセンティメンタルなミディアムのあとには、軽やかなギター・フレーズが幾重にも飛び交う“いろつき”が。ジャジーなアクセントも織り込まれたこの曲もPlastic Tree作品では耳新しい聴き心地だ。
「曲を作ったはいいけど、“いろつき”はいまいち設計図が描けなくて。だからこそバンドに持っていって、みんなにアイデアを出してもらった感じです。ギターの積み方はナカちゃんに任せたり、レコーディングしながら〈この曲は何が引っ張るのかな? ……ああ、ベースか〉って気付いたり。最後はセッション感覚で作った感じですかね。完成まで僕を悩ませた、プラにおいての自分の実験作です」(有村)。
バンドは最終局面へ
さらなる新曲としては、ナカヤマの作詞/作曲による狂騒のハードコア“scenario”と、有村が作曲/長谷川が作詞を手掛けたノスタルジックな風合いのエモーショナル・チューン“ノクターン”も。この2曲は普段の作風から作者が想像できるものと言えるだろう。
「“scenario”を作ったきっかけは、〈ライヴで盛り上がる曲を書こう!〉っていうものですね。聴いた人が音を聴いた瞬間に脳みそ使わないでノッてくれるぐらいのものにしようと」(ナカヤマ)。
「プラの王道っていくつかあると思うんですけど、“ノクターン”は僕が担当しそうな王道というか。これはちゃんと設計図が見えてたんで、それぞれのパートの良さをみんなストレートに出してくれるだろうな、きっとシンプルなバンド・サウンドになるだろうなと思ったし、自分の感情で作ったような曲だったから、世界観は最初から見えてましたね」(有村)。
「“恋は灰色”はデカダンな方向に振り切っちゃったんで、“ノクターン”の歌詞はもっと普遍的な内容にしたいなあって。曲自体の印象もそうだったので」(長谷川)。
ラストは既出の“静かの海”が郷愁感をナチュラルに引き継ぎ、切ない余韻を残して再生を終える『doorAdore』。〈扉〉と〈崇拝〉――全12曲から成る自身の音楽作品を象徴するものとしてこの言葉を選んだのには、こんな理由がある。
「今作のアートワークの象徴的なものはなんだろう?って考えたとき、〈ドア〉だなって。しかも結構視覚的に浮かんできたんです。アルバムの制作中、今、バンドは次に向かおうとしてるなっていう感覚が僕にはあったんですよね。バンドが最終局面に向かうようなイメージというか……去年は本当に今、バンドがやりたいことを全部やり尽くして過ごした一年だったので、今度はこの作品をもって次に行くんだろうなっていう。それを象徴する言葉が〈ドア〉なんです。正君が〈バンドは完成しない建物みたいなもの〉だって別のインタヴューで言ってたんですけど、改めて自分で見直してみても〈ああ、いい建物だなあ〉と思うので、それをもっと完成形に近付けたい。『doorAdore』はその第一歩かなと思ってます」(有村)。
Plastic Treeの近作を紹介。