
小西康陽の、時代に先駆けた新しさ
――そして、90年代に〈J-Pop〉が生まれるわけですね。しかも、その先陣を切ったフリッパーズ・ギターを見出したのは、ノンスタ終了後にポリドールに移った牧村さんでした。あと、音楽だけではなく、映画や文学などさまざまなカルチャーを引用するという渋谷系のアーティストが用いた手法も、ピチカートやワールドスタンダードは率先してやっていましたね。
「当時、小西くんの家で朝までレコードを聴く、という時間つぶしをよくやっていて。僕は朝になるとパンとミルクを食べて始発で帰ってた。それで帰るときに〈小西君は寝ないの?〉って訊いたら、〈このあと、友達が来るから京橋のフィルムセンターに行くんだよ〉って言ってた。彼は毎日、映画を観ていて、ものすごい量のレコードを聴いていた。その一方で、牧村さんという図書館みたいな人がいて(笑)、〈鈴木くん、これ観たら〉ってド・ブロカの『まぼろしの市街戦』(66年)のビデオを貸してくれたりするんだよ。何度も観たね」
――うわあ、また良い映画を(笑)。すごく文化度の高いレーベルだったんですね。ピチカートに関しては、当時、小西さん以外に、鴨宮諒さん、高浪慶太郎さんも曲を書いていて、3人のソングライター/アレンジャーがいるグループっていうのも珍しかったです。
「それって、ひとつのレーベルみたいなものじゃない。たとえばA&Mでは、トミー・リピューマやニック・デカロがアレンジをして、アル・シュミットがエンジニアを手掛けていた。音楽のプロダクションを組み立てるチームがメーカーやレーベルに必ずいるように、バンド内で、曲ごとに、曲作り、アレンジ、エンジニアの役割分担がされていた。そうしたシステムを教えてくれたのがピチカートだった。そのやり方に僕はすごく刺激を受けた」
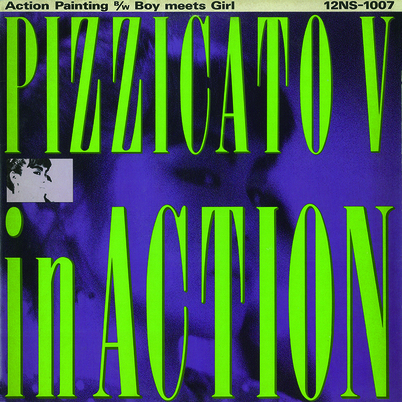
――そういうプロダクションのシステムに自覚的だったからこそ、日本のポップスについて意識するようになったともいえますね。
「渋谷系が盛り上がって、プロデューサーやアレンジャーが注目されるようになるけど、ノンスタの頃から僕や小西くんはプロデューサー志望だった。曲を演奏する、しないは関係ない。いい音楽ができればいいんだっていう感じ。それは細野さんや牧村さんの仕事を横で見て学んだことだったんだよね。当時、テントやミディ、水族館といった新しいレーベルが生まれていたけど、そこにはそういう視線を持ったアーティストって、実はあまりいなかったと思う」
みんな若くて、ゆらゆら揺らぎながら音楽を作っていた
――細野さんからの影響という点では、音楽面でいちばん細野さんの精神性を継承しているのはワールドスタンダードだと思うのですが。
「もちろん、強い影響をいまも受けているけど、ノンスタ時代は細野さんと同じことを知らず知らずのうちに考えていた。いつの間にか共鳴していたというか。細野さんが宮沢賢治のことを考えながら『銀河鉄道の夜』(85年)のサントラを作っていたとき、僕も宮沢賢治を読みながら“音楽列車”っていう曲を作ったりしていたんだよ。細野さんと宮沢賢治の話をしたわけじゃないのにね。ブライアン・イーノが始めたアンビエント音楽を、どうやってポップス感覚で咀嚼するかっていうのが当時の僕の大きなテーマだったけど、細野さんもそれに近いことをアプローチしていた」
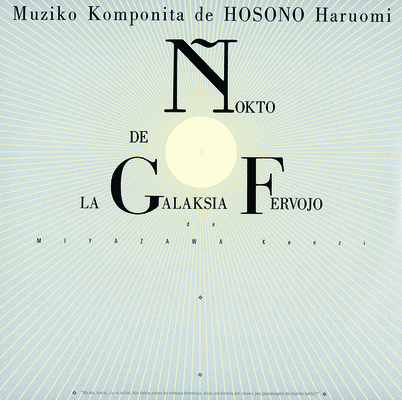
――アンビエントやミニマルといった現代音楽の要素を、ポップスに取り入れたのも先駆的でしたよね、一方、細野さんはF.O.E(フレンズ・オブ・アース)※というユニットを結成して、ヒップホップやファンクをエレクトロニックなサウンドでやっています。いわゆる〈O.T.T.(over the top)〉と呼ばれたアプローチですが、ノンスタのアーティストのなかで、いちばん激しいビートを鳴らしています。
「僕なりの解釈では、F.O.Eにはオジサンのたぎりが出てると思う(笑)。この時期、細野さんの作家性は、モナド・レーベルのほうにしなやかに投入されていて、F.O.Eでは世間が求める〈ポストYMO〉をやっている、激しく反抗しながらも。だから、当時F.O.Eを聴いて〈正直マッチョすぎるな〉と思ってたけど、いま聴くととってもクールに聴こえる。それは僕自身がオジサンになったことと、F.O.Eをずっと聴き続けてきたこともあるし、いまやエレクトロニックなダンス・ミュージックが世界中に溢れているからでもあると思う」

――当時、細野さんがヒップホップをやるというのは賛否両論ありましたね。しかも、ジェイムズ・ブラウンの来日コンサートでF.O.Eが前座を務めて、JBファンからブーイングを浴びるという、いまでは考えられない事件もありました。
「とにかく過剰な音、言わば〈無理をする〉っていうのが〈O.T.T.〉のコンセプトでもあるから。でも無理をしていたのは事実。基本的に細野さんはミーハーだからね。流行っているものにどう反応するか、細野さんなりに(デジタルなサウンドで)素直にヒップホップに反応していたんだと思う。それが強固な原理主義のJBファンには〈O.T.T.〉だった」
――そういうものがあったほうが楽ですからね。判断の規準になるような音楽。
「でも、そんなものはないほうが自由でいられるんだよ。ミーハーでいたほうがクリエイティヴでいられる。今回、モノリスのようなたいそうなボックスを作ったけど、ノンスタンダードは原理主義な存在ではなくて、ずっと揺らいでいたレーベルだったと思う。みんな若かったから当然なんだけど、ゆらゆら揺らぎながら音楽を作っていたんだと思う」
30年を経てわかった、〈プレJ-Pop〉なノンスタンダード
――レーベル名からしてノンスタンダードですからね。規準(スタンダード)を作らない。
「〈なんでもアリ〉っていうことだよね。ブックレットのインタヴューで戸田くんが〈バッタみたいに脊髄反射で音楽を作ってた〉と言ってたけど、それってアスリートみたいに考える前に反射的に身体が反応するっていうこと。そういうことができたのは、若くて頭が柔らかかったからだと思う。
さっき、初々しさがノンスタのエッセンスだったという話が出たけど、初々しくないと脊髄反射はできない。変に経験や知識があると、それにとらわれて動きが鈍くなるもの。だから、クリエイティヴに関していえば、知らないっていうことは強みでもある。細野さんは、そんな脊髄反射のことを〈音楽の即興性〉という言い方をするけど、細野さんは経験を重ねてもそれができる巧みの技を持っている音楽家。しなやかに。そういうのが、すごくうまい人」
――ノンスタがスタートした頃、細野さんは手ぶらでスタジオに入って、いきなり曲を作るというアプローチを始めていますよね。
「そう。何もない状態で始めて、降ってきた音楽をパッと捕まえる。そんな細野さんのレコーディングをときどき側で見ることができたのは、すごく財産になった。当時、自分のレコーディングをするためにスタジオに行ったら、横のスタジオで細野さんがやっていると、もう気になって気になって仕方ない(笑)。例えば“ピエトロ・ジェルミ”っていう曲(85年作『コインシデンタル・ミュージック』収録)を、ずーっとやってるわけ。僕が帰ろうとしている頃になっても、まだ終わってなくて。それで、おせんべいを食べてる(笑)。〈この人、何だろう!?〉って思ったね。細野さん、そんなことを毎日やってるんだよ。どんよりしているんだけど、細野さんのなかからキラキラしたメロディーやハーモニーがわいてくるのが側で見ていてわかる」
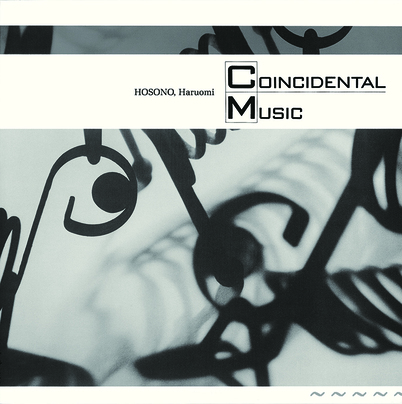
――細野さんにとってノンスタンダードは、時代への脊髄反射であり、若い才能への脊髄反射でもあったんでしょうね。そして、ノンスタンダードのアーティストにとってもそれは同じだった。
「ただ、僕個人のことを言えば80年代の音に対して、だんだん反射できなくなっていったんだよ。当時はMTVの全盛期で、そこで人気のあるアーティストの音楽を聴いても全然反射できない。だから、60年代ポップスとかもっと古い音楽に向かっていった。それは懐古趣味ではなく、自分を刺激する何かを探していたんだと思う。それは映画でも文学でもよくて、そこから何か新しいものが生まれないかと模索していた。それは細野さんもそうだったと思うし。そんな〈過去から新しいものを発見しよう〉という気分が、その後の90年代のリイシュー・ブームにも繋がっていったんじゃないかな」
――なるほど。ノンスタンダードはポスト・テクノというより、〈プレJ-Pop〉なレーベルだったということを、今回のボックスで改めて感じました。
「2001年にノンスタの作品をまとめてリマスターで再発したときは、そういった文脈で語られることはなかったんだよ。でも、30年経ったいまだからこそ、わかることは多いと思う。ノンスタンダードがなんだったのかを理解するには、それだけの時間が必要だったんだと思う」
































