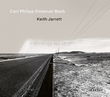Nils Petter Molvær
未来の余白:ECM ambient・minimal
エレクトリック・マイルス以降、ジャズのサウンドにエレクトロニクスが積極的に使われていくようになった。ECMもその流れと決して無縁でなく、エレクトロニクスを使った独自のサウンド・デザインを作り上げてきたと言える。エレクトリック・マイルスからフュージョンへと拡がっていった時流とはやや距離を置いたところで、ECMはアンビエント・ミュージックやミニマル・ミュージックと歩を合わせるように、その音響空間を作り上げていったのだ。
マンフレート・アイヒャーが好んだレキシコン社のリヴァーブを使った録音には、アコースティック楽器の凛とした響きを時にエレクトロニクスのように聞こえさせるマジックがあった。また、その逆もあり得た。シンセサイザーとプログラミングされたドラムが作る80年代のメリハリの利いたエレクトリック・ジャズ=フュージョンの裏側で、別のサウンド・デザインを作ってきたのがECMというレーベルだった。
そして、テクノ/ハウス以降のエレクトロニック・ミュージックのアーティストやDJたちは、ECMの諸作品をアンビエント・ミュージックやミニマル・ミュージックと同列に聴き、再発見をしていった。そうした解釈が、現実のECMのリリースにも影響を与え、作品として登場してきた最初のケースが、ノルウェーのトランペッター、ニルス・ペッター・モルヴェルの『クメール』だった。1998年にリリースされたこのアルバムは、サンプラーとプログラミングされたドラムが使われ、この当時フューチャー・ジャズと呼ばれたクラブ・ミュージックと親和性の高いサウンドだった。
モルヴェルは、 ノルウェー・ジャズのパイオニアの一人であるベーシスト、アリルド・アンデルセンを中心に結成されたマスクァレロのメンバーとして、1986年の『Bande A Part』から1991年の『Re-Enter』まで計3枚のECM作品に参加してきた。また現代音楽畑のパーカッショニスト、ロビン・シュルコウスキーとのデュオ作『Hastening Westward』もECMから1995年にリリースしている。だが、これらの作品とソロ作『クメール』の間には大きな飛躍があった。それは、モルヴェルとECM双方の変化を表していた。モルヴェルはこのアプローチに自信を得て、ECMから次作『Solid Ether』もリリースした。これ以降も、ミュートしてエフェクトの掛かったトランペットとダビーなビートのコンビネーションを自身のスタイルとしている。
そして、ECMも、クラシックや現代音楽あるいは民族音楽へのアプローチと同等に、同時代のエレクトロニック・ミュージック/エレクトロニカやポストロックが作り出すポピュラー・ミュージックのマージナルなところにあるサウンドへの追求を始めた。特に、モルヴェルとの共演でも知られるギタリストのアイヴィン・オールセットや、フードやルーメン・ドローンズといったグループなど、ノルウェーの音楽がその核の一つとなった。また、ピアニストのニック・ベルチェ率いるローニンやコリン・ヴァロン・トリオなど、スイスから登場した先鋭的なサウンドも積極的に紹介するようになった。
こうした中でも、特に近年はアイヴィン・オールセットの活躍が目立つ。アルメニア出身のピアニスト、ティグラン・ハマシアン、ノルウェーの電子音楽家ヤン・バング、トランペッターのアルヴ・アンリクセンの4人で作った『Atmospheres』や、イタリアのドラマーのミケーレ・ラッビア、トロンボーン奏者のジャンルカ・ペトレッラとの『Lost River』で聴くことができるのは、アンビエント・ミュージックへの新たなアプローチだ。これらの作品には、近年のアンビエントやニューエイジの再評価も経て、ECMが手掛けてきたサウンド・デザインを次に進めていく可能性を感じる。ECMはジャンルやフィールドの違いを超えて、サウンドの繋がりを示して来たレーベルでもある。その姿勢はいまも変わることはなく、そしてこれからも継続されていくだろう。 *原雅明