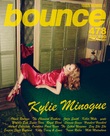新しさへの強迫観念から解放され、ただスタンダードな音楽をめざした
ーー確かにバンドのストーリーを知ったことで作品への気持ちが強まることはありますね。そこで、Turntable Filmsのストーリーを教えていただきたいんですけど、そもそも『Yellow Yesterday』(2012年)から次のアルバムまでこんなに期間が空くとは思っていました?
井上「うーん。前作の後にヴィジョンが特にあったわけじゃないですけど、なんとなく〈3年くらいは空くやろな〉っていうふうには思ってました。単純に(『Yellow Yesterday』が)出たときにメンバーが1人辞めたっていうのがあったし、そこで新しい人を入れても、土台作りに何年かはかかるだろうと。次にやろうとしてること、そのひとつが日本語で歌っていくことだったっていうのは後々わかっていくんですけど、即刻すべきことが見つかるとは思っていなかった」
ーーじゃあ、想定内のブランクだったんですね。
井上「まったく何も焦りはせずに(笑)。淡々と自分の流れでやってましたね」
ーー三船さんは前作『Yellow Yesterday』を聴いたとき、どんな感想を持ちましたか?
三船「前作もマスタリングは海外ですよね?」
井上「そうそう今回と同じハリス・ニューマン」
三船「録音は全部京都?」
井上「うん、大阪もあるけどメインは京都の一軒家で」
三船「でも日本で録った感じがしなかったですね。日本のミュージシャンって、洋楽とか邦楽とか便宜上の分け方みたいなところと、意図せずに向き合わなければいけないことがたびたびありますけど、あのアルバムに関してはそういう昔から決められている枠線をひょいひょい飛び越えていく感じがすごく痛快でした。バンドのツアー中に車でよくかけてましたよ。当時出てた日本のレコードとは一線画してて、あたりまえのロック・ミュージックをあたりまえに鳴らしている感じ。そこにすごく励まされました。日本に住んでる1億人のためだけじゃない、地球の残り59億人を無視していない音楽だなって。それがすごく楽しいし、シンパシーを感じました」
ーー井上さん自身は邦楽・洋楽という枠組みを意識したことはありますか?
井上「でも昔はそうでしたよ。『Yellow Yesterday』を作ってるときもそうだったかも。邦楽というか〈日本人が歌うであろうメロディーの感じやコード進行にはしないように〉とか。洋楽に向かうというよりは、日本人ぽくならへんようにしようってところかな」
ーー三船さんの印象通り、ドメスティックにはならないという志向性があったってことですね。
三船「英語で歌うことをファッションでやってる人と、それが心の中から出てきた表現である人とでは違うと思うんです。僕らはたまに〈そのサウンドで日本語で歌ってるのが偉い〉と言われたりするんですけど、別にそこは意識していない。井上さんの歌がすっと聴ける理由は、無理なく自然に出てきたものだからって気はしますね。それは新しいアルバムでも変わってなかったです。全曲日本語というのはトピックになる変化なんでしょうけど、僕のなかでは〈あんまり大した違いじゃないな〉って思っちゃいました。自然に聴けた」
ーー2人が京都で初めて共演されてた2012年の後半は、井上さんが日本語でも歌いはじめた頃だったように思います。
井上「そうだったかも! でも歌ってたのは自分のソロの曲だったかもしれない」
三船「いや、あの時“Cello”を演ってたんですよ」
井上「ほんまに! よう覚えてるなあ」
三船「僕ねえ、どうでもいいことをよく覚えてるんですよ」
井上「どうでも良くないわ(笑)!」
三船「ははは! いま言葉のチョイスをミスったな(笑)。あの日、井上さんが“Cello”を弾き語りで演ったときに、井上さんが変化したというよりは、聴き手として違うチャンネルで音楽を受け止められたっていうか、扉が開かれた感じがあったんです。〈これはすごく良いな〉って。だから、今回のアルバムを聴いたとき、“Cello”のイントロのタッタカタッタカってスネアの音を聴いて〈うぉー〉ってなりました。思い出もあるし、すごく感動した」
ーー井上さんとしても、いくつかの日本語詞の楽曲を作っていくことで自分の新しい回路が開けていくような経験はあったのでしょうか?
井上「それは実はいまもあんまりないんです。素ではあるけど、方法論はまだ見つけてないかな。だから、日本語で詞を書くことは苦しみながらですね。どこに向かうのが自分のやりたいことなのかはまだ探してるかも」
ーー“Cello”や“Nostalgia”を最初にライヴで聴いたとき、井上さんの声域が英詞の曲と違うと感じたんですよね。ピッチが低いなって。ただ、新作を聴いて、これまでの英語の声域で日本語詞も歌えているなと思いました。
井上「へえ! あんまりそこは考えてなかったですけど、“2steps”とか最初から高いから、あれの感じが嫌やなというのはあったかも。最初はもうちょっと楽さしてくれやって(笑)。そしたら全体的にキーが下がっていった。でも、高い音を封じようと思っていたわけではないですね。それよりも弦の響きとかをいちばん気にしています。〈この響きでこの曲のギター弾くの嫌やから、低いピッチやけどこっちでやろう〉というのが多い」
三船「うんうん。弦の張り具合で響きが変わって自分のテンションも上がるっていう、ギターをメインに使う作曲家にしかわからない世界がありますね。井上さんはライヴでギターを弾いてる姿を観てても〈ギターの響きから考えそうだな〉って思うから、僕より曲を左右する面が多いと思う」
ーー『Parables of Fe-Fum』から『Yellow Yesterday』を経て、新作『Small Town Talk』と、参照点がどんどん古い音楽になってきてるように思います。特に今回は新しさへの強迫観念みたいなものが完全に払拭されている気がして、そこがすごく心地良かったです。
井上「ああ、なるほど! ないです! 確かにない。前はその時代に出てきたバンドを意識してもしなくても、自分が感じる空気感や〈いまはこういうものが良いかもしれない〉っていうのに感化されていたところはあったと思う。そこからは少し解放されたなって気はします。結論を言っちゃえば〈したいことをすればいいな〉と」
ーーどうしてそういうふうに思えたんでしょう?
井上「〈したいこと〉のひとつだった日本語でやることと、新しいと思われるであろう音楽をやることが結びつかなかったんだと思います。それよりももっと違うおもしろさへと目が行っていた。それは、いまの6人編成で音像を作っていくこととか、バンド全体で曲をアレンジしていくこととか、外国の人と一緒にやることとか。前は新しさを入れていくことが〈おもしろさ〉だったけど、そこが変化したんです」
ーーふむ。
井上「あ! でも〈新しい音楽ってなんなのか〉がよくわからなくなったっていうのもあるかな。〈新しいことやってまっせ〉ってバンドがいてもポーズに見えて、〈その新しさって嘘ちゃうん?〉と思ってしまう」
ーー新しさとか同時代的であることは、インディー・ロックの美学のひとつだと捉えているんですけど、新作はそこに重きを置いてないですよね。だからこそ、これまでのSECOND ROYALからじゃなくonly in dreamsからのリリースということに合点がいったんです。
井上「やりたいこととおもしろいと思えることを突き進めていっただけなんですけどね。その過程でonly in dreamsと縁があって。ただ、古い音楽をやろうとは思っていなくて、〈スタンダードな音楽がしたい〉と思ってました。このアルバムはそれを作っていってるんじゃなかろうかって気はしてました。僕が諦めたのか解き放たれたのかはよくわからへんけど」
三船「今作はノイズが減ったように感じましたね。生きてるときの煩わしさみたいなものからクリアになってる。自分のなかにあるものをすっと出してるような気がしました。『Yellow Yesterday』にあった、何か見えないものに足をぐっと掴まれて動けない、みたいな感覚……僕のイメージですけど、そういうものがなくなって、雲が晴れてスパッとしてる感じがあって全体的にアップリフティング。それはジャンルとかテンポの話じゃなくてアルバムのムードとして。カラッとしてて湿気が少ない」
井上「そうかもしれない。これは人に委ねた面が多い作品だから。前は超自分のエゴ丸出しのアルバムやったけど、今回はある程度のところまでは自分で作って、そっから先はガンガン人に振っていった作品。ほんまにチームで作ったアルバムですよ。だから、言葉を選ばずに言えば〈人事〉みたいなものにさえ感じるアルバムでもあって。〈これTurntable Filmsのアルバム?〉って感じさえある」
一同「ハハハハ(笑)」
井上「サポートを含めたメンバー6人に、ミックスのサンドロ・ペリ、マスタリングのハリス・ニューマンも加わったチームで出来たものだって思う。僕は〈まあロゴくらいは書いたけど〉というくらい」