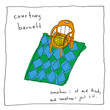――なるほど。ライヴについても話を聞かせてください。〈グラストンベリー〉に2年連続で出演したり、長期間に渡ってツアーを続けていますが、3人とも本当に楽しそうに演奏しますよね。これだけ長い時間を共に過ごしているなかで、円満にツアーを続けるための秘訣があるのでしょうか?
「うーん……。秘訣なんて別になくって、たぶん恋愛とか結婚みたいなものだと思うのよね。これだけ長期間に及ぶツアーだと、〈このへんでオフを取ったほうが良いかも〉っていうのが感覚的にわかってくる。それに、〈この人はいま疲れているだろうから、話しかけるのはやめよう〉って相手を思いやることも必要になってくるのよ。ツアーは確かに疲れるし、過酷だし、毎日同じことの繰り返しのようにも思えるんだけど、やっぱりファンの前でプレイできるのが楽しいから、その瞬間に全部吹っ飛んじゃうわね」
――フル・セットのライヴは初めて観たのですが、ブルーのテレキャスターを弾き倒す“Canned Tomatoes (Whole)”から一気にフロアがヒートアップしていったのが印象的でした。あなた自身もオーディエンスからの反応が楽しみな曲なのでは?
「もちろん! (日本は)初めての土地だし、言葉の壁だってあるけれど、オーディエンスが一緒にシンガロングしたり、手拍子したり、飛び跳ねながら楽しんでいる姿を見るとこっちまで嬉しくなるもの」
――あなたの独創的なフィンガー・ピッキングはどのようにして生まれたのですか?
「昔からこのスタイルだったし、私にとってはこれが自然なのよね。あと、昔バンドにいたときとは違って1人でギターを弾きながら作曲したり、歌ったりもするから、曲全体のリズムを感じやすいというのが理由かしら」
――右手のネイルにだけ黒いマニキュアを塗っているのは、フレットが押さえやすいなどの意味があったり?
「ノー。これといってストーリーはないわ(笑)。それこそ『Horses』のライヴで周りがドレスアップしていたときに、私はやることがなくてヒマだったから何となく塗ってみたの」
――今回のライヴで最大のハイライトは、やはり“Depreston”と“Pedestrian at Best”の2曲だったように思いました。世界中のオーディエンスがあなたの書いた歌詞を合唱する――という光景をどんなふうに受け止めていますか?
「やっぱり嬉しいことよね。私がおもしろいと思うのは、場所や地域によって盛り上がる曲が違ったり、フェイヴァリットに挙げる曲が全然違うことかしら。シングル以外の曲が一番好きだって言ってくれる人たちもすごく多いし。もちろんどの曲もベストをめざしてプレイするんだけど、オーディエンスの反応がバラバラだから新しい発見も多いわね」
――個人的に、“Depreston”はウィルコのジェフ・トゥイーディにカヴァーしてほしい曲なんですよね。あなたもさまざまなアーティストの楽曲をカヴァーしていますけど、逆に〈この人が自分の曲をカヴァーしてくれたら最高!〉と思うアーティストっています?
「いや~、それはちょっと恐れ多くて答えられないな……(苦笑)。でも、ジェフ・トゥイーディは確かに魅力的なオプションね!」
――ちなみに、ライヴ中に投影されていたアニメーション映像が可愛かったんですが、あれは“Dead Fox”のビデオと同じイート・ザ・デンジャー(Eat The Danger)が作られたのですか?
「あれは、いろんなアーティストの素材をミックスしたものね。特に貢献してくれたのがセレステ・ポッター(Celeste Potter、映像作家/イラストレーター)っていう友達で、彼女もメルボルンに住んでいるの。以前“Anonymous Club”のビデオを作ってもらったこともあって、とても才能のあるアーティストよ」
――“An Illustration Of Loneliness (Sleepless In New York)”は、NYで歌詞を書いたのですか? もしくはNYでの実体験をもとに書かれたのでしょうか?
「ええ、そうね。私の曲はほとんどが私自身の実体験から生まれているの。この曲に関しては、数年前に初めてNYに訪れたときの気持ちを歌っているの。あれだけ長い時間オーストラリアを離れるのは初めてだったし、ジェットラグもひどかったし、新しい国、新しい人々との仕事でナーヴァスになっていたときの心情が綴られているわ」
――じゃあ、大阪や東京での体験から何らかの曲のヒントは得られましたか。
「間違いないわね(笑)! きっとすごく興味深いストーリーになると思う」