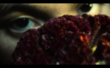〈自分だったらどうするか〉を想像するだけで全然違う
――クラムボンも初期から変拍子バリバリだったり、かつては〈え、ギターいないの?〉という反応をよくされたとおっしゃっていましたが、当時そんなふうに思われていたバンドが、それから20年経って武道館でライヴをやっていたりするわけです。なのでヤセイがいずれあの舞台に立つ可能性も十分あり得ることだと思いますよ。
松下「目標として常にありますね。僕が高校2年の時にモリシタくんといういちばん仲良かった奴の家で〈バンドやろうぜ〉という話をして、同じ時期に親戚の兄ちゃんにPearlの安いドラム・セットを譲ってもらってドラムを始めたんです。その頃に、そいつんちでクラムボンの“はなれ ばなれ”か“君は僕のもの”のどっちかのミュージック・ビデオを観て、〈あ、こんな人たちがいるんだ。カッコイイ〉と思ったことを武道館で観ている時に思い出して、エモかったっすねー(笑)。15年くらい前ですよ。そうやってドラム始める前から見ていた人にいまこうして知り合えたのは、伊藤さんがバンドを続けてきてくれたおかげだし、僕も漠然と〈バンドやろうぜ!〉となって、それからアメリカへ行って帰ってきて、それでもなお良いと思える音楽を続けていられたからこそですから」
――そうですよね。
松下「あのライヴの後に、曲を大事にしようっていうことを改めて思いました。僕、ヤセイとは別でZa FeeDoというバンドをやっているんですけど、ヤセイのアートワークなどもやってくれている沖メイがヴォーカルで、その子がいつもめちゃめちゃ難しい曲を書いてくるんです。Yasei CollectiveよりもよっぽどZa FeeDoのほうが難しくて、僕らは譜面を書かないので頭の中で譜面を起こして、覚えて……」
伊藤「譜面書かないんだ! すごいな」
松下「そうなんです。リズム・セクションはYasei Collecitive、僕と中西(道彦)と(斎藤)拓郎で、それプラス、田中“TAK”拓也というスタジオ・ワークなどもかなりやっている、アメリカに10年くらいいたすごいギタリストがメンバーなんですが、その4人で必死こいて覚えた曲を、ある日突然〈あたしこの曲もうやりたくなーい〉って言うんですよ。すごいがんばって、スタジオに何回入った?っていうくらいの曲を。突然そういうことを言ってやるのを止めちゃうんです。信じられないでしょ(笑)? それで、この間のクラムボンの武道館にその子も一緒に行っていたんですが、ライヴが終わった後に〈やっぱり曲は大事にしなきゃいけない〉とすごく言っていました。〈あの沖メイが! 良かったー〉って(笑)。真面目な話、僕らが高校の頃に聴いていたクラムボンの曲を基本同じ形で、同じ3人で演奏していても、やっぱりいいんですよ。全然古くない。ディスではなく、ちょっと難解に聴こえるリフを入れた曲をやって満足してる、いま勢いのあるバンドはたくさんあると思いますが、それを何年か後に聴いたらどうですかね。〈これダサくねぇ?〉ってなると思うんだけど、クラムボンやtoe、チャットモンチーもそうですが、曲が普遍的なんです。昔の曲っぽい感じがない。それってすごいことだし、なかなかできることじゃないですよ。僕らみたいに、アメリカでやってる最新の音楽に喰い付いてやろうと思って始めたバンドとしては、そういった先輩たちを見ると〈うわ、そうだよな〉と思わされちゃって。考え方が楽器を始めたあの頃にまた戻った気さえします」
――トレンドを追いかけて採り入れることは新しいものを作り出すという意味では大事だと思いますけど、それと同時に普遍性を持たせることも重要と。
松下「普遍性ってめちゃめちゃ大事だと思うんですよね。タワレコとかに並んでるCDで、名盤とされているものはどれもやっぱりいいですもんね。ビートルズ然り、ストーンズ然り、ジャズももちろん。ジャズの50年代、60年代の名盤とされる作品は大体いいですもん(笑)。でも90年代からいまに至るバンドの作品を、何年か後に全部フレッシュに聴けるかと言ったら、たぶん聴けないと思う。でもその普遍性を保っているクラムボンへのリスペクトは大きいですし、これからも30年40年と続けてくれたらなとすごい感じます」
伊藤「(クラムボンの)最初の頃は好きなようにやっていて、夜中のクラブでライヴをやっていたら、お客さんはどうノったらいいかわからないし、もう寝るしかないみたいな感じで(笑)、誰も観てくれてないというステージをだいぶ昔にやったことがあるんですね。そこで、単純に自分たちの曲を聴いてもらいたいなと思ったんです。好きなようにやるだけじゃ聴いてもらえないという経験を踏まえて、初期の頃の曲は出来ているというのはありますね。またそこから時間が経って、最近の曲ではドラムの面で〈歳を重ねて落ち着いてくるかと思いきや、手数が増えてるけど体力的に大丈夫?〉みたいに周りの人から心配されることもあります(笑)」
松下「そうそう、音数が増えてる感じがありますよね」
伊藤「そういう面を喜んでもらえていたらありがたいけど、評価に甘んじるようなことでは生き残れないから〈なんかこのドラマーおもしろい〉と思ってもらえるように、積み重ねてきたスタイル以外のことにもチャレンジしはじめています。だからやることが増えてきちゃってる状況も楽しく思える。それがフレッシュでいるということに繋がるかもしれない」
松下「いろんな音楽を聴いて、いろんなドラマーに目が行くことで、良い意味での嫉妬みたいなものは絶対に出てくる。例えばマーク・ジュリアナやキース・カーロックとかを好きで聴いてるんですけど、そもそも(彼らのプレイは)規格外じゃないですか、〈これって……〉みたいな感じなんですよ。それでもがんばって付いて行こうとして聴くか、〈この人は神様〉と言っちゃうか。でも僕は〈神様〉と口に出したら終わりだと思うんです。〈ブライアン・ブレイドは神様〉〈キース・カーロックは鬼〉みたいなことをみんな言うし、僕も言ったりするんですけど、それをオフィシャルなところで言っちゃったら絶対にダメだと思う。心の中で思うのはいいんですよ、実際に素晴らしいので。でもそれを口にしないで、さっき言ったように自分だったらどうするか、ということを想像するだけで全然違うはずで。モチヴェーションの問題ですけど」
伊藤「そうだと思う。とても悪い言い方をすると、そうじゃないと思考が止まっているということになりかねないので。あの人は神様だよね、すごいよねと言ってそれ以上何も考えないのであれば、それは尊敬の気持ちになるだろうかっていう」
松下「ちょっと宗教的な感じになっちゃうんですよね。それが見てて怖いなと」
伊藤「そうそう。それはそれでそのドラマーが商売をしていくうえで役に立つかもしれないけど、本当の意味でその人がさらにがんばれる糧になるようなものって、祀り上げることだけではない。それはキース・カーロックとマサナオくんと僕が同じ土俵に上がってしまっているという事実のなかで、キースとは会ったこともないし、一生会うことはないかもしれなくても、こちらが勝手に物凄い刺激と、考えるネタを与えてもらっていると感じられる。そういうことが起こるのがすごく良いことで」
松下「僕はこんな感じなので、上の人から否定されたり、出る杭は打たれる的なことがあって。それは甘んじて受け入れるけど、否定する前に僕がやっている内容を見てほしいというのはある。やってる内容を否定されるんだったら、それは考え方が違うということだから仕方ないですけど、ドラムやバンドのこれからとか、アメリカで学んできたことを日本に持ち込んでやろうとしていることに対して、〈この国では……〉という感じで叩いてくる人もいっぱいいて。僕は〈こういう考え方の人もいるんだ、勉強になる〉と思えるからいいんですけど、僕より若いこれからのドラマーだったら〈うわ~、こんなこと言われちゃった。がんばってきたのに……〉って思う奴がほとんどだと思うんですよ。だから僕はそういうことを後輩に絶対にしちゃいけないと思ってるし、同時にそうやって頭ごなしに叩いてくる人たちを納得させるにはどうしたらいいかをいま考えていて。そのためにはもっとドラムが上手くならないといけないし、そういう人たちが屈服するような何かを僕らのコミュニティーのなかで築き上げないと……それが数字なのか、ドラム・ヒーローになることなのか、それだけじゃない何かがきっとあると思うんですよ。それをいま探している」
――なるほど。
松下「だから、伊藤さんのように周りから尊敬されるドラマーたる所以は何なのかが気になっていて。日本の音楽シーンにおいて独特な立ち位置にいるんですよね。バンドマンなんですけど、〈“良い”ドラマー〉として同業者みんなが見てる」
伊藤「そうなの? 怖いね(笑)」
松下「楽器のこだわりもすごくあるじゃないですか」
伊藤「そういうことばっかり考えてるからね(笑)」
松下「ライヴをする際に、スネアやペダルしか持って行かずに他の機材はお任せで、みたいな感覚がわからなくて。僕だったら逆にスネアは何でもいいからシンバルは全部持って行きたいし、セットがダメならヘッドだけでも持って行って変えたいし。たぶんそういうことを考える最後の世代なのかもしれません、機材に対して」
伊藤「かつては自分の楽器でしか自信持ってできないというのは違うかなと思って、〈現地調達〉みたいなことも修行だと思ってやったことがあるけど、だんだんどうでもよくなってきて(笑)。いいじゃん自分ので、と(笑)」
松下「持って行けるうちは持って行ったほうがいいですよ(笑)」
伊藤「僕、楽器はよく変えるんだけど、〈こういう音が出したい〉というのは使う楽器やメーカーが変わってもだいたい統一できてるつもりではある」

――武道館のライヴはすごく音がいいなと思ったんですが、ドラム・セットにおいて何か特別なことはあったんですか?
伊藤「普段通りですよ。それこそああいう大きな会場においての生楽器はもう、普段通りの生音を増幅してもらうしかない。隅々まで届くように、というところはPAさんにお任せしています」
松下「マイク乗りの問題ですよね」
伊藤「マイクで拾われる前にいい音にするというのは工夫してるけど、チューニングの精度と関係なく、その会場に合った良い感じになることも……」
松下「PAが良ければ良いほどそうなりますよね」
伊藤「そうそうそう。現場次第なところはある。ドラムの音って主役ではないし、部品のひとつかもしれないけど、その部品ひとつに至るまでをできる限り質の良いものにしたい、という気持ちで向き合ってますけどね」
松下「そのこだわりはあの機材に出てますよ。PAさんとのやりとりも演奏を聴いていてわかる。クラムボンは伊藤さんのスネアのゴースト・ノートが聴こえなくなっちゃうと一気に違うバンドに聴こえるんですよ。〈ダッ〉とか〈タタタ〉といった小さい音がどれだけ出るか。そういう音はゲートをかけたりリヴァーブをかけたりすると潰されていって、音楽のなかの大事な部分が聴こえなくなっちゃうんです。そのぶん安定感は得られるんですよ。同じ音量で、同じダイナミクスでとなると。細かいニュアンスは武道館のような大きい会場だと出しづらい。生音はもう聴こえなくなるから、どのバランスで出すか、どういうチューニングにしたらそれが出るかをPAさんも自分たちの音楽の一部として考えて動かないと、あの音は出せないんです。伊藤さんが左手1本でやってる内容を理解しているPAさんじゃないと意味がないですから」
伊藤「そこはデビュー前からお世話になってる西川一三さんのおかげ。フィッシュマンズ、木村カエラ、最近ではゲスの極み乙女。など、超売れっ子です」
松下「大御所ですよ」
伊藤「でも本人はいたって飄々としていて、僕には〈好きなようにしなさい〉といつも言ってくれる。バランスを取って、〈こうしたほうがいいですかね〉と僕が機嫌を伺うようなことを言っても、〈いいから好きなことしなさい〉って」
松下「そういう関係性って大事ですよね。僕もいつもお願いしているPAの伊藤ハルクさんやエンジニアの葛西敏彦さんにわがまま言っていろいろ聞いてもらっているので、彼らがいない時は不安になります」