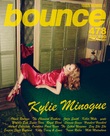【Click here for English translation of this interview】
美しい輪郭に惹かれて近寄れば、そこにあるのは曖昧模糊とした音世界。静かながらもアグレッシヴな創造性が誘うのは、たまらなくエレガント、けれど、どことなく不穏なサウンド・ジャーニーで……
重要なのはムード
実に5年超のインターヴァルを経て、牛尾憲輔のソロ・プロジェクト=agraphの3作目『the shader』が届けられた。前作で覗かせた現代音楽~ポスト・クラシカル志向がここではより顕著に表れており、尖鋭的なアプローチでもって普遍的なロマンティシズムを浮き彫りにしたような、深い奥行きを感じさせる電子音楽が展開されている。
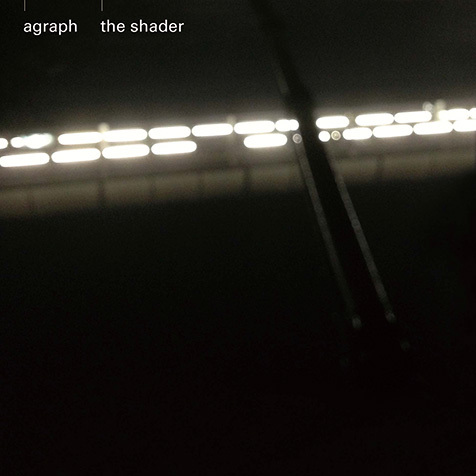
「セカンド・アルバム(2010年作『equal』)のマスタリングの日に制作を始めて、2~3年前には一度形になったんですけど、それはなんだか前作の続編みたいに感じてしまって丸ごと放棄したんですよ。その後に、リュック・フェラーリという現代音楽家の作品を聴いていた時期があって、彼をはじめ、スティーヴ・ライヒとか20世紀の現代音楽について改めて深く考えはじめた。そこからこのアルバムの方向に進むことができました」。
現代音楽を出発点としつつ、そこにベーシック・チャンネルのミニマル・テクノを結び付けるという着想からアルバムのコンセプトが浮かび上がったという。
「フェラーリに〈Presque Rien(ほとんど何もない)〉というミュージック・コンクレート、いまで言うフィールド・レコーディングのような作品があるんですけど、一切変わらないビートが鳴り続けるテクノと、鳴り続けるものが何もない現代音楽が自分のなかで繋がって。そこから、〈意識しているのかしてないのかわからないような音楽〉というイメージが頭をもたげてきたんです。メロディーとかリズムとかハーモニーが重要なんじゃなくて、そういう音楽的な要素を薪にして燃える炎みたいな音楽。そこから立ち上る雰囲気とか世界観だけ作ろうと」。
アルバムを一聴して驚かされるのは、ある種のオブセッションを感じるほど緻密に構築された音像だ。静謐なピアノの後ろにざらついたアンビエンスが敷かれ、メロディーは徐々に遠ざかり重低音に飲み込まれていく。コラージュめいた音の断片が次々と立ち現れては消え、テクスチャーは妙にひしゃげていたりモコモコしていたりもする。遠目には美しい輪郭が見い出せるが、近付いてみると掴みどころがなく曖昧模糊としている……そんなエレガントでいて不穏なサウンド・ジャーニーが待ち受けているのだ。
「例えばヴェイパーウェイヴって、80年代のフュージョンをカットアップしたりするじゃないですか。ソースがソースだからメロディーが綺麗だしハーモニーもリズムも緻密ですけど、そこを聴いているわけではなくて、あれってやっぱり質感とか雰囲気をおもしろがって聴いている。そういう方向をめざしたんです。ドラマティックなメロディーも強めのビートも出てきますけど、あくまでバランスを見ながら記号として置く感じ。重要なのは全体のムードなんです。そこが伝わればいいな……と思いつつ、作品として完成してしまえばあとは好きに聴いていただいていいんですけど」。
曖昧だけどソリッド
前2作よりも遥かにエクスペリメンタルな要素が色濃いし、現代音楽の実験性を近年のエレクトロニック・ミュージックの文脈で炸裂させているようにも受け止められる。だが、現行シーンを見据えたうえで新しいものを追求しているわけではないと彼は語る。
「自分の音楽が新しいことをやっているとは思わないですけど、自分の中では新しい気付きと発展があった。そういう個人的なことだと思うんです。現代音楽にも新しさを求めているわけではなくて、そういうものを聴くことで触発されるし、制作のガソリンになる。そこが重要なんです。基本的にagraphは時代性にコミットしないし、できない。いまのビートを採り入れることにも興味がない。それはLAMAの活動や電気グルーヴのサポート、劇伴制作、プロデュース・ワークといった他の仕事をやっていることも関係しているかもしれないですね。そういうプロジェクトは広く伝えるために時代性が必要になってくる。だからこそagraphは自分で好き勝手にやる研究開発部門みたいな場にしたいんです」。
とは言え、本作は現行のモードからまったく隔絶したものというわけではなく、2016年の新譜として享受できる質感を備えているのも確かだろう。また、この静かながらもアグレッシヴな佇まいは、前作以降のシーンの変遷――ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーやアルカといった先鋭的なアーティストが大きな人気をものにし、エレクトロニック・ミュージックの枠組みが確実に拡張された状況も影響しているようだ。
「やっぱり電子音楽は好きなので新譜も自然と聴いているし、その更新された耳で作ったものですからね。OPNの登場に関して言えば悔しいなとも思ったし(笑)、ああいう音楽を〈カッコイイ〉と言う人があんなにいるんだったら、こういう作品も受け入れられるんじゃないかとは考えました。そこを勇気の種にして、すごい売れる可能性もあるんじゃないかと思って(笑)」。
本作は後半に進むに従ってよりアブストラクトな様相を呈するのだが、ラストに配された“inversion/91”は余白を大きく取ったサウンドが展開される、他の楽曲とはちょっと異なる表情を湛えたナンバーだ。
「最後の曲は自分でもすごく良く出来たなと思っていて、ここで当初のコンセプトから解き放たれて新しい領域に進むことができた。曖昧なんだけどソリッドで確立した世界観を作りたくて、それがこの曲でできたし、次のアルバムの出発点になると思うんですよね。そういう意味で、今回は過渡期のアルバムですけど、だからこそ、こういうものは今後もう作れないというおもしろさがあると思います。改めてのデビュー作みたいな気持ちもあるし、自分なりの発明ができたのですごく満足度の高い作品になりましたね」。