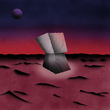歌詞は悲しい内容になるべくしてなった

――前年のEP『All's Well That Ends』を経て新たなメンバーも加わり、〈新生ロス・キャンペシーノス!〉を告げた作品だと言えますね。トムは当時、〈できる限り一貫性のあるダイレクトなアルバムを作りたかった〉と語っていたみたいですが。
「『Romance Is Boring』は大好きなアルバムではあるんだけど、ある意味でゴチャゴチャした作品だった。いろいろな方向にヴェクトルを向けすぎたとでもいうか……。だからこのアルバムでは、あちこちに行きたい気持ちをちょっと我慢して、一貫性のある作品を作ろうとしたんだ。あと、新しく入ったキムの側面を見せたいという想いがあったね。内容に関しては、ちょうど彼女と別れて傷ついていた時期だったから、ちょっと暗めの内容になっているんだ。レコーディングはバルセロナで、すごく綺麗な場所でみんな楽しんでいたけど、僕はちっとも楽しめなくて、ずーっと酔っ払っていた(笑)。だから、自分にとってもファンにとっても、このレコードはちょっとダークに感じるのかもしれない。でも、さっきも言ったように、僕の書く歌詞はすべて誠実で自分のフィーリングがベースになっているから、歌詞は悲しい内容になるべくしてなったんだ。だから、いまでもまったく後悔していない」
――この当時、ロールモデルにしていたアーティストやアルバムはありましたか?
「毎日聴いていたのは、ドリームの『Love Vs. Money』(2009年)だね(笑)。あれは本当に素晴らしいR&Bアルバムだから、影響されている部分もあるとは思うけど、あのサウンドをどこかで再現できているとは思えないなぁ……(笑)。『Hello Sadness』ではトムが初めてプロダクションに関わるようになったから、僕にはわからないけど、彼は何人かのアーティストから影響を受けていると思うよ」
――時を同じくして、音楽付きの季刊ファンジン「Heat Rash」※も発表していましたね。4号目で刊行がストップしているようですが、『Hello Sadness』でやり残したことがあったからこそのアウトプットだったのでしょうか?
※この記事で写真を交えて紹介されている(英語)
「そうそう。あれはかなり大変だったし、結構ストレスだったんだよね(笑)。バンドのメンバー7人全員がそれぞれアイデアや考え方を持っているわけだけど、曲作りのメインはトムと僕だし、それをすべて音楽で表現して発信することはできないから、あのファンジンを作ることにしたんだ。例えば、エレンは素晴らしいライターだし、フィルムメイカーでもある。彼女にとってもいい機会だったんだ。あと、僕たちには決してたくさんのファンがいるわけじゃないけど、ファンのみんなは心から僕たちのことを好きでいてくれているし、みんなも興味があるだろうし、喜んでくれるはずだと思ったんだよね。でも、実際にやってみると本当に大変でさ……(苦笑)。ロブもイラストレーターだから最初は楽しめたんだけど、ツアーをやりながらすべてをこなすには時間がなさすぎてね。それでストップしちゃったんだ」
このアルバムは一番のお気に入り

――この作品からはトムが共同プロデューサーとして関わっていますね。技術的にも精神的にも進化が刻み込まれているという点では『Hello Sadness』と地続きにある作品だと思うのですが、レコーディング・プロセスにより深くコミットするようになったことで、これまでとはどんな部分で違うアルバムになったと自負していますか?
「このアルバムは、僕の一番のお気に入り。それまでは、アメリカ、カナダ、スペインでレコーディングを行ってきたんだけど、このアルバムは自分たちが住んでいるエリアからたった2時間の場所で作業したんだ。天気は悪いし、特に楽しいこともない小さな街なのに、僕個人はすっごくレコーディングを楽しめたんだよね。毎日パブに行って、ノートに歌詞を書いて、ほろ酔いの状態でスタジオに戻ってその歌詞を曲になるよう組み立てていく……。そのプロセスが肌に合っていたんだろうな。自分たちでコントロールできたから自由だったし、歌詞もこれまで以上に自然に、好きに書くことができたのも良かったんだと思う」
アプローチ的には『Hold On Now, Youngster...』に近い

――そして今回の新作『Sick Scenes』は、原点回帰と呼べるほど解放的でパワフルな内容ですね! レコーディングはポルトガルのフリダンで行われたそうですが、その頃ポルトガルは〈UEFA EURO 2016〉で優勝を果たしました。当時の街の熱狂、あるいはエネルギーがアルバムにも反映されていると思いますか?
「ははは(笑)。イギリスはすぐに負けてしまったけれど、自分たちがいるときにポルトガルが勝利するというのはおもしろい状況だったね(笑)。かなり盛り上がっていたよ。でも自分たちがレコーディングをしていた場所は人里離れていて、他のメンバーは仕事を休んで来ていたから、半分ヴァケーションみたいな感じでさ。僕はレコーディングに集中するために、レコード・レーベルで働いていたのを辞めてポルトガルに行ったもんだから、一人でいた時間も多かった。Wi-Fiすらなくて、すごく寂しかったよ(笑)」
――多作なロスキャンにしては珍しく、前のアルバムから4年も空いていますね。トムは2015年にパフューム・ジーニアスのツアーに同行し、昨年はケレスの2作目『Drag It Down On You』をプロデュースしたりと大活躍でしたけど、それらの経験以外にはどんなインプットがあったのでしょうか?
「やっぱりトムのその経験が一番の大きなインプットだと思う。ヒップホップやR&Bのプロダクションの影響も出ていると思うしね。あとは、前のようになかなかレコーディングできない苛立ちとか、レコーディングしたくてたまらないという鬱積やパッションが、このアルバムにはダイレクトに反映されていると思う。だから、アプローチ的には『Hold On Now, Youngster...』に近いんだ」
――今回の新作にサウンド面で大きな影響を与えたアーティストや作品を教えてください。もしあれば、音楽以外でも構いません。
「うーん……どうかなあ。歌詞に関して言えば、最近はもっとメンタルの問題や鬱といったトピックを堂々と歌っているアーティストに影響を受けるようになったと思う。僕もそういうことには触れてきたけど、このレコードではそれがより心地良くできているんだ。そういったことに触れたいだけ触れられるようになったし、前よりもオープンマインドになれているんだよね」

――“5 Flucloxacillin”のシングルを含め、一連のアートワークに登場する若者たちはみんな目の焦点が合っておらず、まるでゾンビのようです。〈Flucloxacillin(フルクロキサシリン)〉は抗生物質の名前でもありますが、『Sick Scenes(病的なシーン)』というタイトルに込められた想いを聞かせてもらえませんか。
「タイトルに関して質問されたのは、初めてだよ(笑)! これは、イギリスの20代後半~30代前半の人々の状況を表しているんだ。日本ではどうかわからないけど、イギリスでは僕たちの親の世代がベビーブームで、すごく恵まれた状況で育ってきたんだよね。国から出る補助や手当ても良かったし、テクノロジーも発達しはじめた時代だった。それに比べて、僕たちが置かれている状況は真逆だ。保障も出なければ手当ても出ないし、不景気でさえある。日々の生活を送るのに、みんなヒーヒー言いながらがんばって働いているんだ。でも、iPhoneみたいなテクノロジーがあるからという理由で、上の世代は僕たちのほうが贅沢だと思っているし、ラクができてラッキーだと思っている。なのに、なんで人をガッカリさせるようなことをしたり、呑んだくれたりするのか? きっとそれが、彼らには理解できないんだ。その人たちから見た僕たちの行動、あるいは彼らをイラつかせる僕たちの言動や状況を意味するのが『Sick Scenes』なんだよ(笑)」
――『No Blues』の制作時、トムは〈レコーディングに入る前の何か月もの間、バンドを続けるべきかどうか悩んだ〉と明かしていましたね。しかし、いまもこうして素晴らしい新作をわれわれファンに届けてくれている。浮き沈みの激しい現代の音楽シーンにおいて、ロス・キャンペシーノス!が10年もの間サヴァイヴしてこられたのはなぜだとお考えですか?
「何もかもがずーっと同じだと、友情を保ち続けるのでさえ大変になると思うし、仲間同士で衝突が起きたり、飽きてしまったり、壁にぶち当たったり、いろいろなことがあると思う。でも僕たちの場合は、さっきも言ったように、メンバーの入れ替わりでそのたびに新鮮な気持ちになれたのが大きい。あと、ファンとの距離も近いんだよね。10年前にコンサートに来ていたファンがいまでも来てくれていたり、そこで知り合ったファン同士が結婚して、その子どもをライヴに連れて来ていたりさ……(笑)。あとは、レーベルのチョイスかなあ。大手のレーベルから〈もっとお金を出すぞ〉というオファーを受けたこともあったけれど、僕たちはそれを選択しなかった。メジャーで短い期間だけ存在するヒット作を作るよりも、僕たちは細々とでも長く活動したかったからね。そういった物事がすべて重なって今日まで活動できているんだと思うし、それがどんなにラッキーなことなのか、いつだって感謝を忘れないようにしているんだ!」