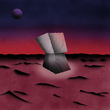キング・クルールはどこから来たのか?
――では、キング・クルールはどういったシーンから出てきたのかを、彼のディスコグラフィーを振り返りながら教えてください。デビューEP『King Krule』はイギリスではなくアメリカ、NYのレーベルであるトゥルー・パンサーから2011年にリリースされています。
小熊「それこそ僕は最初、野田さんのレヴューを読んでEPを買ったんですよね。今も面白いけど、当時のele-kingはシーンの最前線をものすごい熱量でキャッチしていたじゃないですか。それで、〈いよいよ出てきたか……2012年はここから始まる〉なんて書いてあるから、さぞかしヤバい音楽だろうと思って聴いてみたら、これがもう暗くて(笑)。このEPが出た2011年は、ジェイムズ・ブレイクのアルバム・デビューとも同じ年ですよね。音的にもポスト・ダブステップを通過した感じがあったし、タイムリーすぎる逸材が出てきた感じがしましたね」
――キング・クルールはデビュー以前、インターネット上でズー・キッド(Zoo Kid)という名前を使って作品を発表しています。この頃の楽曲は2013年リリースのファースト・アルバム『6 Feet Beneath The Moon』で再録されたものも多い。ファーストはどう聴きましたか?
天井「『The Ooz』を聴いた後だとオーヴァー・プロデュースな感じはするかな。プロデューサーのロディー・マクドナルド(Rodaidh McDonald)はXXも手がけていますよね。実際、キング・クルール本人はXXのファースト・アルバム(『xx』、2009年)を聴いてマクドナルドにプロデュースを依頼することを決めたと話していたけど、少なくともプロダクションに関してはマクドナルドの意向に従う感じだったんじゃないですかね」
小熊「わかります。マクドナルドは最近だとサンファも手掛けていますが、緻密で立体的なプロダクションに長けている人ですよね。だからEPのラフな感じは減退して、その分整っている。改めて聴くと、ギターのアプローチがXXっぽかったりしてカッコいいんだけど、個人的にはEPのほうがインパクトは強かった。あと、ファーストはタイミングに恵まれなかった印象はあります。2013年のUKはディスクロージャーの年じゃないですか。ポスト・ダブステップの流れが落ち着いて、ハウシーでポジティヴな反動があった時期。そのなかで、この作品が居場所を見つけるのは難しかったんじゃないかな」
――2013年頃からキング・クルールはエドガー・ザ・ビートメイカー(Edgar The Beatmaker)という名義を使いはじめ、ラッパーのアール・スウェットシャツと曲を制作したこともあります。そういった活動もあってか、ファーストから2年後の2015年に、アーチー・マーシャルという本名名義でヒップホップ寄りのアルバム『A New Place 2 Drown』がリリースされました。お兄さんと共同制作したアート・ブックのサウンドトラックという位置づけです。ループが多く、MPCで作った感じですね。この作品はどうでしょうか?
天井「サンプリングが多用されていて、トリップ・ホップに喩えられることが多いですよね。実際、キング・クルールはジャズをサンプリングしてビートを作るところから音楽制作を始めた経緯があるわけだけど、『A New Place 2 Drown』はケアテイカーがサロン音楽やクラシックのSP盤を執拗にサンプリングしてドローンやアンビエントのような音楽に作り変えている感覚に近いものを感じさせる。過去の音楽に対する愛着の深さみたいなところとか」
小熊「わかります。ヒップホップの才能もすごくあるんだなと思いました。フリーク・アウトしている印象もあるけど、実際にはプロダクションも緻密だし、トラックメイカーとしてのバランス感覚に秀でていることが『A New Place 2 Drown』を聴いてもよくわかる。それに、この作品はアンチコンっぽくないですか?」
天井「それはよくわかりますね。ドッシュやサトルの音楽に近い」
小熊「ですよね。インディー・ロック的なヒップホップというか。キング・クルールの音楽にはドリーミーでロマンティックな部分があるけど、それをヒップホップに寄せて表現すると、アンチコンっぽくなるんだなと」
〈夜〉を生きるロマンティストの魅力
――キング・クルールのアイコン的な魅力についてはどうでしょう? 彼の赤毛でスキニーな容姿は非常にフォトジェニックです。ミュージック・ビデオにも大抵、彼本人が出演しています。また、2013年には講談社のファッション誌HUgEの表紙にもなりました。
小熊「Instagramを見ていてもカッコいいですよね。奇抜な服を着こなせるルックスに、ダーティー・ヒーロー的な佇まい。そこが絵になる感じ」
天井「今時、〈酔いどれ詩人〉といってもあまり様にならないかもしれないですが、キング・クルールは例外ですね。昔のジャズメンのようなピシッとしたフォーマルなスーツ姿でもカッコいい。スタイリッシュだし、独特のエレガントさがありますよね」
小熊「あとは〈夜〉のイメージがありますよね。インタヴューでも〈俺は太陽よりも月が出ている時間帯に活動することが多い〉と話してましたし」
天井「ノワール感ですね」
小熊「そうそう。『The Ooz』の〈暗さ〉には、彼が不眠症に苦しんでいることも大きく反映されているみたいですし。さっきのXXXテンタシオンのくだりにも通じる話ですが、パラノイアックなイメージが絵になる、ある種のシリアスさありますね」
――ダークなロマンティシズム。彼はカート・コバーンモデルのムスタングも持っています。
天井「そういうことも衒いなくやれるところが良いですね」
――カッコつけなんですよね(笑)。若くして老成している感じ。
天井「そうそう。早熟というよりも老成」
―― “Dum Surfer”のビデオではゾンビに扮していて、そういうホラー映画っぽさやゴシックなイメージもありますよね。
天井「血生臭いことも歌うし、猟奇的な感じもあります」
小熊「新作のテーマがそれに近い」
――『The Ooz』の〈ooz〉とは、〈じくじく流れ出る、にじみ出る〉という意味の動詞〈ooze〉から来ているらしいですね。
小熊「アルバム・タイトルは〈爪が伸びる〉〈髭が伸びる〉みたいに、生きている内にいろいろなものが積み重なることを意味していると。本人はそれを〈自意識の創造、創造力のメタファー〉と表現しているけど、〈業が積み重なる〉みたいなイメージもあるんだと思う。生きている以上は、自意識からは絶対に逃れられないわけで。そう考えるとかなり救いがない(笑)」
天井「前作のタイトル『6 Feet Beneath The Moon』も〈手が届かない、憧れのもの〉という意味です」
小熊「そうそう。モティーフはロマンティックだけど救いがない。こういう作品を若い人が手掛けているのは、やっぱり衝撃的ですよね。EPが17歳の時で、ファーストで19歳、『The Ooz』でやっと23歳になったけど」
天井「年齢はジェイク・バグと近いのかな※」
小熊「そうですね。同じ早熟でも音楽的なスタイルは全然違いますが。キング・クルールは親御さんの影響が大きかったんでしょう。お母さんがファッション系、お父さんがアート系の人で、たぶんポストパンク世代ですよね」
天井「そうですね。お母さんや伯父さんもバンドをやっている音楽一家で、ルーツがポストパンクだというのは象徴的なように感じます」
全然知らなかったけどKing Kruleのお母さんがやってるブランドのシャツがカッコイイ!おもちゃ柄、ガゼル柄、扇風機柄など個性的過ぎて難度高めですが菅田将暉くんなら着こなせそう。 https://t.co/mIVQKPANDz pic.twitter.com/b2HMtSIifA
— monchicon (@monchicon) 2017年10月13日
――お兄さんはヴィジュアル・アーティストで、ファーストのアートワークを手掛けている。キング・クルール自身もアート・スクール出身です。
小熊「アーティスト・ファミリーなんですよね。個性的な服が似合うわけですよ(笑)」
過去と現在を繋ぐキング・クルールのサウンド
――サウンド面に踏み込んでいきたいのですが、キング・クルールはポスト・ダブステップ世代として現れました。一方で、過去の音楽との関係も深い。なので、過去と現代の音楽という2つの軸で考えていきたいと思います。まず、過去の音楽はどうでしょう? 声の特徴からトム・ウェイツと比較されることが多いのですが、これについてはどう思いますか?
小熊「むしろ彼が好きなのはジョン・ルーリーのラウンジ・リザーズですよね。EPの頃から、いわゆるフェイク・ジャズに受けた影響はサウンドに顕著に出ている」
天井「ノーウェイヴからの影響も大きそうですね。ジェイムズ・チャンスとか」
小熊「リジー・メルシエ・デクルーとかも好きそう。あと、“Logos”や“Vidual”といった曲はスーサイドっぽいですね。スーサイドは最近、また重要になってきている気がしませんか?」
天井「偉大なアーティストですよね。スーサイドのアラン・ヴェガもロックンロールへのオブセッシヴな愛着があった。エルヴィス・プレスリーやエディー・コクラン、ジェリー・リー・ルイス、あるいはチェット・ベイカーもそうですが、〈50年代のアメリカ〉はキング・クルールにとってもキーワードなんでしょう」
小熊「スーサイドでは特に“Dream Baby Dream”ですよね。この曲のドリーミーで危うい感覚が、影響力を増している気がします」
天井「サヴェージズやホラーズ、ファクトリー・フロアのニック・ヴォイドなど、近年、多くのアーティストがスーサイドの楽曲をカヴァーしていますよね。UKの中であのトーンが今、合うんでしょう」
小熊「マウント・キンビーも最近のインタヴューで、〈スーサイドのドラムマシンの使い方をパクろうと思った〉と語っていましたよね。一方で、キング・クルールは〈ローファイやDIYと呼ばれるのは嫌いだ〉とも語ってましたけど、それもわかる気がします。特に最近は、機材は良いものを使っているだろうし」
――『The Ooz』の制作ではアナログ・シンセを多く使ったと言っています。
天井「ヴィンテージ機材で〈お金のかかったローファイ音楽〉を作るという点ではヴィンセント・ギャロのようですね。ちなみに、ギャロもまた、ノーウェイヴの時代にジャン=ミシェル・バスキアとグレイ(Gray)ってバンドで活動していたわけですけど」
小熊「ギャロに近いというのは、そうかもしれない(笑)。ローファイやジャンクと呼ばれた音楽を更新している感じもあるし」
――現在の音楽との関係はどうでしょう? キング・クルールは〈周囲の友だちはみんなラッパーやビートメイカーだった〉と言っています。
小熊「グライムのようなイギリスの新しい動きとも、無意識的に繋がっている感じがします」
天井「そうですね。現在のUKにはヤング・ファーザーズもいますし。あと、キング・クルールが登場した背景には2000年代後半から2010年代初頭にかけての〈アンタイ・フォーク〉の流れもありそうです。キング・クルールの場合はフォークよりジャズ寄りですが、クラシカルでトラディショナルな音楽を独自の編集感覚で捉え直していくという点で、ライトスピード・チャンピオン時代のデヴ・ハインズやミカチューなんかとシェアするところがあったのかなと」
――なるほど。〈アンタイ・フォーク〉との関係は盲点でした。
天井「そういえば最近、カニエ・ウェストから〈スタジオに入ろう〉とオファーされたけど、プレッシャーを感じて断ってしまったと明かしてましたよね。カニエがフックアップしたジェイムズ・ブレイク、ボン・イヴェールというシンガー・ソングライターの系譜にキング・クルールを置いてもしっくりきます。UKのクラブ・ミュージックとモダン・アメリカーナを背景として、ジェイムズ・ブレイクとボン・イヴェールが重なり合うところにキング・クルールがいる、というか」
――先に挙げたアールもそうですが、OFWGKTA周辺との関係も深いですね。フランク・オーシャンと共作したというニュースもありました。一方でブリストルのヤング・エコーなど、新世代のメランコリックなインダストリアル・テクノやブリアル以降のベース・ミュージックとサウンド面で共有しているものが多いと感じます。
小熊「本人は最近のお気に入りに、ユセフ・カマールを挙げていましたね。UKジャズの最新モードも追っているんだなと。ところで、『The Ooz』には前作に続いてアンディー・ラムゼイがエンジニアとして参加しているじゃないですか。彼もディリップ・ハリスと同じく、マウント・キンビーと一緒にやっている人で」
天井「ラムゼイはステレオラブのメンバーだった人ですね」
小熊「そうそう。ステレオラブは少し前だと、ディアハンターのブラッドフォード・コックスやタイラー・ザ・クリエイターもお気に入りに挙げていて、最近ではマイルド・ハイ・クラブなどストーンズ・スロウの周辺にまで繋がっている気がしますけど、あの独特なメロウネスが巡り巡って『The Ooz』にも継承されている気がします。それこそ、ブラッドフォードがアトラス・サウンドとして発表した作品に、ステレオラブのレティシア・サディエールが参加していましたよね」
天井「アトラス・サウンドといえば、ブラッドフォード・コックスもロックンロールにハマってリーゼントにしていた時期がありましたね(『Parallax』、2011年)。ディアハンターの『Monomania』(2013年)にも50年代からの影響があった」
――ブラッドフォードとキング・クルールには共通項が多くありますね。
小熊「顔も似ていますしね(笑)。こうやって語り出したら止まらないくらい、『The Ooz』は縦軸にも横軸にも歴史との繋がりが見える。でも、最初に天井さんが話したように謎なところもメチャクチャ多い。それこそが、このアルバムを傑作たらしめる要因なんでしょうね」
――10年後に振り返った時にエポックメイキングな、里程標的な作品になるかもしれないですね。
天井「そうですね。『The Ooz』には既にクラシック、不遜なまでの古典感があります」