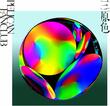オーディエンスと対話しながらライヴをしたいと思った
――『PFC』から次の『OK BALLADE』までは約1年間空いていましたが、その期間のバンドはどういう動きをされていたんですか?
カミヤマ「とにかくツアーだったよね」
エンドウ「僕は当時まだ学生だったので、ライヴに新幹線や飛行機で行くこともありました。卒論を書きながら(笑)」
カミヤマ「エンドウは忙しすぎて精神的に参ってたね」
エンドウ「そういう状況もあって、その頃は曲や歌詞が書けなかったんです」
カミヤマ「タワレコ限定だった『ANALOG』とは違って、『PFC』は本当の全国デビュー盤って感じだったし、ツアーを廻ったときに、まったく知らない人が僕たちの音楽を聴いてくれているんだということを実感できた。そこに対しての驚きもあり、じゃあ次の作品はどうしよう?というところから『OK BALLADE』の制作に繋がっていきました」
――ライヴの反応が作品に及ぼしたという面もありますか?
エンドウ「ライヴをやってみて、お客さんとステージが完全に分かれてしまっているという実感があったんです。聴いてくれているのかな?という不安もあったし、フェスとかで一斉にお客さんの手が上がるとか、そういう瞬間がなぜ僕たちは起きないんだろうと考えて(笑)。それもあって、もっとお客さんと距離を縮めてもいいなと思ったんですよ。
ステージとフロアに隔たりの無い空間を作りたいと感じたし、全国ツアーに行ったことが、すごくきっかけになりました。歌うテーマも、そんなにまわりくどくしなくてもいいなと思ったし、歌詞についてはかなり悩んで、メンバーにもすごく相談しましたね。そこで、自分としては完成していなかった歌詞を読んでもらって、メンバーから〈良いね〉と言われたのが、この作品のスタートになったんです。その歌詞の仮タイトルが“BALLADE”。そこから進むことができたので、『OK BALLADE』というタイトルになった」
――『PFC』にとっての〈謎〉のような、全体を貫くテーマはあったんですか?
エンドウ「〈いまの瞬間〉というものを、先人たちはいろんな形で歌っているじゃないですか。〈この瞬間しかないんだよ〉って。それを僕たちなりに伝わるように歌い、かつサウンドとしても『PFC』と対になる作品をめざしました。だから、リヴァーブを極力切ったし、余韻も残さないようにしたんです」
――ツアーを経て聴き手の姿が明確になったことで、そこへとダイレクトにアプローチしたんですね。
エンドウ「そうです。ライヴの雰囲気も変わってきましたね。僕たちがステージでやっているのをお客さんがただ眺めているような感じから、『OK BALLADE』を出して以降は、ちゃんと対話しているようなライヴになっていった。それが自分たちにとっても続ける糧になりましたし、〈もっと歌を聴いてほしい〉と思えた」
――メロディーや歌が立っている点は共通しつつも『OK BALLADE』に収録した8曲はサウンド的にはバラバラなところがおもしろいです。そのなかで、本人たち的に新しいアプローチができたという実感が特にあったものは?
エンドウ「作曲のうえでは、“M.U.T.E.”ですかね。もともと原案はあったんですけど、それをカミヤマくんがリアレンジしてくれて、かつライヴで化けた曲でもあって」
カミヤマ「“M.U.T.E.”は、それまでになかった感じが逆に受けたのかなと思います。その頃、僕のなかで80年代のファンク的な跳ねた感じが盛り上がっていて、ハイムってバンドがいるじゃないですか? 僕は彼女たちを好きで、こういうアプローチもできたらいいなと思っていたんです。で、やってみたら意外にすんなりとハマり、PFCっぽさを残しつつ、新しさを出せた。ポップな曲と激しい曲、そのどちらでもないというカードだったし、それがフックになったというか。お客さんの反応も良かったし、3枚目のカードも使えることがわかった」
エンドウ「最初にこの曲の原型を持っていったとき、僕はテクノ・ポップみたいなアレンジを想像していて。それをカミヤマくんがまったく違うものに仕上げてくれたことが、僕にとっては衝撃的だった。だから、バンドとしても何かが開けた曲。この頃からカミヤマくんがDTMを使い出し、ソングライターとしても貢献してくれるようになったんです」
――『OK BALADDE』のなかで、カミヤマさん主導の楽曲はほかにもあるんですか?
カミヤマ「2曲目の“記憶について”ですね。あの曲は、デスキャブの感じをもうちょっと日本らしくできないかなと考えて作った。それを念頭にスタジオで合わせていたとき、エンドウがメロを乗せてくれたんですけど、うまく合わさって盛り上がった。あと、個人的にレイジ・アゲインスト・ザ・マシーンがすごく好きなので、6曲目の“説明”――これは僕というより、みんなでセッションしながら作った曲なんですけど、いちばんテンションが上がりました」
――ミクスチャー・ロック的な“説明”はインパクトが大きかったと思います。
カミヤマ「4枚目のカードというか、激しいゾーンのなかでもちょっと異質な楽曲ですよね。それを出しても意外と自分たちらしくなるんだなと」

非現実的、だけど現実的な矛盾した場所を作りたい
――これまで3作を振り返って話してもらいましたが、海外のインディー・ロックからインスパイアされつつ、日本のロック・シーンのなかでどう響かせるかを模索しているスタンスは一貫していますね。
カミヤマ「そうですね。模倣というか、自分たちが日本にいるなかで、どうアプローチしていくかというのは裏テーマとしてあったような気がします」
エンドウ「以前は、海外バンドへの憧れと日本のシーンで活動することにジレンマもありましたけど、それはもうないです。3枚のミニ作を経てフル・アルバム『Home Electronics』を作れたことで、抜け出せましたね」
―― これまでの話を聞くと、バンドとしてすごく順調に発展してきたように感じたんですが、『Home Electronics』を作る前に迷走していた理由は何だったんですか?
エンドウ「タイプの違う楽曲をいっぱい作ってきたことで、逆に〈PFCらしさとは何なのか〉がわからなくなってしまったんです。そこで、バンド内での話し合いを重ねていったんですけど、最終的に辿り着いたのが、〈どうしてバンドを始めたのか〉というきっかけがいちばん大事だってことでした。僕とカミヤマくんは10代からずっと一緒にやってきたし、若い頃に聴いていたBUMP OF CHICKENとか、そういったバンドに憧れて自分たちも始めたじゃないか、という話になった。
初心に戻ったアプローチの曲を作りつつ、PFCとしていままでやってきたこと――過去3枚のミニを踏襲したアルバムにしたいねとなり、メンバー全員が満場一致した状態で制作に挑めたんです。4人の焦点やヴィジョンがだんだん合っていくことで、曲の質も高くなった。コード進行やアレンジにも妥協しないようにしたし、『Home Electronics』は〈これがPFCだ〉と宣言できる作品です」
――『Home Electronics』の達成感を経たことで、リスナーとの関係にも変化がありましたか?
エンドウ「リリース・ツアーのあと、9月と11月に東京の幡ヶ谷forestlimitというすごく小さいハコを会場に、〈ゼロ距離でバンドと一体となり音楽を楽しもう〉というコンセプトのフロアライヴ〈DREAM DAZE〉を開催したんです。それをやったことで、みんながPFCの何に魅力を感じて聴いてくれているのか、その良さみたいなものを確信できました。これがPFCの強味なんだな、こういうことをやりたいんだなって」
カミヤマ「〈DREAM DAZE〉も含めて去年いっぱいライヴをやるなかで、少しずつ見えてきたテーマというのが〈喜怒哀楽〉だったんです。それがライヴのキーになっていると思った。僕らもそれらをすべて出すし、お客さんにもすべてをぶつけてほしい。ゼロ距離ワンマンをやってみて、僕らとしてもすごくしっくりきたんですよ。お客さんもすごく喜怒哀楽を曝け出してくれていたし、これをやれるのが僕たちの武器なんだなとわかった」
――2回の〈DREAM DAZE〉に合わせて、 “SF Fiction”と“Shadow Play”という2つの新曲を配信でリリースしました。
エンドウ「僕が“SF Fiction”を作って、カミヤマくんが“Shadow Play”を作ったんですけど、“SF Fiction”では『Home Electronics』の物語性を引き継ぎつつ、曲の展開をもっと多くしたいと思っていました。だから、同じコード進行のパートが一切ないし、まるで嵐のように去っていく展開の多い曲(笑)。いままでの僕達だったらそれこそJ-Rock的というか、展開の多いものはむしろ避けていたんですけど、〈それもやっていいや〉と思えた。アルバムを経てこその1曲ですね」
カミヤマ「“Shadow Play”に関しては、結構ビートが特徴的というか、PFCにああいう後ノリな曲はあんまりなかったので、そこが軸になっていますね。あのビート感にデスキャブっぽいエモなコード感を乗せることによって、新鮮さが出たと思う」
エンドウ「どちらの曲も、ベーシックに『Home Electronics』のテーマ感――スペーシーというか非現実的でもありつつ、とても現実的でもあるという世界観が確立されたうえで出来たんです」
――〈現実と非現実〉という二面性が、現在のPFCにとってのテーマと言えそうですね。
エンドウ「2回目の〈DREAM DAZE〉では、さらに参加型と銘打って、みんなで歌ったり叫んだりできるようにしたんです。普通のライヴハウスだったら歌うことはあっても、シャウトを一斉にすることってなかなかないと思うし、そういう非現実的なことが起こる、だけど現実的な場所をめざした。バンドは目の前でリアルに演奏しているわけだし、そういう矛盾した空間を作りたいと考えています」
――そして、ミニ・アルバム再現ライヴを経てのツアー最終公演は、〈FUTURE〉と題されたMt.RAINIER HALL SHIBUYA PLEASURE PLEASUREでの大編成ライヴ。これは、PFCの未来を垣間見られるパフォーマンスと期待してもいいのでしょうか?
エンドウ「そうですね。PFC史上初めての試みなので、どの作品を聴いてきた人も衝撃を受けるものになるとは思います。僕らもやったことがないので想像でしかないんですけど、かなり壮大な、それこそ〈SPACE OPERA〉というツアーの名前に恥じない規模感になると思う」
カミヤマ「ホールでの演奏を決めたのも、小さいキャパでのフロアライヴをやってみて、逆にホール・サイズだったら何ができるのかを考えたくなったからなんです。いろいろ試行錯誤しながら準備していますよ」
――詳しくは当日のお楽しみ、と。期待しています!
エンドウ「2018年のPFCはこれまで以上にヤバイですよ。自信しかないのが、むしろ僕は困っています(笑)。誰に何を言われても、もう関係ないなと思えたし、どうでもいい。だから無敵状態ですよ」

Live Information
PELICAN FANCLUB ONEMAN LIVE 2018〈SPACE OPERA〉
2018年1月19日(金)大阪CONPASS -ANALOG-
開場/開演 19:00/19:30
前売り 3,000円(ドリンク代別)
2018年1月20日(土)愛知CLUB ROCK’N ROLL -PELICAN FANCLUB-
開場/開演 16:30/17:00
前売り 3,000円(ドリンク代別)
2018年1月22日(月)東京GARAGE -OK BALLADE-
開場/開演 19:00/19:30
SOLD OUT!
2018年2月4日(日)東京Mt.RAINIER HALL PLEASURE PLEASURE
開場/開演 17:00/17:30
前売り 3,500円(ドリンク代別)