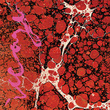ポイント1:『Beyondless』は100%アナログ・レコーディングである
本作のサウンド・プロダクションは極めてシンプルだ。クリアで豊かな階調を持ちながら、全楽器が同時に鳴らされる瞬間のロック・バンドらしいガッツに満ちた音。これはレコーディング・スタジオにあったオープンリールを使ったことによるものだという。
「これまでの作品でもアナログ・レコーディングをしていたけど、100%アナログというわけではなかったんだ。でも今回は素晴らしい機材がスタジオにあったから、初めて100%テープで録音した。音の良さはもちろんだけど、アナログ・レコーディングが生み出す制限もまた魅力的だった」
ポイント2:『Beyondless』は零れ落ちるものを捉えたかのような作品である
本作におけるソングライティングは極めてシンプルだ。アークティック・モンキーズやceroの新作では、ラップやR&Bの隆盛に呼応する、リリック先行で綴られたかのようなフリーフォームな印象のヴァースが特徴的だが、それに比べこの『Beyondless』収録曲はいずれもオーソドックス。どのラインもコードに対してしっかりとメロディーを乗せ、そこに歌詞を当てはめている印象である。
楽曲構成としても〈ヴァース/コーラス〉を中心に時折ブリッジが挿入される程度の極めて単純なものとなっている。こうしたアプローチは、エリアスのメロディーメイカーとしての力を生かすという点、そして流行に迎合しないバンドの姿勢をプレゼンテーションするという点から最善の手法と言えるだろうが、下手をすれば古風な印象を与えてしまう危険性を持っているのも事実である。
しかし、そうしたオーソドックスなソングライティングにもかかわらず、本作の収録曲がこの2018年において新鮮に響いている。
その理由の一つは、エリアスのヴォーカリゼーションにある。コードに対してあえて不安定な音を挟み、聴き手を焦らすようにしながら、落ち着くべきところに落ち着く節回し。言ってみれば聴き手のマゾヒズムを喚起させるような、サディスティックなヴォーカルだが、これがエキサイティングなのだ。
そしてアメリカーナに接近した前作『Plowing Into The Field Of Love』や、マーチング・チャーチでの活動を下敷きにしたかのような〈ロック以前〉への接近も見逃せない。スネア・ロールの多用によるマーチング・バンドのようなリズム・アプローチを始めとした、平凡な8ビートの回避に加え、管弦楽器の導入も含めたアレンジメントは、ロックンロール以前の音楽への逆アプローチのようでもある。
さらには、揺れ動くBPM、スケールや12平均律からはみ出すような節回しやギター・プレイ、神話や宗教的な神聖さと猥雑さ、SF的なものが同居する歌詞の世界観。“Thieves Like Us”での、反アカデミズム的な芸術運動だったラファエル前派への言及。
それらはロックンロール以降、産業化され、効率化、公式化、機能性の追求がなされていったポップ・ミュージックの歴史と現状に対するオルタナティヴと解釈することもできるだろう。
「作品を作っていくうえでは、何かを明らかにしようとか、何かと向き合ってどうしようということではなく、模索していくミステリー・ツアーのようなやり方のほうが楽しくて魅力的なんだ」
それはDAW上のグリッドに沿って、品質保証済みのカラー・パレットから音色を配置していく創作とはまた違う、探求の旅のようなものなのだろう。Spotifyの各プレイリスト入りを目指して音楽を作るような〈現代的な戦略性を持った最先端アーティスト〉とは対極にある、アートを追求するロック・バンドの姿。それは古くも新しい。そして何より複雑性に満ちていながら、単純明快だ。
「『Beyondless』は抽象度が高く複雑な作品でもあると思うと同時に、これまででいちばんシンプルな作品だとも思うよ」