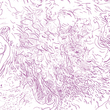ジャズ・ミュージシャンが21世紀、どうやって食っていけるのか?
野田「ユナイティング・オブ・オポジッツは、ジャズっていう感じじゃないんですよね。ダウンテンポ系の気持ち良さもあるし」
小川「まあ、ちょっと亜流ですよね」
野田「UKジャズ自体が亜流なんですけど(笑)。そう考えると雑種っぽくて、UKジャズらしいのかもしれない。ロンドンでジャズっていうと、実はほとんどの場面では、いまだにマイルス・デイヴィスの昔の曲のカヴァーをパブやカフェで演奏しているようなものなんですよ。だから、ジョー・アーモン・ジョーンズとか、こういう人たちって、UKのジャズのなかでも特殊なんです」
小川「異端でしょうね。コンサヴァティヴなジャズ・クラブでは演奏できないので、クラブとか、ウェアハウス・パーティーみたいなところで活動する機会を得てきたみたいです」
――〈ジャズ・リフレッシュト〉というイヴェントがあるそうですね。
小川「それもそのひとつですね。〈ジャズ・リフレッシュト〉は、西ロンドンのブロークン・ビーツとの繋がりもあったイヴェントおよびレーベルなんです。そこがカイディ・テイタムやリチャード・スペイヴン(ドラムス)の作品を出していて、次第にいまのヌビア・ガルシア(サックス)やダニエル・カシミール(ベース)といった若い人たちにも活動の場を与えていったんです。
もうひとつヴェニュー的なところでは、北東ロンドンのトータル・リフレッシュメント・センターという場所でもミュージシャンのアフターアワーズ・セッションのような感じで、通常のギグの後にフリーで参加できるジャム・セッションをやっているようですね。ティム・デラックスにインタヴューしたときに、他のミュージシャンとの交流がそこで生まれていると言っていました」
野田「〈戦略〉という言葉をあえて使わせてもらうと、ジャズの演奏者がサヴァイヴする戦略として、それはすごく有効だと思うんですよね。そこを、UKはうまくやっている。ジャズのミュージシャンが21世紀、どのようにして食っていけるのか?という問題に対して、いつまでも50年代のジャズを酒場で演奏するのか、あるいはもっと別の表現でやっていくのか、二つ選択肢があると思うんです。
後者は、いろいろな人たちと交流して、しかもエレクトロニック・ミュージックや他の音楽とも交流することによって違うものを生んで、そこに自分たちの演奏の場もちゃんと作っているように見えるんですよね」
アメリカより密な、ジャンルを超えた交流
野田「小川さんが作ってくれた別冊ele-kingの〈UKジャズ人脈相関図〉を見ると、中心がないんだよね。誰かが束ねているのではなくて、ものすごくリゾーム的に交流しているというかさ。それが、いまのUKジャズのすごくおもしろいところであり、掴みづらいところではあるのかもしれないけど。でも、これから作品が出てくるから、もっとわかりやすくなるとは思うんですけど」
小川「そうですね。アメリカでは、NYにロバート・グラスパーとその周辺がいて、LAにサンダーキャットやカマシ・ワシントンがいて、という感じで、NYとLAとじゃすごく距離が離れているじゃないですか。イギリスは、ロンドンという東京都とほぼ同じくらいの面積の街にいろいろな人たちがひしめき合っているという印象で、より密な交流がある感じです。ジャズ以外にも、キング・クルールとかトム・ミッシュとか、シンガー・ソングライターやラッパーがいて、ジャンルを超えた交流があります。
それは、実はイギリスのジャズについて昔から言えることで、60年代はジャズとブルースとロックの融合が非常に盛んでした。例えば、カンタベリー・シーンのソフト・マシーンとかがそうですし、キング・クリムゾンにしてもジャズ・ミュージシャンが参加していた時代があります。ローリング・ストーンズのチャーリー・ワッツは、もともとジャズをやってた人ですしね。だから、いまの南ロンドンのジャズ・シーンは、UKの音楽の歴史をそのまま表しているかなと思います」
野田「いまは、細分化したものが一気にまた集合して、20世紀の頃より過剰になった感じもありますよね。例えば、ヘンリー・ウー(カマール・ウィリアムス)みたいにヒップホップ育ちのハウスのプロデューサーもそこに絡んでいるわけで。それにしても、アシッド・ジャズのときはDJが主導して、ブロークン・ビーツのときは打ち込みのプロデューサーが主導したわけだけど、今回のUKジャズの特徴は、演奏家がとても多いということ。
これは、エレクトロニック・ミュージックが一般化した現代に対するなんらかの抵抗じゃないかと思えるぐらいの状況です。ドラマーだけでも3〜4人はすごい演奏家の名前がすぐ挙がるとか、さっきの〈古くて新しい〉という話にも重なることですが、DJや打ち込み系よりも、楽器奏者たちの勢いがすごくないですか?」
小川「そうですね。おもしろいのは、女性が多いっていうことで、ヌビア・ガルシアもそうですし、彼女が参加しているネリヤというメンバーが全員女性のバンドもいます。他のシーンと比べて、女性がすごく多いと思います」
野田「ココロコとかね」
小川「ええ。それはやっぱり、〈トゥモローズ・ウォリアーズ〉の影響がすごくあるんです。ジャズ・ウォリアーズというバンドが80年代にいて、そのベーシストだったゲイリー・クロスビーが91年に発足させたジャズ・ミュージシャンの育成機関みたいなところです」
――ジャズ・ウォリアーズは、コートニー・パイン(サックス)が参加していたバンドですね。
小川「ええ。〈トゥモローズ・ウォリアーズ〉は無料で参加できるシステムで、基本的には黒人などの有色人種や女性ミュージシャンを育成するというのを目的としています。そういったところからヌビアやザラ・マクファーレン(ヴォーカル)が出てきたという感じですね」
シャバカ・ハッチングスとサンズ・オブ・ケメット
野田「ドラマーもこれだけいるのかという感じじゃないですか? 今日のUKジャズを特徴づけているものに、やっぱりアフロビートがあるんです。例えば、モーゼス・ボイド(ドラムス)がトニー・アレンにレクチャーを受けている動画がありますよね。UKのアフロ・ディアスポラって、基本的にはカリブ系が多かったんですけど、21世紀に入ってからはナイジェリア系とかのアフリカ系が多くなったっていうのがひとつあるんです。
アフリカ系移民が作った音楽でいちばん大きいものってグライムなんですけど、それこそヒップホップのようにある世代に限定されがちなものですよね。だから、UKのなかでジャズという音楽がアフリカを表現することって、すごく重要なことなんじゃないのかなって思いますね」
小川「ジョー・アーモン・ジョーンズが参加しているエズラ・コレクティヴというバンドは、アフロビートから強く影響を受けているバンドなんですよね。だから、アフリカ音楽やカリビアン、中近東の音楽からの影響が非常に強いのがUKジャズの特徴のひとつだと思いますね」
――確かに、UKジャズはビートやリズムの多様さが特徴ですよね。
小川「シャバカが参加しているユニットは、ユニークなものが多いですよね。サンズ・オブ・ケメット、メルト・ユアセルフ・ダウン、コメット・イズ・カミング、南アフリカの人たちと一緒にやったアンセスターズもあります。野田さんはサンズ・オブ・ケメットの『Your Queen Is A Reptile』をすごく評価していますよね。僕もすごく良いアルバムだと思うのですが、どのあたりが良かったんですか?」
野田「一言で〈アフロ〉と言ったときの、ある種のステレオタイプ化に対しての抗いというか……。〈アフロ〉がこれだけ多様なんだっていうことを提示したところですよね。小川さんも言っていましたけど、シャバカっていろいろなところに参加していて、年齢も30代前半で、さっきも言ったように、すごく苦労人だと思うんです。インタヴューで〈いま、UKジャズに勢いを感じる〉と言うと、それは彼からしてみるとすごく違和感があるみたいなんだよね。たぶん〈俺らはずっとジャズをやっていたんだ。いまだけ光を当てないでくれ〉っていうことだと思うんだけど。
彼は、さっき話に出たジャズ・ウォリアーズにも参加しながら、エヴァン・パーカー(サックス)とかの前衛、フリー・ジャズの人たちとも共演してきて、本当に真面目にやってきた人なんです。だから、UKジャズの作品がインパルス!というアメリカの老舗ジャズ・レーベルからリリースされることのおもしろさを語っていましたね。やっぱりアメリカのジャズとは似て非なるものですから」
――なるほど。小川さんは、サンズ・オブ・ケメットの新作についてはどうですか?
小川「前二作も良かったんですけど、今回はMCを入れて、よりレゲエ/ダブやダンスホールに近づいて、サウンドシステム的な音楽になっていると思いました。共同プロデュースをしているのがディーマス(ディリップ・ハリス)なんですけど、彼はガリアーノやヤング・ディサイプルズのミキシング・エンジニアもやっていて、トゥー・バンクス・オブ・フォーっていうグループにも参加していたんです。昔からクラブ・ミュージックに関わってきた人がプロデュースすることによって、ジャズとクラブ・サウンドがよりコミットしたアルバムになっていると思いました。
フローティング・ポインツも、モーゼス・ボイドやエズラ・コレクティヴのミックスを手掛けていますが、〈ミキシング・エンジニアが作る音楽〉というのがUKにはあるんですよね。それこそ、エイドリアン・シャーウッドの時代から。マッド・プロフェッサーとか……」
野田「本当にそう。デニス・ボーヴェルとかね」
小川「ディーマスも、そういったうちの一人なんですよね」