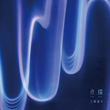作り終わったら、それはもうパーソナルなものではなくなっていた
――『告白』には、平たく言ってラヴソングが多いと思ったんですね。ラヴソングって、ものすごく個人的なものであるのと同時に、他者に開かれたものでもあります。今回は特にパーソナルな側面が強いと思うのですが、そういう個人的な音楽を発表するということについてはどんなことを考えられていますか?
「〈大きな言葉〉――みんなが共有できるような器で歌うことが、もしかしたらなんの意味も持たないんじゃないかと思ったんです。例えば、〈I LOVE YOU〉という大きな言葉を提示したところで、誰にも響かないんじゃないか、誰の歌でもなくなってしまうんじゃないかと。それがとても怖かったんです。
だから、パーソナルなものを提示したほうが共感してもらえる余白が生まれるんじゃないかと思いました。それには節回しのテクニックも関係していて。わかりやすいテーマの道筋をそのまま辿らせるような歌にはしないというか。今回の曲は衝動的に作ったと言いましたが、一方でメチャクチャ俯瞰的に見ていて、とても言葉に気を付けながら作ったんです」
――そうなんですね。
「だから、どこか他人の曲のような気持ちもしているというか……。パーソナルなことをパーソナルなまま保っている気はしないんです。作り終わったら、それはもうパーソナルなものではなくなっていたと」
――個人的な感情を言語化した時点で、それは他人と共有できるものになってしまう?
「そうですね。感情が噴出する臨界点でパーソナルな領域は終わっていて、そこからは分析作業に取り掛かっていくんです。だから、自分の言葉なんだけどそうじゃないというか、曲が出来て、もう一回自分に返ってくるような感じ。曲を作った後にそれを咀嚼して、確かめるような。不思議なバランスですね、それは」

音楽を作り続けていくのであれば、僕はポップスをずっと作っていくと思う
――先ほど、「〈ポップス〉という形式をとても強く信じている」とおっしゃっていましたが、具体的にはどういうことなんでしょう?
「ポップスという形態が〈自分のものじゃない〉って思う瞬間があるんですよ。人を小馬鹿にしたような歌詞とかへの違和感がずっとあって、そういうことに対する怒りがあるんです。〈誰のためにこの歌はあるんだろう?〉みたいな。だから、僕は汎用的なポップソングの〈骨〉を入れ替えるイメージというか、言葉を言い換えたりして、ハッキングするような感覚なんです。
肉だけを借りてきて、血を通わせて、歌詞という〈骨〉を入れ替えると、みんなが共有できるものを作れるんじゃないかと思ったんです。ポップスが好きなのは、自分のものにできて、持ち帰れるような気がするからなんですよ」
――「持ち帰れる」というのは?
「歌えるというのが大きいのかなと。ポップソングには取っ掛かりがあるから思い出せるし、そこが魅力的だと思うんです。僕は孤独について歌っているから、孤独なときに僕の音楽を思い出して欲しい――そう言うとちょっとおこがましいんですけど、〈そんなものがあったらいいよね〉ぐらいの感じで。ひとりでちょっと手持ちぶさたなときに〈これがあったらおもしろいよね〉っていうような。
音楽を作り続けていくのであれば、僕はポップスをずっと作っていくと思う。僕は基本的にひとりで音楽を聴くからポップスが好きなんです。そう言っていいんじゃないかなと思います」
――「ひとりで聴くからポップスが好き」というのは、おもしろいですね。butajiさんは個人の聴き手を想定しているんですか?
「うん、僕が考えているのは個人ですね。ヘッドホンやイヤホンを付けた個人のことをずっと想定しています」
――なるほど。……まったく同じことを宇多田さんが「SONGS」のインタヴューでおっしゃっていました(笑)。
「ホントですか(笑)?」