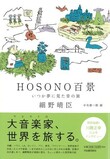大瀧詠一さんとの作業は、油断も隙もありゃしない(笑)。だけど完成したものはどう聴いてもポップス。そこがすごい
――それは僕も楽しみです。では続いて、大瀧さんのお話を伺っていこうと思います。あるアルバムのライナーノーツに大瀧さんご自身が、ふたりが出会ったのは、林さんが大瀧さんが叩いたドラムを評価したことがきっかけだったと書かれていたのですが。
「そうそう、彼のソロの曲(『大瀧詠一』収録曲“五月雨”)のドラムがカッコよかったという話をしたのは覚えてます。彼はドラムから始めたんですもんね。もちろん大瀧さんの曲ははっぴいえんど時代から知ってましたけど」
――で、彼の曲に林さんが参加されたのは『大瀧詠一』の“あつさのせい”が初になるんですか? 録音前に、大瀧さん、林さん、鈴木茂さんの3人でスタジオに入ってプリプロのようなことを行ったとか。
「そうでした。そのときは何にも曲が出来ていなかった。茂の弾くフレーズに、それいいね、って感じで合わせていくような不思議な作り方でしたね。スタジオは、目黒のモウリスタジオで。はっぴいえんども使ってましたよね。当時は質のいい機材が置いてあるのは、あそこぐらいしかなかったんだけど」
――その頃の大瀧さんに対してどういう印象を抱いていましたか。
「すごく好感を持ってましたよ。ウチの母方が仙台だったせいかわからないけど、妙にしっくりきたというか。東北のあったかい感じがとても印象に残っていますね。茂とか細野(晴臣)さんは小さいときから知っているけど、東京のど真ん中の連中ですから。それはそれで違和感なく仲良くできるんですけど、東京人同士特有の付き合いってものがある。で、大瀧さんの持っている東北人的な雰囲気が僕には新鮮だったというか、何か懐かしいような感じもあって」
――へぇ~、そうだったんですね。ナイアガラ・レーベルでの大瀧さんのソロ第一弾『NIAGARA MOON』(75年)で林さんは八面六臂の大活躍をされています。
「大瀧さんとの作業って出会い頭の事故的なものを求めていたように見えるけど、頭の中ではいつもどの方向に行くべきか見えていたし、何がやりたいのかはすごくはっきりしていた。そうじゃなきゃ、僕らもああいうふうに演奏できなかったと思う。
そうそう、“ロックン・ロール・マーチ”(『NIAGARA MOON』)のレコーディングのことはよく覚えてる。冬だったんですけど、福生45スタジオのドラム・ブースがもう寒くて寒くて。そこへ持ってきて、イントロのドラム・フレーズを作れという指示があって、早く何とかしないと寒くてたまんないから、もう必死でしたよ。それは忘れられない(笑)」
――イントロのフレーズ作りに苦労している様子が断片的に音源にも残っていますもんね。でもあれは後世に残る名フレーズです。
「ニューオーリンズとかあの辺のエリアのリズムをベースに何か新しいものを足して、とか言われたような気がするんですけど。それでハイハットを裏で叩く、みたいなフレーズを作ったんじゃなかったっけ。ニューオーリンズ系じゃああいうのは出てこないですから。とにかく大瀧さんはリズムにうるさくて、なおかつトリッキーなんです。ただ曲を聴いていると、何の違和感もないんだけど。Tin Panで再度録音した曲(“Hand Clapping Rhumba 2000”)があって、それもすごくトリッキーなんですよね」
――単なる〈何々風〉というものに、さらに何か別要素を付け加えないと気が済まない性格なんですかね。
「必ず何かいじるんですよ。一回目のブリッジは四小節あるけど、二回目は三小節しかない、だとかざらにある。だからちょっとうっかりしていると、ブレーキを踏み損ねてぶつかっちゃう、みたいな。油断も隙もありゃしないですよ(笑)。なんだけど、完成したものはどう聴いてもポップスなんです。そこがすごい」
――林さんがドラムを叩いているCMソング“サイダー’74”。あれなんか、頭を外して裏を強調したへんてこりんなリズム・パターンなんだけど、めちゃくちゃポップなんですよね。
「そうでしょ、めちゃくちゃややこしい(笑)。譜面に起こせば、なるほどそういうことか、ってわかるんですけどね。ただ、大瀧さんの場合はたいてい口伝えなので、アレ、どうしてここでバスドラが?ってうろたえてしまう。でもいま思えば、ドラムパーツ全部が頭のなかに入っていたのかなって。いろんなドラマーが泣かされたと思いますよ(笑)」

大瀧さんの歌の、あの独特な間の取り方は簡単に真似できない
――打てば響きまくる林さんの存在は、かけがえのない存在だったと思いますね。
「80年代以降、(大瀧が)フィル・スペクターのような分厚いサウンドを作るようになった頃、〈林は飽きっぽいからテイク2までに録らなきゃいけないんだよ〉ってみんなの前で言われたんです。嫌味混じりにね(笑)。でもあながち外れていないなと(笑)。すべての人のことを見抜いているんですよ。特に大勢のミュージシャンを使って作っていた80年代の頃、知らん顔しながらもみんなそれぞれの個性を把握していましたしね」
――信濃町のソニー・スタジオでレコーディングしていた頃※も、参加メンバーひとりひとりに細かく指示を出されていたんですか?
※大瀧詠一が80年代以降(81年作『A LONG VACATION』以降)に主に利用していた
「一応ざっとアレンジをしてくださる方がいたりして、進み方とかアバウトなものは譜面に書いてあった。個別の指示ということでは、たぶんドラマーがいちばん多かったんじゃないかな。ニュアンスにすごくうるさかったですよ。
あとシンガーとしての大瀧さんって、各ドラマーのスネアのタイミングをものすごく強く意識しながら歌う人なんです。当時はクリックなんかほとんどなかった時代でしょ。で、いい感じに歌が揺れているんだけど、それがヘンに揺れていると感じないのはスネアにきっちり合わせて歌っているからで、それはすごい能力なんですよ。
今回僕はセッションのゲストに、〈この曲でお願いしま~す〉なんてお気楽にリクエストを出しましたけど、歌い手からするとあの大瀧さんの独特な間の取り方は簡単に真似できないでしょうね。そういえば以前あるシンガーが、“雨のウェンズデイ”(81年作『A LONG VACATION』収録)はうまくコピーできないって言ってましたけど、特に『大瀧詠一』の曲は難しいと思う。シンガーにとっては大瀧さんの曲ってかなり難易度が高いみたいですね」
――ブレスの位置とかの問題もいろいろあるし、大瀧さん的な変わった譜割ってありますもんね。
「だけども聴いている分にはなんら違和感がない。間違いなく彼は日本のポップス・シーンの足固めをされたミュージシャンのひとりと言っていいでしょうね。さまざまな面での分析力もすごいし」
――昨今は若いリスナーの間で、シティー・ポップの元祖としての評価も高まってますね。
「80年代に大瀧さんと吉田保さんとふたりによって織りなされたあの世界ですよね。すごくエコーがかかったリッチなサウンドで、きちんと除菌されている感じ」
――なるほど、除菌されている感じですか。
「わかります? あの頃の大瀧さんの曲って僕がレコーディングしたものぐらいしか覚えていないけど、“雨のウェンズデイ”に関しては当時から素晴らしい曲だと思っていました。リスナーとしても大好きですね。特に間奏の茂のギターが素晴らしい」
――大瀧さんの最後のオリジナル曲になった“恋するふたり”(2003年のシングル)は林さんがドラムを叩かれていますね。
「たまたまそういうことになってしまったわけですが、それが最後だったということで、やっぱりどうしても記憶に残りますよね。ミックスしたものをオーディオ・ルームのいろんなスピーカーで聴いたとき、〈林の使ったスリンガーランドがめちゃくちゃ良い〉って彼が言ってたこともすごく覚えている。僕の使っていたヴィンテージのスリンガーランドがすごく好きでね。
あとドラム・ブースで世間話をしていて、〈曲の作り方を間違えちゃってさ、俺ずっと歌いっぱなしなんだよな〉ってボヤいてた(笑)。言われてみるとあの曲、最初から最後までず~っと歌ってるんですよ。いっしょに歌ってみると大変さがわかる。曲は穏やかなんだけど、マラソンしているみたいにずっと走ってる感じがする」