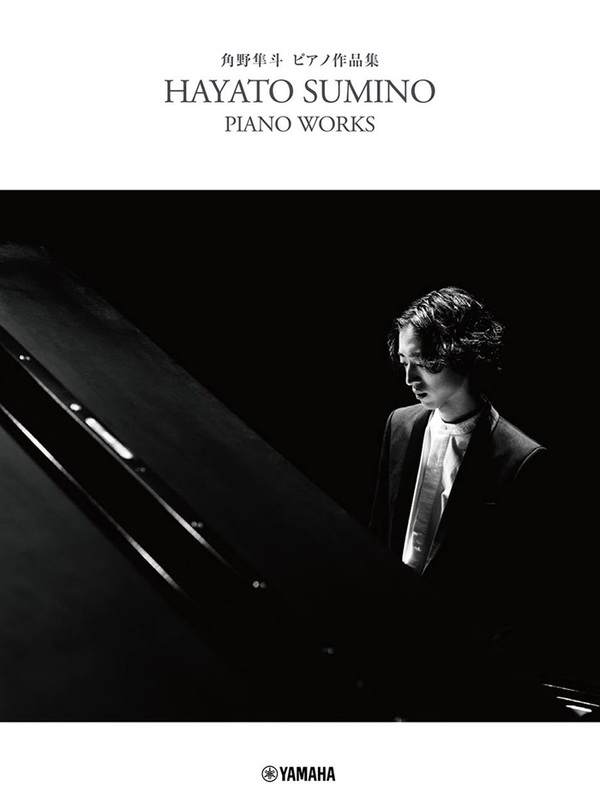HERE COMES YOUR MAN
耳で聴いたピープル・トゥリー
ピクシーズをめぐる音楽の果実は、ここに一本のトゥリーを生んだ
文/香椎 恵

THE SMASHING PUMPKINS Shiny And Oh So Bright Vol. 1: No Past. No Future. No Sun Napalm(2018)
オルタナ界の性格悪い坊主……と聞いて誰を思い浮かべるだろう? それはともかく、ジェイムズ・イハが18年ぶりに合流してほぼオリジナル・メンバーが揃った本作のサウンドは、再結成後のピクシーズにも似たラウドで甘美な大人の味わい。ビリー・コーガンとパズ・レンチャンティンはズワンでの縁もあった。

ピクシーズやブリーダーズ好きで知られたカート・コバーンだけに、かの“Smells Like A Teen Spirit”が“Debaser”のリフの強い影響下にあるというのは有名な話だろう。入れ替わるようなタイミングでニルヴァーナがブレイクしたのも皮肉だが、『Surfer Rosa』の音像を求めて『In Utero』でスティーヴ・アルビニを指名したという逸話もあった。
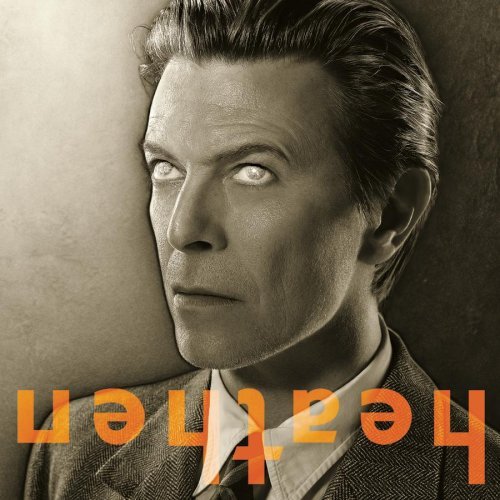
ジョーイがブラックに教えたレコードのひとつはボウイだったそうだが、当の本人は80年代末にソニック・ユースやピクシーズに憧れてティン・マシーンを結成(ライヴでは“Debaser”をカヴァー)。同バンドは短命に終わるも、10年経ったこのアルバムでは改めてピクシーズ曲を正式に取り上げている。その選曲がT・レックスを下地にした“Cactus”だというのもボウイらしい。
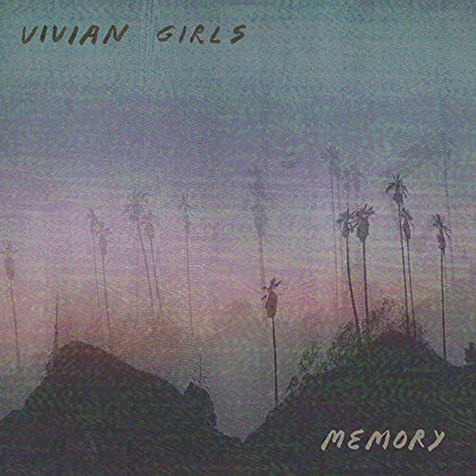
いわゆるヴェルヴェット・アンダーグラウンド(ジョーイ・サンティアゴが心酔していた)的なスタイルから発展してきたノイズ・ポップの系譜において、オルタナ~ガレージを経て近年のドリーミーな潮流を織り成してきたのがブルックリン発の彼女たち。この5年ぶりの再結成作がピクシーズと同時期に出るのも興味深い。

世界同時多発的な動きだったのか、どうなのか、ピクシーズに先んじてUKでドリーミーな爆音を轟かせ、後にシューゲイザーと括られるインディー・ノイズ・ポップの源泉となったJAM。UKでまず受け入れられたピクシーズが彼らの“Head On”(88年)をカヴァーしたのは必然的だったのかも。

ニルヴァーナやヴァインズ直系とも評されたブライトンのバンドによる日本デビュー作。収録曲の核となるのは近年のピクシーズをプロデューサーとして支えるトム・ダルゲティだ。ロイヤルブラッドやダイナソー・パイル・アップらで実績も残してきた彼のオルタナ・リヴァイヴァル的なセンスがレジェンドに瑞々しさを与えているのは言うまでもない。

往年のBEAT CRUSADERSやART-SCHOOL、近年のtricotまで影響下にある日本産バンドも数多いが、やはり代表格となると、御大のストレンジな風情やカリスマ性まで独自の奇妙さに発展させた彼らだろう。本作にはピクシーズ結集時のエピソードをもじったような“PIXIE DU”も収録。ピクシーズとすれ違いで解散、からの再結成まで含めて運命的だ。

『Bossanova』期からジョーイのギターも含めてピクシーズに表れてきたサーフ・ロック志向だが、同作のストレンジなひねくれポップ感はこちらの箱庭感にも繋がるところ。後にブラックがカヴァーした際に“I Know There's An Answer”でなく“Hang On To Your Ego”を選んだのも性格が出ている?

後世がイメージしている〈ピクシーズっぽさ〉の一端を担うのは『Doolittle』から解散までを支えたプロデューサーのギル・ノートンでもあり。エコバニやフー・ファイターズも手掛けてきた重鎮の彼だが、21世紀仕事における〈っぽさ〉ということでは、ポスト・ポスト・パンクなオルタナ・サウンドの漲る本作がひとつの極みかも。

クリスティン・ハーシュとタニヤ・ドネリーを中心にロードアイランドで結成されたポスト・パンク・バンド。彼女たちによって4ADがUSインディーに興味を抱いていたからこそピクシーズが見い出されたのは間違いない。ブリーダーズ結成の縁はもちろん、タニヤのソロ作でデヴィッドが演奏するという繋がりもあった。
BiSHのアユニ・Dが田渕ひさ子らと繰り広げているバンド・プロジェクトの最新弾。もともとBiSH自体が音源的にはアルビニのグランジーな音像をめざして始まった部分もあるが、今作では『Doolittle』あたりを好きそうな本人の嗜好も反映され、田渕からの隔世遺伝も含めてノイジー&ポップなUSオルタナ感が漲っている。