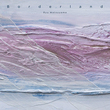『Borderland』はドラマーのアルバム
――なるほど。プレイヤーとしての新しいチャレンジもありましたか?
Jackson「mabanuaさんはドラマーなので、彼が作ってきたデモにどれだけ近づけられるかが今回はテーマでしたね。〈ニュアンスも含めて再現してやろう!〉って(笑)。難しいかなと思ったんですけど、元々僕もブラック・ミュージックが好きだったから楽しくて仕方なかったですね。違和感なく叩けたというか。
Ryu Matsuyamaでは今まで、ブラック・ミュージック的なノリはあまり採用されてこなかったんですけど……」
Ryu「そうだったっけ(笑)?」
Jackson「今回はmabanuaさんが入ってくれたことで、僕の中のブラック・ミュージック的な要素を、Ryu Matsuyamaでも自然に出せたのは嬉しかったです」
Ryu「確かに今作は、ドラマーのアルバムっていう感じがするよね。以前くるりの岸田さんが、〈このアルバム(2004年作『アンテナ』)はクリストファー(・マグワイア〉のアルバムだ〉みたいな発言をされていたんですけど、結構そんな感じがしたというか……。ドラマーがアレンジしただけあって、ドラムがすごく効いてる」
Jackson「フレーズ自体はものすごくシンプルなんだけどね。例えば“Heartbeat”では、14インチの通常のハイハットの代わりに18インチのクラッシュ・シンバルを2枚重ねて叩いてるんですよ。そうすることで、低音の心地よいサウンドになったんです。ドラムの全体的な重心もグッと下がってどっしりとした印象になりましたね」
――リズム・セクションでの挑戦という意味では、前作でもフィーチャーしていたハンドパンを1曲目のインスト“Step over”で用いていますね?
Jackson「僕ら、アルバムをまとめる上でインスト曲をいつも入れてるんですけど、時に『Leave slowly』(2017年)くらいからは、持っているパーカッションを全部鳴らすというのが定番になってきていて(笑)。今回はTsuruちゃんがハンドパンを演奏し、僕はリサイクル楽器店で4000円くらいで手に入れたスティールパンを弾いています」
――Tsuruさんは、ベーシストとして今回どのようなアプローチをしていますか?
Tsuru「今までのレコーディングでは、〈なるべく普通じゃないプレイをしなければいけない〉みたいな気持ちがあったんですよ(笑)。サポート・ベーシストとしてRyu Matsuyama以外の場所で頼まれた時には、絶対に弾かないようなことをしようと。
でも今回、そういうこだわりはやめようと。曲を聴いて、その曲が求めているベースラインを自然体で弾くことを心がけましたね。で、その楽曲に合うベースの機種で味付けをするという感じ。
そういう意味では、今までで一番気負いがなく挑めたレコーディングだったと思います。とにかく楽しかったな」
Jackson「今までのリズム・セクションも、それはそれで緊張感があって良かったけどね。今回は自分たちの得意分野を自然にやれた感じ」
〈境界線〉を越えて人やアイデアが集まり、また〈境界線〉が生まれる
――アルバム・タイトルの〈Borderland〉は〈どっちつかずの境界点、夢うつつの境〉という意味ですが、これにはどんな気持ちを込めましたか?
Ryu「さっきも話したように、曲は以前から書きためていたものだったので、全体としてどんなタイトルをつけたらまとまるのかなって考えていたんです。
そんな中でふと〈Borderland〉という言葉が浮かんできて〈これだ!〉と。それぞれの楽曲を〈国〉だとすると、それを形づくる〈境界線(border)〉上にいるのが僕らやmabanuaさん、スタッフの方たちだと思うんです。
それと今回、ジャケットは僕の親父が描いた絵を採用したんですけど、親父はイタリアに住んでいるし、マスタリングは(米NYCの)ジョー・ラポルタだし、国境を越えた様々な人たちのアイデアやアドバイス、協力によって楽曲が完成し、それらがいくつも集まることでまた〈境界線〉が生まれて……っていう。そういうイメージをタイトルで表しました」