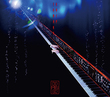異文化同士が混ざって生まれた音楽への敬意
――江森丈晃さんが手掛けたアートワークやアーティスト写真についても伺いたいと思います。前作のアートワークがカラフルでにぎやかだったのに対して、海の中の深い青のなかで無限につづくシンセサイザーを弾く手、というのが印象的です。このアートワークについて田中さんはどういったやりとりをされましたか?

「まず、江森さんを知ったのは、ある雑誌のインタビューをたまたま読んだんです。そこで彼がデザイナーであると同時にロックが好きな方というのを知って、特にインディー・ロックがお好きということで、親和性があるのかなと思ってたんですよね。それで、さっきの夜とかレゲエとかそういったテーマを向こうに投げたんです。参考に返ってきたのが、ヒプノシス※っていうイギリスのデザイン・チームによるジャケットで、それが〈遠くないな〉って印象だった。
江森さんから最初に提案されたのは、〈実際に田中さんが普段使用されているシンセサイザーや楽器をすべて撮らせてほしい〉と。それを組み合わせてジャケットを構成したい、という話をされて。そこからは江森さんの提案にのっていった感じかな。今回のアルバムのイメージ、というのは3枚目を意識した2枚目だというのを含めて、色は1枚目みたいに派手じゃないものがよかった。今回は〈ノスタルジー〉というテーマがあったので、そういうイメージに仕上がるように、やりとりしていきました」
――使われているのはアナログ・シンセのパネルですよね。
「自分が手作りした基盤なんかも混ざってるんですけど、基本的には自分がふだん使っているものです。当然ソフト・シンセを使うことが多いんですけど、ハード・シンセもたまに入れるので」
――アートワークと同じくらい印象的なのがアーティスト写真です。

「これも江森さんからの提案なんです。実は、これまでは〈マエストロ的な感じはちょっと……〉っていうがずっとあったんです。レジェンドだ、とか語ってくれる人もいるけれども、実際の自分は関西のおっさんで、ただの音楽好き。どんだけ音のことしか考えてへんのというくらいひたすらレコードを買い集めて音楽を聴いてってタイプ。この写真とのギャップは相当あるなと思います(笑)。ただ、自分の考えだけを出していくのがベストとは思わないので、こういう印象もおもしろいかなと」
――蝶ネクタイのかわりにパッチング・ケーブルというのがユーモラスですごく好きです。
「ありがとうございます。そこは世代によってぜんぜんちゃうと思うんですよ。あれを何人か、特に海外の人に見せると、〈Rad(イカす)〉って言われました」
――インタビューに冒頭から、〈3枚目を考えて……〉と何度かおっしゃっていましたが、次の作品に対する構想があればお伺いしたいなと思います。
「口で言えることは少ないかも。今回のアルバムも、1枚目のときからある曲もあって。“Night Flight”は1枚目のときからあったし、“Momongah”もずっとあった。いまもすでに作っているのが3、4曲あるし、小節単位の短い曲の種のようなモチーフもいろいろあります。
僕は若いときにあまりブルースを好きじゃなかったんだけれども、歳をとればとるほどそういう、いまのロックやソウル・ミュージックのルーツである、アメリカの古い音楽が残ってくるんですよね。そういう音楽にたいする自分なりのオマージュをどうやったらできるかなと。他にも、わりと仰々しい、昔で言うプログレッシヴ・ロックみたいなものも好きで、そういう要素が一貫して僕のなかにあると思うんですけど。素直にそこを振り返ってみながら、これからの音楽としてどうまとめて行こう?っていうのがいまのテーマかな。

あと、今日の話のなかでは出てこなかったですけど、僕はアフリカの音楽も大好きで、特にナイジェリアの音楽。ナイジェリアのダンス・ミュージックがすごく好き。日本も含めて、西洋って環境として情報が多すぎる。振り返ると、情報過多じゃなく、制作環境もそれほど充実してるとは言えないかも、というような場所から生まれてくる音楽が一貫して好きなんです。そういうところの人が持っているエネルギー、音にしたい衝動の強さをすごく感じるんです。
自分はそういう音楽の影響を深く受けてきている。たとえば歴史的に植民地化され、とにかく生きることで精一杯、そんな状況下で楽器を鳴らし、異文化同士が混ざって生まれた音楽ってたくさんあるでしょう。その経験は必ずしも幸せなことではなかったかもしれないけれど、そういう環境で生まれた音が持っている強さについては、毎回〈足向けて寝られへんな〉という気持ちが強いし、いつもそういう音楽を生み出してきた人たちに対し敬意を感じる。
今後、どのくらい活動を続けられるかは別だけれども、こんな時代だからいろんな国の人たちが自分の音楽を〈おもしろいやん〉と思ってくれたらいいなぁとよく思う。アメリカやイギリスでウケるのもいいけれど、非英語圏、たとえばスペイン語やポルトガル語圏の人たちにおもしろいと思ってもらえる音楽ができたらいいなとか。そこをあえてめざしているわけではないけれども、気持ちのうえでは常にそんな想いがありますね」