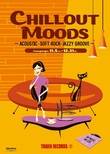須永辰緒のDJならではの身軽さ
須永「僕は、ブルーイとの面識はないんですよね。アシッド・ジャズ全盛の頃、僕はヒップホップDJで、パブリック・エネミーのツアーに同行していたりしたので(笑)」
松浦「辰緒さんって、元々ロックやパンクのバックグラウンドがあって、そこからヒップホップ、ジャズへ繋がっていったという、ある意味イギリス的、ヨーロッパ的な流れが面白いですよね」
須永「面白いものを探していくと、音楽の嗜好って変わっていくんですよ。当時はあれほど面白かったパンクも、その内にいろいろなものが透けて見えてきて。今度はヒップホップにパンク精神を感じてそっちを突き詰めていくと、彼ら(ヒップホップ・アーティスト)が子どもの頃に聴いていた音楽に興味がいく。それで、それまで聴こうとも思わなかったソウルやファンク、ジャズを聴くようになる。ジャズ・ミュージシャンが憧れたブラジル音楽を聴いてみたら面白くて、今度はブラジル音楽を突き詰めたくなる。そうしたら自分でも制作してたくなって、制作をすると、今度は機材について知りたくなる。そういうふうに、いろいろなことに興味が移っていくんですよね。そうすると、テクノやトランスも躊躇なく聴けるようになる。そういう体質なんでしょうね」
松浦「それが本来あるべき形じゃないかなあ、と思います」
須永「それはさ、僕がミュージシャンじゃなくて、DJだったからだと思うんだよね。ミュージシャンだったら転向するときにかなり勇気がいるし、ロック・ミュージシャンがジャズのテクニックを簡単に身に着けられるかといったら、なかなか難しいと思う。僕はDJだから、躊躇なくいろいろなものに手が出せたんだと思いますよ」
ブルーイの高いミュージシャンシップ
――松浦さんとブルーイとの付き合いが始まったのは、ユナイテッド・フューチャー・オーガニゼイション時代にトーキング・ラウドでレーベルメイトになった頃からですか?
松浦「そうですね。ジャイルスからの紹介で、来日したときに一緒にツアーをやったりとか、そういうところで繋がっていった感じですかね。それ以前は彼のことはまったく知らなくて、知り合った後にライト・オブ・ザ・ワールドとかをディスカヴァーしていったのが正直なところですね」
――ライト・オブ・ザ・ワールドはインコグニートの前進バンドですよね。その当時、すでにブルーイは結構キャリアのあるミュージシャンだったわけですよね。
松浦「自分はそう認識していましたね。トーキング・ラウドの中でもインコグニートだけちょっと突き抜けていたっていうか。もちろん初期のトーキング・ラウドにはガリアーノ、ヤング・ディサイプルズ、インコグニートという3本柱がいたけど、いちばんミュージシャンシップに則って音楽を作っていたのがインコグニートでしたし、音楽的な完成度の高さでいうと、インコグニートがずば抜けていた。それはやっぱり、ブルーイがリーダーだったからっていうのがあるんじゃないでしょうか」
――インコグニートはアシッド・ジャズ・シーンに多かったDJユニットとも違い、完全なバンドですしね。
松浦「そうですね。だから、より技術的な面というか、そこで抜けていた。ヤング・ディサイプルズとガリアーノに関しては、もうちょっとアイデアのおもしろさというか、サプライズも含めたイギリスでしか生まれないようなアイデアを重視していて、さらにDJ文化が混ざった音楽だったと思うので。ある意味、トーキング・ラウドのラインナップとしてはバランスがよかったんじゃないかなって気がしますね」