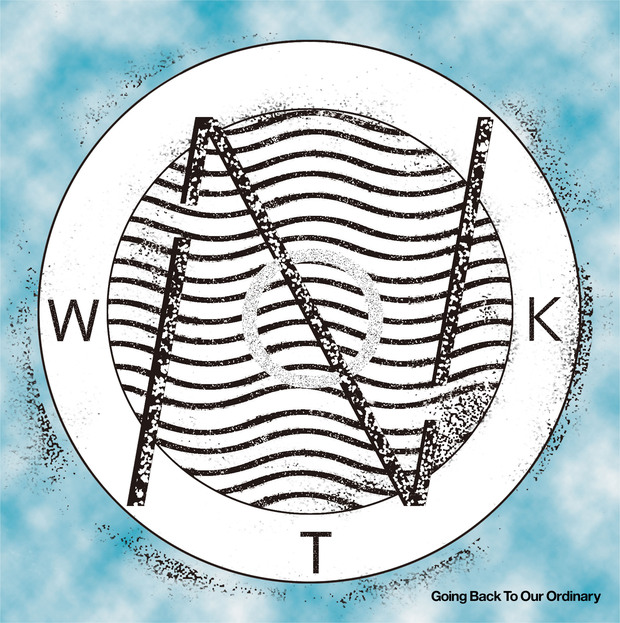北海道・苫小牧を拠点にソリッドなメロディック・パンクを鳴らし、さまざまな世代のリスナー/アーティストから熱い支持を受けるNOT WONK、高校生の頃から栃木・足利のパンク・シーンで存在感を示し、現在はリヴァーブを駆使したインディー・ロックで人気を博すCAR10、そして、京都で自主レーベル・生き埋めレコーズを主宰し、清涼感溢れるギター・ポップ・サウンドに注目が集まるTHE FULL TEENZ――各々が離れた土地で活動しながら、数々のライヴ共演や同じコンピへの参加などを通して親交を深めている3組が、揃って5月に新音源をリリースする。
まず、NOT WONKは5月11日にタワーレコード限定でシングルCD+ライヴDVD『Going Back To Our Ordinary』を、CAR10は5月25日に5曲入りEP『Best Space. EP』を、それぞれKiliKiliVillaから発表。また、THE FULL TEENZはファースト・アルバム『ハローとグッバイのマーチ』をSECOND ROYALより5月25日にリリースする。いずれも、バンドが新しいページを開いたことが伝わる仕上がりになっており、これまで以上に多くのリスナーに届くであろう作品だ。
今回Mikikiでは、各バンドのフロントマンにして同世代の3人――NOT WONKの加藤修平(94年生まれ)、CAR10の川田晋也(91年生まれ)、THE FULL TEENZの伊藤祐樹(93年生まれ)による鼎談を実施した(伊藤はSkypeでの参加)。お互いの新作への所感からスタートし、自身が暮らす街へのアンビバレントな想い、さらに2016年ならではなローカル・バンドのあり方までをたっぷり語ってもらった。活動拠点になっている土地のムードや状況が、いかに彼らの音楽へと反映されているかを伝える、興味深いテキストになったのではないだろうか。
加藤くんのことをヒーローのように崇めている子たちがいた(川田)
――まず、どうしてNOT WONKは、このタイミングでシングルとライヴDVDをカップリングした作品をリリースしたのでしょう?
加藤修平(NOT WONK)「去年ファースト・アルバム『Laughing Nerds & A Wallflower』を出したんですけど、そのあとにリリースしたTHE FULL TEENZとのスプリット7インチ『SPLIT』あたりから、自分の曲がガラッと変わったんです。今回の“This Ordinary”みたいにギターがストレートにガーッと鳴っている曲はやったことがないから、ちょっと恥ずかしさもある(笑)。そういう曲が出来てきたし、ファーストのときよりも絶対上手くできる自信もあった。ライヴDVDに関しては、去年のKiliKiliVillaのコンピ『WHILE WE’RE DEAD.: THE FIRST YEAR』のリリース・ライヴの札幌編から、佐藤(祐紀)くんが、東京や札幌を中心に、僕らが全国各地で行ったライヴを1年を通して撮ってくれていたんです。それらをまとめて観たときに、自分でもバンドが変わっていっていることが若干わかった。いま並べて作品にしても、おもろいんじゃないかと思ったんです」
――川田さんと伊藤さんはNOT WONKのシングルには、どんな感想を持たれました?
伊藤祐樹(THE FULL TEENZ)「去年はライヴをよく一緒にやっていたし、ライヴで聴いた覚えもあったんですけど、CDを聴いた瞬間からヤバイ新曲を作ったなという印象でした。アップテンポな路線とメロウな路線の両方が収録されているけど、いずれも前作より奥行きがあってレンジが拡がっている」
川田晋也(CAR10)「俺も伊藤くんと同じで、ライヴでずっと新曲を聴いてたんですよ。初めて聴いたときに、セカンド・アルバムは凄まじいことになりそうだねと加藤くんに伝えました」
――“This Ordinary”は、これまでよりもハードでノイジーな楽曲になっていますね。バンドが新しいモードになった背景は?
加藤「ファースト・アルバムは予想以上に優しい音で録れたという印象があったんです。でも、ライヴではもっとタフな音だと思っていて。ライヴっぽさというと月並みな言葉ですけど、本当にこうしたいという音にしてみたいと思った。THE FULL TEENZとのスプリットに収録した楽曲“On This Avenue”以降は、ハードコアやグランジに寄った曲を作っていて、サウンドの軸にはいまもそこからズレてないですね」
――“This Ordinary”を録音するうえで、参照点にしたような作品はありましたか?
加藤「シューゲイザーっぽくなったら良いなとは思っていました。メロディー自体はスタジオでいつの間にか出来ていたんですけど、その頃フレーミング・リップスにハマっていて。“Race For The Prize”あたりをすごく良いなと思っていたので、ああいったメロディー一発みたいな曲を作れたら良いなとは思っていましたね」
――7インチ・シングルのみに収録される“This Ordinary”のダブ・ヴァージョン“Disordinary”は特にリップスらしさを感じます。
加藤「あれはもう寄せていきましたね。リップスを聴いて、どう録ったらいいか、どういうミキシングしたらいいのかを研究したんですよ。ドラムのテイクを2回録って、左右のチャンネルで違うテイクを貼ったり、変に音が薄かったりといった点はリップスみたいにしようと狙って、実際にやっちゃった。出来心みたいな感じです(笑)」

――そして、DVDは10会場でのライヴから22曲が収録された80分を超える大ヴォリュームになっています。
川田「俺、(収録された)ほとんどのライヴを観てますね」
伊藤「僕も半分以上は観てるな。でもやっぱりNOT WONKのアルバム・ツアーで回ったときのライヴ(7月18日~20日)が印象に残っていますね。NOT WONKとCAR10と僕らとLINKで東名阪を回って」
川田「加藤くんのことをヒーローのように崇めている子たちがいたのは印象的でしたね。名古屋のときとか、俺とは普通に話しても、加藤くんとは憧れすぎて話せない、みたいな子もいて。これはなんなんだって(笑)。すごい現象だなと」
――おふたりから見て、NOT WONKのライヴにはどんな魅力を感じますか?
伊藤「とにかく男らしくてカッコイイですよね。加藤くんがギターをガシガシ弾く感じはビリー・ジョー(グリーン・デイ)みたいだし。最初に加藤くんと会ったときは、髪も下ろしてたし、いかにも自分より年下の子って感じだったんですよ。それがいまや髪も上げ、男らしくなり、僕もますます好きになっていって(笑)」
川田「なにより音がデカイのが良いですよね。加えて音作りが上手くて、綺麗にまとまっているから聴きやすい。僕は(ベースの)フジくんのパフォーマンスがすごく好きなんですよ。アグレッシヴだし、自分に似ていると言ったらフジくんのファンに怒られるかもしれないけど、そう思える瞬間があるんです。アゴが出てるところを含め(笑)、シンパシーを感じている」