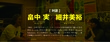坂本龍一の活動に一貫する実験性をみる
YMOの散開、「戦場のメリークリスマス」における役者と映画音楽という初めての仕事をへて、自身のレーベルschoolを設立し、ソロ・アーティストとしての活動を本格化させ、「ラスト・エンペラー」でさらに映画音楽の分野で評価を確立、そして、ヴァージンへ移籍し、世界へと販路と活動の場を広げて行こうとする。坂本龍一〈Year Book〉シリーズの第4弾『Year Book 1985-1989』は、そうした状況にあった85年から89年の坂本の活動から選出されている。それがCD5枚組という分量となったことは、もちろん録音記録を残すということが普通になっていたり、保存環境が向上したりといった要因はあるだろうが、坂本のこの時期の活動がいかに充実したものであったかの証左となるだろう。またこの、坂本の多岐にわたる活動から、音盤としては発表されてこなかった未発表音源、あるいは、現在は入手困難なレアな音源を発掘し、発表していく〈Year Book〉シリーズとは、音盤のリリースやそれに伴うコンサートからだけではとりこぼされてしまうさまざまな活動が網羅され、あらためて坂本龍一という音楽家像を再発見するものでもある。しかも、こんな音源が残っていたのか、というような貴重なものも多く、それにふたたび出会うリスナーも、まったく新しいものとして出会うリスナーも、前回の『Year Book 1980-1984』で、もっと聴きたい、いや、もっとあるはずだ、と思ったリスナーも、今回のヴォリューム感と、坂本の全体像を形作る知られざる、発見されるのを待っているピースが、まだまだあるのだということに驚かれることだろう。



85年のつくば博での、ソニー製の巨大なモニター、ジャンボトロンを使用した、ラディカルTV(原田大三郎+庄野晴彦)による映像とすべてが具体音のサンプリングからなる音響によるライヴ・パフォーマンスを繰り広げる「TV WAR」は、これまでの再構成された映像版ではなく、雨の中の激しいパフォーマンスの完全版。また、坂本、ビル・ラズウェル、近藤等則、山木秀夫、カーロス・アロマーによる、六本木インクスティックでのライヴ〈Inkstick Session〉や、坂本、渡辺香津美、三宅榛名、高橋悠治、如月小春とNOISEによる音楽と演劇によるパフォーマンスで、三上晴子が坂本のオブジェ楽器を制作したという〈マタイ1985 ~その人は何もしなかった〉も今回はじめて音源化されたものである。(吉本隆明がフェアライトCMIで作曲した“人差し指のエチュード”が入っていないのは坂本の作曲ではないからか)
こうした坂本の活動を概観すると、現在の空間的に音を構成していくインスタレーション〈設置音楽〉や、演奏家によらない音楽生成システム、美術家との実験的な演奏、〈非同期〉といったコンセプトなどが、あらためて坂本のアナザーサイドから継続された、一貫した活動であるということが見えてくるだろう。
そして、坂本は、現在まで長きに渡るコラボレーションを続けている、アルヴァ・ノトことカールステン・ニコライとのライヴ・パフォーマンスによる『Glass』をあらたにリリースする。それは、アメリカのモダニズムを代表する建築家、フィリップ・ジョンソンによる〈グラスハウス〉での草間彌生の展示のオープニングで行なわれたパフォーマンスを収めたもので、その名の通り、ガラスの壁に囲まれた、自然の中に建つ〈グラスハウス〉の中で演奏が行なわれている。そこで、坂本は建物自体を楽器として演奏することを考え、坂本が近年使用している高谷史郎のデザインによるガラス楽器のように、建物それ自体でもあるガラスにコンタクトマイクを装着し、それをマレットでこするなどして音を発生させているという。草間彌生のドットの意匠がほどこされた自然の中の人工的環境で、自然音やアルヴァ・ノトとの電子音が有機的に絡み合いながら、音のレイヤーを重ねていくように、環境的な音の状態が即興で作られていく。それは、自然に寄り添い、自然の一部であろうとするふたりのアーティストによる非常に思慮深い作品であると言えるだろう。