
分散・境界・砂
――75年に竹田賢一氏らと設立された〈環螺旋体〉というグループについて、坂本さんは〈反武満的な、メディア論的な運動体〉であったと発言されています。そして、当時の現代音楽の状況を、民族性と切り離されたエリート性・階級性の強いものとして批判しています。
「そうねえ。毛沢東主義みたいなことにすごくはまっていて、芸術なんていう自立した美の領域なんてものは許さん、芸術なんていうものは人民に奉仕してこそ存在意義がある、というような非常に過激なことを言っていました。まあ、当時のゴダールなんかもそうで、彼はそれが原因となってトリュフォーとは訣別するんだけれども、当時の過激な若者はそういう考えを持っていたんですよ(笑)。
悠治さんも70年代には毛沢東主義にはまっていたし。悠治さんの自宅に竹田賢一さんと2人で伺って、長くお話ししたこともあったんです。だからそういう思想に対するアンチとして、武満さんという存在が代名詞になっていたんでしょうね。武満さんを深く研究して批判したというのではなく、武満さんといえば、美の小宇宙、自立した美の代名詞のように考えていたんじゃないかな。だから、芸術とか嫌だよね、みたいなノリでそんなことを言っていたんだと思います」
――76年3月1日に東邦生命ホールにて開催された〈高橋アキの夕べ 6人の若い作曲家のピアノへの捧げもの〉では、「分散・境界・砂」というピアノ曲が初演されています。初演の直後に武満氏と新宿のバーでお会いされた際、このピアノ曲に対して肯定的な評価を受けられたそうですが、この褒め言葉は素直に坂本さんに届いたものと思われます。
「そうですね。〈ビラの君だね、君はいい耳してるね〉なんて言われて、うれしかったりして(笑)。原田力男(いさお)さんというとても志の高い調律師の方がいて、彼は調律の仕事をしながらも、日本の音楽の状況を憂いていたんですね。若い自立した作家を育てなければいけないと考えていたようです。そこで原田さんは、個人のお金で、ぼくらのような学生に声をかけて、高橋アキさんにそれらの作品を初演してもらうコンサートを企画して、そこに武満さんも聴きに来てくださったというわけです」
――しかし、77年に発行された「音楽全書」という雑誌への寄稿では、〈武満の感性ってさ、ユーミンとほとんど同じものを持ってる〉と発言されています。
「それはね、新宿のバーでお目にかかったとき、武満さんがマイクを持ってユーミンを歌っていたんですよ(笑)。こっちもびっくりして。武満さんのポップスじみた曲ってあるじゃないですか。ぼくはあれがあまり好きじゃないんです。ユーミンを歌ったりする人なんだなって、ショックとまではいかないけれども、なるほどなと思うところがあったんです。しかし、ぼくは三善晃さんのことはほとんど書いてもいないし発言にも出てこないのに、なにかといえば武満、武満と言っているのはよっぽど気になっていたんですね」
――79年9月にYMOのセカンド・アルバム『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー』がリリースされています。このアルバムに収録された“キャスタリア”という曲は武満氏の音楽が下敷きになっていると発言されています。
「それは厳密なものじゃなく、雰囲気くらいのことです。音楽的には武満さんなんかよりもはるかに保守的な曲です。ぼくはとくに『地平線のドーリア』が好きだったんですよ。武満さんの『弦楽のためのレクイエム』のような、もやっとしていてあまり音の動きが明確じゃない曲を作りたかったんでしょうね」

――坂本さんによる武満氏への批判を辿ると、〈邦楽器によるジャパネスクを安易に取り入れたこと〉から、〈民族性と切り離されたエリート性・階級性の強い音楽を象徴した作曲家であること〉へと移行し、そして〈時代の流行に乗り、ロマンティックな表現へと向かっていること〉へと推移しているように感じられます。
「ちゃんと動向をフォローしているんですね(笑)。ということは武満さんの作品をちゃんと聴いていたっていうことかなあ。武満さんはどこまで行っても、個人の美意識の世界でしょ。それは武満さんという作曲家にとってどうしようもないことだけれども、悠治さんはもともとがコンセプチュアルな作曲家でしたから、そのころは対照的な存在に見えていた。武満さんを批判したってどうしようもないんだけれども、19世紀的な芸術のありかたはもうやっていてもしょうがないっていう気持ちが強かったんでしょうね」

ロンドンでの再会
――83年5月に映画「戦場のメリークリスマス」が公開され、武満氏は坂本さんによるこの映画の音楽を非常に高く評価されています。武満氏がそうした発言をされているのをご存知でしたでしょうか。
「いや、知らなかったですね。武満さんが評価してくださっているというのは秋山邦晴さんから直接聞きました。それもうれしかったですね(笑)」

――91年10月10日から13日にかけて、ロンドンのバービカン・センターでは〈ザ・タケミツ・シグネチュア〉という特集が組まれています。この特集では武満氏もロンドンに招かれ、坂本さんとデヴィッド・シルヴィアンとで昼食をご一緒される機会があったようです。76年に新宿のバーでお会いしてからロンドンで再会されるまで、武満氏とお話しされる機会はございましたか。
「なかったような気がしますね。ロンドンで会ったときは、その間にデヴィッド・シルヴィアンと武満さんが友達になっていたというのが不思議でね。どうやって知り合ったのかいまだに分からないんですけれども、シルヴィアンから〈明日、武満さんと会うけど来ない?〉なんて電話がかかってきてびっくりした。まったく領域の違う2人が友達になっているという。ぼくが紹介するんならまだしも、シルヴィアンに誘われるっていうのは不思議な感じでした。
ぼくはほいほいと行ってですね、武満さんの娘さんもいて、ずいぶん長く話しました。3時間くらいかな。ぼくの大好きだったロンドンのブレイクス・ホテルの地下にエスニックのレストランがありまして、そこでお昼を食べ始めたんだけどランチ営業が終わっちゃって、残っているのはぼくらのテーブルだけになっても話が盛り上がっていた。わだかまりのようなものは2人ともすっかりなかったような気がします。そこで小津安二郎の映画の話をしたのはよく憶えています」

――3人で創作をしようと約束されたと発言されています。
「誘われました。小津の映画の音楽があまりにも凡庸だから(笑)、2人で作り直しをしようって。小津の映像はバウハウスのモホリ=ナジに匹敵するようなすばらしいものなのに、音楽はそれにまったく釣り合っていないじゃないか、おかしい、それなら2人で作り直そう、って盛り上がったわけだけれども、シルヴィアンもいるわけなので、世代やいろいろな垣根を超えて3人でもなにかをやろうということでも盛り上がったわけですね。それからすぐに武満さんの側からこれをやらないかということで連絡があったのが、あまり好きではない武満さんのポップ・ソングの仕事だったんですよ。
武満さんは石川セリさんと仲がよかったですよね。セリさんが歌っている武満さんのポップ・ソングのアルバムがあるでしょ。あのアルバムでぼくにもアレンジをしてほしいという依頼だったんです。ぼくが忙しかったこともあり、武満さんとコラボレーションするならポップ・ソングじゃないだろうという気持ちもあり、けっきょくはポピュラー・ミュージックの人に見られているのか、というがっかりした気持ちもあり、そして、実験的なことをシルヴィアンも入れてやりたいという強い気持ちもあった。だからうだうだ言っていて、結局やんなかったのね。
そうしたら武満さんが亡くなったあとにセリさんから連絡があって、〈あのとき武満さんは待ってたわよ〉と言われてしまった。やればよかったとそれはショックでした。セリさんの仕事は逃げちゃったけれども、絶対になにかやれるはずだと思っていたので、その後入院されて亡くなったというのを聞いてほんとうに残念だった」
「LIFE」以降
――武満氏に対する評価は、99年9月に初演されたオペラ「LIFE」を機に変わっていったものと思われます。
「『LIFE』という作品は戦争と革命の世紀である20世紀の歴史というものを、いわばオペラのリブレットにして、いくつかのアスペクトで切っていくというものだったんですね。音楽的には20世紀のいろいろなヨーロッパ音楽のスタイルというものを、模倣的に後追いしていくというようなかたちになっている。ちょうど世紀をまたぐあたりのドビュッシーからミニマリズムのあたりまでを追っていくなかで、20世紀の音楽というものを聴きなおしてみたんですね。
長くファンであったピエール・ブーレーズですとか、メシアンとか、ヴェーベルンとか、ケージとかをまとめて聴いたんだけれども、やっぱり武満さんの音楽の強さっていうものを改めて認識させられたんです。100年後にブーレーズの音楽は誰も聴いていないかもしれないけれども、武満徹の音楽は100年後も聴かれているだろうと思いました。ルチアーノ・ベリオなんていう作曲家はすばらしい音楽を書く力を持っている人で、ぼくはとても尊敬しているんです。でも、いまでさえヨーロッパですらだんだん演奏されなくなってきている。残酷なものですよね。
しかし、武満さんの作品はますます再演が繰り返されるようになっているという話を、昨日、藤倉大くんとしていたところなんですけれども、それだけ強い魅力が武満さんの音楽にあると思います。大くんの意見では、ブーレーズは自分で自分の作品を指揮して録音しちゃったから、もうあれ以上の演奏はできない、誰も再演したくならないよね(笑)ってことなんですけれども、確かにそういう面はあるかもしれないですね」

――武満氏が59年に手がけた映画「ホゼー・トレス」の音楽を高く評価されています。
「『ホゼー・トレス』の場合は、映画音楽としてというよりも音楽として佳作であるということで、とても好きな作品です。日本人でこんなに美しい動きによるハーモニーの音楽を作れる人間がいたんだということに、いま聴いてもびっくりさせられるんですよね。武満さんご本人がいちばんそう思っていたかもしれないけれども、なんで俺はフランスに生まれなかったんだ、極東で日本語を喋っている俺は、何者なんだと感じていたんじゃないかと想像させられてしまう。
映画音楽として考えますと、高く評価できるのは実験的な『怪談』(65年)ですかね。『切腹』(62年)っていう映画もあるでしょ。ぼくは何年か前に『切腹』をリメイクした『一命』(2011年)っていう映画の音楽を担当したんです。武満御大がやられた『切腹』のリメイクをぼくがやることになったので、心して見直してみましたけれども、映画音楽としては正直言って古い感じがしてしまいました。やっぱり現代音楽ふうというか。
でも、数年違いで作られた『怪談』はいまでも新しいというか、古くはなっていない。その音楽は通常の映画音楽という範疇に入らないような音楽で、いまでもとてもおもしろいですね。『怪談』には胡弓だけで、数分間ほど一音だけが続く場面があるんです(第1話「黒髪」のラストシーン)。一音しかないのにものすごい強さなんですよね。いまでも自分でなにかを作るときには常にそのことを考えます。
あれは究極だと思うんですよ。回転を落とした琵琶のビィーンっていう音。あれも一音じゃないですか。一発の音だけで映画音楽としてものすごい効果を生み出している。そのように極端に切り詰められたなかで、強い表現力を出すというのは映画の音楽を書くときの課題だといつも思っています。ただ、並の映画であれをやると音楽のほうが強すぎる。ああいう音を入れられるような映画なんてそうざらにあるものじゃないと思います」
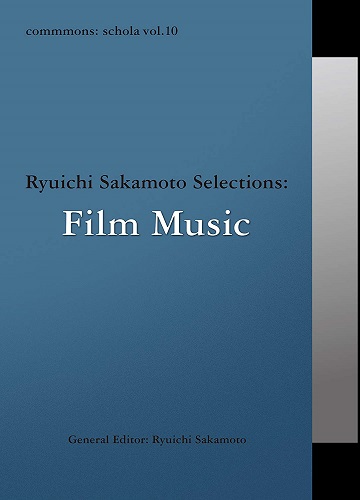
VARIOUS ARTISTS 『commmons: schola vol. 10 Ryuichi Sakamoto Selections: Film Music』 commmons(2012)

武満徹の電子音楽
――武満氏の作曲された広義の〈電子音楽〉をどのように評価しておられますか。
「例えば『ヴォーカリズムA・I』なんていう作品は聴いているとむずむずしちゃってね、実はあんまり好きじゃないんですよ(笑)。ただ、川崎さんの書いた『武満徹の電子音楽』を読んで、〈愛〉という言葉を使ったのはピエール・ルヴェルディという詩人からの影響が関係しているのかもしれないことが分かったし、ミュージック・コンクレートを聴いてもいなかった若いころから、具体音を使った音楽を独自に構想していたことも知りました。
日本最初のミュージック・コンクレートを作った黛敏郎さんですら、武満徹が日本で唯一のミュージック・コンクレートの作曲家だったと認めていた、なんてことも書かれている。ですから、武満さんの電子音楽はたいへん重要だったんだなと思うし、武満さんの尺八やガムランに対する興味も根っこは同じなんだなと思う。また西洋の楽器を具体音として使いたいという欲求があんなに若いときからあったということも驚きですね。
そう思って聴き直すとなるほどなとは思うんだけれども、いまの耳で聴くとリバーブやディレイなどが当時の音ですから、かなり古臭く感じてしまうんだよね。いま作ったら違うと思うんだけど。ただ、ぼくはミュージック・コンクレートのコンセプト自体はすばらしいと思うのね。そのコンセプトを思いついたピエール・シェフェールはすごいと思うけれども、シェフェールの作品というのはおもしろくない(笑)。
当時、武満さんが黛さんによる初のミュージック・コンクレート『X・Y・Z』を聴いて、具体音楽だけれども音楽的には保守的じゃないか、以前の音楽と同じじゃないかと感じたという意味のことも書いてありましたけれども、黛さんという人は昔の音楽語法を守って具体音楽を手がけたわけですよね。武満さんがそれを的確に批判したというのはさすがだと思うし、表層的に使われている具体音だけではなく、その背後にある音楽性をきちんと聴き取っているというのもさすがだと思いますね。
いままでのぼくは面倒だから鍵盤を使って作曲していた。ものすごく遅いんだけれども、ここに来て12平均律などの呪縛からやっと解かれ出したんです。そういう音楽がほとほと嫌になっちゃってね。家に2台あるピアノも1台は調律するのを止めて、どんどん狂っていけばいいと思っているんですよ。塩とか塗って錆びさせたらどうなるんだろうなんて考える。弦の間にコーヒー豆を落としてみるとか、最近はそんなことばかりやっているんです。内部奏法もケージのような繊細なものではなく、石をバーンと転がしてみたりとかね。
だから、10歳のときに草月会館で観たような、ああいうところに戻りつつある。あと20年くらいは生かしてもらって、武満さんを追いかけないといけない(笑)。あらゆる音楽が平均律を土台にしていて、売られているシンセサイザーだってもちろんそういうものですよね。使っている音楽のソフトウェアにしても拍節構造ありきですから、なかなかそこから抜け出すのは難しい。武満さんもそういうことを目指していたと思いますが、ぼくにとって絵を描くように音楽を作るような手段がやっと整いつつある。だから、いまこそ武満さんとコラボレーションできたらおもしろいと思うんですよね」































