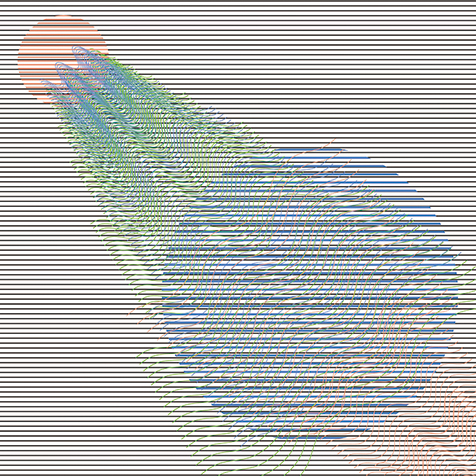2010年代後半のサイケデリック・ポップを先導してきたTempalayが、ニュー・アルバム『21世紀より愛をこめて』を完成させた。
昨年7月にそれまでサポートだったAAAMYYYが正式加入。新体制の初作として発表された『なんて素晴らしき世界』収録の“どうしよう”がBTS(防弾少年団)のRMにSNSで取り上げられ、バズが起こったことも記憶に新しい。海外アーティストのオープニングのみならず、国内の著名アーティストからの対バンオファーも増え、バンドを取り巻く状況はこの一年でドラスティックに変化した。
前作のリード・トラックである“どうしよう”や“SONIC WAVE”も含んだ全12曲のアルバムは、暴力的かつ退廃的な雰囲気はそのままに、これまで以上に〈美しさ〉にフォーカスを絞ったような一枚。ジャンルの融解が前提となったその先で、各楽器の音色をブラッシュアップすることにより、小原綾斗のソングライティングの魅力がより露わになっていて、曲によってはスタンダード感すら漂う。
PERIMETRONと山田健人が共同で制作した“のめりこめ、震えろ。”のミュージック・ビデオでメンバーは戦士のような恰好をしているが、かつて“革命前夜”を歌ったバンドが、いよいよ革命の朝を迎えようとしている。それはきっと、日本の音楽シーンにとっての新たな時代の幕開けにもなるはずだ。
自分が生きた時代=平成の雰囲気を閉じ込めた(小原綾斗)
――『なんて素晴らしき世界』は〈地球の誕生から滅亡まで〉を描いた作品でしたが、SF的な世界観が引き継がれていたり、インタールードだった“THE END”のフル・ヴァージョンが収録されていたりと、『21世紀より愛をこめて』のコンセプトも前作の延長線上にあるのかなと感じたのですが、実際いかがでしょうか?
小原綾斗(ギター/ヴォーカル)「いや、関連性は特になくて、今回は今回で別のコンセプトがあります。前作が〈始まりから終わり〉だとしたら、今回は〈いまこの瞬間から未来へ〉みたいなコンセプトなので、ある種地続きなのかもしれないですけど」
――連作とかではないけど、共通するムードはあるというか。
小原「昔ボイジャー探査機にレコードを乗せて、宇宙人に向けて飛ばしたという話があるんですけど、ロマンチックだなと思って、それにインスピレーションを受けて作ったので、今回もSFチックではありますね」
――この作品を宇宙船に乗せて飛ばすようなイメージがあった?
小原「そうですね。平成が終わったタイミングで、自分が生きた時代の雰囲気をそこに閉じ込めて、どこかで誰かがその匂いとかを感じてもらえればという。まあ、CDってそういうものですよね。元号が変わるタイミングで、何となく残さなきゃいけない気がして」

――そういうコンセプトって、メンバー同士の普段の会話から出て来るものなんですか? それとも、そこに関しては綾斗くんが考える?
小原「完全に一人で、悶々と(笑)」
藤本夏樹(ドラムス)「僕は単純に楽曲に対してどうアプローチするかだけを考えてました。平成に思い出がないわけじゃないですけど(笑)、そのコンセプトを聞いて、〈じゃあ、音楽をこうしよう〉とはあんまりならないと思うので」
AAAMYYY(シンセサイザー)「同じです。私はわりと歌心のほうに心が向いてしまう性質ではあるので、デモの段階では歌詞がないから、曲としてのアプローチに集中して、歌詞ができてからは、より深い世界観を理解して、消化しようとする、そういう作業でした」

〈おどろおどろしいもののなかの美しさ〉をテーマに作りたかった(小原綾斗)
――AAAMYYYさんが正式メンバーとして加入して2作目になるわけですが、曲作りの工程自体は変わらないですか?
小原「変わってないですね。これまでも今回もそうなんですけど、僕らプリプロをやらないので、レコーディングが終わるまでどんな作品になるのか誰もわかってないんです。なので、コンセプト的なものを話してもあんまり意味がないんですよ。
曲の色味とか、そういうことは共有してて、今回で言うと、〈おどろおどろしいもののなかの美しさ〉をテーマに作りたかったので、リファレンスの曲を出したりはしたんですけど、〈このアルバムはこういう想いがあって〉とかは言わないですね。それは野暮だし、恥ずかしいですから(笑)」
――〈おどろおどろしさのなかの美しさ〉は、これまでの作品にもあった感覚ではあると思うんですよね。
小原「それは自分から滲み出た毒素の結果だったと思うんですけど(笑)、今回はそこを意識的にフィーチャーしたので、それはこれまでとは全然違って。
気持ち悪い、違和感の残るものと、美しいもののちょうど間は何だろうと考えて……こういうアウトプットになったってことですね。今回はコンセプトがはっきりしていたので、1曲目から順番に作っていったんです。いままではもっとばらついてたというか、無意識だったんですけど」
――リファレンスとしては、どんなアーティストを挙げたんですか?
小原「いろいろ挙げたんですけど、特にルイス・フューレイと、久石譲の『菊次郎の夏』(99年)と『ソナチネ』(93年)のサントラは大きくて、〈こういうものを混在させたい〉と。根底にそのイメージがありつつ、そのうえでTempalay的なビートやメロディーが乗れば、いままでと違うものが作れると思ったので、そういったことは伝えましたね」
――新しいインプットというよりは、自分のライブラリのなかから、今作のイメージに合うものを引っ張り出してきた感じ?
小原「むしろ後付けというか、曲ができた後に、これをどう伝えればいいのかを考えて、さっきの名前が出てきた感じです。自分の曲はすでにアウトされてて、それを説明するためにリファレンスを挙げたという順番ですね」