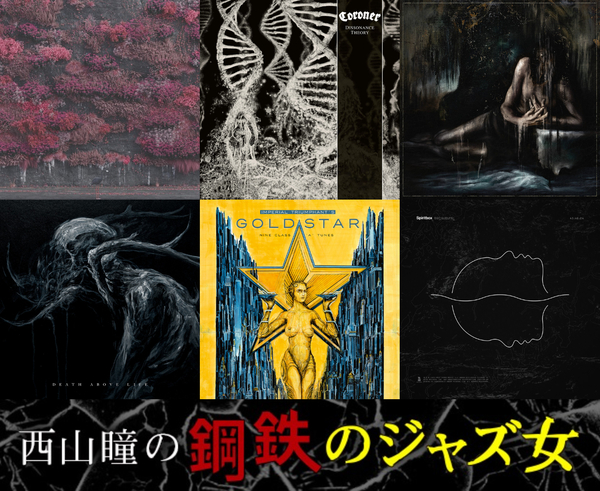「ザ・トライブ」
-少年たちは音のない荒野を歩く-
畏怖すべき傑作だ。人間とは何かという問いに対する一つの強靭な答えが、示されているからだ。加えて、かかる認識に至る過程に、映画とは何かという問いに対する答えもまた、鮮明に浮かび上がってくるからだ。
聾唖の少年少女を集めた学校の寄宿舎を舞台に、彼らの不良グループ内の交流や確執が描かれるのだから、セリフが全て手話で交わされるのは当然としても、字幕が一切ないことに、まずこの映画のスタンスが見てとれる。字幕の排除により、声を介してのやりとりとは全く違う次元の会話が出現する。指と手がナイフの切っ先のように高速で空を切り裂く、激しく強いアクションとしての会話。そこから彼らの心は、原初的な意志と意志とのぶつかり合いとして、投げ出されてくるのだ。

彼らの顔から表情が排除されていることも、それに資するもう一つの映画的要素だ。顔の表情でなく、身体の「言葉」だけが、一瞬一瞬、後戻りなど出来ようもない切迫した思いを表現する。彼らの無表情を見ていると、翻って健常者の顔に浮かぶ表情が、ひどく曖昧で脆弱なものに、見えて来たりもする。
手話はまた、視線のやりとりが作る人間の関係性を描き出す。手話での会話は互いをひたすら見据えることでのみ、成立する。その視線の会話が、人と人とを濃厚に結びつける。新来の主人公は少年たちの見つめる舞台めいた場所での殴り合いに引きだされ、彼らの視線の洗礼を受けることで、「群れ」に受け入れられていく。見る・見られることでしか成り立たない人間関係が、生まれるのだ。
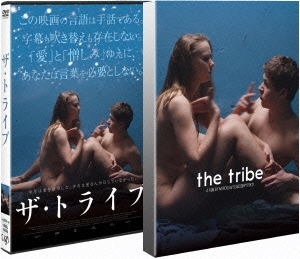
逆に、視線の届かない空間が彼らにとっては常に死角であることを、映画はときに身も蓋もないユーモアを交えて(トラックに緩慢に轢かれる少年!)、ときに凍り付くほどの残酷さで(無音の空間から襲来する致命的な打撃!)、伝えてくる。死角から文字通り死が迫る野生動物のような世界に、彼らは生きている。
人が無言で歩くシーンが多いことにも、この映画の世界観が現れる。カメラが歩く人を延々と追ううちに、歩行は特別な意味を帯びたアクションになっていく。空間を歩き続ける時間の中で、取り返しのつかないものが生起し積み重なる。衝撃のラスト数分、ひたすら歩く主人公をワンショットで追う場面は、愛と憎悪が導火線を辿り、やがて世界を破壊し尽す憤怒が爆発する過程を、見つめ続ける。