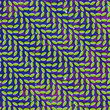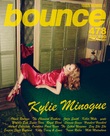EMPIRE STATE OF MIND
【特集】深化するNYインディー
この街からはいつだってヒップでクールな音楽が聴こえてくる――トレンドの賞味期限は日に日に短くなる一方だけど、それだけはずっと変わらない事実。インディーの首都NY、その最新コレクションを覗いてみよう!
★Pt.2 ラ・ラ・ライオット『Need Your Light』のインタヴューはこちら
ANIMAL COLLECTIVE
僕らは誰ひとり、理論的に音楽を語ることができないんだ。だから今回は絵を描く作業になぞらえて制作を進めたよ

前作『Centipede Hz』を2012年にリリースしてからのアニマル・コレクティヴは、メンバーの課外活動が目立っていた。エイヴィ・テア(ギター/ヴォーカル)はエイヴィ・テアズ・スラッシャー・フリックスとして『Enter The Slasher House』を作り上げ、パンダ・ベア(ドラムス/ヴォーカル)はソロで『Panda Bear Meets The Grim Reaper』を発表。さらに後者は2014年の〈TAICOCLUB〉出演のために来日し、素晴らしいステージも披露してくれた。それゆえに不在感はまったくなく、本隊でのニュー・アルバム『Painting With』が完成したとの報を耳にしても、久しぶりという印象は受けなかった。今回はエイヴィとパンダ、そしてジオロジスト(サンプラー)の3人によって制作され、もう1人のメンバーであるディーケン(ギター)は不参加。作品ごとに参加メンツの変わる流動的な活動形態を取ってきたグループなので、この件に関しては特に心配することもないだろう。
〈キャッチー〉の定義がよくわからない

さて、『Painting With』の話。ジャムの要素が強く、実験的な側面が際立っていた前作とは違い、今作にはキャッチーでメロディアスな瞬間がいくつも登場する。チープすれすれのシンセ・サウンドはハッピーなヴァイブスを醸し、ひとつひとつの音が飛び跳ねるように聴こえてくる。アニマル・コレクティヴ特有のトリッピーな音像は健在だが、それがハイな方向に出ていると言っていい。とはいえ、アルバムのキャッチーさは意図して生み出されたものではないようだ。
「そもそも僕には、どういうものがキャッチーなメロディーなのかわからない。〈キャッチー〉とか〈馴染みやすい〉とか、そういう言葉の定義って個人差が凄く大きいんじゃないかな。僕としては、自分が聴いてクールだと思うものを書いているだけ。だから、それがポップかどうかを分析するのは難しいよ。それに、前にも僕らの楽曲について〈あんまりとっつきやすい音楽じゃないですね〉と言われたことがあってさ。でも自分じゃその意味がよくわからなかったんだ。だって僕からしてみれば、そういう曲にもいっしょに歌えるようなメロディーがちゃんとあったからね」(パンダ・ベア:以下同)。
気を取り直して、本作ではヴェルヴェット・アンダーグラウンドのオリジナル・メンバー、ジョン・ケイルとの共演も果たしている。言うなればこれは、NYの過去と現在が繋がったコラボレーション。同地のロック・シーンを追い続けてきたリスナーにとっては、まさに夢の合体といったところか。
「デイヴ(エイヴィ・テアのこと)の姉妹がジョンのライヴの視覚効果を担当していて、それがきっかけでジョンとは繋がったんだ。ブライアン(ジオロジストのこと)の書いた“Hocus Pocus”には、ストリングス・サウンドを使ったパートがあるんだけど、あれはもともとサンプラーの音で作っていて、誰かが生の弦楽器を弾いたわけじゃなかった。でも、音のクォリティーがいまひとつでさ。そこで、〈誰か呼んでヴィオラを弾いてもらおう〉という話になった。幸運にもジョンとの都合がついてヴィオラを弾いてもらったんだけど……それがハマらなかったんだよね。で、ジョンが持って来てくれた他の楽器をあれこれ試してみたなかから、あのサウンドを採用したんだ」。
また、“FloriDada”ではホーン楽器が使われているのも興味深い。というのも、アニマル・コレクティヴにとってそれは馴染みのない音色だからだ。彼らからしてみれば新たなチャレンジとも言えるが、コリン・ステットソンの力を借りることで、その挑戦を見事に成功させている。
「“FloriDada”にはサックスの音色が欲しいと最初から考えていた。ああいう音って、これまで僕らが作ってきた音楽のなかでは、適切な居場所を見つけることができずにいたからね。でも、今回は何とか成功させたかった。僕らにとってはクールで、新しい試みってことだよ。メンバー全員がコリンの大ファンだったから、彼がスタジオに来てくれたのは本当にありがたかったね。中間部のインストのブリッジがそうなんだけど、スタジオに来てくれたコリンにその部分を聴いてもらって、あとは彼にお任せ。すぐにサックスを吹きはじめ、45分間くらい吹きまくっていたかな。ひと通り吹くと、違うサックスに持ち替え、また吹きはじめて……みたいな感じ。コリンはあの楽器にかけては自由自在で、本当に凄いプレイヤーだと思う」。
音楽というよりも絵画
NYは音楽だけでなく、さまざまな文化の更新を常に促してきた。ポップ・アート、ハーレム・ルネサンス、抽象表現主義など、例を挙げたらキリがないほどだ。今回メンバーにインタヴューをして思ったのは、アニマル・コレクティヴもまた、その例のひとつに数えられるのではないか、ということ。この考えは、次の発言を受けてより強くなった。
「僕らは誰ひとり、理論的に音楽を語ることができないんだ。相手に何かを伝えるのもジェスチャーだったり、イメージだったり、メタファーだったり……そうやって何とかわかってもらおうとする。どういう曲にしたいか、どういうプレイをしてほしいか、この曲には何が必要か、みたいな説明は全部そんな感じだよ。『Painting With』の制作中は、絵を描く作業になぞらえて会話することが多かった。〈この曲の僕のパートは、単色で思い切り太く、バシッと筆を入れて、わりと遠慮のない感じで全体に塗りたくりたい〉とか言ってみたりね。文字通り〈何で描くか〉を語り合ったんだ」。
もはや彼らは、音楽シーンだけに留まる集団ではない。たくさんのカルチャーを吸収しながら発展と撹拌を続けてきたNYという街の化身、それがアニマル・コレクティヴだ――言われてみれば、〈音楽〉というよりも〈絵画〉と表現したほうがしっくりくるこの新作を聴いていると、そう思えてならない。