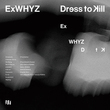フィリピン出身、LA在住のトラックメイカー、マーク・レディート。彼はスパズキッド(Spazzkid)名義で活動を始めると、フューチャー・ファンクの代表的なレーベルであるキーツ・コレクティヴからリリースした2013年作『Desire 願う』で認知を拡大。その後もネット・シーンを中心に世界各地の才能溢れるアーティストたちと親交を深めながら、EP『Promise』(2014年)やそのリミックス盤『Promise Remixes Pt. 1』〈同Pt. 2〉などを次々と発表。2015年にはアーティスト名義を本名のマーク・レディートに改名し、この度日本デビュー作となる編集盤『Krista』をタワーレコード先行でリリースした(5月13日に全国一般リリース)。
本作に収録されているのは、スパズキッド時代から現在までの楽曲のなかから厳選された、これまでのベスト盤とも言える楽曲の数々。UKのケロ・ケロ・ボニトからサラ・ボニトを迎えた“Truly”や、There Is A Foxを迎えた“At Fault”を筆頭に、どこか愛らしくプレイフル、それでいて時に懐かしい記憶を思い起こさせる彼の楽曲には、まるで〈日常のなかに生まれた小さなファンタジー〉とも言うべき魅力がぎっしりと詰まっている。
今回は幼少期から現在までの記憶をヒントに彼の音楽性のルーツを聞いたメール・インタヴューに加えて、記事の後半ではリミックスなどを通して交流のあるtofubeats、Seiho、banvox、八王子Pからのコメントも掲載(マークからも彼らへのメッセージが到着!)。この不思議なポップ職人の素顔に、さまざまな角度から迫ってみた。

――あなたはもともとフィリピンで生まれて、両親が音楽好きだったために自然と楽器を演奏するようになっていったそうですね。小さい頃はどんなものが好きで、どんな子どもでしたか。また、そこからLAに引っ越したきっかけは?
「当時は僕と母と父、そして2人の妹とで小さな家で暮らしていて、いつも笑いと温もりに包まれた家庭だった。何時間も砂場でお気に入りのトラックのおもちゃで遊んでいたよ。自分の手で物を作ることに興味を持っていたから、父親は僕が彼のように建築技師になると思っていたみたいだね。あと、子供の時はよく〈He-Man〉(コミックとアニメ・シリーズのキャラクター)の絵を描いていて、結構上手かったんだ。その当時から親戚の半分はアメリカに住んでいたんだけど、母が他界したときに父親が新しい仕事と新たな出発を求めてアメリカに移った。そして残りの家族も数年後にそれに続いたんだ」
――DTMを始めたきっかけは? どんなところに魅力を感じましたか。
「DTM やエレクトロニック・ミュージックは10年以上前からやっているね。最初はインディー系のロック/エモ・バンドをやっていて、メンバーに聴かせるデモを録音するのにMIDIを使っていた。そうするうちに、その技術を身に着けるのにハマって、ソロでのプロジェクトも追及したくなったんだ。それがスパズキッドを始めるきっかけになったんだよ。DTMやエレクトロニック・ミュージックがいいのは、好きな楽器を何でも選べたり、無作為ななかから自分だけの音を作れるところ。楽器も一通り少しずつ弾けるけど、ソフトウェアで得られる表現の自由がすごく気に入っているよ。バンド・メンバーやそのパートに頼らず、自分だけで曲を作ったり演奏できる。僕はもともと自分でいろいろこなすのが大好きだからね」
――では、自分の音楽観に大きな影響を与えた作品というと?
「まずはPerfumeの“Chocolate Disco”。中田ヤスタカがプロデュースした曲で初めて聴いたのがこの曲なんだ。キャッチーでシンプルなところが気に入っているよ。数秒も聴けば、みんなでシンガロングして一緒に歌いはじめられる。彼のプロデュースはいつも天下一品で、どの作品でも音が美しく重ねられているし、豊かに聴こえるところに感銘を受ける。ミュージック・ビデオでのメンバーのダンスもかなりイケてるよね」
「それからプナウ“Baby (Breakbot Remix)”。実はブレイクボットの大ファンなんだ。グルーヴを揺るぎなく操るところや、素晴らしいメロディー・センスを備えているところが最高だよ。これは初めて聴いた彼の楽曲のひとつ。シンプルなメロディーやコード、ソウルフルなディスコ・グルーヴに、最新の技術がイイ具合に組み合わさっている。彼の音楽にはいまでもインスパイアされているんだ」
「トロ・イ・モワの“You Hid”は、初めて聴いたときにその場で心を奪われた。泥臭くて過剰なまでに圧縮されている仕上がりが好きなんだ。チルアウトしたビートに乗って、シンプルなメロディーが繰り返されるところもいい。チャズ(・バンディック)の歌声を聴いて、僕も自分の曲でもっと歌おうと思うようになったんだ。彼は作品ごとに異なるサウンドをめざしているのも素晴らしいよね。それは僕もアーティストとして心掛けていきたいことだよ」
――2013年の『Desire 願う』はあなたの音楽が認知されるきっかけになった作品でしたが、以降の作品にも日本のモチーフが頻繁に登場します。日本のカルチャーに興味を持ったきっかけや、そのなかでも特に好きなものを教えてください。
「小さい頃から『超電磁マシーン ボルテスV』や『闘将ダイモス』『鉄腕アトム』みたいな往年のアニメを観ていたよ。サントラも本当に気に入っていたし、それが僕のメロディー感覚を特徴付けることになったと思う。日本のアニメはいまでもインスピレーション源で、スタジオジブリ作品は特にお気に入りだね。最近では『スペース☆ダンディ』もかなり良かった。この作品はサントラもイケてるよね(岡村靖幸“ビバナミダ”、ジャンクフジヤマ“星屑のパイプライン”などを収録)。若い頃はピチカート・ファイヴを聴いていて、僕はそこからCAPSULEやPerfume、きゃりーぱみゅぱみゅのような中田ヤスタカのプロデュース作品に辿り着いた。あと、食べ物も最高。そこは絶対だね。親しい友人のRyoと日本の食べ物を食べたり作ったりしてるよ。最近の日本のストリート・ファッションの熱烈な愛好家でもある。それに、〈必要なものだけ所有する〉という日本のミニマリズムの美学が好きなんだ」
「ここアメリカでは、メジャーな音楽シーンでアジア人が取り上げられることはあまりないから、アジア系アメリカ人として自分のコミュニティーを取り上げることには責務だと思っている。だから、僕のMVには意図的にアジア人やアジア系の人を登場させているんだ。映画作りをしている友達のツァー・カンポス(Czar Campos)が日本に住んでいて、彼がMVの監督を務めてくれた。それが最高の出来だったから、これまで3本作ってもらったんだ」
――近年は日本も含む世界中のアーティストがインターネット上で繋がるようになりました。インターネットによって世界は近くなったと思う? それとも広くなったと思う?
「どっちもかな。自分が好きなアーティストに直接連絡を取って友人関係を築けるようになったという意味では小さくなったと思う。でも一方で、物理的には無理でも友達になりたいと思えるクールな人たちを知ることになったという面では、広くなったとも言えるからね」
――今回の日本編集盤『Krista』では、これまで発表した楽曲のなかから、どのように収録曲を選んでいったのでしょう?
「『Krista』に選んだ曲はどれも間違いなく僕の気に入っているものだよ。スパズキッド名義のものからマーク・レディートとしての作品まで、これまで表現してきたサウンドの幅広さや感情などを披露できたらって考えていた。なかでもハイライトを選ぶなら、まずは“Getting To Know You”。ガールフレンドを思いながら歌詞を書いて、歌はワンテイクで歌い切った。ファンの人から〈これを愛する人に捧げている〉なんて聞くこともあって嬉しい曲だよ」
「あと、“Truly”のトラックとメロディーは数時間で書き上げたんじゃないかな。それをケロ・ケロ・ボニトのサラに送って、歌詞を付けて歌ってもらった。サラとはオンラインで繋がって、〈一緒に曲を作らない?〉って訊いてみたんだ。そしたら、すぐに〈イエス〉って返事が来てね! 数日後には歌詞のついたヴォーカル・パートが送られてきたよ。サビは20種類ほど用意したけど、結局一番シンプルなものに落ち着いた。これまでやったコラボのなかでも最上級に楽しかったな。去年の〈SXSW〉では一緒にこの曲をプレイできて嬉しかったよ。それともう一つ、アップテンポで楽しい曲を作ろうとしたのは“Don't Tell Anyone”。曲中で使っている音声は、Twitterで〈don’t tell anyoneと(声を)録音したものを送ってください〉って募集したものなんだ」
※ケロ・ケロ・ボニトとMaltine主宰・tomadの対談記事はこちら
――“At Fault”に参加したThere Is A Foxと知り合ったきっかけは?
「2013年にShanghai’d Room というライヴハウスでプレイしたときに、There Is A FoxのHiroと出会ったんだ。クールで才能溢れるギタリストだよ。彼の音楽をSoundCloudで聴いてすごく気に入ったから、それをサンプリングしていいか訊いてみたらOKが出たうえに〈追加するギター・パートも作ろうか?〉と手を差し伸べてくれた。彼はちょうど日本に引っ越そうとしていて、曲が完成するまでに時間は掛かったけど、仕上がりは最高だから僕はすごくハッピー。いつかまた一緒に仕事したいな!」
――アルバム・タイトルの『Krista』は、女の人の名前から取ったものですか?
「そう、一般的に〈Krista〉は女性の名前だよね。でも、僕がこのアルバムの曲の大部分を作ったときに住んでいた通りの名前でもあるんだ。クリスタ通りの家は妹のもので、僕はそこに数年間住んでいた。小さな部屋の控えめなレコーディング機材で、本当にたくさんの時間をレコーディングや作曲に費やしたよ。あとは小さな姪っ子がいて、その子がしょっちゅう邪魔をしてくるんだ。そんな彼女の声を録ったり、キーボードで遊ばせてやったりもしたよ」

――あなたの音楽にはどこか懐かしい記憶を呼び起こすような感覚があります。音楽にまつわる思い出のなかで、もっとも嬉しかったことや、逆に大変だったことを教えてください。
「うん、僕の作品を〈懐かしいもののように感じる〉と言ってくれる人はいる。意識してやっていることではないんだけどね。これまででこの上なく楽しかった体験といえば、Giraffageと一緒にやった僕のホームタウン、LAでのステージかな。1,000人を超える観客のエネルギーもすごかったし、みんな僕の音楽で踊ったり、一緒に歌ったりしてくれて。フライドチキンを客席に投げ込んだらすごく喜んでいたよ、ハハハ。逆に駆け出しのときには、もちろんありがちな困難も経験した。例えば誰もライヴに来てくれない、とかね(笑)。観客が2人のこともあったよ(しかも、そのうちの一人は僕の彼女だった!)。でも、それでも全然良かったんだ。〈これも必要なことだ〉って、いつも自分に言い聞かせていたからね」
――あなたが音楽を作る時に、もっとも大切にしているのはどんなことですか。
「僕は音楽を通して、ストーリーや経験、感情といったものを伝えていきたい。パフォーマンスにおいては、ポジティヴィティー(前向きな気持ち)と安心感を届けたいと思う。自分にとって偽りがなくて、同時にリスナーにとっても親近感のある音楽を作っていきたいんだ」