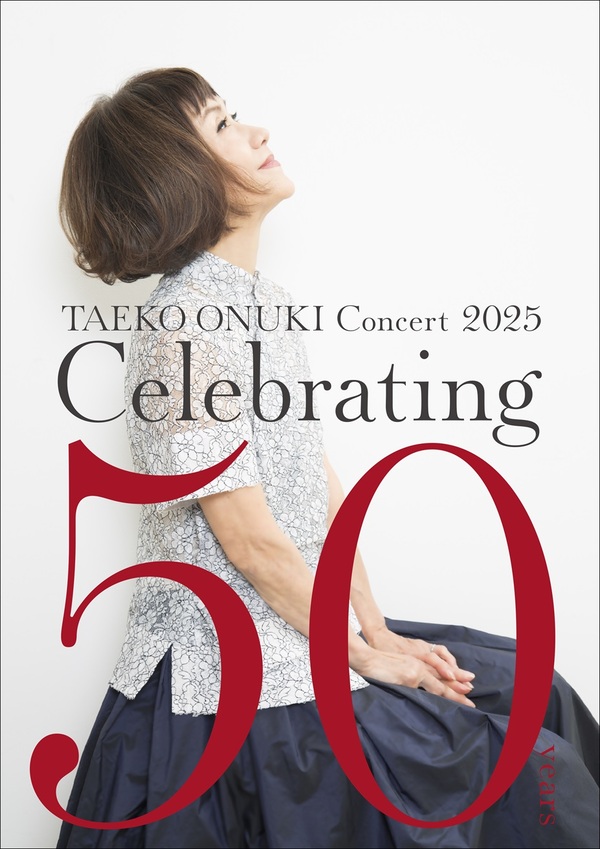沖野俊太郎がShuntaro Okino名義で2015年にリリースした15年ぶりのソロ・アルバム『F-A-R』は、サイケデリックなロック・アンサンブルと緩急自在のダンス・ビートが、虹色の昂揚感を煽る作品だった。Venus Peter時代を彷彿とさせる艶やかなソングライティングと、Indian Ropeで探求された美しくトリッピ―なサウンドメイク。双方を併せ持ちながらグルーヴィーなロックンロールに仕上げられたナンバーの数々は、沖野のキャリアを総括しつつも、作り手として次のヴァージョンに更新していくような開放感があり、従来の彼のファンを歓喜させるとともに、若いリスナーにとってもフレッシュに響くはずだ。
そして『F-A-R』のリリースから早7か月、コーネリアスや片寄明人(Akito Bros、GREAT3)、Salon Music、Koji Nakamuraなど沖野の旧友を中心に計14組が参加したリミックス・アルバム『Too Far [F-A-R REMIXES]』が完成した。バレアリックなハウスや硬質なテクノ、アンビエントやエレクトロニカ、さらに捻ったタイム感のブレイクビーツまで、『F-A-R』の楽曲を多彩なエレクトロニック・ミュージックに料理。いずれのリミックスにもダンスフロアの歓びの記憶が息吹いている今作は、90年代前半に花開いたセカンド・サマー・オブ・ラヴの多幸感をいまに甦らせてくれる。
そしてここでは、『Too Far [F-A-R REMIXES]』のリリースを記念して、Venus Peter最初期の作品にA&R/プロデューサーとして携わった与田太郎を進行役に迎え、沖野俊太郎と吉田仁(Salon Music)との対談を実施。90年代初頭のロックとダンス・ミュージックの邂逅で受けた刺激を保ちながら、新しい音楽にも好奇心旺盛に接する両者の感受性の強さには、移り変わりの激しいポップ・シーンをサヴァイブし続けているヒントを垣間見ることができるだろう。
熟成感と瑞々しさ併せ持つ『F-A-R』と、旧友たちが手掛けた『Too Far』
与田太郎「まず吉田さんは『F-A-R』にはどんな感想を持たれましたか?」
吉田仁「アルバムのリリース前にコンヴェンションみたいなライヴがあり、そこで何曲か聴いたんです。そのライヴで1曲目に収録された“声はパワー”を聴いて、すごく沖野くんらしいんだけど、それまでの沖野くんにはない瑞々しさと前向きさを感じた。僕のイメージでは、沖野君はどちらかと言うといろいろな気分を内包していくような曲が多いんだけど、あの曲には外に出るパワーがあったんだよね。で、アルバムを聴くと、特に前半の曲にはそういうイメージがすごくあって。沖野くんも(ソロでは)ずいぶん作品をリリースしてなかったから。その間には作った曲を、ボツにしたり、また新たに作ったり、たくさん試行錯誤をしていたと思うんだよね。Salon Musicも2011年に9年ぶりのアルバム『‘Sleepless Sheep』を出したんですけど、丸3~4年はかかったし、最後の最後でバーッといろいろ変えたりもした。『F-A-R』には、沖野くんにもきっとそういう流れがあったんだろうなと思える熟成感と、フルーティーな瑞々しさが両方あった。すごく良かったな」
沖野俊太郎「ズバリです」

吉田「沖野くんのソロになってからの作品のなかでもトップのほうにあるアルバムだよね」
沖野「ありがとうございます」
吉田「だから、この勢いのまま外に出ていってほしいですね(笑)」
与田「沖野くんが今回『F-A-R』のリミックス・アルバムを作ろうと思った理由は?」
沖野「それはもう流れで。小山田(圭吾)くんにプロモーションを手伝ってもらいたくて、相談していた流れで彼にリミックスを頼んだらやってくれて。それがすごくおもしろかったから」
与田「自然な流れなんですね。今回のリミキサーは僕も含めて同世代や昔からの友達が多いですよね。そうしたラインナップにした意図は?」
沖野「生活していて、例えば仁さんに会ったら〈あ、そういえば仁さんが良いんじゃない?〉とか、ホントそういう流れで。探したというより、例えばGREAT3も、たまたまライヴを観にいったらすごく良くて、〈片寄くんのリミックスって聴いたことないな。頼んでみようかな〉と。Salon Musicもリミックスの印象はあんまりなかった」
吉田「ほぼやってないんじゃない?」
沖野「ですよね。ちょっと意外でした」
吉田「1人でならあるけれど、バンドとしてやったことはもしかしたらないかも」
与田「とすれば、すごく貴重なリミックスですよね」
吉田「まあ相方を動かすのが大変だったけど(笑)」
一同「ハハハ(笑)」
吉田「でも、(竹中)仁見さんも沖野くんの『F-A-R』を気に入っていたから、すぐにでもやるとなった」
与田「僕もリミックスさせてもらったんですけど、制作前のSalon Musicのリミックスを聴かせてもらったときに、ちょっとプレッシャーというか、このレヴェルでは作れないな、と思いました。今回のSalon Musicのリミックスはすごく独特なスタイルですよね。がっつりフロア向けのダンスではないけれど、ある種の浮遊感もあるし。なにかお手本があったんですか?」
吉田「お手本はなくて、キーワードとして仁見さんが〈ドリーミーなフロア〉と言ってたんです。そこから始めた」
与田「まさにそういうサウンドでしたよね。自分はすごく90年代を感じた。あの頃に僕らがいた場所はまさにドリーミーなフロアだったじゃないですか」
吉田「どこかに当時の感じを入れようとは思っていました。いまの音像や音色なんだけれど、当時を感じさせる何かを。沖野くんからも、Venus Peter時代の“Life On Venus”や“Splendid Ocean Blue”のイメージで、と言われていたし、でも同じようなサウンドにするんじゃなく、それに通じる空気感とかそういうものがあればなと」

与田「そこは見事に出ていますね、ほかのリミキサーについては、どのように決まったの?」
沖野「1曲目の“I’m Alright, Are You Okay?“を手掛けたIzuru Miuraくん(The LakeMusic)は、彼自身が立候補して。もともとIzuruくんがSecret Goldfishというバンドをやっていた頃から仲が良かったんです。彼はいま山梨で映像の仕事をやっているから、自分のMVなんかも頼んでいるなかで、リミックス・アルバムを作るという話をしたら、やりたいと言ってくれて。Izuruくんは地元に根差した音楽仕事もやっているんですが、オーケストラの譜面を書いたり、そういう勉強もしていたらしく、それを活かしたいと言っていたので、じゃあ(リミックスしてもらうと)おもしろいかなと思った」
与田「Secret Goldfishは90年~93年くらいに、Venus Peterとよく一緒にライヴをしていたね。ハッピー・マンデーズのようなダンサーのメンバーもいたバンド。僕らがちょうど熱に浮かされたようにマンチェスターやインディー・ダンスに夢中になっていたときの仲間なんです。2曲目の“The Love Sick”をやってくれたAkio(Yamaoto)くんも一時期Secret Goldfishのベースだった」
沖野「Akioくんには、『F-A-R』のマスタリングをやってもらったんです。でも、TanzmusikやHOODRUM名義での彼自身の作品こそ凄かったというのをすっかり忘れていた(笑)。そういや、こんな近くにいるじゃんって」
与田「彼もインディー・ダンスからスタートしたんだけど、それからど真ん中のテクノに行ったんだよね。田中フミヤと一緒にやったり、90年代後半からはいわゆるテクノ・シーンで活動していて。彼がマスタリングとかをやりはじめたのは、たぶん2000年を過ぎてからだよね?」
沖野「そうだと思う」
与田「ちょうど沖野くんと同じようなルートを辿っている気がする。だから曲との相性がものすごく良いというか、出来上がりも自然な感じだったね」
沖野「〈なんで最近自分の音源をやってないんだろう?〉と思っていたし、良いきっかけになったらいいなと」