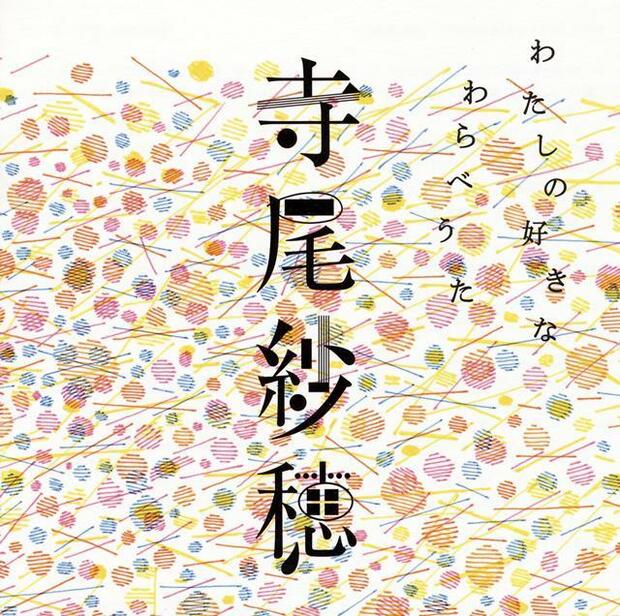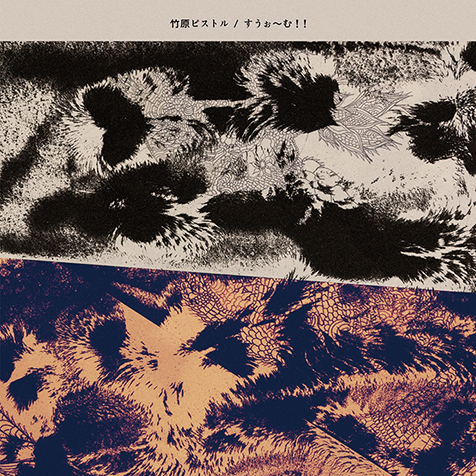シンガー・ソングライターの寺尾紗穂が、日本各地に伝わる〈わらべうた〉を歌ったアルバム『わたしの好きなわらべうた』をリリースした。同作に合わせてインタヴューの依頼が舞い込んできたとき、〈なぜ自分に?〉と訝しがる僕の気持ちを慮ってか、依頼文には〈演奏/アンサンブル面でプログレッシヴな側面が強く出ているので〉と一言添えられていたのだが、『わたしの好きなわらべうた』は、果たしてその通りの実に興味深いアルバムになっている。わらべうたを歌うということのなかには、歌詞やメロディーのみならず、演奏、アンサンブル、それにサウンドといった面においても解釈の自由を許す余地があり、寺尾紗穂はそれをいまの時代のやり方でアウトプットしてみせた。
過去から未来にリニアに進んでいく進化ではなくて、綿々と連なり、循環し、共鳴していく連続体というものがあることを、さまざまな音楽が教えてくれるのだが、わらべうたの存在もそうだろう。『わたしの好きなわらべうた』もまた、そうしたものを照らし出していて、その意味でとても今日的な作品でもある。わらべうたを歌うことから見えてくる寺尾紗穂の音楽性や音楽観を、このインタヴューでは追ってみた。
昔の人の価値観や気持ちを知ることができる
――なぜ、わらべうたをやろうと思ったのでしょうか?
「いちばんはじめは山姥(やまんば)なんです。子供と一緒に『まんが日本昔ばなし』を観ていると山姥が出てきて、そこで(山姥のことが)気になって調べはじめて。いろんな論文などを読むなかで、オザケンのお父さん(小澤俊夫)が出している『子どもと昔話』という季刊誌に出会った。そこに、彼が採譜した“徳之島の子守歌”の楽譜が載っていたのでふと口ずさんでみたら、すごく良かったんです。もしかして〈わらべうた〉という、ものすごく綺麗な歌が生み出されてきたにもかかわらず、いまその多くが知られないでいるのかなと思って。そこからですね※」
※寺尾が山姥を経由してわらべうたに出会う経緯は、〈WEB 本の雑誌〉での寺尾の連載〈私の好きなわらべ歌〉第1回に詳しい。
――そもそも、わらべうたって何なんでしょうか?
「狭い意味だと子供が歌う歌だと思うんですけど、実際はもうちょっと広く使われていて、お母さんたちが歌った子守歌とかも含めて、口承と言うんですかね、民間で歌い継がれてきた歌ということだと思います。明治時代に作られて体裁が整えられた童謡とは違って、もっとその土地ごとのヴァリエーションを持っているもの。自然を歌ったものや手毬歌、お手玉歌なんかも含めて、わりと広い意味での使われ方をされていると思います」
――寺尾さんにとって、わらべうたならではの魅力とはどういうものですか?
「このアルバムにはあまり入れてないんですけど、(わらべうたには)童謡にはないようなふざけたものや下品なもの、子供が大人をからかう歌とか、そういうものも入ってくるんですよね。富山の薬売りをからかう歌とか。彼らは〈萬金丹〉という錠剤を売っていたみたいんなんですけど、〈鼻くそ丸めて萬金丹〉と歌われていたり(笑)。おもしろいんですよね。魅力という点では、地方によってヴァリエーションが変化することや、同じ地域でも歌う人によって差が出るところが自由で楽しい。昔の人の価値観や気持ちを知ることができるのもすごいことだと思います」
――残酷なものもありますよね。
「はい。守子唄というのは子守奉公に出された少女たちが歌った歌なので、〈早く家に帰りたい〉という気持ちだけでなく、〈泣く子は川に流すぞ〉というちょっとおっかない心情も歌われていて。そういうものも多いですよね」
――でも、それが恋愛の歌に変わっていくこともあるという話を、寺尾さんの連載〈私の好きなわらべ歌〉で読みました※。そういうことは、どうして起こるのでしょうか?
「たぶんどんどん付け足されていくからだと思うんですよね。聴いたまま歌ったあとに、その先を自分で作ってみたり。わりと決まりがない歌なので、そういう意味では伝えられた方がすごく自由というか、自分自身もいろんなアレンジをすることに抵抗がない。私がこの時代にやっているという意識で今作の曲はアレンジしました」
――アレンジが曲によって本当にいろいろだから、すごくおもしろかったです。ゲスト・ミュージシャンも多く参加されているので、彼らの今作への関わりについて教えてください。まずは冒頭の新潟の“風の歌「風の三郎~風の神様」”を筆頭に、6曲でいろいろな楽器を加えている歌島昌智さん。彼はどんなミュージシャンなんですか?
「歌島さんは、出雲の方で、世界のいろいろな民族楽器ができる人なんです。今回は全面的に入ってもらいたいなと思って。それぞれの曲で、歌島さんはどんな楽器ができますか?と最初に訊きました。そのうえである程度当てはめてお願いして、歌島さんのほうでさらにこれを足すといいかも、みたいな感じで案をくれて」
――歌島さんは今作で大活躍されていますけど、そのなかでも名古屋の“お手玉唄「裏の畑のちちゃの木に」”が耳に残りました。もともとお手玉の歌で聴いていた覚えもあるから、そこから意外なリズムやメロディーが生まれてくる感じがあって。
「これはおもしろい感じになりましたね。歌島さんのタイコングのおかげかも」
――カラカラする音とか、チャスチャスですよね?
「そうですね」
――また歌島さんが高知の“ちょうちょの歌「蝶々かんこ」”で弾かれている十七弦琴は音も響きも不思議ですね。メランコリックな曲調ともすごく合っていて。
「ありがとうございます。歌詞は童謡の“ちょうちょう”と一緒なんですけど、全然雰囲気が違いますよね。わらべうたを知ったときは、こっちが本当だったんだと思いました(笑)。童謡のほうはドイツ民謡が元になっているんですよね」
――童謡とわらべうたの違い以外にも、今作を作って改めて感じたことはありますか?
「作ってというより出会ったときに思ったことですけど、もともとあったメロディーが知られないで埋もれているのをすごくもったいないなと。明治に確立されたものを日本の伝統だと捉えられている節が歌に限らずあると思うんです。保守の人が主張する〈伝統〉もときどきそうですね(笑)。だけど、もっと知ってみると明治以前にも豊かな世界があるんだなと感じますね。だから、その美しい部分をこのアルバムでは紹介できたら嬉しいなと思う」
――この曲は高知に行かれたときに知ったんですか?
「そうですね。安藤桃子さんが映画『0.5ミリ』の特設劇場を高知の公園内に作っていて、そこの劇場でライヴしてください、と呼んでくれた。そのときですね」
――地方に呼ばれるのは昔からなんですか?
「年々増えている感じですね」
――結構回りました?
「うん、全国の8割以上は回っています。5分の1くらいは残っているかもしれないですけど」
――行ったときに、そこのわらべうたなり、地方の歌を発見するんですか?
「その土地に行ってから発見するというよりは、そこに行くから予習するといった感じでレパートリーが増えていきました。いまは、わらべうたの連載と山姥の連載※を持っているので、朝一で東京を出発して午前から午後くらいまでは、その研究のために動いて……という動きもやっていますね」
※〈ウェブ平凡〉での連載〈山姥のいるところ〉
――なかなかそういうスタイルでやっている人はいないですよね?
「そうですね(笑)」
――おもしろいですね。
「きっかけは山姥です(笑)。でも山姥の取材を始めてから、なんか不思議なことばっかり起きるんですよ。猪苗代湖の湖畔に、〈おんばさま〉という姥神がいるんですけど、郡山から車でも1時間かかるところで、なかなか行けないなと思っていたら、猪苗代湖畔の音楽フェスに呼ばれて、ついでに取材できた(笑)。この間も福島の飯豊山に登ってきたんですけど、そこの頂上付近のおんばさまと会うには、どう移動しても2泊くらいしないと無理なんですよ。でも、このおんばさまのことはどうしても(連載で)取り上げたいと思っていたら、Twitterをフォローしてくれた飯坂大さんという写真家のHPを見ると、飯豊山の山小屋で番をしていたと書いてあって。〈この人だ!〉と思って、連れて行ってくださいとお願いして、先週行ってきたんです」
――不思議な縁があるんですね。
「だから、〈おんばさまの間でも噂になっているんじゃない〉と言われます。〈いまこんなのがいるらしいよ〉って(笑)」