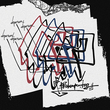Homecomingsがセカンド・アルバム『SALE OF BROKEN DREAMS』以来、約1年2か月ぶりとなるニューEP『SYMPHONY』をリリースした。ストリングス・アレンジ導入という新機軸を採り入れつつも、通しの印象としては、これまで以上にペイヴメントやアメリカン・フットボールといったオルタナ/エモ的なギター・サウンドが耳を引く同作。そうした〈バック・トゥ・ルーツ〉な背景には、学園の風景を切り取りながら〈たまにはちゃんと思い出すから〉と歌うリード曲“PLAY YARD SYMPHONY”を筆頭に、これまでいた場所からの出発や友人との離別に向き合った今作のテーマも関係しているのだろう。加えて、アメリカの青春/学園映画への愛情をもっともストレートに表した作品にもなっており、“SLACKER”なる曲名には、ニヤリと口角を上げるリスナーもいるはずだ。
前作に続き、アートワークのイラストは、シャムキャッツ諸作でも知られ、昨今はチャールズ・ブコウスキ著「パルプ」や島田雅彦の新刊「カタストロフ・マニア」の装画を手掛けるなど音楽以外の分野での活躍も目立ってきたサヌキナオヤが担当。Homecomingsとサヌキは今年の2月に映画上映とライヴを合わせたイヴェント〈New Neighbors〉を京都のみなみ会館で開催し、ホラー映画「イット・フォローズ」で名を馳せたデヴィッド・ロバート・ミッチェルの初監督作にして、お泊り会の一夜を舞台にした青春映画「アメリカン・スリープオーバー」を上映したことも記憶に新しい。
そして、「アメリカン・スリープオーバー」の日本配給元にあたるのは、未公開映画のあらすじを紹介する映画サイトであり、これまで数々のインディペンデント・ムービーの日本初公開を実現させてきたGucchi’s Free Schoolだ。昨年、同グループは初の映画雑誌「ムービーマヨネーズ」も発行し、〈青春映画〉を特集した創刊号は、Homecomingsの福富優樹(ギター)やサヌキも愛読しているという。そうした縁もあってか、Gucchi’s Free Schoolをヴィジュアル面で支えている佐川まりのが、今作『SYMPHONY』のデザインを手掛けている。ここ最近では、「アメリカン・スリープオーバー」のBlu-ray化を実現すべくクラウドファンディングでサポートを募り、なんと目標金額の3倍以上を集めて達成。秋頃のリリースに向けて、鋭意製作中とのことだ。
今回は、Homecomingsの畳野彩加(ヴォーカル/ギター)&福富、さらにサヌキナオヤとGucchi’s Free Schoolの〈教頭〉こと降矢聡も加えて座談会を実施。「アメリカン・スリープオーバー」を中心に、アメリカ青春映画の魅力を語り合いつつ、バンドが『SYMPHONY』に込めた〈旅立ち〉の意味を紐解いた。
Homecomingsのレパートリーが流れたエンドロール―運命的な出会い
――まず、Homecomings(以下、ホムカミ)とサヌキナオヤさんで共同開催した、映画「アメリカン・スリープオーバー」の上映&ライヴのイヴェント〈New Neighbors〉について、あらためて整理したいんですけど、そもそも企画の発端は?
畳野彩加(Homecomings)「最初は、私とサヌキさんが『アメリカン・スリープオーバー』を観たのがスタートじゃない?」
サヌキナオヤ「そうかもね。畳野と『アメリカン・スリープオーバー』の話で盛り上がって、その勢いで〈あんまり関西で上映されてないからなんかできひんかな〉という話になった。ただ、僕はそれ以前からホムカミについて、映画と共にあるバンドというイメージを持っていて〈映画館でライヴしてくれたらいいのにな〉と思っていたんです。僕はもともと京都出身なんですけど、京都の〈みなみ会館〉という映画館でやったら最高やなって。あそこは、僕が映画館の魅力を考えるうえで、その雛形になったような場所なんです」



――サヌキさんが〈ホムカミは映画と共にあるバンド〉と思う理由をもう少し掘り下げていくと?
サヌキ「ストーリーテラーとしてどういう目線でいるか、ってことを完全にイメージできている歌詞もそうですけど、まるで映画のあの四角い画面に収まっていくような音楽やと思うんです。例えば僕はシャムキャッツのジャケットもしばらく手掛けてきましたけど、彼らにそんなイメージを持ったことはあまりない。シャムキャッツが開いているのに対し、ホムカミは箱庭的に閉じているというか」
――あー、なんとなくわかります。シャムキャッツもストーリーテラーとして優れているけれど、彼らの音楽はどちらかと言えば、リスナーが自分に起きた出来事として投影できるという魅力が強いような気がする。一方で、ホムカミの音楽はまるで映画鑑賞のように完成した物語に触れる喜びがあるというか。
サヌキ「しかも、語り方自体に緩急があって落としどころもあるけれど、物語としては、派手さがなくてささやかじゃないですか? 自分としては、〈こういう伝え方をする作品が存在する〉ということに勇気をもらえていて。ささやかだからこそ分母として多くはないのかもしれないけれど、僕みたいな人は絶対に少なからずいるわけで、そういう人にはすごく伝わる音楽やと思う」
福富優樹(Homecomings)「まさにそうで、僕らの音楽は、間口を拡げているつもりもあるんですけど、それと同時に閉じていると思うんです。〈わかる人にはめちゃくちゃわかるでしょ?〉という感じは絶対にある」

――では、ホムカミ側として映画館でライヴをしたいという想いは昔からあったんですか?
福富「やりたいなーと思っていたし、むしろ〈温泉とか行きたいよねー〉くらいの実際にやれそうな距離感で考えることもできていましたね。〈世界一周してみたいなー〉というハードルの高い夢ではなくて、〈たぶん、できるんだろうなー〉みたいな。だから、きっかけがあればいつでも、と思っていました」
畳野「昔、Turntable Filmsも映画上映とライヴが合わさったイヴェント※をみなみ会館でやっていたし、みなみ会館だったらできるんだろうなというのはあった」
※2013年7月16日に開催された〈Late Show Films〉。「ウッドストックがやってくる!」「レニングラード・カウボーイズ・ゴー・アメリカ」「ミッドナイト・イン・パリ」の3本立ての合間に、Turntable FilmsとYeYeがライヴを行った
福富「そこで『アメリカン・スリープオーバー』という映画が、トンと背中を押してくれたというか」
――じゃあ、映画とライヴを一緒にやるという企画ありきで、その上映作品としていくつかの候補から1作を選んだというより、まず「アメリカン・スリープオーバー」を上映しようというところからスタートした?
サヌキ「そうですね、『アメリカン・スリープオーバー』ありきでした」
――みなさんが「アメリカン・スリープオーバー」を知ったきっかけは?
畳野「私はあのポスターが良くて、それで気になったんですね」
福富「海外版のイラストの奴ね」
サヌキ「アメリカン・オルタナティヴ・コミックみたいなタッチの」
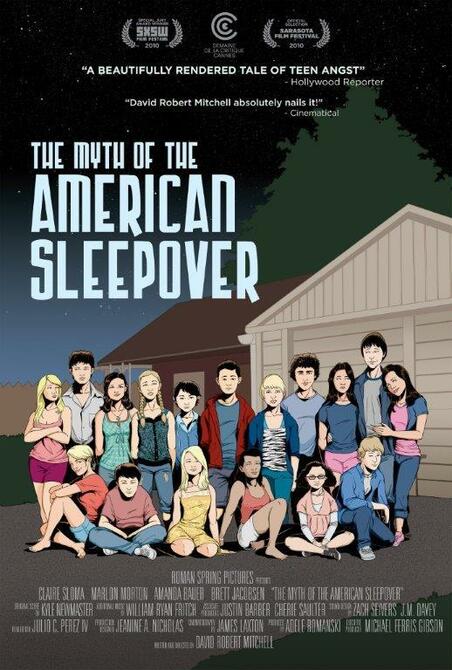
畳野「それで、観に言ったら内容も良かったし最高だったんですけど、さらにエンドロールでマグネティック・フィールズの“The Saddest Story Ever Told”がかかるじゃないですか? Homecomingsも昔カヴァーした曲※だったので、もうなんか運命みたいなものを感じて、すぐサヌキさんに〈これはちょっと何かあるぞ〉とLINEして(笑)」
※2014年の『I Want You Back EP』に収録
降矢聡(Gucchi’s Free School)「僕がホムカミさんやサヌキさんのことをちゃんと認識したのは、サヌキさんから〈上映したい〉という旨の連絡をいただいてからなんですけど、よくよく考えたら『アメリカン・スリープオーバー』を上映していたときに、音楽が良いと言ってくれる方が多くて、マグネティック・フィールズの曲についても〈ホムカミのカヴァーも良いんだよ〉とつぶやいている方がいらっしゃったんです。だから、ホムカミさんというバンドがいるというのは認識していました。そのあとに、サヌキさんからお話いただいて、〈あ、あのホムカミさんですね〉と思ったんですよ」
――ここでGucchi’s Free Schoolの活動についても紹介していくと、オフィシャルサイトでは、日本未公開/日本でソフト未発売の映画についてあらすじをまとめていくというのが根幹にあるようですね。そうした活動を始めようと思った理由は?
降矢「僕自身、海外の映画を輸入DVDで観ることも多くて、でもそんなに英語が得意ではないから、あまり内容がわからないんですよ。でも、映画を観たら知りたくなるじゃないですか。だから、未公開映画とかのあらすじを掲載したサイトがあったら個人的には嬉しいなと思ったんです。僕だったらそういうのを活用して映画をより楽しめるなと思ったし、それは僕以外にも欲している人はいるだろうと、まあ始めた感じですかね。それをやっていくなかで、おもしろい映画があったらみんなと観てみたいなとか、共有して盛り上げたいなという気持ちも強くなってきて、最近では上映活動や配給がメインの活動になりつつあります」
――海外で話題になっている作品が、日本ではいつ公開されるかわからないみたいな話もよくあるじゃないですか? そういった現状がモチベーションになっている面もありますか?
降矢「もちろん、あります。最近はTwitterとかでも〈あの作品まだ公開しないのか〉とか〈結局されないのか……〉みたいな声も多いじゃないですか。僕もそういうタイプだったんですけど、自分たちでやってみると、すごくメジャーな作品は無理ですけど、結構小さめの……『アメリカン・スリープオーバー』くらいの作品だったら、わりかし海外の配給も話を聞いてくれたんです。だから、自分たちでもやれるなと思ったし、〈あの映画、公開されないなー〉とつぶやく人たちの気持ちも共有しつつ、自分で配給するのも楽しいですよ、という」
サヌキ「Gucchi’sを知ったときは、こういう団体が本当にいるんだと思いましたね。自分でやっちゃえるというか、〈やる人がいないんだったら自分たちでやってしまおう〉というスタンスに後押しされる感じがあった。しかも少人数で……失礼かもしれないですけど、もっと大人数の団体やと思っていたんですよ。そしたら本当に数少ない有志でやられていて」

福富「僕は、去年の夏から秋くらいにかけて、Gucchi’sさんがやっていた〈青春映画学園祭〉がまわりで話題になったり、その流れで京都の立誠シネマでも『スラッカー』が上映されたり、一気に情報が流れてきて〈こういうシーンがあるんだ〉と興味を持ったんです。で、同じ時期に雑誌の〈ムービーマヨネーズ〉※も発刊されて、もちろん購入して」
※Gucchi’s Free Schoolが創刊した映画のムック。〈青春映画特集〉をテーマに、数々の未公開映画を紹介。柴田元幸や山崎まどからも寄稿した
青春映画の根幹にある〈未決定であることの可能性〉を純化した魅力
――ちなみに『アメリカン・スリープオーバー』は海外だと評判になっていた作品なんですか?
降矢「一応カンヌの招待部門で〈批評家週間〉というセレクトがあって、そこで2010年に上映されたんですよ。アメリカ映画が選出されることが少ない枠だから、それはちょっと異色で。だから、どちらかというとヨーロッパから盛り上がったという感じが強いみたいです。同じデヴィッド・ロバート・ミッチェル監督の次作『イット・フォローズ』のときは、アメリカでもタランティーノが絶賛したりして、彼の名前もそこでワッと拡がったようですけど」
――降矢さんはどうやって発見したんですか?
降矢「それは特に何かあったわけではなく、いっぱい観ていたうちの一本だったというか(笑)」
一同「ハハハ(笑)」
降矢「この作品がデビュー作なので、監督を知っていたわけでもなく、たまたまクリックして買ったうちの一本だったんです。それで観てみると、やっぱりあの色合いや雰囲気が独特だったし、話があるのかないのかわからないけど何か心に残るみたいな魅力があったんですね。ストーリーを強引にまとめると、一晩のお泊り会を舞台に、男の子たちや女の子たちがあっちに行ったりこっちに行ったりするのを淡々としたタッチで描いた群像劇ということだと思うんですけど、まだ将来の定まってない彼ら――いまは未決定な子どもたちの一瞬が純粋に表れていた。よくある青春映画というのをカテゴライズするなら、ある人物がプロム・クイーンになりたいとか、この街から出ていきたいとか、何がしかの収束に向かって物語が進んでいき、それが〈叶いました〉とか〈実現しなかったけど違う何かを発見し、新しい自分になりました〉とかの結果に辿り着くと思うんですけど、『アメリカン・スリープオーバー』はそこもまた違っていて、未決定なままで終わっていく。あらゆるものになれるかもしれないという可能性自体にフォーカスしているんですよね。それは派手ではないけど、何か心にくる〈新しさ〉でした。いろいろな方が〈良かった〉と言ってくれるのに触れていくと、それこそが魅力なんだなとあらためて感じています。青春映画の根幹にある〈未決定であることの可能性〉という純粋でピュアなところが描かれていて、本当に神話のよう※だと思う」
※原題は「The Myth Of The American Sleepover」
――僕が新鮮さを感じたのは、それまで観てきた多くの青春映画の大半よりも、主人公たちの年齢層が低いということでした。それは、いまお話しいただいた保留のまま映画が終わっていく、というところにも関係しているのかなと思うんですが。
降矢「それは絶対に関係していると思います。あと、無名の俳優さんばかりが出ているということも、もちろん関係していて、実際にデトロイトのロケ地でオーディションをしたみたいなんですよ。だから、この映画の俳優は、実際にあの場所に慣れ親しんでいるティーンたちなんです。さまざまな可能性があるなかで、特権的に選ばれた人たちが可能性のひとつを成就させて、それこそ有名人になる/映画スターになるという現実もあるけれど、そこからこぼれ落ちてしまった人たちも、実際になった人たちと同じくらい可能性は共有していたはずですよね? それはみんなが共有できるものだし、共感できる。すべての人たちが持っていた可能性みたいなものが、この映画には収められていて、それも魅力なんじゃないかな」
サヌキ「無名の俳優さんだからこそいっそう感じるんでしょうけど、何かに決定する前の顔や体がもはやドキュメント的に映っていますよね。それらが一夜にザワザワ蠢いている感じが、僕は写真の現像に近いなと思ったんです。暗室で写真を現像液に浸していて、まだどんな写真になるかもわからないような状態というか」
福富「わかります。『アメリカン・スリープオーバー』はよく『バッド・チューニング※』と比較されているように思うんですけど、『バッド・チューニング』は、一応最後、部活を辞めるとか選択して終わる。でも、『アメリカン・スリープオーバー』は特に何も選ばないじゃないですか? 彼らはまだ選ぶ年齢でもなくて」
※リチャード・リンクレイター監督による93年の青春映画。夏休みに入る直前の高校生たちの一夜を描いた群像劇
降矢「主人公含め多くのキャラクターは、今度高校生になるという年齢ですからね」
福富「青春映画でよく描かれるのはやっぱり高3が多い気がして」
――『バッド・チューニング』もそうだし『プリティ・イン・ピンク』や『スーパーバッド 童貞ウォーズ』あたりもそうですね。
福富「僕は最後のシーンがすごく好きで。お泊り会の夜にはワーッとみんなが熱にうなされたようになったんだけど、次の日の朝にはそれはそれとしてケロッとしている感じが、すごく神話っぽいなと思った」
サヌキ「翌日の朝の光の感じは印象的でしたね。白っぽい光で」
畳野「自分とあてはめられて考えられちゃうことが、いろいろなポイントであって、〈わかるな、共感できるな〉となれる部分が『アメリカン・スリープオーバー』の魅力だと思います。さっき福富くんも言っていたけど、夜に起きた嫌なことも嬉しいことも次の日の朝になると忘れちゃうとか、そういうところがリアルだし、良いなって。今回の『SYMPHONY』に収録した“PAINFUL”は『アメリカン・スリープオーバー』を観たことで出来たんですよ。〈ここまで影響されているんだから、曲にしないと〉と思って夜をテーマに書いたんです。深夜っていろいろな感情が動く時間だし、そこに焦点を当てたかった」