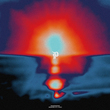〈サニーデイなんてなんぼのもんじゃい〉って思ってます
――なるほど。“ラブソング 2”や“ジーン・セバーグ”だけでなく、『the CITY』の多くの楽曲では曽我部さんの声にエフェクトがかけられていて、曲によってはピッチも変化させています。そういった声の変調やエフェクトで、曽我部さんはどういうことを表現しようとされているんですか?
「それは、やってみたいっていうだけなんですよね。単純に、オートチューンいけるじゃん!みたいな。……オートチューンをかけただけで良くなるんだよね、音楽って(笑)」
――(笑)。それはなぜでしょうか?
「オートチューンがすごいとしか言いようがないですね。オートチューンをかけると流麗になるんですけど……いまは人間の歌の情感とか情緒みたいなものっていうのが、どのくらい重要なのかっていうことを量ってるような時代だと思うんですよ。オートチューンはそれにぴったり合ってるエフェクトだと思う」
――というのは……?
「〈ヴォーカル〉というものが、いま表現できる情緒や温度っていうのがあると思うんです。例えば、60年代はオーティス・レディングとかJB(ジェームス・ブラウン)みたいにガツンって歌ってよかったと思うんですよね。で、オートチューンは、いまの歌の〈熱〉なんだと思います。あれをかけると、〈熱〉が良い感じにハマるんだよなあ。とにかく、歌にオートチューンをかけたいんですよ。ソウルフルな、ヴォーカリゼーションをパフォーマンスしてる曲は、なるべくかけたくなるんだよね。それはなんとも言いようがないんだけど(笑)。
声のエフェクト――コンピューターでかけられるエフェクトってすごく大事だと思います。カニエ・ウェストの『My Beautiful Dark Twisted Fantasy』(2010年)のオープニング(“Dark Fantasy”)を聴いて、〈いまのコンピューターだとこれができるんだ〉と思って。あの表現って聴いたことがないものですよ。〈ああ、コンピューター最高だな。そういうことをやるべきだな〉と思いましたね。だから、あれ以降、僕はオートチューンももちろん、エフェクトや声の変調にすごく惹かれてます」
――なるほど。
「アナログ回線の電話って、いまはもうほとんど使わないけど、電話越しのこもってる声だけに宿る情感ってありますよね。何かがマスキングされることによって、隠されたものをこちらに想像させるというか、逆説的に伝えてくるものっていうのはあるんでしょうね」

――では、ビートやプロダクションに関してはいかがでしょうか。『the CITY』はヒップホップ、ラップ・ミュージックの要素が強いですよね。MARIAさんやMC松島さんなど、ラッパーが多数フィーチャーされています。
「曲は、やってて出来たって感じなんです。MARIAとやった曲(“Tokyo Sick”)も、ラップを入れてもらってからまた、トラックを変えてるし」
――そうなんですか!?
「そう。反則とも言えるんだけど(笑)。MC松島の曲(“23時59分”)も、全然違う曲だったの。もっとスペーシーでファンキーな、パーラメントかファンカデリックか何かのネタの曲だったんですけど。あのラップが来て、全部変えようと思って変えましたね。
ラップは単純に好きなんです。基本的には自分がやるものじゃないですし、ラッパーはラッパーであってヴォーカリストじゃないから、だったら一緒にやったほうがいいって感じで。例えば、ストリングスは自分では弾けないから、プレイヤーを呼んでやってもらう――それと同じぐらいの感覚なんですよ、自分としては」
――こんなにラッパーがフィーチャーされていて、それでもサニーデイの作品として成り立つのかという不安も覚えます。
「確かにね」
――『Popcorn Ballads』の頃から気になっていたのですが、サニーデイというバンドは曽我部さんのなかでどういう位置づけになっているんですか?
「それは、正直、何も考えてないです。〈サニーデイを維持しなきゃ〉とか、なんにも考えなくなっちゃいましたね……。サニーデイをまたやりはじめたときは、歴史があるし、良い老舗看板だと思っていたんですよ。これまでのお客さんもまたいっぱい来てもらえるし、自分が20代の、才能がまだ有り余ってた頃に作った名曲の数々があるから、それをやれば何年でも商売できると思ってね(笑)。でも、いま(ライヴで過去の曲を)全然やってないから、ダメじゃん!っていう(笑)。
もちろん、サニーデイは自分にとってすごく大事なものだし、20代の頃の輝かしい、いちばん重要なキャリアだと思って、また再開したわけですよ。なのに、こんなことになってしまって、もう目も当てられないなと思ってます、本当に。でも、そこに〈ああ、昔からやってるバンドなんだ〉みたいな顔した若者とかがやって来て聴いてくれてるのは、ただただ痛快なんですよね」
――『東京』(96年)も知らないような若者がいまのサニーデイを聴いてくれている?
「そう。〈三越が潰れた跡地でみんながスケボーをやってる〉みたいな(笑)。だから、〈サニーデイなんてなんぼのもんじゃい〉って思ってますよ。サニーデイが大事だからこそ、いまがあるんだけどね。もちろん、いつも真面目に考えてますよ。一生懸命、120パーセント、いや、200パーセントの力で真剣にやってきてよかったと思ってますね。
90年代、毎年アルバムを出してた頃っていうのは、20代の、マックスの情熱でやってたんです。いまはあの頃のような若さとか曲を書くスキルとかはもうまったくないかもしれないけど、情熱は変わらない。〈情熱〉って言うとちょっと違うかな……一生懸命とにかくやる、ひたすらやる、やり倒すってことはやっぱり大事だと思ってて、それは当時とあんまり変わらないですね。だから、やり方はちょっと違うんですけど、同じことをやってると思います」
早く死んで、楽になりたいなと思います
――ここまで『the CITY』の制作の経緯などをお聞きしましたけど、それでもまだ、よくわからない作品だと感じています。
「僕も全然わからないんです(笑)。『DANCE TO YOU』や『Popcorn Ballads』はアルバムとしての意義とか目的とかがわかりやすいんですよね。『the CITY』にはないんです、出来損ないだから。出来損ないのものに、ひょっとしたら何かがあるんじゃないかなっていうことです。もしかしたら何もないかもしれない。僕もわからない。だから、よくやったなあと思いますね。自分のキャリアのなかでも最高傑作じゃないですかね」
――僕も〈もしかしたら最高傑作なのかな?〉って思いました。
「でしょ? 〈最高傑作なのかも?〉みたいなね。良くもないし、悪くもないし……。〈良い〉っていうものはさ、〈悪い〉っていうものがあったとしての話でしょ。そういう二元的に捉えることができないような、自分にもここまでよくわからない、手が付けられないものっていうのが、よく出来たなって思います。
例えば、ポップ・グループのファースト『Y』(79年)のライナーで、水上はる子さんが〈ポップ・グループは踊れない。踊れないってことが現代の危機なんだ〉って書いてるんです。そういう感じに近いのかな。〈踊れて楽しいですね〉〈聴いて心地良いですね〉ってならないようには、頑張ってしてるんです。じゃないと、まったく意味がないと思う」
――それはどうしてですか?
「それはやっぱり、消費されて、理解されて終わるだけだから。それだと、その人の心との関係性が生まれないんじゃないかなあ」
――聴き手とサニーデイの音楽との関係性ですか?
「うん。最初に〈アルバムを聴いて落ち込んだ〉って言ってたじゃないですか。そういうことはすごく重要で、そういうものを作るべきだと思うんですよね。〈最高!〉〈良かった!〉〈感動した!〉って言ってしまえるものではない作品を。その気持ちがどんどん極端になっていってはいると思うんですよね。
〈あなたが見やすいものを用意しましたから、こう見てください〉っていうことじゃないんですよね。作品を聴いて、〈なんでこの人はこういうことやってるんだろう?〉って思うものを作りたいんです。それって、僕のことを見てくれてるってことじゃないですか。僕を見ながら、その人は自分のことをまた見つめてるのかもしれないし、そういうことが重要なんです」
――ええ。
「いつもそういうものを目指してるんです。映画の『地獄の黙示録』(79年)や『マグノリア』(99年)みたいな、途中から作者のキャパを超えちゃったような作品を。なんとか最後まで完成させただけで、途中から作者の意図とか能力っていうものから完全に乖離しちゃってるっていうか、逸脱しちゃってるものが、やっぱり良いんですよね。〈これ、作者は何をやろうとしたかわかってないでしょ?〉みたいなさ」

――そういった、作り手にとっても何かわからないようなものを作っているときは、快楽があるんですか? それとも辛いんですか?
「どっちもですよね。辛い時もあれば楽しい時もあるっていうんじゃなく、常に一緒なんですよね。僕はあるときから、お酒を飲まなくなったんです。快楽物質を自分に与えてないから、脳が休んでないんだよね。だから、結構しんどいんですけど、自分の脳の隅々まで分け入って、感情とかも全部押さえてやろうと思ってるんですよ。
そのためにインプットできるものは、手法も含めて全部勉強するんです。毎日、音楽を大量に聴くんですけど、それは手法の勉強なんですよね。音楽を聴いて、〈ああ、こういうふうにしたら、もうちょっと進めるかもしれない〉みたいな。
お酒を飲んでリセットしない、ストレス発散がないから、ストレスを究極まで溜めている状態なのかもしれない。だから、早く死んで、楽になりたいなと思います、本当に。普通の人だったら病院に駆け込んで、抗鬱剤とかをもらって、それを抑えているような精神状態なのかもしれない」
――タナトス的な……。
「そういう人体実験みたいな、SM的なところはあるよね。いままで自分が抱いてきた、道徳的な決まりごとからもどんどん逸脱していきたいとも思いますし。〈音楽っていうのはこういうものだ〉って自分で勝手に決めた考え方だったり、信条だったりっていうものを捨て去って、〈もっと自由に〉と言うとまた語弊があるんだけど、スッと音楽をやり続けたいなって思います」
――その〈人体実験〉に果てしなさを感じたりはしないんですか?
「それが作品になるから、まだ救いはありますよね。だから、僕は多作なのかなと思うんですけど。出さないと、ちょっと無理ですね。だから、これからもどんどん作品を出しますよ。誰も聴いてなくても。誰が聴くとか聴かないとか、そういうことはどうでもいいなと思って。自分の人生、あと数十年じゃないですか。それなのに〈誰が聴く〉とか〈何枚売れた〉とか、もうどうでもいいなって。もうとにかく、やってやってやりまくるっていうことなんですよね」
――なるほど……。
「〈名曲〉なんてさ、誰が決めるの? 〈名曲〉じゃなくてもいい。〈名曲〉って数十年単位で変わってしまう価値観にうまくはまっただけのものだったりするわけじゃないですか。〈百年後の人が名曲って思ってくれたらいいな〉なんて、ちょっと思ってたナイーヴな自分もいたんですけど、それって傲慢というか、高慢というか。そういうことはもうホントにどうでもいいなと思って。
犬と散歩してると、犬は絶対にそんなこと考えてないんだろうなと思います(笑)。もっと現実的だし、欲望に忠実で本能的だし――そこに戻りたいよね。そこにある音楽みたいなものをやりたい。もちろん、それをできてる人はいっぱいいると思うんだけどね、自分は努力しないとそれができないから、なんとかそこに行き着きたいですね」