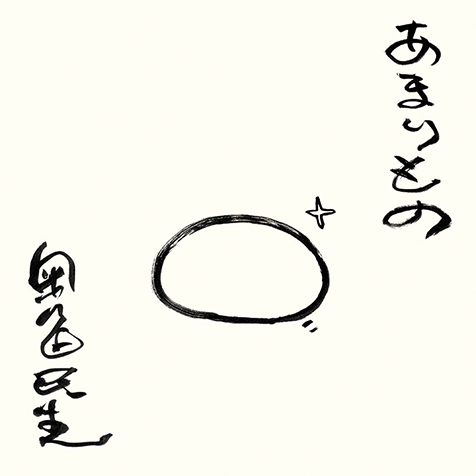シャムキャッツの新作『Virgin Graffiti』は〈いなくなること〉についてのレコードだ。それは、文字通り〈別れ〉を歌った作品であり、こんな世界からさっさとおさらばしちゃおうぜ、と〈逃避〉を耳打ちするアルバムでもある。さらに加えるなら、これは、悩みを抱え傷つき続け、にもかかわらず、その優しさゆえに、いまいる場所から足を踏み出すことができない〈あなた〉へ向かって、〈もういいよ〉と手をとり、別の世界へと連れ出してくれる音楽だ。
それゆえに、サウンドの質感はいつになくサイケデリックでトリッピー。ビッグなアンセム“このままがいいね”、メロウでさりげない名曲“カリフラワー”という2つのシングルはもちろん、ハウス・ミュージックを下敷きにした“逃亡前夜”、バンド持ち前の甘やかなバラードをアラバマ・シェイクス以降の音作りでモダナイズした“俺がヒーローに今からなるさ”、さらにはドライヴィンなサウンドでロック・バンド・ライフを歌った“BIG CAR”など、収録された13曲いずれも個性が際立っている。前作『Friends Again』(2017年)が、バンド4人のアンサンブルに焦点を当てたフォーキーな装いのアルバムだったのと比較するなら、今作は音作りの面でもカラフルな仕掛けの多い、プロダクション重視の作品とも言えるだろう。
聴き手を〈ここではないどこか〉へと運ばんとする、このアルバムの力強さ、逃避的な作風の背景には、シャムキャッツが初のアルバム『はしけ』(2009)でデビューする以前から、バンドに連れ添い、苦楽を共にしてきたマネージャーとの離別があったという。詳しくは以下のインタヴュー本文に譲るが、彼らの活動において、もっとも大きな別れを経ることで、バンドはあらためて、ポップ・シーンにおける自身のアティテュードを、さらには現在の若者がどのような生きづらさを感じ、バンド・ミュージックはいかに彼らをアップリフトできるかについて、考えざるをえなかった。はたして、シャムキャッツが見つけた答えとは? 彼らが『Virgin Graffiti』に託したメッセージについて、メンバー4人に訊いた。
人が動き出したり、表情が変わったり、何かポジティヴな要素を音楽で与えたいと思った
――バンド・サウンドのシンプリシティーを突き詰めた前作『Friends Again』と比較して、今作は楽曲、音作りとも実に多彩なアルバムになりました。2作の間には、どんなモードの変化があったんでしょうか?
夏目知幸(ヴォーカル/ギター)「『Friends Again』を作ったことで、メンバー4人が均等に並んで、非常にシンプルなアンサンブルで作品を作り上げるってことに関しては自信が持てたんだよね。あの作品を作ったときの自分の心象としては、前のインタヴューでも話したけど、〈この世界はあんまり甘くない〉というか、〈明るい未来なんてないぞ〉という視点を作品に定着させようという気持ちがあった。
だけど、それをやり終えてツアーを回ったとき、お客さんの顔とかを見ていると、もうちょっと元気の出せるものも作れるんじゃないか、僕たちも人にパワーを与えられるんじゃないかっていう気持ちがちょっと湧いてきたんです。次、作品を作るなら、人が動き出したり、人の表情が変わったり、何かポジティヴな要素を音楽で与えたいというのはあった。そういうマインドの変化が、まず“このままがいいね”になり、それ以降の作品に繋がっていく」
――“このままがいいね”は、(ブルース・)スプリングスティーン的と言うか、力強い疾走感を備えたロックで、『Friends Again』からのネクスト・ステップを感じました。
夏目「前作のモードから変わりつつあったけど、まだ下地としては『Friends Again』の作風が濃く残っていた面もあって、制作当初は、みんなを焚きつけるようなビートや音像というより、もうちょっと静かに踊らせるような楽曲をめざしていた。
僕がメンバーに〈こういう感じが良いんじゃない?〉と聴かせたのは、アマソンというスウェーデンのバンド。彼らに、マイナー調のコード進行で、まぁ“このままがいいね”よりは遅いんだけど、静かにずっと踊れる曲があって。2、3年前くらいから、僕はどういうわけかクラブ・ミュージックばっかりを聴く人間になっているんだけど、バンドでクラブ・ミュージック的なアプローチをやるにあたって、最初に参考にしたのがアマソン。で、わりと暗い曲調のデモをみんなに出したんだけど、〈せっかくなら明るいほうがいいんじゃない?〉ってシンプルな助言をもらって(笑)。ドラムのパターンはそのままに、BPMを少し早くして、仕上げていった」
大塚智之(ベース)「俺はLCD(サウンドシステム)かと思ってた」
夏目「LCDやニュー・オーダーもあったけどね。いちばん最初の取っ掛かりはアマソン」
藤村頼正(ドラムス)「俺のドラムに関しては、ウォー・オン・ドラッグス的な疾走感を意識していたかな。荒野を駆けるみたいな(笑)。スネアが重たい感じとか、音作りの面でも参考にして」
――菅原くんはギタリストとして、もう1人のソングライターとして、この楽曲をどう描いていました?
菅原慎一(ギター/ヴォーカル)「俺は、“このままがいいね”に関しては、あんまり曲に対する具体的なイメージや想いとかはなくて。シャムキャッツとしてちゃんとポップスにしたい、なんかシングルが切れるような曲になればいいなとしか考えていなかったかも」
――前作がバンドの関係性にフォーカスした作品だっただけに、“このままがいいね”という曲名は、含みを持っているようにも感じました。この言葉は、そもそも永遠を感じていたら出てこないですよね? ゆえに、離別の予感をそなえた曲でもある。
夏目「まぁ僕という作家のクセではあるんですけど、常に時間が動いているということに、執着しているんです。時が過ぎていくんだということばっかりを考えている。なので、昨日や明日のことを歌うことが多いんだけど、“このままがいいね”では自分としていちばん苦手な〈いま〉というものを捉える歌を作ろうとしたんです。だから、刹那のなかでギリギリ捉えられた〈いま〉が、“このままがいいね”だった。楽曲の種明かしをしちゃうと、サビまではずっと同じコード進行だけど、サビが終わったあとにEマイナーが入るんですね。だから、やっぱり〈このままではいられない〉曲ではあるんだけど……」
大塚「シンガー・ソングライターの江本(祐介)くんが、“このままがいいね”をカヴァーしてくれていて、俺は彼のヴァージョンもめっちゃ好きなんだけど、彼が歌うと、すごく〈このままがいいね感〉が出るんだよね。それを聴いたあとに、自分たちの“このままがいいね”を聴くと、こいつらは、この言葉をまったく信じられていないなと、めちゃくちゃ感じたな」
藤村「苦みが強いよね」
夏目「もう今回、言っちゃうことにしているんだけど、“このままがいいね”を出すタイミングで8年間とか一緒にやってきたマネージャーの山口さんが体調を崩して、抜けることになったんだよね。なので、バンドとしても変化せざるをえない状況だった。内情としては、まったく〈このまま〉では立ち行かなくなっていて。2回のアジア・ツアーを行い、ホールワンマンの〈らんまん〉も開催し、シングルも2枚出したから、相当活発に見えていたとは思うんだけど、内側では必死で身辺整理をしてたんだよね」
大塚「だから、それまで以上にメンバーの4人で運営面も回さざるをえなかったし、そのうえで、バンドにやれることってそう多くはないなとも感じた。曲を作ってライヴをやってグッズを作ってとか、そういうことしか自分たちが出せるものはない。俺らは、それを積極的に出していく団体だよね。逆に言えば余計なことをしているヒマはないってこともわかった」
いま僕たちが持てる共通のテーマは、〈誰かがいなくなった〉ってこと
――『Friends Again』以降に実施した、2回のアジア・ツアーを経て、自分たちがいる日本という場所についても、より客観的に捉えることができたんじゃないですか?
藤村「やっぱり、日本はちょっと堅苦しい面が多いなという印象はありますね」
夏目「まぁどこの街に行っても、日本と比べて良いところと悪いところはあるね。ただ、僕たちみたいな音楽と活動のスタイルでやるには、日本がいちばんやりやすいなってのも感じる。でも生活のことを考えると、日本は家賃や食費は高いし給料は安いし、めちゃめちゃ暮らしにくいなとも思う。僕としては、日本の特徴がわかってきたというよりは、それ以外の国で演奏したり音楽が好きな人と関わりを持ったりすることで、音楽にできることが見えてきた感じ。
『Friends Again』では、すごく柔らかい手触りで現実をそのまま曲にして、聴き手に押し当てようとしたんだけど、ツアーを回っていくと、〈音楽ってもっともっと特別な魔法がある〉とも思えた。束の間、現実から離別するというか、逃亡させる力があるし、僕たちの音楽が、他の国でもそういうものになってるというのが、海外に行けば行くほど感じたんだよね。だから、シャムキャッツで5枚アルバムを作ってきて、自分としてははじめて、〈音楽って逃避なんだ、これを聴いている間、一緒にどっかに逃げよう〉って感覚で作った。それには結構アジアの影響は強くて」
――菅原くんはいかがですか?
菅原「うーん……ちょっと話の方向性が急に変わった気がして、亮太の質問の意図がイマイチつかめないな。俺がアジアをどう見たかってこと? それとも新しいアルバムに影響を与えたのかってこと?」
――えーと、アルバムの逃避的な側面が、どういう経験に起因したものなのかを教えてほしいってところですね。
夏目「その答えとしては、最大の要因は、やっぱり長年一緒だったマネージャーと離れてしまったってことでしかないんだよね。アルバムを作り出す最初の段階で、いま僕たちが持てる共通のテーマは、〈誰かがいなくなった〉ってことだよね、と話していたとは思う」
――じゃあ菅原くんにとっても、そのテーマが念頭にあったうえで曲を作れた?
菅原「念頭……うん、だいたいそうかな」
――なるほど。じゃあバンドにとっての大きな別れが一つ起点としてはあるとして、最初に夏目くんが言ってくれた、ロック・バンドとして聴き手の気持ちをもっとアップリフトできるんじゃないか、といった視点もメンバー全員が共有していたんですか?
夏目「知らない(笑)」
菅原「なんかね、そういうふうに誰かが思っていることを共有した感じは、今回あまりないかもしれない」
――たとえば、前作は、シャムキャッツというバンドをいかにプレゼンテーションするかを、かなりバンド内で固めて作り上げた印象だったんです。
菅原「今回は、そんな感じはないかもね」
夏目「というか僕は、作りはじめたときに、みんながあまり共有したがってないなという空気を感じていたな」
一同「笑」
夏目「いや、僕は『Friends Again』はプロジェクトとして上手くいったと思っていたんですよ。ジャケも良かったし、内容も粒が揃っていたし、ツアーも上手くいったし。だから次はもっと良い作品を作って、もう一段階評価されようという気持ちが強かったんですよね。ちゃんとシャムキャッツが歩んできた道のりをふまえて『Friends Again』があって、バンドのストーリーとして次は〈最高傑作〉を作ろうと。で、まぁ次は滑れないよなとメンバーにも言っていたんだけど、あんまり響いていないなとは思っていて(笑)」
菅原「“このままがいいね”と今作の間に“カリフラワー”というシングルをリリースしたんですよ。“カリフラワー”はただただ良い曲で、俺ら的にもめっちゃ良いと思っていたんだけど、出してみるとすごくヒットするような感じでもなかったんだよね。そこでいったん見つめ直すっていうか、現状確認とも違うけど、この方向でどうなのかな?みたいな空気は瞬間的にあったんだよ。その感じが夏目に響かなさとして伝わったんだと思う」
――アルバムの制作をスタートしてからも、コンセプトを詳細に詰めていくことはなかった?
大塚「今回のレコーディングは、仕事的にと言っていいかはわかんないんだけど、俺のなかではシステマティックにこなすって感じもあったんだよね。あんまり練習する時間もなかったし。俺は……もしかしたら藤村もだけど、瞬発力で勝負する感じだったな。夏目や菅原からもらった曲をできるだけ短時間で熟読して意図を汲んで、作り手の意図通りに演奏しようと思ってた。だけど、夏目ってこういう意図があるんだよね?といちいち確認する時間はなくて、すぐ答えを出さなきゃいけないという印象。なので、演奏面で難しいことは特にしてない」
菅原「それが逆説的に、夏目のやりたいことを共有する感じになったのかもしれないね。音を足していくうえで、彼の考えに乗るしかないじゃないですか? ホントに申し訳ない言い方だけど、たとえばバンビ(大塚)がベースを〈やったる〉みたいに気合い入れて弾くことはなかったってことでしょ?」
大塚「そうそう」
藤村「俺もそうだな。だから、いままででいちばん肩の力を抜いて作れた。その場で良い感じにやればいいなってノリで」
――たとえば、“完熟宣言”では、大塚くんと藤村くんがメイン・ヴォーカルをとられるパートもあります。バンドして初の試みではあるけれど、意外にサラッと流せるという感じ。リンゴ・スターをフィーチャーしてみたいな雰囲気ではなくて。
夏目「そうそう(笑)」
藤村「去年や一昨年に、歌えと言われたら、〈やべぇな、ちゃんと歌わないと〉と思っていただろうけど、いまはなんにも気にせずに歌えたな」
夏目「積極的にアイデアを出し合う感じではなかったにもかかわらず、不思議なことに、結果的には『Friends Again』以上に自由にやっている印象になっているとは思う。前作は、煮詰めてシンプルにしていくという作業だったから、考える時間は長かったけど、今回は考えていない。煮詰める前のフレッシュな状態で出しているんだよね」