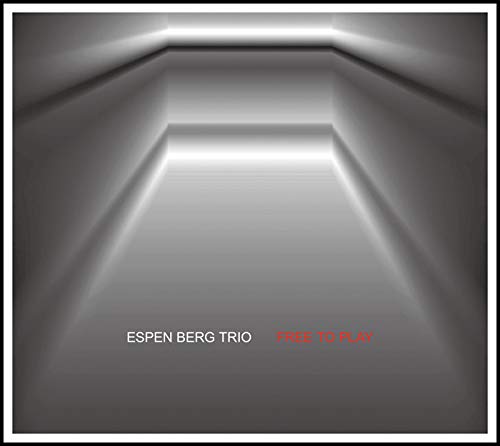近年、世界で注目されるアーティストが続々と生まれる北欧のコンテンポラリー・ジャズ・シーン。その中でもノルウェーはECMなどからリリースするクリエイティヴなアーティストを数多く輩出している。国際的にも評価の高い同地のジャズ・フェスティヴァル※は、60年代から国の手厚い助成を受けて組織的な運営がなされており、そうした様子はこれまで行ってきた現地取材で筆者も目の当たりにしてきた。
※モルデ・ジャズ・フェスやコングスベルグ・ジャズ・フェス、ベルゲン・ナイト・ジャズ・フェスティヴァル
そうしたノルウェーの伝統あるジャズ・シーンを受け継ぐ、次世代のピアニスト/作曲家として人気を集めるのが、エスペン・バルグだ。彼がバルー・ライナット・ポウルセン(ダブルベース)、シーモン・オルダシュクーグ・アルバートシェン(ドラムス)を率いたエスペン・バルグ・トリオ(EBT)としての3枚目のアルバム『Free To Play』を携え、去る5月31日、6月1日に3度目の来日公演を行った。
エスペン・バルグは、ジャズ科が有名なノルウェー科学技術大学(NTNU)出身。2003年にトリオ、リッスン!でプロ活動を開始し、2012年と2013年に〈モントルー・ジャズ・フェスティヴァル〉のソロ・ピアノ・コンペティションにノミネートされた。さらに、2016年にはノルウェーの権威あるミュージック・アワード〈JazZtipendiatet〉を受賞。今回来日したトリオでNTNUの大使に任命され、トロンハイム市から表彰されるなど輝かしい実績を誇る。近年は、NTNUのジャズ科で講義を受け持ち、後進の育成にも力を注いでいる。
来日前の4月末にはドイツ・ブレーメンで毎年開催されているジャズ・フェス〈ジャズアヘッド〉の〈ノルウェーナイト〉にトリオで出演。約30分間という短い時間ながらも、メロディアスで高度なレヴェルのインタープレイが印象的なステージが下掲のライヴ映像からも確認できる。
われわれは来日公演最終日、本番前にエスペン・バルグへの単独取材を実施。高度でクリエイティヴィティーあふれる彼らの音楽はどのようにして生まれるのか、その背景を探ってみた。
音楽は自由に演奏されるべき
――2016年、2017年に続き今回が3度目の来日となりますが、日本の印象は最初と比べてどう感じていますか?
「そうだね、今回は少し違いを感じているよ。自身では前よりは慣れてきた、とも感じるかな。これまでは何か圧倒されるものがあって、特に最初はここ日本が初めて訪れたアジアの国だったので、僕にとっては〈アジア=日本〉だった。その後、2017年以降に中国、香港と2度ツアーを経験して日本との違いを感じて、今回は〈ホーム〉というか、帰ってきたなという気分だね。ある程度日本の文化も知っているのもあって、リラックスして過ごせているよ」


ⒸAtsushi Toyoshima
――今回の来日にあたって、最大のトピックとなるのがニュー・アルバム『Free To Play』ですね。今作のコンセプトやテーマはありましたか?
「ひと言で言うと〈非常に異なる曲のコレクション〉かな。 3人で集まり、これまでの2作品――『Mønster』(2015年)、『Bølge』(2017年)よりも、さらに多様性を追求した結果、とても複雑でダイナミックな変化に富んだ作品が出来上がったんだ。全体的に柔軟な発想で作品作りをするようになってきたし、事実、1曲目“Monolitt”は自由な感覚で演奏しているので、オープニングに相応しいのではと思ったんだ。 コンセプトとしては複雑な構造とメロディーを結び付けて、複雑なリズムであると同時にメロディアスであることを目指した結果、よりエモーショナルな作品になったんだ」
――タイトルがこれまでのノルウェー語から英語になったのはなぜでしょう?
「何か良いタイトルはないかなあと考えていた時にパッとこれが浮かんでね。英語にしようと特別に意図したわけじゃないんだ。過去2作ではルーツであるノルウェーの音楽が反映された良いタイトルを付けたなと思うんだけど、今回の『Free To Play』も気に入ってるよ。というのも、現在はアーティストがなかなか自由に音楽を制作しにくい状況にあって、音楽産業に対し、〈音楽は自由に演奏されるべき〉という気持ちを込めたという感じかな。それから、もう一つ重要なことは、どうやってより自由に、また何にも縛られずにプレイするかということなんだ。これまでになくメンバー同士がしっかり且つ自由に音楽的コミュニケーションが取れた結果、それぞれの音楽的なルーツが顕著に表れた作品になったと思うね」

他のトリオとは一線を画すリズムへの追求は、トリオでのテーマ
――アルバム収録曲“Camillas Sang”は奥さんへ捧げた曲ということですが、作曲することに至った経緯は?
「これは2014年に作った古い曲で、妻に対する想いを込めたラヴソングなんだ(笑)。妻のカミラとは結婚して15年になるんだけど、出会いは学生時代で、僕らはシェアハウスで偶然出会ったんだ。彼女の好きなところは、曲にも反映されているんだけど、例えば最初に会った時に感じたチャーミングさや、居心地が良いところ。その一方で、儚げというか繊細で感受性の豊かなところも曲の中で表現しているよ。彼女はとても聡明で頼りになるので、音楽的にちょっと意見が欲しい時にも相談したりしてるんだ」
――録音スタジオをオスロのレインボー・スタジオからスウェーデン・ヨーテボリのニレント・スタジオに変更した意図は? スタジオを変えたことは、どんな影響を及ぼしましたか?
「理由は2つあるんだ。一つは音作りを変えたかったこと。レインボー・スタジオで録った前作『Bølge』はとても素晴らしかったんだけど、今回の『Free To Play』にはちょっと違うなと思ったんだ。僕はつねに進化し続けたいと思っているので、スタジオを変えてみることにした。
2つ目の理由は、自身が創設した伝説のレインボー・スタジオで70年代から活躍してきた、過去作のエンジニアのヤン・エリック・コングスハウグが、残念なことに去年辞めてしまったこと。そうなった以上は、ヤンのいないレインボー・スタジオで録る選択は僕にはなくなってしまった。そんな時、知り合いからニレント・スタジオが良いスタジオだという話を耳にして、実際、ニレント・スタジオの自然豊かな場所でインスピレーションも得られた。たまたまそこにあったチェレスタをアルバムの1曲目に使ってみたり、何といっても、とてもリラックスして取り組めたんだ。というのも、レインボー・スタジオは凄いミュージシャンが傑作を生み出した歴史の詰まった場所だから、実は力が入っちゃったんだけど、今回はアットホームな寛いだ雰囲気の中でレコーディングができたんだ」

――EBTはリズムの追求がテーマやコンセプトのひとつであると思われますが、『Free To Play』はどういったリズム・アレンジを意図しましたか?
「このアルバムでは、いくつか異なるリズム・コンセプトがあるけれど、共通するのは、それらがすべてアシンメトリックなリズムや素数をベースにしているということ。そこには革新的だったり、取り立てて新しいものはないけれど、同じようなことをする他のトリオとは一線を画す、自分らしいアプローチを見つけようとしている。
例えば、今作は5/16拍子(新作の“Skrivarneset”、“'Oumuamua”、“Episk-Aggressiv Syndrom”)の曲を多く書いたけれど、11/16拍子(“Kestrel”)と19/16拍子(“Meanwhile In Armenia”)のものもある。僕の5拍子へのアプローチは、テンポを速くすること。そうすれば、小節の中の1拍が安定したパルスになり、ゆったりとリラックスしたように聴こえるようになるんだ」
――“Kestrel”は今作の中でもっともコンテンポラリー・ジャズの要素が詰まった特筆すべき曲だと感じました。
「“Kestrel”など11/16拍子で書かれている曲では、小節を小さな断片へと分割したり、伝統的なノルウェーのフォーク・ミュージックを踏襲しつつも現代的な手法を用いて、いままでにないビートを作ったりと新しいことにチャレンジしたよ。
ノルウェーのフォーク・ミュージックの中には3/4拍子のものもあるけれど、ビートが同じ長さである必要はないんだ。これまでにはそういうフォーク・ミュージックのビートをクオンタイズしようとしたミュージシャンもいて、例えば11/16拍子、つまり(3、5、3)のグループそれぞれの2拍目を長くしてアクセントを置いたスタイルがうまくいくと発見したんだ。これは理論上の話で、実際にはまったくされていないけれど〈感覚的に〉クオンタイズするというやり方だね。
“Kestrel”では、各小節の16分音符の部分すべてについてこの概念を応用して現代ヴァージョンを作ってみたんだ。ベルリンを拠点に活躍しているスウェーデン人ベーシスト/作曲家のフランス・ペッター・エルド(Frans Petter Eldh)という人がいるんだけど、彼の楽曲“Love Declared、Disaster Averted”(2016年)では、7/16拍子で(2、2、3)のグループでまとめて、1拍おきにアクセントをつけることで、通常の7/8拍子とは異なるフィーリングを生み出しているんだよ。
で、”Kestrel”の最後でもこれと同じことをしていて、(2、2、2、2、3)のグループの中の1つおきにアクセントを付け、これらのアクセントに基づいてハーフタイムのバックビートのグルーブで、4小節を作る。すると不規則なヒップホップのノリのようなグルーブになるんだ。おもしろいのは、それがすべて抽象的な感じではなく、11/16にクオンタイズされていて、非常に具体的であるということだね。曲の前半はもっとシンプルなアプローチをしているよ。同じグループ(2、2、2、2、3)に属するものを通常の4/4拍子と考えるんだけど、 5つのグループがあるので、わずかに長い3つのグループをつねに4/4拍子の4つの架空の小節にまたがって広げて埋め合わせることになるんだ」
★参考記事:同じNTNUジャズ科出身であり、エスペンの教え子でもあるトリオのメンバー、バルー&シーモンが在籍するバンド・WAKOへの2019年のインタヴュー(Real Sound)。〈エスペンからは幾何学的な音列や複雑なハーモニーを学び、彼の音楽を表現するには深いレヴェルでの理解と高度なテクニックが必要だ〉など、エスペンからの音楽的な影響について言及されている

トロンハイムは北欧イチのジャズのメッカかも
――アルバムの中でも、“Episk-Aggressiv Syndrom”は個人的に好みの楽曲です。現代音楽とジャズのインプロヴィゼーションの融合は、ノルウェー・ジャズではよく耳にします。
「タイトルが示す通り、あらゆる感情やダイナミクスといったことも含んでいるんだけど、自由に、心の赴くままにプレイしたかったんだ。これはミスやクレイジーになることを厭わずにプレイに集中した数少ない曲の1つであり、曲の中盤は完全にフリーだね。 実はこの部分ではテクニックを駆使して〈攻めた〉演奏でいこうと最初から考えていて、それがアルバムに必要なコントラストを作り出すと僕は思っていたんだ。コンテンポラリー・ジャズ、新ロマン主義、そして自由な即興演奏を次々に繰り返すスタイルで、それらが上手くミックスされた、調和のとれた作品だと思う」
――おしなべて北欧の大自然を思い起こさせるモチーフの曲が多いように思いますが、やはりそういったものから影響は受けていますか?
「ここ数年多くの国を周ってきたけれど、やっぱりノルウェーの大自然は一番だなと感じるし、それらは僕の音楽に多大な影響を与えていると言える。特に今作の最後の曲(“Furuberget”※)は僕が生まれ育ったハーマルの自然からインスピレーションを得て書いた曲なんだ。その景色は特別目を見張るような凄いものではないけど、僕にとって穏やかで心が休まるその風景をこの曲に込めたよ」
※Furuberget=松の丘の意
――現在の拠点であるトロンハイムのジャズを取り巻く環境はどうですか?
「ここ30年、依然としてトロンハイムはノルウェーで、もしかしたら北欧で一番のジャズのメッカかなと思う。誰にも門戸は開かれていて、ジャズの基礎から理論を勉強したり、もちろん納得するまで自由に練習することができるよ。僕が教える際も、自分らしいやり方を大事にしていこうということに落ち着いたんだ。まずバンドを組んで自分達らしい音を追求してもらう。何にもとらわれず自由に学べる環境であることは断言できるね」
――ご自身の今後の活動はどうなっていきそうですか?
「秋には日本以外の地域で『Free To Play』の発売が控えているのと同時に9月にはオスロでリリース・コンサートもあるよ。それから、シリエ・ネルゴールとデュオでツアー、それにソロ・コンサートのライヴ録音も予定している。さらにはこれまでにない大規模なプロジェクトなんだけど、トロンハイム・ジャズ・オーケストラとのレコーディングもあって、作曲に9か月間かかった、(楽譜が)200ページもある楽曲をこなさないといけないんだ。他にも少なくとも3つのバンドに曲を提供しているし、トリオ、デュオ、ソロとたくさんやることが待っているよ」
――最後に、日本のファンに向けてメッセージをいただけますか。
「いつも僕の音楽を気に入ってくれてありがとうございます。これからも良い作品を届けられるように活動していくので、ぜひ期待して待っていてください!」