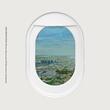〈言葉と音楽の関係〉の〈あたりまえ〉を問う日本語詩歌論
うたはしぜんにまわりにあった。耳にし、声にだした。長じて、楽器を手にする。楽器がうたう。声のかわりになる。大きく小さく、高く低く、しかも、ことばに制約されるもしない。意味の束縛からはなれている。このほうが自由じゃん! でも、うたはやはりそばにある。日常の意味、文法、シンタックスに、声域に、声色に制約されながら、でも、音楽=うただよね、としばしばおもいこまれてさえいる。じゃあ、うたって何か? あらためて考えようとするのだが、手掛かりはありそうでほとんどない。うたについて語るひとは、うたをあたりまえにおもっているひとばかりだ。ほんとは〈あたりまえ〉を問うところからやらなくちゃいけないのでは?
大谷能生の試みを、わたしなりにシミュレーションしてみると、こうだ。いや、見当はずれも甚だしい、って言われるかもしれない。むしろこれはわたしのことだ。わたしがうたについてぐちぐち考えているのを、大谷能生の本に投射しただけだ。やりたいとおもいつつできなかったことが、ここではおこなわれている。あっぱれ(くっそ~w)。
この列島の言語、詩・詞、うたをめぐる時枝誠記、吉本隆明、菅谷規矩雄ののこした論考をすこし時間をかけて読みかえし、大著のところどころで、参照する。浪花節、流行歌、唱歌からフォーク、ロック、J-POP、椎名林檎、宇多田ヒカルへと個別に論じてゆく。道すがら、さまざまなリズムが、つまりはカラダのうごきとダンスがからめられ。
でもねでもね、これが一直線になっていないんだ。そんなふうに読もうとすると、肩透かしをくわされる。講義をもとにしているらしいのだが、研究書の顔をしながら、研究書にはできないことをやる、講義=声=はなしことば(パロール)がもとでこそのインプロを。クラブでダンスしてるとき、ある瞬間にリズムが、曲調が変わって、あれ?!っとアタマは疑問符だらけになってもカラダはちゃんとノッている。客観的な論考がつづくかとおもうと、大谷能生(らしき一人称)の自伝的語りやコメントがあり、シナリオがあり。この列島のよく知られた、あるいは、よく参照される文献は、余計な道草はくわないよ、まずは言いたいことを言わせてくれいとばかりに、故意にすっとばす。
つまりは大谷能生のほかの著作と同様、内容とことばの音楽がシンクロしているのが醍醐味。意味内容をこえたものが感じとれるひとにこそ、という長丁場。このなかから、拾えるものを拾ってちゃんと栄養に。