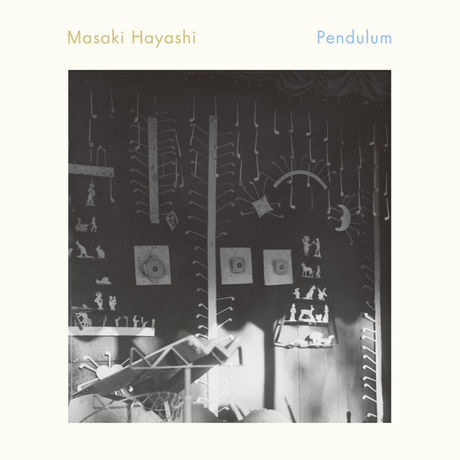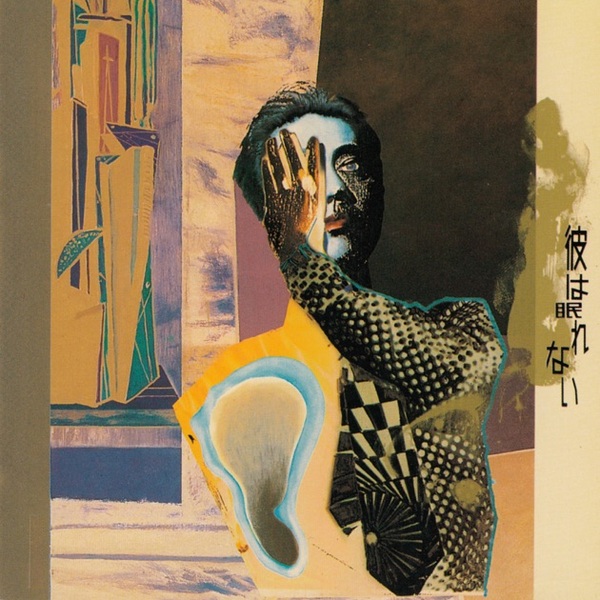Mikiki読者のみなさん、ちょっと遅くなりましたがあけましておめでとうございます。このブログを2016年もがんばりたいと思います、今年もよろしくお願いします!
2016年はデヴィッド・ボウイを筆頭に、ミステリー・ジェッツ、サヴェージズ、ドーター、アンダーソン・パックなど、すでにおもしろい新譜がたくさん出てきていますね。今回はその辺の新譜を紹介しようかなぁとも思ったのですが、ふと気づいてしまいました。自分が2015年の年間ベストを選んでいないことに。
というわけで、今回のテーマはぼくの〈年間ベスト・アルバム2015〉でいこうと思います。2015年はとにかく大豊作な一年で、あらゆるジャンルで良い新譜がガンガン出てきたように感じます。そのなかで、ぼくがもっとも注目して聴いていたのはクラシック~現代音楽の流れを汲んだインディー・クラシック(このジャンルについては連載第1回で簡単に説明しました)やポスト・クラシカル、ジャズ・ラージ・アンサンブル(これは2015年に限らず、近年の作品をいろいろ漁ってました)、そしてUSインディーにおけるバロック・ポップです。
このあたりのチェンバー・ミュージック・シーンは近年、急速にアップデートされている印象です。その原因は、クラシック~現代音楽の訓練を受けた若者たちが、彼らの培ってきたヴォキャブラリーと同時代の他ジャンルを意図的に混ぜはじめているからではないかと考えています。特にインディー・クラシックの勢いは目を見張るものがあり、インディー・ロック界隈とコラボレーションしたり、シーンの中心的なレーベルであるニュー・アムステルダムからジャズ・ラージ・アンサンブル作品がリリースされたりなど、多様な展開を見せているのです。また、以前このブログでも取り上げているように、ミニマル・ミュージックのポップ・ミュージックへの導入が様々なところで見られているという事象もあります。こういったチェンバー・ミュージックを巡る大きな動きを、自分の年間ベストを通して可視化できたらと思います。

去年の2月、新作『Garden Of Delete』が世界中で絶賛されたワンオートリックス・ポイント・ネヴァー(以下OPN)は、ロンドンのユニオン・チャペルで作曲家のニコ・ミューリーとオルガニストのジェームズ・マクヴィニーと共に、オルガンをテーマにしたライヴを行っています(動画はこちら)。2人はインディー・クラシックを代表的なレーベルであるベッドルーム・コミュニティーに所属しており、この共演からもOPNが現行のクラシック・シーンに興味を持っていることが窺い知れるでしょう。そんなOPNがポール・コーリー(OPN、ティム・ヘッカー、ベン・フロストなどに携わってきたエンジニア)と共にプロデュースし、自身が主宰するソフトウェアからリリースしたのが本作です。パーカッション、ギター、弦楽器、トロンボーンによって構築された霧がかったサウンドの中でたゆたうガビのヴォーカルは、元々オペラ・シンガーとして鍛えられたもの。きめ細やかな作曲が産み出す、静謐でヒリヒリしたサウンド・デザインからは、彼女の表現者としての毒が見え隠れします。ポスト・クラシカル的なアンビエント性と、インディー・クラシック的な現代音楽メソッドの衝突地点として聴くと理解が深まるかもしれません。シャラ・ワーデン(マイ・ブライテスト・ダイアモンド)に続くインディー・クラシックの歌姫となってほしいと期待しています。
9. ジュリア・ホルタ―『Have You In My Wilderness』
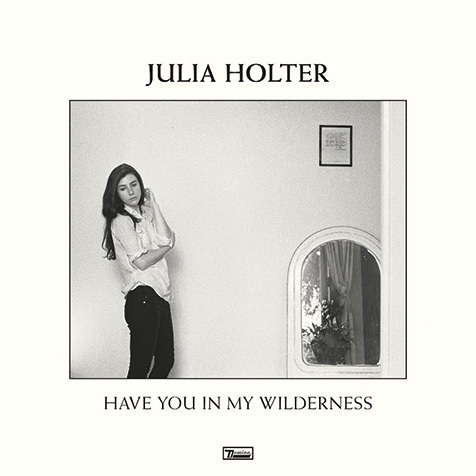
あらゆる音楽メディアが本作を手放しで賞賛していましたが、それも納得の出来栄えですね。前作『Loud City Song』(2013年)に引き続きコールMGM(元アリエル・ピンクス・ホーンテッド・グラフィティ)がプロデュースを担当。ジュリア・ホルタ―の歌が前面に出ているのが本作の特徴で、これは彼のディレクションに依るところが大きいそうです。ヴォーカルについては、ジェーン・バーキンやシャルロット・ゲンスブールにも通じるアダルトなフレンチ・ポップのニュアンスが感じられるのも素敵ですよね。また、ウォール・オブ・サウンドからチルウェイヴに至るまで、ポップ・ミュージックはリヴァーブの可能性を追求してきたわけですが、本作はその伝統の末裔にして、現時点での最高到達点と言いたいくらいサウンド・デザインが素晴らしい! あとクラシック~現代音楽の視点から注目すべきは、不安定に揺らめきながらレイヤーを構築するストリングスでしょうか。こういった先鋭的なサウンドとポップネスを恐ろしいレヴェルで両立させており、〈21世紀のバート・バカラック〉と形容したら褒め過ぎでしょうか。
8. ニルス・フラーム『Music For The Motion Picture Victoria』

ニルス・フラームは昨年、オーラヴル・アルナルズとのコラボ作『Loon』『Life Story Love And Glory』と、ソロ名義で『Solo』に本作と、4枚ものアルバムをリリースしました(『Screws Reworked』はリミックス作品なのでここでは割愛、『Solo』はフリー・ダウンロードできます)。『Loon』は綿密に構成された優れたアンビエント/ドローン・アルバムで、『Life Story~』は2人の連弾によるピアノ作品。『Solo』はクラヴィンズ370という高さ3.7mのピアノによる演奏がレコーディングされており、そのサウンドはもはやピアノなのか電子音なのかわからないくらい凄まじいものです。
そして本作はゼバスチャン・シッパー監督による映画「ヴィクトリア」のサウンドトラックで、全編を通じて絶妙にコントロールされたアンビエンスが途方もないほど美しく、滴り落ちるように弾かれるピアノと、ゆっくりレイヤリングされていく幽かなストリングスが織り成す世界観は、ポスト・クラシカルの1つのピークだと言っても過言ではないでしょう。ぼくはこの繊細なサウンド・デザインこそが、ニルス・フラームの音楽における唯一無二の本質だと考えています。“Them”の気が狂いそうなほど儚いストリングスを聴くと、彼こそがECMの血をもっとも色濃く受け継いだ、〈沈黙の次に美しい音楽〉を体現している音楽家ではないのかと思わずにはいられません。
7. グウィリム・ゴールド『A Paradise』

ゴールデン・シルヴァーズの元フロントマン、グウィリム・ゴールドによるソロ・デビュー作で、自宅のピアノで作った楽曲をプロデューサー/エンジニアのレックス(Lexxx:エヴリシング・エヴリシング、ワイルド・ビースツなど)と丹念に磨き上げ、さらに共同プロデューサーとしてダークスターのジェイムズ・ヤングと、トゥルー・パンサーに所属するヒエタル(Hyetal)とブリオンを迎えているうえに、ストリングス・アレンジにニコ・ミューリーを召喚するという徹底ぶり。これで傑作にならないわけがありません。グウィリムの弾くピアノはポスト・クラシカル的でもある深い音色で、寂寥とした自身のヴォーカルとの相性は抜群。鼓膜を穿つように高速で突き刺さるビートとピアノ・サウンドが絡み合う“Triumph”を聴くと、ヒエタルとの共同プロデュースが大成功であることがわかりますし、ストリングスとファルセット・ヴォーカルが奇跡的な按配で溶け合っている“I Know, I Know”は、個人的にも2015年のベスト・ソングに選びたいほどです。このサウンドはまさしくポスト・クラシカル/インディー・クラシック以降のモードであり、なおかつ〈スフィアン・スティーヴンス『The Age Of Adz』(2010年)へのUKからの返答〉とも言えるのでは。
6. 林正樹『Pendulum』
ポスト・クラシカルにはポスト・ロックと同様に、〈音楽〉になる前の音/音響をテクノロジカルな手法を用いて磨き上げるという側面がありますが、そういった性質を念頭に置きながら『Pendulum』を聴いた時、本作は世界でも類を見ないほどの輝きを放っています。音響空間全体を視野に入れた林正樹のコンポジションはもちろん、ディレクターを務める山上周平、レコーディング/ミキシング・エンジニアの奥田泰次、マスタリング・エンジニアの木村健太郎といったスタッフ陣の技術と知性が注がれており、〈これぞ録音芸術!〉と言いたくなります。アントニオ・ロウレイロ(ヴィブラフォン/ヴォイス)、ジョアナ・ケイロス(クラリネット)、藤本一馬(ギター)、徳澤青弦(チェロ)、Fumitake Tamura(エレクトロニクス)と豪華メンバーが織り成す音の輪郭や定位、レイヤー、ハーモニーは中毒的で、こういったプロダクションの革新性こそが音楽を進化させるとでも言いたげな、強い想いすら伝わってくるようです。BGMとしてもリスニング・ミュージックとしても機能する、2015年におけるチェンバー・ミュージックの最高峰でしょう。