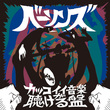GOING UNDER GROUNDが新たなスタートを切ろうとしている。埼玉・桶川市で同じ中学校に通う仲間たちを中心に結成されたこの5人組は、94年から青春の香り溢れるキラキラしたポップソングを世に送り出してきた。しかし、その長い旅路も終わりを迎える。2009年にキーボードの伊藤洋一が脱退、昨年にはドラムスの河野丈洋もバンドを離れることを発表した。
5人から3人へ。ヴォーカル/ギターの松本素生自身が「両翼を失った」と語るバンド最大の危機においても、彼はバンドそのものを辞める気はなかったという。その言葉通りにGOING UNDER GROUNDは歩みを止めず、2015年9月にシングル『もう夢は見ないことにした/Soul train』を発表、そしてこのたび“the band”をYouth Recordsよりリリースした。彼らのこれまでのイメージをひっくり返すラウドでパンクなサウンドは、小学校5年生のときにクリスマス・プレゼントにもらったブルーハーツの『TRAIN-TRAIN』(88年)が人生を変えたという松本のルーツを感じさせる。
〈歌うのに理由など要らないぜ〉――みずからの原点と現在地を確かめるかのように演奏するGOING UNDER GROUNDは、いま確かに新たなフェイズに入っている。そんな原点回帰にして新境地のシングル“the band”について、松本素生が語った。
野良犬みたいに自分たちのなかでの独自のルールがあった
――自分は中学生のときに三ツ矢サイダーのCMで流れていた“STAND BY ME”(2005年)でGOING UNDER GROUND(以下、GUG)を知ったんです。取材にあたって、久しぶりにこれまでのアルバムを全部聴き返したんですけど……恥ずかしながら号泣しまして。あの頃は歌詞の意味なんて一つもわかってなかったんだなと。
「ふふふ(笑)。嬉しいですね。それを言うなら、僕もわかってなかったですよ」
――松本さんもわかっていなかった……?
「等身大というか、感じたことをそのまんま書いていただけだから。自分以外の人にどういうふうに聴かれるのか、ということをまったく考えていなかったから、自分でも昔の曲をたまに聴くと、〈良い曲書いてるじゃん!〉って思います(笑)」
――“STAND BY ME”は追憶と旅立ちを描いた歌ですよね。〈今を生きるんだね君はいないけれど/そばに君がいる気がした〉という歌詞に、松本さん自身も振り返ってみて思うことがあるのかなと考えたんですけど。
「初期の頃は、背伸びしてたなという感じですね。純粋で綺麗な生き方とかが丁寧に描かれていて。そういう背伸びが尊いものだったんだなと、いまになってみると思います」
――背伸びしなきゃいけなかったのはなぜですか?
「僕らは、埼玉でずっとバンドをやっていたんですけど、東京のシーンに対する憧れがすごく強くて。サニーデイ・サービスとか、当時は下北沢のバンドにすごく勢いがあった。でも、そこに属したいかというとそうじゃない。それにはリアリティーがなかったんです。〈ライヴで必ず盛り上がるような曲を書かなきゃいけないのか?〉みたいな反骨心があったと思う。やっぱり幼馴染み同士のバンドですからね、野良犬みたいに自分たちのなかでの独自のルールがあって、それが当時は良いほうに作用していたんだろうなと思います。自分たちは自分たちのやり方を突き詰めることしか、アウトプットする方法がなかった」
周りの友達に〈良いのが出来たんだ!〉と聴かせたくなるシングル
――なるほど。では、今回シングルをこのタイミングで出そうと思ったのは?
「去年ドラムが抜けて、もともと5人組だったのが3人になったんです。事務所も半分は自分たちで経営していたんですけど、それも辞めた。とはいえ、バンドを辞めるという選択肢はまったくなかったし、曲は無限に書けるので、書き続けてはいたんです。Youth Recordsからのリリースが決まったときに1つ決めたことが、自分たち自身が〈やったぜ、これ出来た!〉というものが出来なかったら、もう辞めようと。ただ他人から〈良い曲だね〉と言われるものでは意味がないと思っていました」
――“the band”もカップリング曲の“Drifting Drive”も、これまでのGUGのイメージを覆すような、でもちゃんと松本さんの中にあったオルタナやガレージ・パンクのエッセンスが出ている曲ですよね。まったく新しいバンドのようにも聴こえます。“the band”にはこれまでと違ってキーボードが入っていないですよね?
「キーボードは1回入れたんですけど、全部抜いたんです。やっぱり、自分たちが作ってきた〈型〉を破れていなかったんですよね。せっかく“the band”のような〈これが生身のロックンロールっしょ!〉という曲を書けたのに、癖でキラキラする部分を入れちゃうという。だから抜いたんです。抜いたら抜いたで、メンバーやスタッフがザワつきましたけどね(笑)。でも今回は、これまでとはまったく違う部分が出したかった」
――松本さんの〈変化したい〉という想いは、そこまで強いものだったんですね。
「そうですね。自分の周りの友達に〈良いのが出来たんだ!〉と聴かせたかったんですよ。これまではそんなこと絶対なかった(笑)。でも今回の作品は(周りに)配りまくってるし、なんならその場で流してますよ。〈これ聴いてよ!〉って」
――今回のシングルの新曲2曲は、対になっていると思ったんですよね。“the band”はどちらかというと、ファンに対して〈自分たちはこれからこういうことがやりたいんだ〉と宣言をしているのに対して、“Drifting Drive”は自分に対して決意を言い聞かせているような曲だなと思ったんです。
「去年、〈BAR天竺〉という酒場を始めたんですよ。バンド活動と並行してお店を始めて、いろんな人と関わることになって心と身体がバラバラになりかけたんですけど、そこを持ちこたえたら〈全部アリだな〉と思えるようになったんです。お客さんには、綺麗な呑み方をする人もいれば、くだらない呑み方する人もいる。俺のことを知っていて来てくれる人もいれば、全然知らない人もやってくる。そういうのは全部アリなことだと思った。Youth Recordsの庄司(信也)さんと打ち合わせをしていたときに、そんな話をしながら出てきたのが〈全肯定〉という言葉だった。カッコイイこともカッコ悪いこともいろいろあるけど、1回全部肯定しないと物事は前に進んでいかないなと。状況を全部受け入れて、全肯定するという。いま自分が歌いたいことはそういうことなんだとわかってからは、歌詞を書くのがすごく速かったです」

――自分のダメさや、できないことも認めてあげないと、こういう歌詞は書けないのかなと思うんですけど。
「そうですね。〈もう失うものはないな〉と思いましたね。〈俺はいったいなにを守ってきたんだろう?〉とハッとすることがあり、それは去年から今年にかけてずっと考えていました。やっぱりプライドとして、〈昔は良かった〉とは言いたくなかったし、言われたくなかったというのはあります」
――この曲を聴いていると、すごく勇気付けられるし、〈応援歌〉のような効果もある気がして。そういう意識を持って書かれたりは?
「いや、ないですね。自分みたいな気持ちでいる人のことは考えましたけど、ライヴに来るファンに向けて……とか、そういうことは全然考えなかった。もっと言うと自分にしか向いてないと思います。俺は俺なりのやり方で、間違ったやり方でも正解にする――そんな作業だったような気がします」
――でも、決して閉じた作品にはなっていないと思います。普遍的なポップソングに昇華されている。
「“the band”の歌詞に、〈窓ガラス割れないやつが教室で組んだバンド〉という一節があるんですけど、ずっとそっち側に自分はいると思っている。そうじゃなきゃ、このバンドを始めなかったし、そういうことも全肯定したかったんですよね。〈それアリでしょ〉って。窓ガラスを割れなくて、ヤンキーにもなれなくて、じゃあ何ができるんだよ?という存在。〈いや、それで全然OK〉と言いたかった。そうした想いを抱えている人には作用する曲だと思いますね」
――松本さんが“the band”を書いたときは、いまのようなアグレッシヴなアレンジにするというイメージはあったんですか?
「ありましたね。モダン・ラヴァーズみたいなロックをやりたかったんです。ナードだけど、強くて太いロックンロールをやりたいと思った。そういえば、歌詞は〈BAR天竺〉で書いたんですよ。その日、宴会の予約が入っていたので深夜まで営業していて。呑み会は勝手に盛り上がっていたからだんだん暇になってきて、〈じゃあ歌詞でも書こうかな〉と書きはじめたんですけど、とにかく眠くて中学生レヴェルの言葉しか出てこない(笑)。でも、そのあとに書き上げたものを読んでみたら、思っていたことが全部歌詞になっていたから〈これ、良いじゃん〉となったんですよ(笑)。今回ほど人の評価が気にならなかったのは、十何年ぶりじゃないですかね。自分のなかでスタート地点に立てたし、0が1になった。周りの言葉ではブレないバンド感とグルーヴを手に入れられたなと」
――レコーディングに際して、メンバーとはどのようなお話をされたんですか?
「これまでGUGは〈丁寧に〉というのがあったんですけど、今回は、〈チャッチャとやっちゃおうよ!〉みたいな(笑)。“the band”の歌は1回しか録ってないですし、直してもいない」
5人の頃をノスタルジックに想う気持ちは1mmもない
――このシングルで、何度目かの新しいスタートを切るわけですが、いま中学生の頃のバンド結成当時のことを思い出していかがですか?
「いや、なにも変わんないです。なにも変わってなくてびっくりするぐらい。ただ、そういうバンドが1つぐらいあっても良いかなと思うし……。ベースの石原(聡)なんて、クビにしたいくらいミュージシャンに向いていなくて、通称〈妖怪ゴムベース〉なんですけど、GUGには絶対に必要なんです。バンドは長くやっていると、だんだんヤスリを掛けたように綺麗にはなっていくんですけど、おもしろくなくなっちゃんですよね。歪なところがないと、バンドとしては魅力がない」
――妖怪ゴムベース……すごいあだ名ですね(笑)。5人が3人になったという事実については、どのように受け止められていますか?
「良かったなと思います。決して、メンバーが抜けて良かったという意味ではなく、3人になってもバンドをやるという気持ちがあって、続いている。そして、新しいものが見えてきているという事実が嬉しい。それまでは自分たちが作った型に自分たちをはめ込んで、音楽をやらなきゃいけないことを重荷に思っていたし。でもそこから抜けきれない自分もいた。だからバンドを辞めたほうが良いのかなとも思っていたので」
――新しいなにかが見えてきたという事実だけで、とても良い変化ですよね。
「最初の5人でやっていたGUGの音楽は、〈卒業する音楽〉だと思うんですよ。最初にさっき“STAND BY ME”を久しぶりに聴いて号泣したと言ってくれましたけど、それはそれで最高の音楽の在り方ですよね。これまでは自分たちもそういう意識で音楽を作っていたと思うんです。曲ごとに、一枚一枚写真を撮るように、思い出を切り取っていくように作っていた。でも5人が3人になって、やっぱりまだ音楽をやりたい、バンドをやりたいとなったときに、写真を撮るような作り方はもう適切じゃないんですよね。もっと自分の日々のことや想い、内面を素直に見せたくなった。そういう違いが生まれたと思います」

――あえて伺いますが、今後に脱退した2人がバンドに戻ってくる可能性はあると思いますか?
「それだけは無理だと思いますね。戻ってきたとしても、あの頃と同じものを作ることは絶対にあり得ない。演出はできるかもしれないですけど、やっぱりサボったらサボったぶんだけ、速攻でバレますからね。ちょっとカムバックみたいな感じでやろうとすると、物足りなさしか感じないんじゃないですかね? 別のものになっているんだったら話は別ですけど。寂しいけれど、あの頃をノスタルジックに想う気持ちは1mmもないんです」
“the band”は、会えなかった人ときっと会える曲だろうなという予感がある
――松本さん自身が、GUGにこだわっている理由は? ソロでやるという選択肢もあるようにも思えるんですが。
「それは自分でもよくわからないんですけど、GOING UNDER GROUNDじゃなきゃダメだったんですよねぇ。友達からも〈一人でやってみたらいいじゃん〉と言われるんですけど、やりたいと思わない」
――それは残った2人のメンバーがいるからですか?
「なんでだろうな……。まとめると〈悔しいから〉ということなんだと思うんですけどね。俺、サニーデイ・サービスの頃から曽我部(恵一)さんが大好きなんですよ。この前、同じDJイヴェントに出て、久々に曽我部さんと話したんですが、そのときに〈俺、曽我部さんの『超越的漫画』(2013年)、『まぶしい』(2014年)、『My friend Keiichi』(2014年)がブルーハーツと同じぐらい大切な作品なんです〉って伝えたら、〈それめちゃくちゃ嬉しいけど、あの3枚は全然売れなかったし、誰も評価してくれなかったんだよねー〉と言われて(笑)。でも、曽我部さんは、そのアルバム3枚共すごく気に入っているらしいんです。だから俺もそれぐらいの心構えでやりたい。評価されなくても、〈俺はこれが好きだからやってるんだ!〉と言えるような音楽が作りたい。音楽で食っていく術を探していると、どんどん自分の音楽がつまらなくなっていくんですよね。それはもしかすると、自分がプロフェッショナルじゃないからかもしれない。だったら別の何かをしながらでも、自分が正解と思える音楽をやるしかない。それをGUGでやりたいんだと思うんです」
――松本さんが、曽我部さんのそれら3枚のアルバムに惹かれる理由は?
「あの3枚は〈簡単にわかられてたまるか!〉という想いで作られているように思うんです。拒絶してる。でも、リスナーは作品から拒絶されても、そこから自分がなにかを拾い上げるることができる――そういう感動ってありますよね。僕はブルーハーツを聴いたときにも同じことを思ったんですよね。〈俺も、こんなこと思っている!〉って」
――それは“the band”にもありますよね。閉じた楽曲ではないけれど、拒絶してる一面がある。結局、俺のことは俺にしかわからないよという。
「この曲が万人受けするとも思わないし、大ヒットするとも思わないんです。ただ、これまでGUGを〈へー〉程度に思っていた人も〈あれ?〉と思ってくれるだろうな、という予感はしているんです。会えなかった人ときっと会えるだろうなと。ようやく自分たちの足跡や背中を、胸を張って見せられる、そういう作品だと思うんですよね」

――“the band”には〈歌うのに理由などいらないぜ〉という歌詞がありますが、最初に聴いたとき、ここまで言い切るのかと思ったんですよね。ある意味で、音楽家として大上段に振りかぶってるし、完全に脇を晒してる。そこまで言い切った松本さんには何か〈覚悟〉を決めているところがあるんでしょうか?
「何かを変えたいとは一切思わないです。そりゃバンドをやっている身としては、売れたいですよ。だって売れないと聴いてもらえないし、お金だって欲しいし。ただ、スタンスは絶対に変えない。ポップソングって不思議で、作り手が個人的な思い出を歌っている曲でも、それを自分のことのように変換して聴いて涙を流す人がいる。最初から〈応援歌を作ろう!〉とするとバレちゃうと思うんですよ。そうじゃなくて、ある意味自分勝手な曲をこれからも作り続けたいなと思います」
――やっぱり、この2曲はすごく嬉しかったです。新たな始まりを感じさせる力強い歌だし、GUGはここでこんなことができるんだ、と素直に感動しました。
「ありがとうございます。音楽が本当に必要な人っているじゃないですか? でも、音楽がなくても大丈夫な人もいて。音楽が日常に必要ない人には、何かを言うつもりもないし、それはそれでいいと思うんですよ。ただ、自分も含めて音楽がないと不安定で、生きていけないという人たちに買ってもらえるようなバンドになりたい。音楽好きだな、ロック最高じゃんと思ってる人全員にCDを買ってもらいたい。これからは、そういうモチヴェーションでやっていきたいんです」