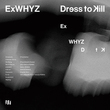LUCKY TAPESとSugar’s Campaign(以下、シュガーズ)が出演したライヴ企画〈ミキキの平日〉が、去る12月7日に東京・六本木VARIT.で開催された。共にセカンド・アルバムを今年発表し、日本語ポップスの新たな担い手として注目を集めた両者は、先日のレポート記事でもお伝えしたようにエンターテイメント性の高いステージングも高く評価されている。それぞれが持ち味を遺憾なく発揮し、笑いと感動に溢れたパフォーマンスで観客を魅了した。
一番手のシュガーズは、SeihoとAvec Avecに加えて、冨田ラボの新作『SUPERFINE』にも参加したakio (ヴォーカル)に、お馴染みのサポート・メンバーであるKASHIF(ギター)と、今回が初参加だったというPELICAN FANCLUBのカミヤマリョウタツ(ベース)の5人編成でステージへ。上述のレポート記事で〈MCが抜群におもしろい〉と書いてあったことを切り口に、往年のアムラー風ファッションで登場したSeihoを中心にトークを展開してフロアを大いに沸かせた。もちろん演奏面でも、ステージ下手に座るAvec Avecの味のあるドラミングや、akioの前のめり気味な熱唱など見どころ満載。“ネトカノ”や“ホリデイ”といったキャッチーなポップソングを連発しながら、一体感のあるアンサンブルで大いに盛り上げた。
続くLUCKY TAPESは、11月下旬にツアー・ファイナル公演を終えたばかりで、コンディションも完全に仕上がった状態。さらにこの日は、MC担当の高橋健介も明言していたように“レイディ・ブルース”や“Mr.Robin”、“Touch!”などアップテンポのナンバーを中心に並べたセットリストが用意されたこともあり、オープニングからフロアは最高潮に。田口恵人が弾く黒いベース・ラインを土台にして、高橋健介によるキレッキレのギターや、大比良瑞希のコーラス、ブラスやパーカッション、そして高橋海のメロウな歌と鍵盤が自在に踊る様は、まさに大所帯ならではの魅力。新曲が披露されたアンコールに辿り着くまでの優雅なステージ運びには、〈横綱相撲〉という形容すら頭によぎった。
今回は〈ミキキの平日〉の開催を記念して、イヴェント当日に両グループのメンバーを迎えた座談会を実施。お互いの出会いと2016年のトピックを振り返り、年間ベストも選んでもらった。ポップスを標榜しながら、まったくキャラクターの異なる両者のトークは微笑ましい内容になったはず! *Mikiki編集部
バンド演奏ならではのマジック
――これまで両者に接点はありましたか?
Seiho(Sugar’s Campaign)「ありますよね。ちょくちょく」
高橋健介(LUCKY TAPES)「ちょこちょこ」
Avec Avec「Slow Beach(LUCKY TAPESの前身バンド)の時に聴いてたよな、Bandcampとかで」
高橋海(LUCKY TAPES)「ホントですか? 嬉しい」
Avec Avec「(高橋の)ソロも聴いてましたよ」
――じゃあ結構前から存在としても知っていたんですね。
Seiho「そうですね。もう20~30年くらい前から」
――LUCKY TAPESはシュガーズのお2人のことをいつ頃から意識していましたか?
健介「僕は海くん経由で知ったかな」
海「シュガーズより先にそれぞれのソロ音源を聴いていました。当時の自分にとっては聴いたことのないような音で、そこから自分もトラックメイクに興味を持ったりして」
Avec Avec「あー、そうなんですね」
Seiho「2010年~2012年くらいって、ヒップホップの人もテクノの人も、エレクトロニックの人もジャンル的にクロスオーヴァーした時期があったじゃないですか」
Avec Avec「みんな交わってたよね。クラブの人らもネット・レーベル系の人らも、インディー・バンドも一緒くたにやってた感じ」
Seiho「いまとなっては、やっぱり元の畑に戻っていくんや、という感じだけど。その頃はもっとゴチャッとなっていたもんな」
海「それ以前はバンド・サウンドや生音の音楽しか知らなかったので、(SeihoやAvec Avecのトラックが)新鮮に聴こえたのかも」

――そういった流れを経て、いまのお互いをどう見ていますか?
Seiho「(LUCKY TAPESは)編成がしっかりしているというか……良くも悪くもそんなにしっかりせんでも全然イケるのに、本当にしっかりしてる(笑)」
健介「しっかりしすぎですか(笑)?」
Seiho「いや、めっちゃイイと思う!」
Avec Avec「自分はあんまりライヴを重視していなくて、家で音源を聴くほうが好きなんですけど、ラッキーの曲はライヴで聴いた時の印象がすごく強い」
――そう思わされるのは、LUCKY TAPESが10人規模の華やかな編成でライヴをしているのも大きいですよね。現在の編成でやろうと思ったのは、どういう経緯が?
海「打ち込みでデモを作っていると、どうしても楽器を重ねてしまいがちで。それをバンドに落とし込むとなると、同期はなるべく持ち込みたくないので、(デモの)音源を再現するためにどんどん楽器が増えていく(笑)。ツアーは結構大変ですね」
Seiho「それがすごいよな、やっぱ」

――シュガーズのライヴも、バンド演奏ならではのマジックを感じました。バンドでやる時と2人でやる時とで、棲み分けはどのようにされているんですか?
Seiho「(ライヴに)呼ばれる時間だよな?」
Avec Avec「そうですね」
Seiho「もともとクラブで深夜帯にやることが多かったから、その場合は2人でDJセットでやっていました。そのほうがフレキシブルにやれるしスリリングだから」
Avec Avec「いまでも深夜帯でやる時は2人ですし、今日みたいな対バン形式の日はバンドでやろうかという」
Seiho「今年はフェスとか昼間にやることもあったから、ワンマンでやったようなバンド・セットにしてる感じですね」
――Avec Avecさんの叩くドラムがイイ味を出してるように思ったんですけど、好きなドラマーは?
Avec Avec「僕ね、イアン・ペイス※とか」
※ディープ・パープルやホワイトスネイクなどに参加した、UKハード・ロックを代表するドラマー
――ハハハ(笑)、マジっすか。
Avec Avec「あとラス・カンケルって知ってます? 70年代にジェイムズ・テイラーやジャクソン・ブラウンの後ろで叩いていたアメリカン・ロックの人なんですけど」
――そういう人たちのドラミングはご自身のプレイに反映されていると思いますか?
Avec Avec「わからないですけど、もしかしたら(笑)」
各々がめざすポップスとは?
――では、年末ということで、2016年が各々にとってどんな1年だったか振り返ってもらおうかと。
Seiho「終わったかなって」
Avec Avec「うん、おしまい」
Seiho「さよなら~って。全体的なムードとして、そういうものが流れていた気がしますね」
――へえ、おしまいってムードが?
Seiho「うん。お別れのムードみたいな。2016年はあまり行動しても意味がない年、〈考える年〉やったんですよね。だから考えれば考えるほどおもしろかったし、深く入っていけたというか。それは別れの季節やから、一人でいるということを強く意識したのかなと」
Avec Avec「さっき話していた、2010~2012年はみんなが一緒の所にいたっていうのの真逆。そういう時期が終わって、みんながそれぞれの持ち場に戻ったような」
Seiho「MyspaceやSoundCloud、Bandcampとかを介して一人で聴いていた音楽が、いつしかクラブやライヴハウスで流れて、それは一人で聴いていたわけじゃなかったんや、と気付いてグッときたのが2010年頃。それから、この曲はこんなにみんなが知ってるんや、みんなが歌えるんや、というのがクラブやライヴハウスでわかったのが2012~2013年で。そこからそれがあたりまえの状態になった。それは僕らがメジャー・デビューして、僕らがリリースする曲はファンの人たちが知っててあたりまえになったのと同じで」
――“ネトカノ”が発表されたのが2012年ですよね。
Seiho「そうそう。だから今年は逆に、どうやって自分たちの音源を〈一人のため〉にするかを考えるようになった。これはあなたのためだけに作った音楽なんですよ、ということをいかにプレゼンテーションするか、それがわかるように作るかを。だから俺たちが今年出したアルバム(『ママゴト』)は自分のために作っているんですよ。そこは極端に意識していました」
海「ラッキーはどちらかというと外に向いていた年だったと思います。ひとつの目標だった〈フジロック〉に出演したりとか、初の海外公演を経験したり。あと、セカンド・アルバム(『Cigarette & Alcohol』)でようやく自分たちのやりたいことが見えてきたのは大きかった」
――では、両者のいまおっしゃったようなムードを踏まえて、今年発表された各々のアルバムについて振り返ってもらえますか?
Seiho「〈誰もが知っている〉ポップスではないものではないものを作ろうとしました」
Avec Avec「そうね。既視感のあるものじゃないものを」
Seiho「あまりにも〈あるある〉が世の中に多すぎるから。このコードでこういう歌詞ってよくあるよね、というのがあまりにも増えすぎちゃって。自分たちにとってはそれがちょっと退屈だった」
Avec Avec「〈共感〉というのがすごくキテるじゃないですか。Twitterなんかもそうやし。ネタを一発ドーン!みたいな。だから、それとは違う方向のポップスをめざしましたね」
Seiho「あとは猿ですよね。というか猿がほぼメインのテーマでした」
Avec Avec「そう、猿については結構考えましたね」
――その話は他のインタヴューでも読んだんですが、改めて教えてもらえますか?
Seiho「ネアンデルタール人とクロマニヨン人というのがいたじゃないですか。僕らはクロマニヨン人の最後なんですよ。最後というかクロマニヨン人が進化した結果なんです。もともとネアンデルタール人がいて、さらにクロマニヨン人も同時にいた。だけど、ネアンデルタール人は絶滅したんです。ではなぜ絶滅したのかと」
Avec Avec「というのも、僕らクロマニヨン人は言語を取得したんですよ」
Seiho「喋れるようになったんですね。だけどネアンデルタール人は喋れなかったから生き残れなかった。ではネアンデルタール人がどうやって意思の疎通をしていたかというと、歌でコミュニケーションを取っていたんです。そもそも歌と言葉には大きな違いがあるんです。文節に意味があるか、音に意味があるかどうか」
Avec Avec「それぞれの組み合わせの意味みたいなね」
Seiho「でも僕たちは、鳴き声とか音楽が示すもののほうに全体性を感じるんですよね。悲しいことを歌われると悲しみが伝わるんじゃなくて、悲しい気持ちになるというか。逆に言ったら、すごくシリアスなことを歌っていても、後ろでおちゃらけた音楽が鳴っていたら言葉が意味するものもおちゃらけて感じられる、みたいな。つまり、言葉以上に音や音楽のほうが上の階層を示すんですよね。すると僕たちは、なぜいま音楽をやっているのか……それを踏まえたポップスをちゃんと作ろうとしました」

――なんだか大層な話になりましたけど(笑)、でも『ママゴト』は言われてみれば確かにそういうアルバムですよね。最初はキャッチーで親しみやすいポップスで始まるけど、聴いているうちにだんだんヘンな展開が増えていくところも。
Seiho「ちょっとSFっぽいですよね。あれは猿から人工知能まで繋がっていってるんです」
健介「僕は(『ママゴト』に)ちょっと懐かしさを感じました。90年代、バブル期に聴いたような。シンセの使い方とかがいいなと思いました」
田口恵人(LUCKY TAPES)「自分たちの音楽性の深いところを攻めている感じがしましたよね。これまでと変えるんじゃなくて、もっと追究するというのが伝わってきたというか」
――では一方のLUCKY TAPESは、今年リリースした『Cigarette & Alcohol』を振り返っていかがですか?
健介「前作(2015年作『The SHOW』)に比べてスケールが大きくなりました。めざした方向にあるものを作れたかなと。さっきも言ったように、やっと録りたい音で録れているし。アレンジもすごくしっかり作ることができています」
――toeの美濃隆章さん、mabanuaさんに類家心平さんといった名うてのミュージシャンが参加したこともトピックでしたよね。それもあって、理想の音に近付けたのかなと。
Seiho「どんどん音が良くなっていますよね。やってることはこれまでと変わらなくても、音が良くなってくのがすごい」
――両者の音楽性を大きく括るならポップスになるんだろうけど、お互いのポップス観は随分違うような気がするんですよね。
Seiho「根本的に僕らがめざしているポップスは、ポピュラリティーじゃないです」
Avec Avec「もともとはポピュラリティー(とイコール)だと思っていたんですよ。でも、本当はそうではなくて、ポップスが最大公約数の音楽じゃないということに気付いたというか」
健介「僕らは逆に、ポピュラリティーに向かっている気がしますね。でも音楽的にはいわゆるポップスと別のところから引き出してきているから、演者としてはそれほどポップスをやっているとは思っていないかもしれません。メロディーの感じもあって、結果的にポップスにはなっているという」