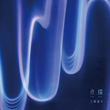Twitterでbutajiから突然DMが届いたのは、今年の3月のことだった。「アルバムのデモなんですけど、よかったら聴いてみてください。愛情の可能性というか、僕はどうするんだろう、みたいなことを強く感じながら作りました」。唐突に届けられたそのファイル名は、〈kokuhaku〉。何か切迫したものを感じ、1日かけて彼の歌と音に繰り返し耳を傾けた。
2015年の前作『アウトサイド』から3年ぶりとなるbutaji=藤原幹のセカンド・アルバム『告白』は、3月に聴いたデモからそれほど大きな変化があったわけではない。しかし、その時点でほぼ完成されていたとも言えるこの作品がこうしてリリースされるまでには、制作過程も含めると長く曲がりくねった道のりがあった。それは、以下のインタヴューで語られている通りだ。
ボーイズ・ドント・クライ。ひとりの男の苦悩や迷いが強く刻まれた9つの楽曲は、極めて私的だが、まぎれもないポップソングだ。パーソナルな思いは美しい詞へと昇華されている。そして、流麗なメロディーに乗り、深みのある声で切々と歌われている。私的な愛についての音楽が聴き手に共有されるとき、ポップ・ミュージックの可能性を信じる音楽家はその新たな局面、地平を切り開くだろう。そう思わせるほどの作品について、じっくりと話を訊いた。

〈完成〉が何かっていうのがわからなかったんですよね
「アルバム、どうでした?」
――大変素晴らしい作品だと思います。こんなことを言うのは本当に失礼なのですが、正直に申し上げて、前作の『アウトサイド』には飽き足りないものを感じていたんです。
「前作はファースト・アルバムでしたし、〈こういうものができますよ〉というショウケース的な側面もあったんです。でも、それを作り続けることはできないなって」
――ええ。なので、今回の『告白』がこれほどまでに真に迫るものになったことに驚いているんです。まさにbutajiさんが作るべくして作った作品だと感じています。ご自身としては完成されていかがですか?
「完成……したんだなって。〈完成〉が何かっていうのがわからなかったんですよね。最近はサブスクリプション・サーヴィス上でプレイリストとして作品をリリースする人もいますが、僕もそうやって作り続けていた可能性もあるんです。アルバムのデモも3パターンあって、どんどん形が変わっていって。
完成させて形にしてしまうことは、ひとつの決意表明ですし、何かの意志を固めたっていうことになってしまうのが怖かったんです。それはちょっと臆病でしたね。今回の制作は、ある雰囲気を〈こんな感じ?〉と掴んでいくような作業で、完成形が見えていなかった。それは、仕事で音楽を作る者としてはあるまじき作業でもあったと思うんです」
――というのは?
「リファレンスや影響を受けた音楽があって、そこから作っていく感じじゃなかったんです。衝動的に、1時間くらいでコードと歌詞とメロディーを作ってしまったような曲が多かったので。それは、子どもの純粋で無垢な遊びのようなことだったんじゃないかなと」
――内側から湧き出てきたような?
「そう……言わざるをえないですね。〈噴出〉したような」
――前作のリリースが3年前ですが、この3年間の作業というのはどういった感じだったんですか?
「前作は2015年の8月に出したんですけど、その後に〈スランプなんじゃないか?〉って不安になって。でも、12月に“名前のない愛(nameless love)”という、配信だけでリリースした曲が完成したんです。その後に“EYES”が出来て……〈この曲はなんだろう?〉ってずっと考えていました。
さっき言ったように、“EYES”は1~2時間で完成したんです。そんな経験はいままでなかったから、〈何が起こったんだろう?〉〈この曲はなんだろう?〉っていう疑問のほうが多かった。だから、曲の意味を解き明かしていくというか、“EYES”とずっと対話をしているような気持ちでした」
――なるほど。
「それをきっかけにいくつかの曲を作って、でも、2017年にまったく作業ができないくらい精神的に落ち込んでしまって……。で、やっと2018年の初頭までにはまとめる作業に入って、完成を迎えました。
2016年の前半までに出来た“EYES”“秘匿”“あかね空の彼方”の3曲は1~2時間で出来たもので、何かの感情が表出したような曲なんです。それは……当然、感情が高ぶるような出来事が起こったからなんですが」
――“EYES”が突然生まれた理由はなんだったんでしょう?
「『アウトサイド』では〈自分が今いる場所から外に向かっていく〉〈今いない場所に向かっていく〉ということを歌っていたんです。でも、そんな移動もできない人、そのコミュニティーにいるしかない人、そこで隣人と付き合っていくしかない人もいるわけですよね。そういった人たちのことが、ずっと心に引っ掛かっていた。それなのに〈どこへでも好きに行ったらいい〉なんて無責任なことを言ってしまったんじゃないかと、強く反省をしたんです」
――とあるインタヴュー記事の見出しにそういう言葉が付けられてしまったとおっしゃっていましたね。
「そうなんです。でも、それは僕の口から出てきた言葉だし……そこは悩んだところだったんですね。“EYES”は、そういった思いから生まれてきたんじゃないんかなと」