
シネマティック・オーケストラが実に12年ぶりとなるオリジナル・アルバム『To Believe』をついにリリースする。新作を携えて来日公演も行う彼らだが、結成20年というキャリアの長さに比してアルバムはまだ4作目。寡作ではあるものの、この12年間彼らの名前は決して忘れられることはなかった。
ヒップホップ的なサンプリングを駆使し、エレクトロニックな要素をジャズに持ち込んだシネマティック・オーケストラ。その音楽はアシッド・ジャズやクラブ・ジャズとは一線を画する。しかし『Every Day』(2002年)で完成を見た音楽性を、ビートレスな曲が大半を占める叙情的な『Ma Fleur』(2007年)で覆すなど、その歩みは真っ直ぐなものではない。それでも彼らの音楽がリスナーの心を掴んで離さないのはなぜだろうか?
今回MikikiはOvallのShingo Suzuki、mabanua、関口シンゴにその魅力を訊いた。ソウルやヒップホップをベースに独自の音楽を追求するOvallとシネマティック・オーケストラとでは、表面的な音楽性は似ているとは言いがたい。しかし、見えないところで共振するところが確実にあると3人は言う。待望の新作も制作中というOvallが語った。
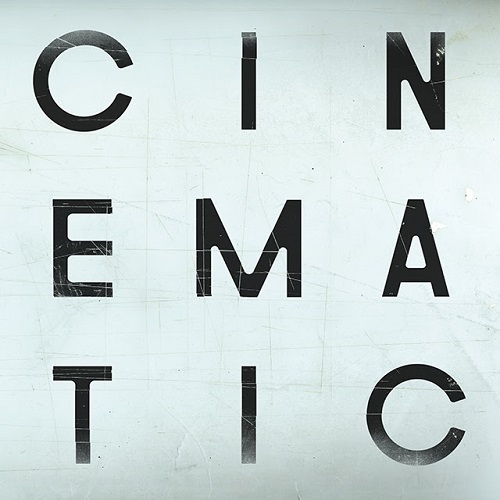
THE CINEMATIC ORCHESTRA To Believe Ninja Tune/BEAT(2019)
Ovallとシネマティック・オーケストラの関係性
――今回Ovallのみなさんにお話しをお伺いしたのは、ゴーゴー・ペンギンについてのインタヴューで関口さんがシネマティック・オーケストラ(以下、シネマティック)の名前を挙げられていたからなんですよね。お三方のなかでも関口さんがいちばんファンなんですか?
関口シンゴ「そんなに語っても大丈夫なんですか?」
――ぜひ語ってください!
関口「僕が初めてシネマティックを聴いたのは『Every Day』というアルバムで、大学生のときでした」
――2002年の2作目ですね。
関口「当時は生演奏でドラムンベースをやるのがカッコイイって思っていた時期で、そういう曲調のイメージが強いですね」
――Suzukiさんは?
Shingo Suzuki「僕は『Ma Fleur』とアルバート・ホールでのライヴ盤(2008年作『Live At The Royal Albert Hall』)がすごく好きでした。『Ma Fleur』はシンプルかつ牧歌的で、クラブ・ミュージック的な要素はわりと排除していますよね。そこがすごく好きだったんです。ライヴ盤は音が生々しくて、技術的なことを言うとライヴ・ミックスがすごい。だから、今回の(昭和女子大学)人見記念講堂での来日公演もどうなるのかなって思っています」
――mabanuaさんはいかがですか?
mabanua「僕もたぶん『Ma Fleur』ですね。2人(Suzukiと関口)がすっごく〈シネマティック、シネマティック〉って言っていたから……(笑)」
Suzuki「確かに、Ovallの初期の曲作りをしているときにわりと名前が出ていたよね」
mabanua「それで調べて聴いたのが最初でしたね。関口くんの〈vusik〉っていうプロジェクトはシネマティックに通じるものがすごくあるんじゃないかな。僕は2人を通してシネマティックに影響を受けていたことに改めて気づきました」
シネマティック・オーケストラのストーリー性
――関口さんはどんなふうに彼らの音楽を参照されていたんですか?
関口「(vusikで)インストをやろうと考えたとき、ジョン・スコフィールドとパット・メセニーという2人のギタリストについて考えていたんです。それで、自分で曲を作るならメセニー寄りのものがいいなって思って。
2人は何が違うのかなって考えると、〈ストーリー性〉なんですよね。ジョンスコの音楽はジャムっている感じが強いけど、メセニーやパット・メセニー・グループの音楽にはもっとストーリー性がある。それこそ映画のワンシーンのような曲もあるんです。そういう音楽をやりたいなって。
シネマティックってそういう音楽の最たるものじゃないですか。その要素として大きいものは、曲が長いということなんです。2、3分の曲だと一つのモチーフで終わっちゃうから、曲が長くないと物語を表現できない。今回のアルバムには10分以上の曲もありますよね。長尺のなかで曲調が変化していって、カタルシスや結末がある――そういうところがすごく好きで、影響を受けましたね」
――なるほど。では、Ovallというバンドとしては?
Suzuki「インスト・バンドとして曲を作ろうというときに、ジャズだとどうしても〈テーマがあって、インプロ(ヴィゼーション)があって、またテーマに戻って〉とフォーマットが決まってしまう。重きを置くところがアドリブやプレイヤーの音楽性になってしまうんです。
でも、Ovallではもう少し綿密にアレンジメントして、音色(おんしょく)も考えて、プレイヤーの力も見せたいって考えていて。そういう点で、ジャンルやスタイルは違っても、フォーマットとしてシネマティックと似ていると思います。彼らのインテリジェントな計算され尽くした曲やライヴがしっかりしているところは、本当に素晴らしいと思いますね」

――シネマティックの音楽はジャズとエレクトロニクス、ヒップホップの3つがバランスよく組み合わされた音楽だと思います。みなさんが分析するとどうですか?
関口「ドラムは生が基本なんだけど、打ち込みの音と混ぜて使っていますよね。それに、今回は弦が大々的に入っている。でも、生のストリングスだと思って聴いていたら、途中から全部シンセサイザーになっていたりするんです。すごくグラデーションがあって、幻想的ですよね。
たぶん、打ち込みやシンセと生楽器とを分けて考えていないんです。全部の音を同じものとして考えていて、〈ここはこの音が必要だから〉というふうに入れていく。でも音質がガラッと変わった印象に与えないように、打ち込みやシンセの音色が浮き立たないようにしていますね」
――そういう点でもOvallに通じるものを感じます。
関口「そうですね。作っているときの気持ちやねらいは、なんとなくわかりますね」

――今回はミゲル・アトウッド・ファーガソンというLAの重要なミュージシャンが弦を手掛けています。ストリングスについてはいかがですか? このアルバムの肝だと思うのですが。
関口「完全にそうで、サウンドの中心に弦がありますよね。初期の作品のハーモニー感ってそれほど分厚くなくて、だからこそストンってくるエッジもある。でも、今回のハーモニー感、和音感はすごく立体的。〈うま味!〉みたいな感じがすごく強いというか、何回も聴きたくなるのは弦の力かなって。音の景色がグラデーションになっていて、色数が圧倒的に多くなったというか」
多面的なシネマティック・オーケストラの音楽
――シネマティックの背景にはどんな音楽があると思いますか?
関口「ジャンルで括るのはよくないんですけど、最初の出会いが『Every Day』なのでクラブ・ジャズやドラムンベースのイメージがあります。でも、一定のビートの上でやっているソロは、ちょっとフリー・ジャズに近い雰囲気がある。
『Ma Fleur』ではだいぶ雰囲気が変わって、この作品から知った人にとってのイメージは、それこそ映画のワンシーンで使われるような歌が入っている音楽かもしれません。『Ma Fleur』には有名な曲も入っていますよね?」
――映画やCMで何度も使われている“To Build A Home”ですね。
関口「その落ち着いたイメージもあるのかなと。初期はフューチャー・ジャズやニュー・ジャズといった括りだったと思うんですけど、曲によっては全然その要素がなかったりする。すごくいろいろなバックグラウンドがある音楽家だと思いますね」
Suzuki「多面的な音楽ですよね。きっと小さい頃からいろいろな音楽を好きで聴いているような音楽オタクなんですよ。例えば、若い頃はクラブ・ミュージックだったけど、大人になってから子どもの頃に聴いていた音楽や観ていた映画の音楽に立ち戻ったり――ジャンルを決めたくないっていう姿勢を感じます。あえて絞らずに、〈あれもこれも作品でやろう〉という」






































