
『Stories』(2013年)、『Apologues』(2015年)、『Book Of Life』(2018年)というヴィブラフォン三部作で、ポスト・クラシカルの文脈と身体を寄せ合いながらヴィブラフォンという楽器を徹底的に追求したMasayoshi Fujitaは、いま急激なモード・チェンジを試みる。ヴィブラフォンはマリンバへ。アコースティックはデジタルへ。このふたつの大胆な方向転換を軸にしながら、彼は自身が培ってきたサウンドの再編を試み、新しいフィールドへと繰り出してゆく。その最初の成果報告が新作『Bird Ambience』だ。
かつてヴィブラフォンをストリングスなどクラシック楽器と同居させることで、独自のサウンドを作り上げてきた彼が、新作ではマリンバを中心的な素材としながら、それをデスクトップ上でプロセッシングしてゆき、パーカッションやグリッチ・ノイズと組み合わせている。ひとつの楽器へこだわりを見せているところはこれまでと変わらないが、それを楽曲として組み立ててゆく際のヴォキャブラリーがまったく異なっている。
Masayshi Fujitaはなぜここに来て、さらなる変化を志したのか。いま歩いていこうとしている道は、どのようにして作られていったのか。そのあたりをクリアにするために彼にSkypeで話を訊いたところ、その新たな変化は自身の過去と密接につながっていた。
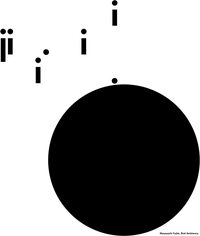
Masayoshi Fujita 『Bird Ambience』 Erased Tapes(2021)
ベルリンから自然豊かな兵庫・香美町へ
――Fujitaさんは約15年間、活動拠点にしていたドイツから日本に移住したそうですね。
「ええ。兵庫県の香美町っていう小さな町にいます。日本に移り住むなら自然が豊かなところがいいよね、ということで家族と相談してここに来ました。いろいろと幸運が重なって、山の上の保育所だった場所をお借りすることができて、そこをスタジオにしたんです。いまもそこにいるんですけど」
――『Bird Ambience』を制作したのは移住の前ですか?
「そうです。このアルバムはベルリンにいたときに完成させていて、スケジュールの遅れで2年くらいかかってやっとリリースされたという感じ。移住したら1年くらいは環境の整備なんかも含めて何もできないだろうなと思っていたので、ベルリンにいるうちに仕上げました。アルバムを完成させたらブランクが空くので、ブランク期間を移住に充てられたらなと思って、スケジューリングしたんです」
――日本へ移住してきたのは、コロナ禍と関係あります?
「いえ、コロナの前から移住は決めていました。もうドイツに13年くらい住んで子供も3人いるし、いつか日本に帰りたいなというのはあったんです。あと、自然豊かなところで制作したいっていうのがずっと夢だったんですよね。ヴィブラフォン三部作のときは自然がテーマになっている曲が多くて、常に自分の音楽の背景には自然があるんです。
ドイツに長くいたんですけど、そこが自分の場所だと思えなかったというのも移住の大きな理由のひとつです。外国人として許可をもらってそこに住んでいるし、外見も違うし、言葉が不自由っていうのもあるし。常に〈異邦人〉という感じで住んでいて、自然をベースにした音楽をやっているものとして、すごく不健全な気がして違和感があったんです。
そういう気持ちだったから、〈イレースト・テープス(Erased Tapes)〉と契約できたのはすごく大きかったんですよね。イレースト・テープスから作品をリリースして(彼らと)信頼関係を築けて、このレーベルを経由して世界に発信できれば、逆にどこにいてもいいなっていう気持ちにもなれたんです」
――いま、ぼくの目に入っているFujitaさんのスタジオはすごくいい感じです。
「保育所の遊戯室みたいなところを使っているんです。ほとんど使われていなかったようなところらしくて。あとはたまに子供が遊びに来て使ったり。環境的には本当に最高なところです。この地域に、古民家を改造してピザ屋をやっている若くておもしろい人たちがいるんですけど、移住してからすぐ、その人たちのところに突撃したんですよね(笑)。彼らに(スタジオ用の)物件を探していると伝えたら、その日にこの建物まで連れて行かれて、すぐにこの場所を気に入りました。
そこから町に掛け合って、去年の8月からお借りできることになったんです。機材を買い直したり、揃え直したりして、やっとスタジオらしくなってきました。リリースもあって、いろいろとひと段落して、新たに制作できるかなっていう状況なんで、これからが本当に楽しみでしょうがないって感じですね」






















