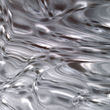birdの通算10枚目となるアルバム『Lush』がリリースされた。プロデュースを務めたのは数々の名作を手掛けてきた冨田ラボ(冨田恵一)。全曲の作詞をbird、作曲と演奏、エンジニアリングを冨田が担当して2人だけで作り上げた本作は、〈瑞々しさ〉を掲げたタイトル通り、斬新なマシーン・ビートがbirdにとっての原点回帰を促すと同時に、冨田が近年表明している〈新譜のおもしろさ〉からの影響をダイレクトに反映させた挑戦的な内容に仕上がっている。Mikikiでは、birdのデビュー時からの大ファンであり、自身が監修を務めた音楽ガイド「Jazz The New Chapter 3」での鼎談企画で、冨田の〈いま、おもしろいと思う音楽〉への関心を引き出したジャズ評論家の柳樂光隆を進行役として2人にインタヴューを企画。14,000字を超えるヴォリュームで、ポップス新時代の到来を告げる傑作の背景、birdのシンガーとしての特性や冨田のプロデュース論にまで迫った。 *Mikiki編集部
★冨田ラボ×原雅明×柳樂光隆の鼎談も掲載! 新世代ジャズ本「Jazz The New Chapter 3」の紹介記事はこちら
★コラム「冨田ラボが解析! ネオ・ソウル含め多彩なジャンル横断する異能集団、ハイエイタス・カイヨーテの力学」はこちら
近年はマーク・ジュリアナやクリス・デイヴなど、新世代のジャズ・ドラマーが叩き出すリズムに強い関心を持っていたという冨田ラボがbirdの最新作をプロデュースすると聞いて、ワクワクする気持ちを抑えきれなかった。そもそも僕は2000年前後に、エリカ・バドゥやディアンジェロ、ローリン・ヒルなどのネオ・ソウルと同列にbirdを聴いていたし、ニュー・アルバム『Lush』のジャケットにおける横顔のシルエットも、99年のファースト・アルバム『bird』のセルフ・オマージュのようで期待を煽った。冨田といえば、生演奏のグルーヴを打ち込みで再現する術に長けていることで有名だが、この『Lush』においては、〈ヒップホップやクラブ・ミュージックのビートを人力に置き換えて演奏する〉現代のジャズ・ドラムをさらに打ち込みへと置き換え、そのリズムとサウンドは結果的に、世界中のどこにもない新しいポップスの扉を開けてしまったようにも思える。そして、この後の両者の発言を読めばわかる通り、その野心的な試みを叶えることができたのは、birdの唯一無二なヴォーカルと培ってきた経験があったからなのだ。
タイム感がなまっているというか、いままでの冨田さんの音やリズムからは予想外で、 すごく衝撃を受けました(bird)
――birdさんのここ2作(2011年作『NEW BASIC』と2013年作『9』)はライヴ感のあるバンド・サウンドが印象的でしたが、『Lush』は冨田さんと2人だけで作った〈スタジオ録音作〉といった感じに仕上がりましたね。冨田さんと一緒に作ることになった経緯を教えてください。
bird「少し前に15周年記念ライヴ(昨年12月に開催された〈bird 15th Anniversary Special - sings Early Years「bird」&「MINDTRAVEL」〉)をやった時に、〈birdは声の人〉というか、〈この人はこういう声の人なんや〉って思われるようなアルバムを次は作りたいと思ったんです。これまでもいろんなことにチャレンジしてきましたが、次は〈声〉と一生懸命向き合いたくなって、そこを最大限に引き出してくれそうな冨田さんにお願いしました」
――冨田さんと一緒にアルバムを作るのはかなり久しぶりですよね。
bird「そうですね、2006年の『BREATH』以来なので10年ぶりくらい」
――今回はどういうサウンドをめざすか、ヴィジョンは当初から頭にありました?
bird「前の2作は、まずはステージで新しい曲を演奏しながら育てていって、それを録音していくという形を取っていたので、ライヴをやる前提で曲作りも進めていたんです。でも、今回はそういうのを全部取っ払ったところで新しくておもしろいことができたらいいなと。そう冨田さんにお話ししました」
――冨田さんはその話を聞いて、サウンドのイメージはすぐに浮かびました?
冨田ラボ「〈声をフィーチャーしたアルバム〉と聞いて、ネナ・チェリーの『Blank Project』(2014年)についての話をしたんだよね。フォー・テットのプロデュースが絶妙で、birdさんもそれが好きだったから、最初はそのイメージを共有していた。ネナ・チェリーのそれと、声をフィーチャーするっていうことが〈なるほどね〉と思ったの。それで1年前に“Wake Up”っていう曲が最初に出来上がった。タム回しの感じに直接的な影響を感じさせるんだけど、最初はそこから始まったの」
冨田「でも、そこからしばらくお互い忙しくて(制作の)期間が空くんです。その間に、方々で述べている通り新譜がおもしろいから、いろいろ聴くわけですよ。そうしたら、birdさんの話していたコンセプトで〈こういうのもできるな〉っていうのがいろいろと浮かんできたの。クリス・デイヴとかマーク・ジュリアナがカッコイイと思っても、僕はすぐに真似したりはしないんですね。(影響が)自然に浮かぶまではできないタチでもあるわけ。でも、その空いた期間に、2011年くらいから好きだったそういうジャズ・ミュージシャンの叩くリズムが制作中の曲との関連でも自然に思い浮かぶようになってきて。だから休んでいる間に、ちょうどそういうものができるようになった時期と、新譜がおもしろいと思っている時期が重なって、それで出来たのが“Lush”だよね」
bird「いままでの冨田さんの音やリズムからは予想外だったので、“Lush”を聴いたときは思わず〈カッコイイ……〉って(笑)。タイム感がなまっているというか、すごくリズムがレイドバックしているじゃないですか。〈この、後ろで引っ張るこれは!〉みたいな、すごく衝撃を受けましたね」
冨田「そこからはわりとグイグイ作っては送って。さっきの“Wake Up”もアレンジは休息前とだいぶ変わりましたよね。最初はネナ・チェリーのあの感じにもっと似ていて、だいぶシンプルだった。でもbirdさんの声はどう考えても特徴があって、一声でbirdだってわかる。これはすごい重要なことですよね。どんなオケがきてもbirdさんの声は揺るがないと思ったので、その後はバランスを考え直して、もうちょっと飾り付けをしてもいいかなって、だいぶ変えた印象があります。しかも、“Wake Up”は詞が先だよね」
bird「冨田さんが〈詞先をやってみたいんだよね〉って言ってくれて、それで何個か書いて、出来上がったのが“Wake Up”」
冨田「詞先って僕もあまりやったことがなくて、やっぱりおもしろかった。今回は作曲も全部僕がやることになっていたから、何でもできるじゃない。〈限定〉がないと、どこから手をつけていいのかが難しくて。音楽的なトピックとしてやりたいものがあったとしてもさ。だから最初は、その〈限定〉を歌詞に頼ろうか……みたいな気持ちがあったの」
bird「私もおもしろかったですよ。自分が思っているものとまったく違うものが上がってくるので楽しいですよね。〈おお~、カッコイイ!〉ていう感じで。それが誰かと一緒に作る楽しさですね」
――しかも、このアルバムに関しては〈これ本当に冨田ラボかよ!〉感がありますもんね。
冨田「いい意味に受け取っておきます(笑)」
――これまでの冨田さんの音のイメージと違って、音数自体が少ないというか、わりと削ぎ落として作っていますよね。
冨田「そうですね。それは今回やろうとしたことと大きく関係があるんです。〈JTNC3〉の鼎談でも話したような、リズム的なトピックが自分のなかで大きかった。だから、頻繁なコード・チェンジとか、デコラティヴ(装飾的)すぎるウワモノとかで、そのリズム的なトピックを薄めたくないなっていうのがあったんですよね。僕のイメージって、ウワモノというか、ストリングスとか、ホーン・セクションとかそういうものの印象が強いかもしれないんだけど、今回はそこじゃないなって思ったので、その結果じゃないですかね。例えば、デコレートするにしてもコーラスとかをいっぱいやったよね。ハーモニー的にふくよかにしたいなって思ったら、まずはコーラスっていう感じで」
――実際は音は少ないんですけど、聴感上は少ない感じがしないんですよね。
冨田「あとはアレンジ的なことというか、リズム的なものというか、少なくともなにかしらのトピックになるようなものはずっと流れているようなつもりでは作ったので、そういうのがあると音数が多くなくても聴いていられるというかさ。逆に音数が多すぎると自分がトピックに思っているものが埋もれてしまうような構造なのかなって今回のものに関しては思うし」

――とはいえ、今回はやっぱりリズムが印象的ですね。例えば、パーカッションとかもドラム・セットに組み込まれたパーカッションって感じですよね。
冨田「クリス・デイヴみたいなね、そんなアプローチもしたかな」
――それと、ベースの使い方が印象的でした。エレキ・ベースとシンセ・ベースを使い分けていて、シンセの時は音が前に出ているけど、エレキの時は引っ込んでいて、その使い分けがすごくうまいというか。
冨田「それも僕は〈JTNC3〉の鼎談で言っていたよね(笑)。ベースとドラムを両方フィーチャーするのが難しい構造っていうのも関係あるんだけど、今回作りながら〈俺が言ったこと合ってんな〉とか思ったりとか(笑)。アタッキーな生ベースでやってしまうと、人間の演奏は精度が高くなったとしても必ずその人のグルーヴというか、揺れを含むので、その生ベースの揺れとドラムに訛らせているものの相乗効果というものが聴こえてしまう感じがしたんですよね。もちろん曲に拠るんだけど、(今回の)僕のドラムの場合は、〈機械の真似をした人間の真似をしている〉みたいなところがあるじゃない? そこで厳選したグルーヴを生のベースによって若干薄めてしまう心配があったんですよね。でも、その相乗効果がいい場合もあって、“アイスクリーム”とかは薄まってすごく良かった。でも数曲では、相乗効果で普通に聴こえちゃったりしたのね。だから、若干でもトピックだと思っていたグルーヴだとか、そういったものが薄まった時点で再考するということを繰り返しましたね」
――ロバート・グラスパーみたいな音楽でジャズ・ミュージシャンがやっているものだと、ベースはすごく音数を減らして、ウォーキングになる直前で止めているみたいな、むしろ直前の2歩手前くらいで止めているものもあるじゃないですか。でも、この『Lush』は〈歌ものにする〉っていう前提がある感じがして、ジャズ・ミュージシャンがやっているものを模しているようでありながらも、減らしすぎずにベースでもグルーヴが出るギリギリの案配にしていますよね。ジャズのベーシストよりは音を足しているけど、ドラムのリズムは壊さない。そういう加減の調整に腐心したのかなって、確かに感じました。
冨田「そこは繊細に考えてましたね。それぞれの曲にリズム的なコンセプトがあって、例えば、“Lush”はドラム自体も訛っているんだけど、〈フレーズ・サンプリングで作ったような曲を演奏で真似た振りをした曲〉なのね。どういうことかというと、フレーズ・サンプリングで作ると、ドラムやキーボードやベースのループがあっても全部別のところから持ってくるから、組み合わせるとちょっとずつズレたりして、詰まっちゃうとか、足りないとか、そういうのがあるじゃないですか。それを演奏で真似る。〈ラーッシュー♪〉ってところで、キーボードが〈タタタタ〉って 8 分音符でやっているんだけど、〈チャチャチャチャ〉ってのが2小節で1、2 個足りないんですよね。これはキーボーディストだけちょっと遅いBPMのクリックを聴いて演奏しているイメージです。言ってみればマルチBPMみたいな感じで、ドラムとベースとキーボードのBPMがちょっとずつ違って、そのなかでもキーボードがちょっと遅いBPMだから、2小節くらいで1、2個足りないまま、またループで戻る……みたいなのを演奏で真似たりして。サンプルで作ったトラックの、わりと僕がトピックに思うものを演奏で真似て作ったのが“Lush”」
――他に、リズムのおもしろさがわかりやすい曲はどれだと思います?
冨田「“アイスクリーム”に関しては完全に5連符で作って、訛ったシャッフルにしてみたの。あそこで重要なのがジャズの4ビートとウワモノの関係で、シャッフルの上にスクウェアな8分音符のウワモノが乗るのは全然自然なことなので、オケが5連符の訛ったシャッフルであっても、僕はbirdさんに何も特別な指示はしてない。それはジャズの4ビートの上に乗るウワモノと同じ感覚で、普通に歌ってくれればいいわけ。そうすると最終的には少し訛った感じに聴こえる。そこで重要なのがドラムの具合と、それに合わせて弾くベース。歌手は意識的にしろ無意識的にしろ、かなりベースを(歌うときの)指標にするんです。ベースはリズムと音程を両方出している楽器だからね。そういう意味でベースを弾く位置というか、置き場所っていうのは、結構試行錯誤した曲もあるし、やりながらシンセ・ベースをエレキ・ベースに変えた曲とか、かなりエレクトリックだったオケを急に生ドラムみたいにした曲もあるよね」
bird「“リズムだけ残して”はガラッと変わりましたね」
冨田「あれは歌入れする時まではもっとエレクトロなドラムだったんだよね。だから歌入れした後に(楽器を)変えるということもやりました」