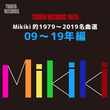〈空気感の変化、浅はかなようでいてそれが重要なんです〉
KiliKiliVillaにいる新鮮さと、ハブになるという意志
――ヤブさんはいま『少数の脅威』を、腰を落ち着けて聴くことはありますか?
ヤブ「もうほとんど聴かないですね、ハハハ! 作ってるときは他人の音楽を聴くと、自分が作っているものとすぐに対比したくなってしまうから、制作中は毎日100~200回とか同じ曲を聴いてたんです。作り終わった瞬間にヒュッと聴かなくなりますね。たまに誰かが褒めてくれたり、感想を教えてくれたりしたときに〈あー、そう言えばそうなのかもしれないな〉と確認のために聴くくらいです。先のことを考えているほうが楽しいので、あんまり深々と思い返したりすることはないです。と言うとせっかくアナログ盤が出るのにまったく宣伝にならないですけど……(笑)」
与田「SEVENTEEN AGAiNにとって『少数の脅威』がリリースされた2015年はKiliKiliVillaと歩んだ1年だったと思うんだよね。自分たちでI HATE SMOKEというレーベルを運営しているにもかかわらず、KiliKiliVillaと一緒にやろうと言ってくれたのは俺たちとしてもすごく嬉しかったし、そうすることでなにか変化を感じられたのかを教えてほしいな」
ヤブ「I HATE SMOKEはベースの大澤くん(OSAWA17)が主宰しているんですが、以前と違っていまはなんの後ろ盾もなく、完全に独立してやってるんです。同じバンドのメンバーであり、レーベル・オーナーでもあり、アルバム制作に際して双方の側面から彼にいろいろな負荷をかけてしまうのはどうなんだろうかと、ずっと考えていたんです。安孫子さんにはセカンド・アルバム『FUCK FOREVER』の頃からいろいろアドヴァイスをもらってましたし、今回は全面的に一緒に作ってもらえた。与田さんや福井(隆史)さん(KiliKiliVillaの運営スタッフ)にいろいろ助けていただいて、精神面にもゆとりができていた。作業自体はきつかったですけど、アルバムを作ることに集中できていたと思います」

――KiliKliliVillaから出したことで、いままでとは異なった達成感は得られましたか?
ヤブ「まだアルバムが完成して、それを放り投げて進んでいっている最中でもあると思うんですが、いままでとは異なる方面に響いているという実感もあります。アルバムのリリースごとに音も歌詞のニュアンスも異なっているんですが、バンドの本質はファースト・アルバム『NEVER WANNA BE SEVENTEEN AGAiN』から『少数の脅威』まで変化していないんですよ。もちろんサウンドも歌詞も、進化させているつもりではあるけれども、本質自体は変わっていない。変わっているとすれば空気感なんです。でもそれは浅はかなようでいて実は重要なことで、やってる本人がそれを感じられているのかどうかですごく異なってくる。KiliKiliVillaというレーベルが出来て、そこで僕らもやらせていただいていることで、僕ら自身も新鮮な気持ちを共有できている面が多々あって。『少数の脅威』をKiliKiliVillaから出すことで、僕らの存在に気付いてくれた方が少なからずいるように感じています」
与田「俺たちにとって、SEVENTEEN AGAiNとヤブくんは、レーベルのなかの一バンドとそのメンバーという領域を越えているんだよね。CAR10やNOT WONKもSEVENTEEN AGAiNがきっかけとなってリリースできている。すごく心強い存在であるし、レーベルのストーリーとして整合性を持たせてくれたよね、レーベルとしてもSEVENTEEN AGAiNをリリースできると決まったあたりから全体が回りはじめたんだ。ヤブくんの存在が求心力になって勢い付けてくれたと思うんだよね」
ヤブ「NOT WONKの加藤くんも逐一SEVENTEEN AGAiNの話をしてくれますけど、僕らはまったく規模の大きいバンドじゃない。名前だけでも知ってくれている人が全国にはたして数千人もいるんだろうかと思うんです。それでもとても気にかけてくれている人が局地的にいるというのがある意味特殊なことだと思うんですよ。僕自身もめちゃくちゃ不思議なんです(笑)。それをめざしてやってきたわけでもないけど、僕も他のメンバーも、いろんな音楽を好きな人間が集まっているバンドで、さまざまな音楽の複合体なんです。ツアーをするにしても、複合体であったから、さまざまな場所にいろんなことを思ってくれる人がいらっしゃっるのかもしれない。正直自分ではよくわからないものですけれど」
与田「CAR10やNOT WONKの世代から見ると、SEVENTEN AGAiNは1つの理想形ではあるんだろうね。嘘をつかずに自分たちのスタイルとアティテュードで自分たちがやりたいことをやっててさ。KiliKiliVillaのイヴェントでSEVENTEEN AGAiNがライヴをすると他のバンドのメンバーたちがいちばん前で飛び跳ねてるじゃん。あの姿を見ると、これは普通の出来事じゃないなと思うんだよね。ヤブくんがそうなりたくてやってるわけではないだろうけど、彼らにとっては自分たちもこうなりたいと思うんだろうね。シーンの真ん中にいて、いろんなところにアクセスできるハブになっている。その恩恵をいちばん受けたのはKiliKiliVillaなんだよ」
ヤブ「そうなんですかね。ですが、その〈ハブ〉という表現はとても嬉しいです! なんとなくバラバラだった人や物事が、ときどきでも集合したら、新しいなにかを生み出せる可能性があるんじゃないかと考えてきました。例えば『少数の脅威』のツアーで、名古屋ではガガガSPとSTANCE PUNKSに出てもらえて、そこに東京からTHE SATISFACTIONという僕らの好きな東京の若いパンク・バンドを呼んだんです。彼らはガガガSPやSTANCE PUNKSと対バンする機会はなかなかないと思う。そういった、本質的には価値観を共有できそうなのに、なかなかあり得ない組み合わせを実現することで、年齢や興味の異なるバンドが交わる機会を作れたらいいなと。本当は僕らなんかより、もっと活動規模の大きいバンドがそういうことをたくさんやるべきだと思うんですけど、僕が知らないだけかそういう動きはあまり目立たない気がする。でも、そういうことを積極的にやらないと、どんどん閉鎖的でつまらなくなってしまうとも思うんです。僕は行ったことすらないですけど、傍から見てて、いまの大きいフェスにもそういう印象を持っています。なので小規模であっても、風通しの良い空間を作れたら良いなと常々思っているんです」
与田「それは安孫子の言っていることとまったく一緒なんだよね(笑)」
ヤブ「海外だと、グリーン・デイみたいなバンドが地元の若手バンドをツアーに連れて行って、そのバンドがまたさまざまに派生していくといった動きが多々ありますよね。最近だとイギリスでもリバティーンズがサーカ・ウェイヴスのような若手をヨーロッパ・ツアーに連れて行っていた。それを僕らに置き換えるのは規模が遥かに違いすぎるんですけど、そういうことは誰かがやるべきだと思う」
――ヤブさんのそうした動きは確実に下の世代にも影響を与えていると思います。例えばHomecomingsがLUCKY TAPESを招いた大阪Pangeaでのツーマンでは、And Summer Clubというほとんど無名のパンク・バンドをオープニング・アクトにしていたんですよ。
ヤブ「僕らからの影響では絶対にないと思いますけど(笑)。そういった風潮が多方面に広がると、とてもおもしろいですよね。それを日本で早い時期から鮮明に打ち出せていたのはGOING SETADYじゃないかな。彼らが一気に売れたとき、それまで西荻WATTSで一緒にやってたバンドを、赤坂BLITZなど大きい会場で共演させて、いままで知らなかった人に紹介していったのは凄く意味があったと思うんです。安孫子さんとも話していたんですけど、GOING STEDAYがライヴに呼んだバンドに、お客さんはピクリとも反応しなかったみたいなんですよ。本人たち的には〈やっぱりこういうことをやっても意味がないのかなー〉と当時は落胆していたそうなんです。でも一定期間やり続けた結果、僕らの世代から下はGOING STEADYから繋がる事柄やルーツに気付いて、自分たちでもこういうことができるんじゃないかと掘り下げはじめた人が多いんです。それが地続きで今日まで繋がってきてるんですよね。だから規模の大小はあれど、やり続けないといけないと思うんです」
与田「いまの話を聞いて、あらためてヤブくんと安孫子は芯が近いと思ったな」
ヤブ「でも、いまどき安孫子さんほどメジャー的なものを拒絶する人は珍しいですよね。それを拒絶する価値観は、日本だと90年代後半から2000年代前半にとても盛り上がった感覚だと思うんですよ。ここからは〈YES〉、ここからは〈NO〉という感覚が、その頃はいまよりもわかりやすかった気もします。その価値観は、メジャーとインディーの境目が不明瞭になっている2016年の日本では、以前よりも稀薄になったと思うんです。近年だと、インディーのアイドルがそれまでパンクに熱中してた人たちも巻き込んで熱狂させたことなどが、そうした状況を如実に表してましたよね。そこで安孫子さんが正しいのは、一見飽和しているように見えるけど、実はいまのほうがハッキリと分断されているからなんです。メジャーとインディーの境目は見えづらくなっただけで、むしろ大きくなっている。だから安孫子さんみたいにめちゃくちゃわかりやすく拒絶反応を示す人は、いまとても貴重で重要だとも思うんです」