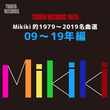安孫子真哉が主宰するKiliKiliVillaから昨年7月にリリースされたSEVENTEEN AGAiNの最新作『少数の脅威』は、筋金入りのパンク・アティテュードと貪欲な音楽愛を溢れんばかりに詰め込んだ、まさにマスターピースと讃えたくなるアルバムだった。個人的にはこの1年間でもっとも愛聴した一枚になったが、音楽シーンのなかでも、もっと脚光を浴びるべき作品ではなかっただろうか。いまのところ、その内容に見合った評価や認知を得ているとは言い難い。
むろん筆者も偉そうに言えた義理ではない。すでに活動歴10年に及び、NOT WONKら若いパンクスからは熱狂的な支持を集めている彼らの魅力に気付いたのは、『少数の脅威』を聴いて、ライヴを体験してから。フロントマンのヤブユウタは、社会への問題提起を発するメッセンジャーと、ただだ音楽を愛して止まないバンドマンという、2つの軸を常に抱えているように見え、その狭間で揺れ続ける彼の残像が筆者の心を掴んだのだ。その後ライヴを観れば観るほど、その蜃気楼の如きイメージにこそヤブの本質が投影されているように思え、いつか対話をすることで、その幻影に輪郭を与えることができればと願っていた。
今回、幸運にも『少数の脅威』のアナログ盤のリリースに合わせて、ヤブにインタヴューする機会をもらった。レーベルを裏側から支えるスタッフの与田太郎を交えて、ヤブという男のパンクスとしての矜持――それが育まれた過程から彼を突き動かし続ける動力源までを大いに語ってもらった。
★KiliKiliVilla安孫子真哉のインタヴューはこちら
★NOT WONKのインタヴューはこちら
〈僕の思うパンクとは自分のなかで答えを出すこと〉
表現者としてのあるべき姿と、アルバム『少数の脅威』
――ヤブさんの表現には、特にライヴで顕著な気がするんですけど、政治にであれ社会にであれメッセージを発しつつも、その背後には常に逡巡が見える気がするんですよね。
ヤブユウタ「いま伝えていただいたニュアンスはすごくありがたいです。そもそもパンクが好きだからパンク・バンドをやっているという自負はあるんですけど、パンクをやるならなにかを発信しなくてはいけないという前提を持っています。生活していくなかで問題がたくさんあるじゃないですか。誰に頼まれているわけでもないんですけど、誰かに伝えるなら、そのひとつひとつに答えを出さなきゃいけないと思っているんです。〈共感してほしい〉や〈わかってほしい〉ではなく、まず自分のなかで答えを出したい。それができていなかったらなにか言っているようで、なにも発してないのと一緒だと思うんです。〈こういう問題があるよね?〉〈こういう感情があるよね?〉という提起だけじゃなく、現時点での答えを出していきたい。その答えを押し付けようというのではもちろんなくて、〈僕はこう考えてます〉というのを発しているだけなんですよね。なので極めて独り言に近いとも言える」
与田太郎「考えを思い浮かべるだけの人も多いよね。考えを言語化して説明するのは訓練がいるじゃない? 意識してそうしようと自分を訓練しないと、できないことだと思うんだよね。だから、ヤブくんはよく意志を持ってやれているなと思う」
ヤブ「それを簡潔に言うと〈イメージする〉ということですよね。イメージと答えは対極にあると思っているから、僕はイメージじゃなく答えを出したいんです。〈人それぞれ〉というメッセージもあるし、例えばSEKAI NO OWARIの“Dragon Night”はそういうことを歌っていますよね。それは僕のなかではパンクとは対極にあるもので、パンクは自分の答えを出さなきゃいけないものだと思っているんです」
与田「ヤブくんは自分に落とし前を付けている感が半端ないよね。ミュージシャンでそういう意識でなにかを語ろうとする人ってあんまりいない。僕はその内的動機はどんなものなのかが気になっているんです」
ヤブ「なんなんでしょう……。もう性分なんでしょうね。お2人が指摘してくれた自分のスタンスは、商業的な意味ではバンドの成果に繋がるものではまったくないと思うんです。そこを努力したってバンドの成功とはリンクしないですし、むしろネガティヴに受け止める人も多いかもしれない。でも自分がスッキリした気持ちで発せられない言葉を選んでいる時点で、なにもやってないのと同じになっちゃうかなと思うんです」
与田「表現者としてのあるべき姿がヤブくんのなかにあって、それを自分に課してる感じがあるよね。それがセールスには結び付かないことを知っている感じもまたカッコイイ」
ヤブ「光栄です。僕の存在を知ってくれてたりライヴを観てくれたりした人のなかでも、それを好意的に捉えてくれている方は少ないような気がする。けれども、好意的に受け取ってくれる方が、いまのこのやり方でも少なからずいることは本当にありがたい。もっとキャッチーな人間でいることよりも意味のあることのような気がするし、きついですけど無駄骨じゃないんだなと思えます」

――2015年は3作目のアルバム『少数の脅威』も出し、ツアーも回り、その後カセット音源の『LEMON』も出して、と精力的に活動をされていた印象でしたが、改めて振り返ってみてどういった年でした?
ヤブ「1月から振り返ってみると前半はずーっとアルバムの制作をしてましたね」
――確か、2014年の11月から始めていたんですよね?
ヤブ「そうですね。死ぬほどきつかったことが思い出されます。去年はバンドをやってるなかでいちばんきつかったんじゃないかな。一生忘れられないと思います。ミックスはいろいろな経緯があって、僕が自分でやることにしたんです。録りながらミックス作業も並行して行って、毎日4時、5時に寝て、朝7時に起きて、会社に行って、帰ってきてからまたミックスをやるという繰り返しでした。〈これはもしかしたら死んでしまうのではないか〉と思っていましたね(笑)」
――どうしてそんなに過酷な道を選んだんですか?
ヤブ「毎回ちゃんと更新したいんです。それが第三者から見て良いものになってるか悪いものになっているかは、その人の判断にお任せするんですけど、僕自身のなかではファーストがありセカンドがあり、それを踏まえて今回も前作以上のものになってないと嫌だなという気持ちで、作曲からなにから取り組んでいたんです。自分が描いている音像を作るための方法論は、これまでの2作を経て少しずつ培ってきていたので、それだったら今回は思いきって自分たちの手で、自分たちが納得できるものにしていこうという単純な理由でした」
――今作の音作りの面で参照にしたものはあるんですか?
ヤブ「うーん、まず近年流行っているサウンドや特定の作品に極端に似ている音像にはしたくないなという意識がありました。広い視野からすれば局地的だと思うのですが、例えばリヴァーブやディレイが強烈に効いている空間系の音像――2009年頃のペインズ(・オブ・ビーイング・ピュア・アット・ハート)を思わせるようなサウンドが巷で流行っている印象があったんです」
――2000年代終盤〜2010年代初頭にスランバーランドやキャプチャード・トラックスがリリースしていた音源のイメージですよね。
ヤブ「そうですね。そういう音を僕たちが前面に押し出すのは違うかなと。すごく微妙なニュアンスなんですけど、普遍的なものをめざしつつ、それでも現在進行形の音とかけ離れたものにはしたくないんです。ちゃんと2015年のサウンドにしたいと思っていました」
――“ダイヴ”あたりは、ポッシュ・アイソレーションに代表されるコペンハーゲン周りのハードコアな音ともシンクロしているように思ったんですよね。
ヤブ「それは嬉しいですね。実際にコペンハーゲンのバンドの音作りは参考にしました。『少数の脅威』のあとに作ったカセット『LEMON』の1曲目“Come & Through”はコミュニオンズの7インチ“Love Stands Still”が頭にあったんです。ただ、それをできるだけわからないようにはしようとは思いました。カッコ良く言えば自分たちの音に昇華しているというんですけど、カッコ悪く言えばバレないようにしようと(笑)」
――以前のインタヴューで、中田ヤスタカが作るサウンドに感銘を受けたとおっしゃっていましたけど、そういう観点で、音にぶっとばされた作品は昨年ありましたか?
ヤブ「この1年はサウンド趣向に大きな変化はないですね。勘違いかもしれないですけれど、個人的にはいまは過渡期のように思います。すごく局地的にポスト・パンクやハードコアがまたリヴァイヴァルしている印象もありますが、それも数年前からありますし、もっと言えば一時的な流行ではなく、地続きで連鎖しているものですよね。ブルックリン周辺でトキシック・ステイトというレーベルがあって、ハンク・ウッド&ザ・ハマーヘッズやクレイジー・スピリットとかを出しているんですけど、それら現行のバンドと往年のハードコア・バンドとの違いは、ほんとちょっとの新鮮味だけだとも思うんです。アイスエイジが2011年に出したファースト『New Brigade』がハードコアの枠組みを超えて評価されたのも、そういったほんの少しの新鮮さだけだと思う。それができてるかできてないのかという差異なのかなと」
ヤブ「だからサウンドのアップデートはちょっとのニュアンスの変化や新しい配合だけで良いように思う。NOT WONKやTHE SLEEPING AIDES & RAZORBLADESもそうなのかもしれないのですが、そのわずかな差異こそが、多くの人にとって新鮮に聴こえるサウンドを構築する要素なのかもしれないなと。彼らが作る音楽と彼らが参考にしてきた音楽には、熱心なパンク/インディーのリスナーじゃないと気付けない変化しかないのかもしれない。NOT WONKやTHE SLEEPING AIDES & RAZORBLADESは物凄いハイブリッドですよね。NOT WONKは、加藤(修平)くんの好きな80年代や90年代前半の音を、新鮮な気持ちで2015年に鳴らしてあれになったというのが大事なんですよ」
――少しのニュアンスの変化が新鮮さを生み出すというのは、インディーやパンクに限った話ではないですよね。ところで『少数の脅威』のアナログ盤はCDとは曲順が違うんですね。
ヤブ「A面とB面で独立した道筋を立てて構成したような気がします。特に“少数の脅威”がB面の1曲目というのは意識しました。CDのときも1曲目を“ダイヴ”にするか“少数の脅威”にするか迷ったんです。僕が好きなインディー・ロックの作品のなかでも、1曲目はすごくラフでバーストしたガレージ・ソングで始まるアルバムが多い気がしてて。そのマナーを一度模倣してみたかったという安直な理由だったりもするんですけどね。アナログ盤にしたことで〈2つの1曲目〉を作れたのが良かった」
――ラフなガレージでスタートするアルバムで、具体的に念頭に置いた作品はありましたか?
ヤブ「いまパっと思いついたのはヴューのファースト『Hats Off To The Buskers』ですね。僕のなかではとても思い入れが強いアルバムなんです。世間的にはストロークスやリバティーンズと比較すると印象が薄いと思うんですけど、僕にとっては当時のUK、USのギター・ロック/ガレージ・パンク・リヴァイヴァルのなかで初めて、一聴したたけでしっくりきたアルバムだったんです。ヴューを聴いてから、やっとストロークスもリバティーンズも受け入れることができたようなところもあります」