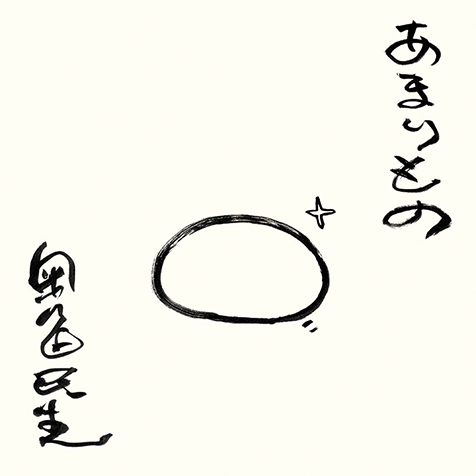アンネ=ゾフィー・ムターの秘蔵っ子、待望のニュー・アルバムをリリース!
5月22に開催されたクリスチャン・ヤルヴィ指揮都響演奏会でメンデルスゾーンの《ヴァイオリン協奏曲》を演奏したヴィルデ・フラング。大向こうを唸らせる過剰な表情づけを一切排し、ただひたすらに音楽と同化していく独奏は、彼女の無垢な表情と同様、「穢れ無き純真」と呼ぶのがふさわしい演奏だった。
「メンデルスゾーンは、余計な味付けをしたりスパイスを振りかけたりしなくても、素材そのものがすでに素晴らしい音楽。あるいは、ヴァイオリンの“音色の風景”の中を進む列車の旅のようなもの。その列車に乗るたびに、いつも心を奪われてしまうのです」
最新録音盤はコルンゴルトとブリテンの協奏曲。誰もが知っているメンデルスゾーンとは真逆の世界だ。
「録音を思い立ったのは2011年。レコード会社と長い議論を重ねた上、実現に漕ぎ着けました。そもそも、この2曲をカップリングした前例が存在しませんし。でも、2曲とも後期ロマン派の語法に基づきながら、演奏者に高い技術を要求しているという意味で、20世紀が生んだ偉大なドラマだと確信しています」
まずはコルンゴルトの協奏曲について。
「ロマンティックなオーケストラをバックに、あたかもヴァイオリンが歌ったり飛び跳ねたりするような音楽。協奏曲の基になった映画は、もちろん見ました。例えば『放浪の王子』は、第3楽章の力強い主題に流用されていますが、彼が主題素材に映画音楽を用いたこと、まさにその事実によって、人々がコルンゴルトの作品を見下し続けてきたのが残念ですね」
一方のブリテンは、彼女によれば、いろいろな意味でコルンゴルトと強烈な対照をなす作品だという。
「あたかもX線を照射したような、非常に明晰な語法で書かれた音楽。ドライな響きのオーケストラの中に、不安と絶望が詰まった作品です。特に第3楽章のパッサカリアは、恐ろしいほどの集中力を必要とします。いわば、独奏ヴァイオリンが死と格闘していくような音楽です。楽章終わりのコーダでは、死の向こう側にある楽園の存在が仄めかされていますが、ヴァイオリンは『まだ死にたくない!』と生にしがみつく。そんな凄まじい音楽を弾き終えると、アンコールでは何も演奏する気が起きなくなってしまうのですよ」
この2曲以外にも、20世紀の音楽や同時代の音楽への関心はあるのだろうか。
「私と同世代の作曲家に関しては、エベーヌ弦楽四重奏団のチェロ奏者ラファエル・メルランが、才能に恵まれた人だと思っています。私より上の世代では、エサ・ペッカ・サロネン。具体的な演奏計画はないですが、しばらく探索を続けてみたい作曲家ですね」