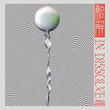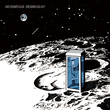岸田剛のソロ・ユニットとして大阪を拠点に活動するインディー・ポップ・バンド、Post Modern Team(以下、PMT)がサード・アルバム『COME ON OVER NOW』をリリースした。2012年の始動当初から、アノラック的な甘酸っぱいギター・ポップで関西のインディー愛好家たちを虜に。2016年の前作『Be Forever Young?』では、ディスコ・ビートとギター・カッティングを両手に眩いダンス・ポップへと傾倒していたが、今作では自身が若かりし頃に立ち会ったという90年代のブリットポップや2000年代のロックンロール・リヴァイヴァルへと回帰。躍動感に溢れたギター・ロックを快活に鳴らしている。
そして、同作のリリース元が、全国に散らばるインディー・バンドの(主に)自主制作CD/レコードを取り扱っているディストロ・ショップ、HOLIDAY! RECORDSだ。もともとはバンドマンだった植野秀章が〈興味があってノリではじめた〉というHOLIDAY!だが、その審美眼の確かさと溢れんばかりの情熱で多くのリスナーの信頼を獲得。現在は、CDショップのバイヤーやメディア関係者からも〈いまフレッシュでおもしろいバンドを探すならHOLIDAY!〉と注目を集めている。
★HOLIDAY! RECORDSの植野秀章がショップを開始した経緯やこだわりなどを語ったインタヴューはこちら
今回は、同ショップのレーベル活動をサポートしているタワーレコード/レーベル事業部の行達也が、PMTの岸田剛とHOLIDAY! RECORDSの植野秀草にインタヴュー。PMTの前作『Be Forever Young?』はHOLIDAY!のレーベル第1弾リリースでもあり、かねてから親睦の深い2人に、HOLIDAY!がディストロのみならずレーベル活動をスタートした経緯やPMT新作の聴きどころ、さらに関西シーンで注目すべき新鋭たちの紹介まで、たっぷりと語ってもらった。 *Mikiki編集部
2000年代初頭のカレージ・リヴァイヴァルを反映しつつ、いまの〈音〉をめざした
――まず、そもそも植野さんがHOLIDAY!の活動のなかでレーベルもやろうとなった経緯から教えてほしいんですけど、これは僕が誘ったからですか(笑)?
植野秀草(HOLIDAY! RECORDS)「そうなんですよね」
――僕が〈レーベルやりませんか?〉という話をしましたよね。そして、第一弾としてリリースしたのがPost Modern Teamの前作『Be Forever Young?』。PMTを一発目に選んだ理由は?
植野「えー、岸田さんから提案があったというのがやっぱりデカいんですよね」
岸田剛(Post Modern Team)「行さんから植野さんに話があった直前に、僕もHOLIDAY!から出したいと言うたんですよ。自分でレーベルとかを立ち上げてもよかったんですけど、HOLIDAY!はずっと自分の自主音源を取扱いしてくれて、プッシュしてもらってたんで」
植野「行さんとの話でもPMTの名前が出ていたので、いろいろとタイミングも良かったんですよね」
――じゃあ、いま『Be Forever Young?』を振り返ると、このユニットのどんな要素を出せた作品になっていると思いますか?
岸田「前作含めて、これまでは結構時代に合わせて変化していたんです。たとえば1枚目の『Post Modern Team』(2014年)を出したときは、ネオアコのリヴァイヴァルやドリーム・ポップが流行りだしているように感じてたんで、その流れに合わせたというか」
――ふまえて前作にはどういった影響があったんですか?
岸田「『Post Modern Team』を出してから、いろいろライヴの出演も誘ってもらえるようになったんですけど、DJのイヴェントに出させてもらえることが結構多くて。で、当時そこでDJがかけている音楽がギター・ロックというよりシンセありきのもの――エレクトロ・ポップやシンセ・ポップが多かったんですよね。だから、ライヴの場でそういうのを自然に吸収していって、自分の音楽に返したんが『Be Forever Young?』。スタイルはバンドだし、シンセも入っていないんですけど、曲調は4つ打ちだったりダンスっぽくなった」
――じゃあDJがかけている音楽を聴きながら、〈こういうんもええんちゃう?〉みたいな?
岸田「そうですね。それで気になったらDJの人に〈これ、なんですか?〉と訊いたり。そうやって吸収していったものを反映したアルバム」
植野「前作を聴いて、岸田さんが世の中の流れに意識的なんやなとは感じたし、PMTはそういう時代時代の要素を採り入れていくバンドなんやなと思いましたね」
――では、新作『COME ON OVER NOW』を作るにあたってのコンセプトは?
岸田「(いま言ったように)前までは時代に合わせて作ってたんですけど、去年くらいから、このジャンルが流行ってるみたいなんがあんまりないように思えてきたんですよ。ジャンルが多様化してきたように感じていて」
植野「ああ、それはHOLIDAY!やっていても思うね」
岸田「そうなんですよ。2014年あたりまでだったらシンセ・ポップが流行っているとかわかりやすい形であったんですけど、去年くらいからインディーのなかでもいろんなジャンルが出てきた感じがあって。そうなったときに、じゃこのタイミングで自分のルーツに戻りたいなと思った。僕のルーツのひとつは2000年初頭のカレージ・リヴァイヴァルでストロークスやリバティーンズなんですけど、そういった音楽性を反映したのが今回のアルバムですね」
――そして、今回はミキシング、マスタリングも岸田くん1人で全部やったという完全セルフプロデュースの作品になっていて。
岸田「作詞作曲はもちろんなんですけど、僕はなんでも1人でできてしまうっていうのが当たり前の時代になってくるんじゃないかなと思っているんです。今回のやり方は、自分自身への挑戦でもあるんですけど。ミックスもマスタリングという過程も、自分のなかでは曲作りっていう考え方になってきています」
――ミックスって難しくないですか? 僕もたまに自分でちょっとやるんだけど、ヴォリュームの加減でなんとかなるやろ、と思ってもまったく違う。ほんまのプロがやるのと明らかに違いますよね。そこは聴きながら勉強したの?
岸田「そうですね、自分なりになんですけどプロの音源と波形を比較して見るようにしたり、自分なりに今回は研究して。僕の性格っていうのもあるんですけど、全部自分1人でやりたがるんですよ」
――やってみてどうでした? これで満足というか、ひとつ完成させた気持ちですか?
岸田「自分で言ったことを後悔するくらい大変だったんですけど、一応まあひとつの完成形として今回は満足してます」
植野「参考にした音源はどんなものが?」
岸田「音楽性に関しては2000年の音楽を意識したんですけど、マスタリングは結構今っぽくというか最近の音楽をめざしました」
――80年代のギター・ポップとかペラペラな音質のものが多いし、いまそれをめざしてもね。若い子にはそれが新鮮だったりするんでしょうけど。
岸田「そうですね。それが良さだったりもするんですけど」
ポップでキャッチーというのは大前提
――ちなみにPost Modern Teamのライヴに来るお客さんはどれくらいの年齢層が中心なんですか?
岸田「PMTのお客さんの年齢層は僕よりも高い気がします(笑)」
一同「ハハハ(笑)」
岸田「他のバンドのお客さんは若い子ばっかりなんですよね。僕らは若い子もいることはいるんですけど、年配の人も結構います。リアルタイムでオアシスの初来日を観たとかホンマそういうレヴェルの人。だから物販でSサイズが全然売れないんですよ(笑)」
――オジサン体型(笑)。でも、ある意味それはオッサン世代にも認められている音楽というか、当時聴いていた人をグッとこさせるものがきっとあるんでしょうね。
岸田「だから逆に嬉しいんですよね」
――岸田くん自体は昔の音楽が好きなんですか?
岸田「僕は90年代のブリットポップがリアルタイムなんで、どっちかっていうとイギリスの音楽が好きですね。スミスやオレンジジュースとかネオアコも大好きですし」
――PMTの曲は2~3分くらいの尺が多いじゃないですか? 僕はあの短さがすごくいいと思うんです。ストレートにズドーンといくというか、サウンドは全然違うんだけどモータウン・ポップを聴いているような気持ち良さがあって。
植野「短いのにこだわりはあるんですか?」
岸田「初期パンクとかも好きなんで、その美学みたいなものはあるかもしれませんね。あんまり長い曲が好きでないというのもあるんですけど。あと、やっぱり日本で英語の曲をやるうえでは、ポップでキャッチーでないと言葉が伝わらないと思うんです。小難しい言葉とかいろいろ凝ったことを歌詞に入れていても、日本人にはわかりにくいじゃないですか」
――岸田くんの歌詞はほんとにタイトでわかりやすいですもんね。
岸田「オアシスの曲とかは言葉の意味がわからない日本人でも合唱できるじゃないですか? そういうのをめざしていますし、ポップでキャッチーというのは大前提ですね」
――じゃあ〈日本語でやろう〉とかそういう話にはならないんですか?
岸田「自分のなかで〈Post Modern Teamは英語〉って決めているんです。最近、GOODNITE(グッナイ)という新しいバンドをはじめたんですけど、〈そのバンドは日本語〉と僕のなかで分けるようにしています。なんかちょっと違うんですよね。洋楽と邦楽は、言葉が違うだけじゃなくって、音楽自体の小節が同じじゃない。日本語が乗る/乗らないっていうのが僕はあると思んです」
――言葉の乗りかた、乗せかたが違うっていうね。
岸田「そうなんです。だから、PMTの曲に無理矢理日本語を乗せたら、めっちゃカッコ悪くなると思いますね。やっぱり拍数が合わないっていうか」
――なるほど。そうやって英語でやっているのって、僕はスタンスとしてカッコええなと思うよ。やっぱりクールっていうか、〈絶対に俺ら売れるぜ〉ってギラギラしていない感じ? 純粋に自分の好きな音楽、やりたい音楽をやる。で、わかっている人だけにわかってもらえたらええねん、みたいなね……。そういう魅力があるかな。
岸田「僕はもう36だし、年齢的なものもあるのかもしれないですね」